
オリヴィエ・メシアン:
・世の終わりのための四重奏曲
ヴァイオリン:ルーベン・ヨルダノフ
チェロ:アルベール・テタール
クラリネット:クロード・デスルモン
ピアノ:ダニエル・バレンボイム
ポリドール: F28G 50488
フランスの作曲家メシアンの作風は新神秘主義として知られています。メシアンは敬けんなカトリック信者であり、特徴的な音楽語法によって聴き手に神学的世界を擬似体験させるという意図があります。その手法は、通常の四拍子などのリズムに拍を追加するなどして時間の流れの感覚を曖昧にさせるもの、などがあります。
このディスクの「世の終わりのための四重奏曲」というタイトルは悲劇的なものではなく、現世を超越して永遠の世界に到達するという意味を持っています。ここでメシアンの奇妙なリズム語法は聴き手に変容した時間感覚を与え、その結果として時間の概念を捨て去ることができるとされています。
全8楽章構成ですが、第6楽章「7つのラッパのための狂乱の踊り」では特異なリズムが顕著です。
この楽章は最後まで全ての楽器がユニゾンで演奏するという異様な部分でもあります。その上に全く先の読めないリズムが組み合わさって、人智を超えた風景を見ているような感覚があります。全曲を通じてキラキラした印象があり、天上の世界を目の当たりにしているようです。
この作品は1940年にドイツ軍に捕らえられたメシアンが捕虜収容所にて作曲し、翌年に収容所の中庭でマイナス30度という寒さの中に初演が行われたとのことです。その時にこの曲を聴いた捕虜達の興奮はいかばかりのものであったでしょうか。
クラシックCD紹介のインデックス










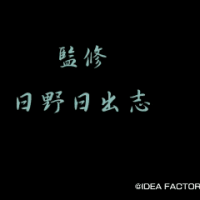
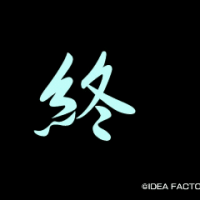
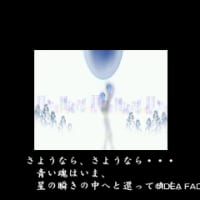


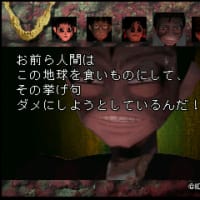

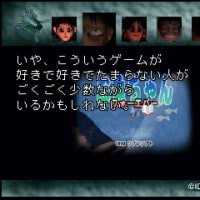

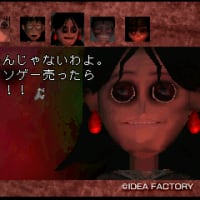
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AA%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A8%E3%83%BB%E3%83%A1%E3%82%B7%E3%82%A2%E3%83%B3
動画も拝見しましたが、本当に予想が付かない旋律で、不思議な印象でした。
長生きしていたメシアンが亡くなった1992年にはちょっとしたニュースになったのを憶えています。それだけ巨大な存在感のある人でした。そういう人であるから日本から弟子入りした人が多かったのでしょうけど、そのこともメシアンが日本への親しみを感じた要因の一つだったのかもしれません。
ところで、メシアンを含めたかなり多くの西洋の作曲家が日本に関する作品を残しています。20世紀前半から西洋音楽に「引き算」で構成された作品が目立っており、究極の引き算芸術である俳句も音楽化されています。こういった日本の文化や風景は当時からかなりのインパクトがあったようです。