100年前「明治の三陸」地図

この地図は、今から約100年前の明治45年(1912年)に宮古市で開催された「岩手県沿海四郡聯合物産共進会」の記念写真帳の付属地図です。
地図には当時の岩手県沿岸部の4郡(九戸郡・下閉伊郡・上閉伊郡・気仙郡)の主な地名が描かれています。明治期は三陸沿岸には市制を施行しているところはなく、私の住む宮古市は、宮古町・鍬ケ崎町の2町と、山口村・千徳村・花輪村・磯鶏村・津軽石村・崎山村・重茂村・刈屋村・茂市村・田老村・川井村・小国村・門馬村の13村に分かれています。
中でも興味を引かれるのは、三陸沿岸を結ぶ陸路がとても細いことです。内陸部へ向かう道路は2重線で表記されていますが、現在の国道45号線に当る様な幹線道路この当時はなく、三陸の各地域間の交流は陸路より海路が主だったことが伺えます。
したがって明治三陸大津波(明治29年/1896年)の復旧復興は、今回の東日本大震災より困難を極めたであろうことがこの地図からも容易に想像できます。この道路事情は、昭和三陸大津波(昭和8年/1933年)でも変わりなく、当地に支援の手が届くのに相当な時間が経過した後でしょうし、それまで間互いに助け合って凌いだのでしょうか。この三陸が自助自立の精神が強いのはこうした故もあろうかと思います。
また今では殆ど利用されていない峠越えの道があることや、一部の山名などが今と異なるなど、とても興味深いものがあります。

















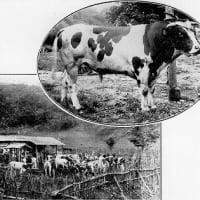
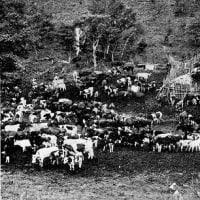
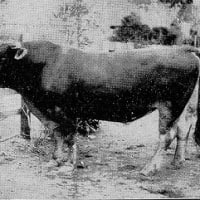
馬が大好き タンタンです