表題の「シスト線虫の騙し打ち」の話、農業研究者は良くぞこんな事を考えたり、思いついたりするのかと感心しているのですが、先日の3月18日付けのサイエンスデイリーで紹介されていた話です。
その原理、寄生植物からの偽の生理活性物質によって休眠している線虫のシストを孵化させ、結果的には、寄生できる植物根からの養分摂取が出来ずに線虫を餓死させると言う戦法です。
尤も、「シスト線虫」と言っても、それ程知識をお持ちでは無い一般の方には中々イメージ出来ないかと思い、一寸線虫の話を致します。

―シスト線虫被害が発生したジャガイモ畑―北大研究紹介より
「線虫」は、線形動物門に属する動物の総称であり、この生物、地上でもっとも繁栄している動物であると言われ、きわめて多様で多数の個体が存在しています。
その種類は1億種を超えるといわれ、1m3当たりの土壌には100万頭もの個体が生息している事になるのですが、そのほとんどは体長1mm以下のウナギ型をした微細な生物であることや、主に土壌中で生活しているために、私たちが実物を目にする機会は殆ど無いのが当たり前と申せます。

―シスト線虫のオスとメスーWebphotoesより
又、これらの線虫の大部分は、人間にとって無害であり自活生活をおこなっている分解者として働いているのですが、その中に動物や植物に寄生する有害線虫が居て、人間やペットに寄生する回虫や蟯虫の類、松枯れを起こす松のザイ線虫、植物の根に寄生して農業生産上で大変な減収を伴う線虫被害が問題となって居るのです。
線虫は土壌中で生活する種が多いため、植物寄生性線虫が寄生する部位のほとんどは根であり、根に寄生を受けた植物は、生育不良を起こして収量が低下するのですが、単なる生理現象とみなされて見過ごされる例も多く、線虫の被害として認識されないことが多いのです。しかし、いわゆる連作障害の多くは線虫によって引き起こされていると考えられます。
そして、植物寄生性線虫にもさまざまな種類があるのですが、その中でも被害が大きいのが、ネコブセンチュウ、ネグサレセンチュウ、シストセンチュウの3種類と言います。

―代表的な線虫の種類―Webphotoesより
その中のシストセンチュウ、メスが産卵せず、胎内に残したまま表皮が丈夫な殻となって卵を守る「シスト」を形成するのですが、その寄主範囲はきわめて狭く、大豆、小豆、いんげんなどのマメ科作物数種類に寄生するダイズシストセンチュウ、じゃがいも、トマト等のナス科の数種類の作物にしか寄生しないのがジャガイモシストセンチュウと言います。その「シスト」、普段は卵の状態で休眠し、寄主作物が生育して根が伸びてくると、そこから分泌された物質に反応してふ化が起こり、植物に寄生するのですが、環境変化や農薬などに大変強く、土壌中では10年以上も生存することが可能と言います。

―線虫のシストーWebphotoesより
国際的なじゃがいもの大害虫であるジャガイモシストセンチュウ、日本では1972年に初めて確認されて以来、徐々にその分布を広げていると言われ、 この線虫が発生した圃場での種いも栽培が禁止されるなど、その被害の拡散を防ぐ努力がつづけられています。
安易に食用ジャガイモを種いもに転用することなどによって分布が広がりつつあると言い、線虫被害を防ぐためには、家庭菜園でも定められた種いも以外は使用すべきではないと言います。

―ジャガイモの隔離栽培の標識―WebPhotoesより
ダイズシストセンチュウでは、畑にダイズ、アズキ、インゲン等の寄主作物が栽培されると、根から分泌される物質の刺激によって「シスト」のふ化が始まります。ふ化幼虫は根に侵入して養分を摂取すると、雌は次第にレモン状に肥大し、頭部を残して根の外側に乳白色の虫体を露出し、雌成虫は数100個の卵を体内に保持した状態で死亡し、「シスト」となって栗色に変わるとともに根から離れて土中に残ります。
そして、一度圃場に侵入した線虫を完全に根絶する事は大変むずかしく、略不可能と言い、普段から線虫が侵入しないように注意することが肝心と言います。
扨て、この話、日本でも2011年の北海道農研の成果情報の中で、ジャガイモの根由来のふ化促進物質「ソラノエクレピン」の全合成に成功し、精製物3.8mgを得た。この合成品は、1ppb(10-9g/ml)レベルの低濃度でジャガイモシストセンチュウの卵から幼虫を60%程度ふ化させる顕著なふ化促進活性が認められと発表されて居ます。

―蔓延するジャガイモシスト線虫―Webphotoesより
しかし、このシスト線虫孵化促進物質の研究の歴史は古く、1922年に最初にオランダのBaunackeがジャガイモの根から、ジャガイモシスト線虫の卵内2齢幼虫の孵化を引き起こす物質が分泌されている現象を報告し、それが孵化促進物質(HatchingFactor)と呼ばれていています。その後、世界の科学者が孵化促進物質の単離と同定に挑戦し、一方、日本では北海道大学・理学部の正宗、福澤らが1985年、近縁種であるダイズシスト線虫の孵化促進物質グリシノエクレピンAを単離し、その構造を報告したとあります。
そして、オランダのMulderらは、ジャガイモシスト線虫の孵化促進物質については1992年特許としての「ソラノエクレピンA」を報告していると言います。

―土壌で長期残存するシストーWebphotoesより
しかし、先に北大の研究者らが発表した研究報告の中で、孵化促進物質グリシノエクレピンAは、単体では十分な効果は得られず、ジャガイモシスト線虫の孵化は、孵化促進物質とともに、孵化共力因子の存在が必須であり、其の共力因子によって、これらが相乗的に働くと活性が10万倍以上になるとその「まとめ」の中で発表して居ます。そしてそのヒントは、トマト水耕栽培の廃液に含まれる根系から分泌される老廃物にあると示唆しています。

―ジャガイモの根茎に付着しているシストーWebphotoesより
ところが、今般、サイエンスデイリーで紹介されていた話では、孵化促進物質(HatchingFactor)に加えて、線虫の繁殖に寄与しない根系からの粘着分泌物を排出するある種のナス科(NightShade)の「おとり植物」を植え込むとあります。

―野生のNightShade-Webphotoesより
これぞ、まさにケミカルな孵化促進物質(HatchingFactor)のみならず、生体反応を利用して騙すシスト線虫の駆除法の新たな発想と言うのかも知れません。
![]()



















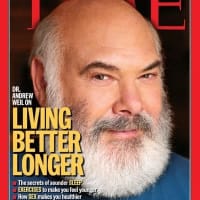

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます