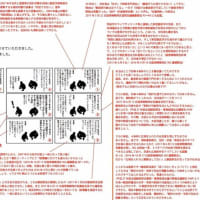……………
日本人のIT活用は、ものすごく非効率だ 自分たちも気づいていない強みを意識せよ- 東洋経済オンライン(2015年2月2日08時00分)
閉塞感を打破し、稼ぐ力を取り戻す日本人の付加価値アップの公式とは。『日本人の「稼ぐ力」を最大化せよ』(東洋経済新報社)を書いた野村総合研究所の谷川史郎理事長に聞いた。
──冒頭にあるカトリックの総本山、バチカン市国とのエピソードが心強いですね。
聞かせてくれたのは国立公文書館の前館長でフェローの高山正也先生。バチカンの図書館にある約8万冊の古文書の電子化プロジェクトを日本企業が請け負った。その際、バチカンが評価したのは技術だけでなく、電子化したデータのバックアップの保管・保存に関して、宗教に対する日本の寛容性が大きな魅力だったという。日本人はとかく無宗教だと自嘲的に言うが、バチカンは八百万の神を含めて「節操のない信仰心」に違和感はなく、むしろ特殊性として評価している。
──強みになる?
日本人が意識すらしなかった宗教的寛容性が魅力に映ったわけだ。自分たちでは気づいていない強みはほかにもたくさんあり、外との接点を豊かに持てば、外部視点から意外な強みが浮き上がってくる。
■受容し、変容させて超越するのが日本文化
──日本社会や文化がブランドになるのですか。
日本の文化は海外から伝来した文化を取り込んで、それを国内で自分たちなりに解釈し、オリジナルを超越していくことを繰り返しやっている。つまり受容し、変容させて、超越する。この一連の流れは改良・改善で日本の物作りに反映されているが、この面では諸外国にキャッチアップされた。
違うのは、日本はこの受容・変容・超越をいくつも同時に多層でやっていることだ。受容・変容・超越という行為を単純に一方向の流れとするのではなくて、外から入ってきたいろいろなものをまぜこぜにする。それは言葉を換えれば多様性を尊重すること。多様なものが多様なものに変わっていくことに対して極めて寛容なところがある。並存しても誰も違和感を抱かない多様性に対する寛容さは、日本の誇れる強みなのではないか。日本の強みを定義し直すことが必要になってきた。
──海外発が加わりアニメや「かわいい」がもてはやされています。
文化とまでいわなくても、日本人がどんなライフスタイルを持っていて、そのよさは何なのかを伝えることで、世界の中で日本が貢献できる要素はまだ大きくある。
アニメやかわいいを外が発見してくれてそのまま受け入れているが、実は日本のコンテンツを海外に紹介しようとしても英語できちんと紹介されているものはない。日本語ででさえしっかり説明されているものは意外に少ない。たとえば日本文化そのもののわかりやすい解説も、またクールジャパンの定義もない。ジャパニーズ・ポップカルチャーでありサブカルチャーである、と書いてあるものもあるが、「それって何?」と再度問うことになる。
自分たちでどう発信するか。そろそろまじめに考え、ロジカルに理解して伝えていく。実はこれが次のビジネスチャンスを生む。そういうタイミングに今入っている。
──競争力の基盤になる?
「日本力」で使い切っていないものがいくつもある。文化はその最たるものだ。その際、日本の各地域の産物を見直すのは確かに大事だ。ところが、今は地方の物産を大消費地・東京に売るスタンスだ。たとえば、松阪牛、佐賀牛、米沢牛などといった売り込み。東京もあと5年もすれば人口減少が始まり、食べ物を売り込んでも上限が見えている。海外からの目線に変えないと短期勝負になる。外に向かってなら和牛は何が違うのか一丸となってメッセージを出していくべきだろう。来日観光客の目にも触れるように。その転換を今起こさないと、チャンス自体も雲散霧消しかねない。
──日本人のITの使いこなしにも切歯扼腕しているようですね。
日本はITを使いこなさなくても困らないものを進化させた。ファクシミリだ。今でも中小企業では受発注は手書き利用のファックスが少なくない。カルテや保険点数計算の電子化はようやく動き出したが、キーボードを使わない方式が根強い。これはトータルではものすごく非効率だ。それが、ITインフラは世界最高水準なのに、使う能力は先進国水準に追いついていない理由だ。
キーボードを操作する能力は、まだ今後10~15年必要だろう。ITを使いこなし、かつ楽しんでいこうとすると、プログラミングできる能力がないと面白さがわからない。日本はITインフラが後れているのではなくて、使い方だけが問題なのだから、頑張ればここで新たなコストがかかることはない。
■プログラミングでおもちゃ遊びを楽しめ
──今はプログラミングでおもちゃ遊びですか。
われわれの世代はおもちゃを手作りした。それは面白かったし、そういうものをきっかけにエレクトロニクスの世界に飛び込んだり、機械をやってみたりする人間が出てきた。今プログラミングという世界がまさに同じような状態に入っている。いじくり回すと、すごく面白いことができる。欧米はそれに気づいて一般教科として始めている。ずいぶん違う世界があると思えてくる。
──さらに日本が付加価値をつけるにはどうすべきですか。
次の稼ぎ頭というと、グローバルな展開の産業の話ばかりが出てくるが、国内での付加価値増強の議論をしないと豊かさは実感しにくい。人口減少に比例して、単純に内需は縮小すると皆思っているようだが、マーケット規模で見ると、けっこう拡大に出遅れているものがある。中でも住宅と教育だ。住宅はマーケットの構造がガラッと変わり、中古売買の回転率が上がることで規模として大きくなる可能性が大いにあるし、教育のマーケットは社会人以降がポイントだ。
たとえば住宅は住み替えたいときに売って、自分に合った家に買い替える。人生ステージに応じて中古住宅の売り買いが増える方向に行くだろう。手をかけただけ家の値段が上がるなら、家を大事に使ってしっかりメンテするようになる。一方の教育は従来の社内教育が外部化する。今やサービス業が増えて、社内教育は減る一方だ。だが、教育費をかけてでも生産性を上げていかないと勝てない。人材投資で個人の付加価値を上げる。そういう未来志向が普及するだろう。
──となると、日本人の付加価値アップの公式はどうなりますか。
日本人の「一人ひとり」の付加価値を上げる公式としては、「日本文化のブランド価値を最大化」「ITを使いこなし日本人機能最大化」「国内に残る付加価値最大化」の3要素を掛けたものが、稼げる日本の姿だ。
http://news.infoseek.co.jp/article/toyokeizai_20150202_59097
……………
ED解消法には「おさかなすきやね」という食材がカギ- オトコクラス(2015年2月2日08時00分)
EDの原因の一つに骨盤周りの血行不良があります。そのため下半身のトレーニングや血行をよくするための食材摂取が重要となります。今回は「おさかなすきやね」という食材が挙げられていますが、どんな食材でしょうか。
40代男性からの相談:「ED解消法はなにがあるのか」
『EDの解消法を教えて欲しいです。病院治療もあるようですが、まだ早いと思っています。ほかの方法で解消法があるようであれば、知りたいです。食事や運動などで解消する方法はあるのでしょうか? 』
「おさかなすきやね」という食材がED解消法のカギ
EDは骨盤周辺の血行不良が原因です。運動不足などもありますが、栄養バランスが傾き血液中の脂肪分が増えると血行不良を促進します。食材はなるべく脂肪分の吸収を防ぐような食材を取り入れましょう。キーワードは「おさかなすきやね」です。
『それではまず、ED(勃起障害)のメカニズムですが、これは血行不良で骨盤の中の血の巡りが悪くなる事で勃起が妨げられるために起こります。普段の生活で栄養のバランスが悪いと、血液中の脂肪分の数値が増え、さらに運動不足で筋力が衰えたらますます血行が悪くなり悪循環ですね。(看護師)』
『血液サラサラ、おまけに脂肪分が吸収されにくい食材のフレーズ、ご存知ですか?「お、さ、か、な、す、き、や、ね」そう、血液がサラサラになる食材の頭文字。お茶、魚、海草、納豆、酢、キノコ、野菜、ネギの8つの食材を上手に取り入れてください。(看護師)』
下半身のトレーニングが重要だが、自転車には注意
下半身周りの血行促進ということで、トレーニングではスクワットがおススメです。自転車なども下半身を鍛えるには良さそうですが、サドルの影響で血行を悪化させる可能性があり、注意が必要とのことです。
『運動ですが、下半身を中心に鍛えると、ED対策にによいと言われており、メニューとしてはスクワットがおすすめです。日々のトレーニングにぜひ取り入れましょう。(看護師)』
『また、下半身の運動という点で注意したいのが自転車です。これは、自転車のサドルで、勃起に使われる血管や神経を圧迫、陰茎の血行が悪化します。特にマウンテンバイクなど前傾姿勢で乗るタイプには注意が必要です。(看護師)』
EDを解消するにため、薬などを服用するのも良いですが、普段の食生活の改善や簡単なトレーニングを行うだけでも変化があるかもしれません。ぜひ取り入れてみましょう。
http://news.infoseek.co.jp/article/otokoclass_archives_4064
……………
【レポート】男性はなぜ「鈍い」のか- マイナビニュース(2015年2月2日17時42分)
「男性って、女の子の気持ちに気づかないよね」。女性たちからよく聞く声です。確かに女性たちからすると、好きというオーラを出しているにもかかわらず、それに気づかない男性って多いのかもしれません。ですが、本当に男性は察することが苦手だったり、誰かの感情に対して鈍かったりするのでしょうか。
○男性は察することが苦手
男性は察することが苦手だという理由については、以前に紹介しました。そこでは、はるか昔から男性と女性にはそれぞれの性にあわせた役割があり、それが影響していることを紹介しました。つまり、家事や育児が主な仕事である女性は家や村に残り、同じく家や村に残っている他の女性と1日の大半を過ごします。女性は、一緒に過ごす他の女性の気持ちや真意を察することができなければ、心地よく1日を過ごすことができなかったわけです。
それに対して男性の場合は、猟に出る。基本的に猟は1人で行うので、相手の気持ちを察する必要はありません。また、もし仲間と一緒に猟をするにしても、リーダー的存在の男性の指示に従う必要があります。つまり、男性は単独行動、もしくは明確な指示に従う団体行動を昔から行ってきており、それが影響して「察するのが苦手」となっているのです。男性が誰かの感情を察することが苦手だったり鈍かったりするのも、同じ理由からでしょう。
ですが、こと恋愛に関して考えてみた場合、男性が鈍いというのは必ずしもあてはまらないかもしれません。というのも、以前COBS ONLINEが男性288名に行った「興味のない相手から好意を示されたときにとる行動ランキング」の結果を見ると、興味のない相手から好意を示されたときにとる行動として、第1位は「好意に気付かないふりをする」(26.4%)、第2位は「恋人や好きな人がいることをアピールする」(18.8%)、第3位は「まんざらでもないから、しばらく様子をみる」(18.1%)という結果になっていました。
つまり、「好意に気付かないふりをする」も「まんざらでもないから、しばらく様子をみる」というのも、実際は女性の感情に気づいているということがわかります。気づいてながら、知らないふりをしているだけなのです。もしかしたら、男性は鈍いのではなく、鈍いふりをしているだけなのかもしれません。男性は鈍いと思っていると、大きな間違いをおかしてしまうかもしれませんね。
ただ、男性が女性の気持ちに本当に気づいていないのか、本当は気づいているけれどスルーしているだけなのか、といったことは別として、女性はさりげなさ過ぎるアピールをして「私の気持ち、気づいてよ」と思うのではなく、男性がわかりやすいように気持ちを伝える努力も、コミュニケーションとしては大切なことだと思います。
http://news.infoseek.co.jp/article/mynavi_1123555
……………
自分だけじゃなかった! 30代以降の「男性が感じる衰え」TOP5- nikkanCare.ism(2015年2月2日17時11分)
みなさんは、仕事や私生活の中で心や身体の「衰え」を感じること、ありますか?
30代を過ぎると体力や身体のはたらきが衰え、10~20代の頃とは生活スタイルが変わってくると思いますが、「自分だけこんなに衰えているのでは?」と不安になったりしませんか?
実はその悩みや実感は、あなただけではないかもしれません。『マッサージン』編集部が30歳~54歳の男性98名を対象に行った「男性が感じる衰え」の調査結果から、30代以降の男性が感じる「衰え」TOP5をご紹介します。
■第5位:食欲
第5位は“食欲”。「脂っこいものが喉を通らなくなった」、「和食が好きになった」、「1日1食で十分という日もある」などの意見があがりました。
代謝が下がる30代以降こそ、代謝を高めたり筋肉や骨を維持したりするための栄養が必要になりますが、そもそも食べる元気が出ない、というのが悩みの種でしょうか。
■第4位:視力・頭脳
次に多かったのが日常生活での“頭の回転”の衰え。「いきなり視力が落ちて、今じゃメガネが不可欠になりました」、「小さい文字を読むのに苦労する」、「本の内容がなかなか入ってこない、集中力が下がったのかも」などの意見があがりました。
「“アレなんだっけ?”と言う事が多くなった」という意見に賛同できる人が多いかもしれません。
■第3位:肌・体型
第3位には“見た目”で感じる衰えがランクイン。「鏡を見て、“うわあ老けたなぁ”と思った」、「お腹が出てきてしまった」、「太ってしまった」、「シワが増えた」、「白髪が増えてきたし、抜ける……」などの意見があがりました。
食欲が衰えた実感がある一方で、代謝が落ちて太りやすくなったり、見た目に現れる老化現象にガッカリすることが多くなるようです。
■第2位:体調・腰痛など
やはり日々の体調は老化の実感に直結する様子。「腰の痛みとずっと付き合ってます」、「ちょっとした事ですぐ体調を崩してしまう」、「ケガの治りが悪くなっている気がする」、「マッサージ、整体通いは絶対欠かせない!」などの意見があがりました。
みなさん病院や整体に通う頻度が増えたり、思うように身体が動かなくなってしまったりするようです。
■第1位:体力
「久しぶりに運動したら、ビックリするほど疲れた」、「筋肉痛が1日遅れで来た」、「仕事終わりはすぐ眠くなるし、徹夜もそうそうに出来なくなった」、「お酒に弱くなったし二次会のカラオケもしんどくなってきた」、「疲れがぜんぜん取れない」などの意見があがりましたが、頷いている方も多いのではないでしょうか。
気持ちは若いままでも、頭で考えたイメージに身体が付いていかない!なんて経験が体力の衰えを実感させるようですね。
いかがでしたか。
やはり体力や見た目の変化は衰えの実感に直結してしまうようです。だからといって、30歳を超えたらゆったりと休んでいい、とはいかないのが悩みどころですよね。
30歳を超えてもバリバリ働き続けるためには、食生活や運動週間を見直して、体調不良に悩まされない健康的な身体づくりやいつまでも動ける体力作りをしていく必要がありそうです。
http://news.infoseek.co.jp/article/nikkancareism_55347
……………
だからいつも金欠なんだ!「なぜかお金が貯まる」考え方のクセ3つ- VenusTap(2015年2月2日21時40分)
イベントシーズンが過ぎてしばらく経つが、「浪費しすぎていまだに貧乏気分が抜けない……」という女子も多いことだろう。今からそんなふうに悶々としていては、今年の金運は暗い。もしかしたら、あなた自身のそんなネガティブな考え方がお金をブロックしているのかもしれない。
そこで今回は、海外のライフスタイルサイト『Mind Body Green』の記事を参考に、もっと“お金を引き寄せる”ためのステップを紹介しよう。
■1:自分の財政状況をしっかり把握
あなたは銀行残高を確認せず、「今月あといくら使えるか」という現実も知らんぷりして、好きなときに好きなだけお金を使っていないだろうか?
そんなことを繰り返していては、毎月お給料日前に「どうしよう、お金がない!」という悪循環に陥ってしまう。自分の財政状態をしっかり見つめないというのは、お金のトラブルに陥る人の大きな特徴だという。
まずは基本策として、自分の収支をしっかり把握し、管理することから始めたい。「お金よ入って来い……」と祈っているだけでは何も起こりはしないのだ。
■2:無駄な浪費をせず“自分のために”貯蓄
「貯金なんかすると、お金が自由に使えなくなってヤダ」というあなた。
毎日のラテや外食、アルコールやタバコ、ロクに使いもしないブランドもののバッグなどにお金を使うのと、マイホーム、旅行、結婚資金、留学資金など、実際に必要なことや本当に欲しいもののためにお金を貯めるのでは、どちらがいいだろうか?
今すぐ貯蓄に対する考えを改め、“お金を貯めるのはうれしいこと、ポジティブなこと”と考えよう。
■3:お金に対する恐怖感を見つめ、克服する
普段意識していなくても、多くの人々には“お金の欠乏に対する恐怖感”がある。「お金がなくなったらどうしよう」「離婚したら、どうやって生きていくの」「私なんて、1人じゃ絶対に暮らしていけない」などがそれだ。
自分の心にそんな恐怖感があるのはなぜだろうか? 幼少期の体験? それとも両親や先生に教えられた、お金についての“知識”を鵜呑みにしているからだろうか?
“使うお金がない恐怖”が、かえって浪費を助長しているかもしれないし、まわりへの余計な見栄でありもしないお金を使ってしまうのかもしれない。自分自身の“お金への恐怖感”を認識したら、その考え方を改めよう。自分の内面にもっと目を向けて、お金を使わなくても楽しみや喜びを与えてくれることを探すのだ。
以上、お金を引き寄せるためのステップをご紹介した。「今年こそは貧乏を脱出して、お金を貯めなきゃ」と決心したら、きちんと内面を見つめてから行動を起こすことをオススメする。年末には「こんなに貯まった」とニコニコ顔になれるよう、いまから行動を起こそう。
http://news.infoseek.co.jp/article/venustap_1091583
……………
刀ブーム到来!? 別冊宝島『日本刀』が異例の23万部突破!- ダ・ヴィンチニュース(2015年2月2日22時00分)
ブラウザゲーム『刀剣乱舞』の大ヒットの影響か、刀が今巷でブームとなりつつある。2015年1月16日(金)に発売された別冊宝島『日本刀』も、昨年発売した第1弾と合わせて累計23万部を超える異例の売れ行きだ。『日本刀』では名刀92振りが大きめのビジュアルとともにわかりやすく解説されており、日本刀の姿形を眺めるだけでもその美しさに目を奪われる。さらに秀頼・家康へと継承された「南泉一文字」を実物大で楽しめるポスターまで付いているほか、追悼企画「日本刀と高倉健」では、名優と日本刀の関係を紹介している。
第壱部「刀を詠む」では、天下三作として「藤四郎(粟田口吉光)」「正宗」「江義弘」の刀を紹介。徳川8代将軍吉宗の命で、刀剣鑑定や研磨の名家・本阿弥家の13代光忠が編纂した『享保名物帳』にある天下三作だ。各刀工につき2~3振りが一度に見比べられるのも、誰もが名を知る有名刀工たちの姿が多角的に感じられ、興味深い。そして「号(愛称)」を持つ日本刀の各刀にまつわる伝説や、多くの武将のもとをわたってきた由来などを読むと、いかに日本人が日本刀を愛し大切にしてきたかが感じられる。『利休にたずねよ』で直木賞を受賞した故・山本兼一氏の追悼コラムで、山本氏は刀の品格を「鉄の潤い」とともに感じていた。佐野美術館館長・渡邉妙子氏のインタビューでも「ヨーロッパでは金銀銅が大切にされ、鉄はいやしい金属とされているが、(中略)日本人は自然に生まれた特性を尊重する。鉄を磨き上げて鉄そのものの美しさを鑑賞する日本刀は日本人の精神性にうまくはまるものであった」といった内容がある。
考えてみれば、放っておけば錆びてしまう鉄を磨き上げ、現代にまで美しい姿で伝え続けるところに、日本人の美学があるのだろう。
「刀を感じる」の頁では、刀姿のみならず、刃文を大きい写真で見せており、鉄そのものや刃文に宿る美が感じられる。刀の鑑賞では実物を握ってみること以上のものはないが、誌面でここまで鑑賞できることは多くの人が刀を理解するうえで貴重である。
『日本刀』では拵(こしらえ:柄や鞘に施す細工)もまた大きな写真で紹介されている。雅楽の有名な場面を装飾としてあしらった華やかな大小拵や、貝殻の造形を文様として活かした洒落た脇差拵など、まさに日本の技が集結した一級の美術品である。日本人は刀だけでなく、拵までこだわり、刀を大切にしてきたことがわかる。
刀は刀匠、研師、白銀師、鞘師、鐸師、柄巻師といった職人たちが魂を込めて制作した「共同創造」の賜物である。第弐部「刀を創る」では、鎌倉から室町時代の名刀の「映り」を7世紀ぶりに再現した、現代の刀匠・河内國平氏の刀神の技を筆頭に各職人たちの技に迫っている。現代の作品を眺めると、古代からの日本の技が今に生きていることを感じ、感慨深い。
続いて第参部「刀を知る」では、上古時代の直刀から現代刀まで、各時代を象徴する刀が紹介され、刀の変容や、安綱、友成、来国俊、村正といった有名刀工とその作風について知れ、刀を詠むうえでの大きな手助けとなる。
刀の初心者もある程度の知識人も、自分なりの見方、感じ方で楽しめ、多方面から日本刀の魅力、洗練された日本人の心や美学が感じられる。「刀と神社~神との対話~」のコラムに、刀を奉納することを通し日本人は自然や神と対話してきたとあるが、そこには崇高な日本人の精神性があるように思う。それらを私たちが求めているからこそ、今この本が多くの人の手にとられているのではないだろうか。
http://news.infoseek.co.jp/article/davinci_5979
……………
あなたも家族も必読 認知症「最初の最初」この30兆候を知っておけば大丈夫 すぐに気付いて対処すれば、間に合う
現代ビジネス 2月5日(木)6時2分配信
映画を見ても泣けなくなった
手拍子がうまくできない
好きな食べ物が変わったほか
何でも「歳のせい」にしていないだろうか。そんなあなたは、すでに認知症の「始まり」に差しかかっているかもしれない。最初のちょっとした異変に気付くことが、本当の認知症にならないための第一歩だ。
.
ドアノブがうまく回せない
「高速道路のインターチェンジで降りて、トイレ休憩をしたあとのことでした。なぜ逆方向の道に入ったのか、わかりません。自宅に帰ろうと思っていた」
80代の男性はこうつぶやいた。その後、病院で受けた検査で、軽度の認知症が発覚。今回は幸いにも大事に至る前に気づいて事なきを得たが、運が悪ければ殺人者になっていたかもしれない。
いま高齢者による高速道路の「逆走」が多発している。最近では、1月19日に佐賀県の高速道路・長崎道で88歳の男性が逆走し、2人が重軽傷を負った。東日本高速道路など6社の調査によると、'11~'13年で確認された逆走運転は541件で、その約7割(370件)が65歳以上のドライバーによるもの。さらに4割ほど(200件)に認知症の疑いがあったという。
認知症を発症すると、現在の医学では残念ながら完治は望めない。しかし、「不治の病」だと思って、悲観的になることはない。
「ごく初期に発見された場合、症状を抑えたり、発症をかなり遅らせることもできます」
南魚沼市立ゆきぐに大和病院(新潟県)の院長・宮永和夫医師はこう話す。
認知症の症状には、「同じことを何度も言う」「食事をしたことを忘れる」などさまざまなものがあるが、一般的に知られているこうした症状が出たときには、すでに「手遅れ」。だが、ごく初期に起こるちょっとした異変に気付ければ、発症を防ぐことができるのだ。
「認知症は初期では検査方法もなく、医師による診断は非常に難しい」(千葉県袖ケ浦さつき台病院認知症疾患医療センター長・細井尚人医師)。つまり、医師任せではなく、「認知症の始まり」は自分自身やその家族が察知しなければならない。患者や家族、専門医らの証言をもとに、認知症の「最初の最初」に出てくる30の兆候を紹介していこう。
愛知県に住む64歳の男性は、ペットボトルのお茶を飲もうとしたとき、こんな違和感に気付いた。
「蓋を開けようとしても、うまく回せないんです。何度やってもできず、妻に頼んで開けてもらいました。瓶ビールの蓋を栓抜きで開けることはできましたし、握力が落ちたのとは違う感覚でした」
これは、認知症になる前段階の軽度認知障害(MCI)によく見られる兆候だという。日本認知症学会の専門医でおくむらクリニック(岐阜県)院長の奥村歩医師が解説する。
「認知症の初期では、視空間認知機能が低下します。そのため、初期の段階から『回転』を必要とする動作に弱くなるんです。蓋を回して開けるのが苦手になるだけでなく、靴ひもが結べなくなる、引き戸は開けられるけどドアノブがうまく回せなくなる、ネクタイを結ぶのに時間がかかる、といった症状も出てきます」
このほか、自動販売機にうまくおカネが入れられない、道に迷いやすくなる、電話をかけるのに時間がかかる、といった兆候が出てくることもある。認知症になると、基本的には症状を自覚できなくなる。まず一緒に暮らしている家族が異変に気づくことが多いのだが、ごく早期に限れば、自分で気づくことができる。
2つのことを同時に行うことができなくなる、というのも日常生活で気づく症状の一つだ。認知症予防のための「脳リフレッシュ教室」などの活動を行う脳リハビリネットワーク代表の清水孝俊氏が言う。
「たとえば、歌いながらリズムに合わせて手を叩けない、といったことが起きます。若い頃は意識せずとも普通にできていたことが、脳の機能が低下することで、できなくなってしまうのです」
他にも、散歩しながら簡単な暗算ができない、電話をしながらメモを取るのが困難、といった同時の動作が苦手になってきたら、それは認知症のサインだ。
イライラすることが増えた
埼玉県に住む74歳の斉藤啓子さん(仮名)は、3歳年上の夫との会話の途中でこんな異変を感じた。
「会社員の息子が、中国に転勤することが決まったと聞き、夫に伝えたんです。空気も悪いし食べものなども心配で、相談したかったのですが、『そうか』と生返事しかせず、話の途中でふいに立ち上がって、自分の部屋へ行ってしまった」
こうしたことが何度か続いたので、啓子さんは夫を病院へ連れて行こうとした。
「そうしたら、『俺はどこも悪くない! 』と突然怒鳴ったんです。温厚な性格で、声を荒らげることなどない人だったので、驚きました」
この夫の行動にも、初期の兆候が見られるという。『社会脳からみた認知症』(講談社ブルーバックス)の著者で、勤医協中央病院(北海道)名誉院長の伊古田俊夫医師が解説する。
「まず、大切な話をしているのに聞き流したり無視するというのは、他人に関心を持つ脳の働きが低下していると考えられます。数分であれば相手の目を見て話ができるのですが、すぐに関心が薄れてしまう。認知症の初期には、何かに取りつかれたような状態や心だけ別の世界に行ってしまったような状態が認められることがあります。
また、すぐにカッとして怒鳴るのも特徴的です。怒る相手は赤の他人ではなくて、一緒に住んでいる妻や嫁、息子や娘など身近な人に対してのことが多い。怒りを抑える脳の機能が働かなくなってしまうのです」
最近、ボーっとする時間が増えたり、ちょっとしたことにイライラする、何事にもやる気がなくなるといったことはないだろうか。
もちろん認知症では、記憶への影響も出てくる。ただし、勘違いしがちだが、認知症による記憶障害は「忘れる」ことではないのだという。
「じつは『忘れる』というのは誤解で、過去に覚えたことが記憶から失われるのではなく、『新しいことが記憶できない』というのが認知症の記憶障害なのです。ヒントを出して思い出せるのは『単なるもの忘れ』ですが、認知症の症状では、最近体験した出来事でも、記憶からすっぽり抜け落ちてしまいます」(前出・奥村医師)
こうした認知症の初期症状は、酒を飲んで泥酔したときの状態と同じだという。奥村医師が続ける。
「認知症では、短期記憶をつかさどる脳の海馬という部分の機能が低下しますが、アルコールも海馬の働きを麻痺させてしまう。同じことを何度も繰り返し言ったり、どうやって家に帰ったか覚えていなかったりするのは、認知症の疑似体験とも言えます」
ただし、「単なるもの忘れ」だとしても、油断はできない。「もの忘れは脳の疲労からくる警告であり、無視し続けると、後に認知症になる可能性が高まる」(奥村医師)からだ。隣の人の名前が出てこない、買い物に行ったのに何を買いに来たか忘れた、携帯をどこに置いたかわからなくなる……こんな単純なもの忘れが、一日に4~5回起きているようなら注意が必要だ。
歳を取ると涙腺が弱くなるというが、認知症になるとその通説は当てはまらないらしい。
「他人の心の痛みを自分のことのように感じる共感、同情の感情も薄れてきます。感動する映画を見ても泣けなくなるということもあるでしょう」(伊古田医師)
たとえば大きな災害や事故で多数の犠牲者が出たというニュースをテレビで見ても、何も感じないようになってしまう。
話のオチがわからない
それだけでなく、感情の変化はこんなところにも表れる。伊古田医師は、小学校で教師をしている50代の男性からこんな相談を受けた。
「その方は、子供たちが何を考えているのかわからなくなった、とおっしゃいました。毎朝の朝礼では、子供たちの表情を見ながら、いつもと違った様子の子がいないかをチェックしていたそうですが、あるときから気に掛けることがなくなったそうです。同僚から『先生が変だ、と子供たちが騒いでいる』と指摘されて自覚したそうです。
脳の扁桃体という部分の働きが低下すると、人の感情がわからなくなってしまいます。笑っている人や怒っている人の写真を見せても、どんな感情を表しているか理解できなくなってしまうのです」
これはつまり、「空気が読めなくなる」と言い換えてもいい。不機嫌そうな妻の表情を読めずに夫婦ゲンカが頻繁に起こるようになったり、身近な人との人間関係がぎくしゃくし始めることが増えたら、要注意だ。皮肉やダジャレが通じない、落語や漫才を聞いてもオチが理解できず笑えなくなる……ということもある。
高齢者が詐欺にひっかかりやすいのも、脳の機能が低下して、空気が読めなくなっているせいだ。
「警戒心が薄れるんです。相手の表情やしゃべり方、しぐさなどから心の内を察することができなくなってしまうので、騙されやすくなってしまいます」(伊古田医師)
大阪府に住む深江恵美子さん(72歳・仮名)は、夫がここ数年で人が変わったようになっていくのを感じていた。
「現役時代は、休日も何かしら予定を入れて忙しくしていましたし、いつもオシャレな人でした。けれど、65歳で仕事を辞めてからは、いつもゴロゴロしてばかりいました。そのうち、起きてからも着替えずに一日中寝間着のまま過ごしたり、身なりに気を使わなくなった。
これまで40年以上、働いてきたんだから、ゆっくりさせてあげたいと思っていたのですが、ここ最近、さらに様子がおかしくなってきたんです。お酒が好きで甘いものは一切口にしなかったのに、大福や羊羹など甘いお菓子を好んで食べるようになった。それも一日に1つや2つじゃなく、10個近く食べることもあるんです」
恵美子さんの夫も、まさに認知症のごく初期の典型的なケースを辿っている。「もの忘れ」とは異なる症状なので、うつ病などと間違えられることもあるが、何事にも興味がなくなり、だらしなくなる、というのも初期に現れてくる。
「食べものの好みが変わることもあります。一般的に、辛いものや甘いもの、しょっぱいものなど味の強いものが好きになります。これまで嫌いだったものをよく食べるという傾向が出て来たら、少し気にしたほうがいいかもしれません」(伊古田医師)
こう対処すれば、元に戻る
近年、日本で認知症が急増しているのは、高齢化というだけでない「理由」が存在しているという。
「『認知症を増やす病気』と『認知症を増やす生活様式』が広がっているという要因もあるのです。生活習慣病は、主に高血圧症と糖尿病。高血圧のある人は、ない人に比べて2~3倍、糖尿病の人は2倍ほど認知症になりやすいと言われています。他には、うつ病にかかったことのある人は、認知症のリスクが2~3倍というデータもあります」(伊古田医師)
さらには、性格も「認知症になりやすさ」に関係している。
「社交的で、さまざまな人とお付き合いができる人は、脳への刺激も多いので認知症になりにくいんです。逆に、人付き合いが悪く内にこもるタイプの人は危ない。
とくに、仕事一筋でやってきたサラリーマンが定年退職したとたん、何もせずに家に居る時間が増えるというパターンは、認知症の始まりと言えます」
前出の宮永医師はこう指摘する。脳を刺激する仕事、たとえば指先を常に動かす画家や音楽家などは認知症になりにくいことが明らかになっているという。
これまで述べてきたような認知症の「最初の最初の症状」に気づくことが第一歩。あとは、健康な脳になるための対策を取るだけだ。
「軽度認知障害の場合、放っておくと5年以内に過半数の人が本当の認知症に移行する危険性を持っています。その一方で、適切に対応すれば、進行を阻止でき、正常な状態に戻る可能性もあるんです」(前出・伊古田医師)
では「兆候」に気づいたとき、どんな対策を取ればいいのだろうか。自宅ですぐに始められるおすすめのものは、次の3つだ。
(1)一日30分以内の昼寝
「筑波大の研究で、30分以内の短い昼寝をする習慣がある人は、そうでない人に比べて認知症の発症が75%に減少し、記憶テストの成績もアップしたという結果が出ています」(前出・奥村医師)
(2)簡単な計算問題を解く
「難しい計算ではなく、小学校1~2年生がやるようなレベルの計算ドリルを1回10分間、日に2回ほどすると効果的です」(前出・伊古田医師)
(3)新聞の音読
「音読は脳に良い刺激を与えます。社説などを毎日声に出して読むのがいいでしょう」(伊古田医師)
このほか、適度な運動や食事の改善も効果的。緑茶やコーヒー、トマトなどに含まれるポリフェノール、イワシなどの青魚やオリーブオイルに含まれる不飽和脂肪酸の摂取は認知症の発症を抑制することがわかっている。
「風邪にかからないよう、身体の免疫力を高めるのと同様に、認知症にならないために脳の免疫力を高めると考えればいい。我々には、認知症から守ってくれる脳自体の免疫力が備わっています。その力をアップさせることは誰にでもできるのです」(前出・奥村医師)
認知症をむやみに恐れる必要はない。身近な人や自分自身にここで挙げた30の兆候に当てはまるものがあった人も、今から対処しておけば大丈夫だ。
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150205-00041899-gendaibiz-bus_all
……………
「頭痛」「腰痛」慢性的な体調不良に効く呼吸法
2015年2月5日 20時0分
新刊JPニュース
仕事をしているうちに、いつの間にか慢性化してしまった「目の疲れ」「頭痛」「腰痛」……。本当に辛いものですよね。
ほとんどの場合、こういった不調の原因は「体の筋肉の凝り」だと考えがちですが、では、その「体の筋肉の凝り」にはどんな原因があるのでしょうか。
「同じ姿勢を保ち続けているから」「血行が悪いから」など、これにはさまざまな意見があります。そんな中、体内に充分に酸素が行きわたっていない「酸欠」を原因に挙げているのが、『弱ったカラダが1分でよくなる!』(日本文芸社/刊)の著者、今野清志さんです。
■「ねこ背」「運動不足」が酸欠のもと!
普段から呼吸で酸素を吸いこんでいるのに酸欠になるのには、こんな理由があります。
今野さんによると、現代人は「運動不足」や「ねこ背」などによって「深い呼吸」をすることが少なくなり、その結果呼吸から取り込む酸素の量が不足しがちなのだとか。しっかり酸素が行きわたった筋肉は緊張がゆるんでやわらぐのですが、体内に酸素を取り込む量が少ないと、これがうまくいきません。
■酸欠にならない呼吸法は、○○してから息を吸うこと
では酸欠を回避する方法にはどんなものがあるのでしょうか。
一番にくるのはやはり「呼吸」です。
呼吸によってしっかりと酸素を吸いこむことが必須なのですが、呼吸は「吸う」と「吐く」でワンセットですので、「吸うこと」だけを意識してもダメ。「しっかり吸う」ためには「しっかり吐く」ことがポイントです。
まず大きく吐いてから吸うというクセをつけると、意識せずとも深い呼吸ができるようになります。
■血流は自分で改善できる
また、呼吸によって吸った酸素を「効率よく体内に行きわたらせる」というのも酸欠を防止するためには欠かせません。
ご存じのとおり、酸素は血中のヘモグロビンによって全身に運ばれていきますから、「血行」は酸欠防止に大きな役割を果たします。
20代~40代の血行不良というのは、よく言われるような「血液がドロドロになっている」というのではなく、「血管の収縮」によって起こるケースが多いので、「ゆっくりと入浴する」「簡単なマッサージをする」といったことで解消できます。
本書には、「酸素」という観点から、体の不調の原因を探り、その対策を授けてくれます。
「あるのが当たり前」な酸素だけに、欠乏しているとあらわれるさまざまな悪影響には、あまり目がいきません。
「なんとなく体調が悪い」「漠然としただるさがある」という方は、試してみると元気を取り戻すきっかけになるかもしれませんよ。
(新刊JP編集部)
http://news.livedoor.com/article/detail/9755354/