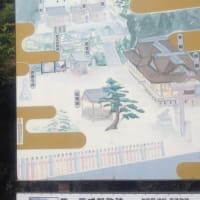もうすぐ運動会で、Kちゃんは10人ピラミッドの一番上になったらしいです。私は心配だから3段目の土台でもいいかも?と思ったけど、kちゃん頑張ってるようで運動会、楽しみです。kちゃんは99年生まれで今年の2月が来ると12才になります。もう小学校を卒業かぁと思うと早いです。あんなに大きかったランドセルも6年間使用してぺったんこ?になりつつあります。
子供の成長を感じると共にKちゃんが生まれた年の4月14日にあった山口県の光市母子殺害事件を思い出します。kが2ヶ月で地元で出産し実家から帰って間もない頃でした。亡くなった夕夏ちゃんは、Kちゃんと9ヶ月しか変わらず、家で子供と2人で帰ってくる旦那を待っている時間が長い主婦には、他人事とは思えない事件でした。私も水質検査と言われて、ドアを開けたことがありましたが実際は浄水器の訪問販売だったりして。
事件の詳細は述べるのは、控えようと思いますが、押し入から遺体が発見され第一発見者はご主人でした。
亡くなった弥生さんと洋さんの共著となっている本「天国からのラブレター」原作の映画を以前、観ました。
洋さんと弥生さんの出会いから、結婚と出産までの物語で十八歳で知り合った二人の純粋にお互いを愛して幸せな家庭を築いていた様子がわかります。
小学校の高学年の時に、お父さんが亡くなり母子家庭で妹さんとお母さんとの3人で暮らしていた、弥生さんはお母さん思いのしっかりした、優しい方だったようです。
洋さんは、真面目そうで一途な感じの青年で、小さい頃から持病を抱えながらも懸命に生きて来られて小倉で出会った二人は、その後、広島大に進学した洋さんと遠距離恋愛を続けて妊娠し、学生の身で結婚にまで辿りついたのでした。
結婚には当初、お父さんは反対していて堕胎をすすめましたが、就職もして孫の顔を見てからは理解を示してくれて、やっと掴んだ幸せを喜んでいて、これからという時に起こった事件で家族が一緒に生活をしたのはわずか7ヶ月でした。
映画を観ていて、弥生さんの明るさ、優しさ、素朴な強さが持病を持つ洋さんに前向きに生きる支えになっていたかのようでした。弥生さんも母子家庭で得られなかった、家庭の暖かさを洋さんと結ばれたことで愛情に包まれて、思い出したようなそんな二人に見えました。
『天国からのラブレター』は映画と本では、内容が随分ちがうようで、手紙に編集が施されていないので、未成年時の飲酒や法に触れる行為、性への描写、そしてふたりの共通の友人が実名で挙げられ、彼女らのプライバシーの暴露など、不特定多数の人物の目に触れる書籍としてはかなり激しい内容とういうことで、これに対しては批判的論評もあるそうです。
映画は若い二人の青春時代らしい恋物語となっています。本の中で弥生さんが、洋さんを狂おしいほど恋してやまないのは、お父さんと早くに別れた背景もあるように感じます。
自分を可愛いと思って愛してくれる男性への惜しみない愛情と甘えたい、守られたい心理が伺えます。それが、第3者から観ると異様にも感じられるかもしれませんが、本当に可愛い方だったのでしょうし、それを可愛いと思えた本村さんの広い心も伺えます。
この事件に限らず、不慮の事故や事件で愛する家族を亡くした人にとって、突然の別れは頭ではわかっていても、持って行きようがない悔しさ・切なさ・悲しみが心に、残ってしまいます。
それは今まで、愛する家族がいた風景はそのまま、時間は流れるのに「家族だけ」がいないからですよね。一緒にすごした家の中には、愛する人の使っていた洋服や食器、いつも座っていた場所もあるのにでも、その人の笑顔も声も息使いも聞こえず、記憶の中の話し声と笑顔やしぐさだけが脳裏によみがえり、その無邪気な姿や景色が頭の中で何度も浮かぶ度に「もういないんだ」と一人、部屋で我に返り悲しみと向き合うことになるからだと思います。
夕夏ちゃんの名前は夏の夕陽からとったのだそうです。本村さんはきっと夕暮れを見るたびに夕夏ちゃんへ思いを馳せたでしょう。
何故、愛する人が、事故や事件に遭わなくていけなかったのか教えてほしいと思ったり、犯人と出会ったことがただ、不運だとしたら「あの時、あの場所に自分がいれば、自分が守ってあげられることができたなら」その不運を避けられたのに、それもできなかったことで自分を責めたかもしれないし、命を奪われたのに、奪った方が刑務所内で生きていることに悔しい思いを抱いたことでしょう。2人の大切な家族を失い、その後の遺体の扱いを聞くと耳を塞ぎたくなり、第一発見者であった本村さんはいたたまれない気持ちだったにちがいありません。
事実が明るみになると、犯人のした愛する人に対する犯行の数々がまた、心に波をよんで、犯人が存在しなければ、この不幸も存在しなかった。本当なら家族は僕の傍らにいて、笑顔で笑っていたかもしれない。そんな思いと長く向き合っていたのかもしれません。
そして自分のできることは、愛する人の被害者遺族として犯罪被害者の権利を守るために、二度とこのような事件が起きないように、していくためにも全国犯罪被害者の会を設立、幹事にも就任され、そしてさらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力しました。
愛する家族のためにそう願うしかなかった。そう願うと同時に犯人を許せない気持ちもあっただろうし、本当は心のどこかで、こんな気持ち膨らませるのは、よくないかもって思っていたかもしれません。(本村さんは1、2審で起訴事実を認め、反省していると情状酌量を求めていたそうです。その後の少年の知人に宛てた手紙が更に遺族感情を逆なでしたのですね。)
自分がその道を歩むと、どんどん厳しい気配を背負うことを感じていたけど、その気持ちを忘れると愛する家族の存在も消えそうで、それが辛かったのではないでしょうか。犯人を糾弾することが家族の存在を守る唯一の手立てだと思っていたように感じます。
本村さんは自分も二人の後を追って自殺も考えられたこともあったそうです。
まだお若い本村さんですから、「もう、自分の幸せを考えても…」と周囲に言われたこともあったでしょう。「きっと、弥生さんもあなたの幸せを願っているよ」と言われても「あんな酷い死に方したんだよ。やりきれないんだよ」と悲しみや悔しさ、が襲って来て、本当は犯行を犯した者が背負うはずの罪を、ご主人が「幸せにしてあげられなかった」という思いから、背負って生きているそんな風に感じました。また、弥生さんのご実家のお母さんや妹さんのことを思うと、その責任感の強さからもう一度、結婚などと、今までは考えられないのかもしれません。
母親と姉妹だけで細々と生きて来たお家の不幸は、弥生さんを産んだお母さんには特に辛いものだったのではないかと想像します。弥生さんが優しい娘さんであったからこそ、嫁いでもその存在の大きさは本村さんと変わらずあったことでしょうし、本村さんは弥生さんを幸せにすることがお義母さんへの孝行であると、結婚する時に思ったように感じます。妹さんも事件当時は高校3年生ぐらいでしょうか?妹にとってお姉さんは小さいお母さんです。お母さんがいない時は、お姉さんが食事の用意をしてくれたり、一緒に家事をしたりして、結婚するまではお母さんより一緒にいる時間が長かったかもしれません。
弥生さんと本村さんが交わした手紙は全部で71通だったそうです。今の時代の携帯でボタンを押してポンと飛ぶメールとちがって、すごく情感と会いたいのに会えないもどかしさが伝わってくる手紙がたくさん劇中に出てきたり、結婚してからも家庭内で交換日記を書くなど筆まめなお二人だったようです。 (つづく)
子供の成長を感じると共にKちゃんが生まれた年の4月14日にあった山口県の光市母子殺害事件を思い出します。kが2ヶ月で地元で出産し実家から帰って間もない頃でした。亡くなった夕夏ちゃんは、Kちゃんと9ヶ月しか変わらず、家で子供と2人で帰ってくる旦那を待っている時間が長い主婦には、他人事とは思えない事件でした。私も水質検査と言われて、ドアを開けたことがありましたが実際は浄水器の訪問販売だったりして。
事件の詳細は述べるのは、控えようと思いますが、押し入から遺体が発見され第一発見者はご主人でした。
亡くなった弥生さんと洋さんの共著となっている本「天国からのラブレター」原作の映画を以前、観ました。
洋さんと弥生さんの出会いから、結婚と出産までの物語で十八歳で知り合った二人の純粋にお互いを愛して幸せな家庭を築いていた様子がわかります。
小学校の高学年の時に、お父さんが亡くなり母子家庭で妹さんとお母さんとの3人で暮らしていた、弥生さんはお母さん思いのしっかりした、優しい方だったようです。
洋さんは、真面目そうで一途な感じの青年で、小さい頃から持病を抱えながらも懸命に生きて来られて小倉で出会った二人は、その後、広島大に進学した洋さんと遠距離恋愛を続けて妊娠し、学生の身で結婚にまで辿りついたのでした。
結婚には当初、お父さんは反対していて堕胎をすすめましたが、就職もして孫の顔を見てからは理解を示してくれて、やっと掴んだ幸せを喜んでいて、これからという時に起こった事件で家族が一緒に生活をしたのはわずか7ヶ月でした。
映画を観ていて、弥生さんの明るさ、優しさ、素朴な強さが持病を持つ洋さんに前向きに生きる支えになっていたかのようでした。弥生さんも母子家庭で得られなかった、家庭の暖かさを洋さんと結ばれたことで愛情に包まれて、思い出したようなそんな二人に見えました。
『天国からのラブレター』は映画と本では、内容が随分ちがうようで、手紙に編集が施されていないので、未成年時の飲酒や法に触れる行為、性への描写、そしてふたりの共通の友人が実名で挙げられ、彼女らのプライバシーの暴露など、不特定多数の人物の目に触れる書籍としてはかなり激しい内容とういうことで、これに対しては批判的論評もあるそうです。
映画は若い二人の青春時代らしい恋物語となっています。本の中で弥生さんが、洋さんを狂おしいほど恋してやまないのは、お父さんと早くに別れた背景もあるように感じます。
自分を可愛いと思って愛してくれる男性への惜しみない愛情と甘えたい、守られたい心理が伺えます。それが、第3者から観ると異様にも感じられるかもしれませんが、本当に可愛い方だったのでしょうし、それを可愛いと思えた本村さんの広い心も伺えます。
この事件に限らず、不慮の事故や事件で愛する家族を亡くした人にとって、突然の別れは頭ではわかっていても、持って行きようがない悔しさ・切なさ・悲しみが心に、残ってしまいます。
それは今まで、愛する家族がいた風景はそのまま、時間は流れるのに「家族だけ」がいないからですよね。一緒にすごした家の中には、愛する人の使っていた洋服や食器、いつも座っていた場所もあるのにでも、その人の笑顔も声も息使いも聞こえず、記憶の中の話し声と笑顔やしぐさだけが脳裏によみがえり、その無邪気な姿や景色が頭の中で何度も浮かぶ度に「もういないんだ」と一人、部屋で我に返り悲しみと向き合うことになるからだと思います。
夕夏ちゃんの名前は夏の夕陽からとったのだそうです。本村さんはきっと夕暮れを見るたびに夕夏ちゃんへ思いを馳せたでしょう。
何故、愛する人が、事故や事件に遭わなくていけなかったのか教えてほしいと思ったり、犯人と出会ったことがただ、不運だとしたら「あの時、あの場所に自分がいれば、自分が守ってあげられることができたなら」その不運を避けられたのに、それもできなかったことで自分を責めたかもしれないし、命を奪われたのに、奪った方が刑務所内で生きていることに悔しい思いを抱いたことでしょう。2人の大切な家族を失い、その後の遺体の扱いを聞くと耳を塞ぎたくなり、第一発見者であった本村さんはいたたまれない気持ちだったにちがいありません。
事実が明るみになると、犯人のした愛する人に対する犯行の数々がまた、心に波をよんで、犯人が存在しなければ、この不幸も存在しなかった。本当なら家族は僕の傍らにいて、笑顔で笑っていたかもしれない。そんな思いと長く向き合っていたのかもしれません。
そして自分のできることは、愛する人の被害者遺族として犯罪被害者の権利を守るために、二度とこのような事件が起きないように、していくためにも全国犯罪被害者の会を設立、幹事にも就任され、そしてさらに犯罪被害者等基本法の成立に尽力しました。
愛する家族のためにそう願うしかなかった。そう願うと同時に犯人を許せない気持ちもあっただろうし、本当は心のどこかで、こんな気持ち膨らませるのは、よくないかもって思っていたかもしれません。(本村さんは1、2審で起訴事実を認め、反省していると情状酌量を求めていたそうです。その後の少年の知人に宛てた手紙が更に遺族感情を逆なでしたのですね。)
自分がその道を歩むと、どんどん厳しい気配を背負うことを感じていたけど、その気持ちを忘れると愛する家族の存在も消えそうで、それが辛かったのではないでしょうか。犯人を糾弾することが家族の存在を守る唯一の手立てだと思っていたように感じます。
本村さんは自分も二人の後を追って自殺も考えられたこともあったそうです。
まだお若い本村さんですから、「もう、自分の幸せを考えても…」と周囲に言われたこともあったでしょう。「きっと、弥生さんもあなたの幸せを願っているよ」と言われても「あんな酷い死に方したんだよ。やりきれないんだよ」と悲しみや悔しさ、が襲って来て、本当は犯行を犯した者が背負うはずの罪を、ご主人が「幸せにしてあげられなかった」という思いから、背負って生きているそんな風に感じました。また、弥生さんのご実家のお母さんや妹さんのことを思うと、その責任感の強さからもう一度、結婚などと、今までは考えられないのかもしれません。
母親と姉妹だけで細々と生きて来たお家の不幸は、弥生さんを産んだお母さんには特に辛いものだったのではないかと想像します。弥生さんが優しい娘さんであったからこそ、嫁いでもその存在の大きさは本村さんと変わらずあったことでしょうし、本村さんは弥生さんを幸せにすることがお義母さんへの孝行であると、結婚する時に思ったように感じます。妹さんも事件当時は高校3年生ぐらいでしょうか?妹にとってお姉さんは小さいお母さんです。お母さんがいない時は、お姉さんが食事の用意をしてくれたり、一緒に家事をしたりして、結婚するまではお母さんより一緒にいる時間が長かったかもしれません。
弥生さんと本村さんが交わした手紙は全部で71通だったそうです。今の時代の携帯でボタンを押してポンと飛ぶメールとちがって、すごく情感と会いたいのに会えないもどかしさが伝わってくる手紙がたくさん劇中に出てきたり、結婚してからも家庭内で交換日記を書くなど筆まめなお二人だったようです。 (つづく)