(前回の続き。blog表示では上下逆になるので、読みにくいのは御容赦を。)
一方、楽天の場合は、ちょっと様相が異なります。
同社の起業ビジネスであり、現在も中心であるビジネスモデルは、ECを行う小売店や卸売業者に対して、ECシステムをネット・サービスとして提供するものです。
そのビジネスにおいて同社は、米BUY.COMやタイTARAD.COMといった海外の同業他社を買収することで、成長を図る戦略を打ち出しました。
これまでは、国内においてチャネルとその上で販売するコンテンツを拡大する成長戦略を採ってきた同社ですが、コア・ビジネスを海外展開することで、その“壁”を乗り越えようとするものであろうと評価できます。
そうした拡張戦略の中で、ECシステムを国内の“楽天市場”と海外の各ECインフラ・サービスで共用できれば、単位コストの削減という形で“規模の利益”を追求できます。
そのためには、これまでのECインフラ事業で国内顧客のみに対応してきたSEやサポート・スタッフに、海外の小売業者や卸売業者への対応が求められることになります。
今後有り得る、海外に拡げたチャネルを介してコンテンツを販売する“次の一手”を考えると、ECインフラ・サービス以外の分野においても、英語が使えるようにしておいて損はないでしょう。
従って同社の場合は、事業全体にわたって英語の重要性が高まったことから、英語の公用語化の持つ意味は大きいと言うことができます。
とはいえ、その必要性が社内に対して十分説明されているかというと、“中のヒト(といっても在米子会社出向中の方)”のblogを拝見すると、必ずしもそうでない状況が見てとれます。
三木谷社長ご自身は、とても優秀な方であることが、各種メディアにおける露出から推測されます。
しかし、もうちょっと社内全体に戦略ベースの共通認識を“下ろして”いかないと、社員の反発による求心力低下を招きかねないリスクがあります。
結果として同社の場合は、英語公用語化は必要であったけれども、その実施の有り様が拙速に過ぎたと言えるでしょう。
いずれにせよ、日本国内の市場が縮小傾向(≒デフレ傾向)にある限り、非製造業においても、企業による海外への拡大を求める動きは続くでしょう。
ワタシ自身も、もうちょっと英語力を上げないといけないと思ってはいるのですが…(汗
 貴方の“1日1クリック”を是非。
貴方の“1日1クリック”を是非。 もヨロしく!
もヨロしく!
一方、楽天の場合は、ちょっと様相が異なります。
同社の起業ビジネスであり、現在も中心であるビジネスモデルは、ECを行う小売店や卸売業者に対して、ECシステムをネット・サービスとして提供するものです。
そのビジネスにおいて同社は、米BUY.COMやタイTARAD.COMといった海外の同業他社を買収することで、成長を図る戦略を打ち出しました。
これまでは、国内においてチャネルとその上で販売するコンテンツを拡大する成長戦略を採ってきた同社ですが、コア・ビジネスを海外展開することで、その“壁”を乗り越えようとするものであろうと評価できます。
そうした拡張戦略の中で、ECシステムを国内の“楽天市場”と海外の各ECインフラ・サービスで共用できれば、単位コストの削減という形で“規模の利益”を追求できます。
そのためには、これまでのECインフラ事業で国内顧客のみに対応してきたSEやサポート・スタッフに、海外の小売業者や卸売業者への対応が求められることになります。
今後有り得る、海外に拡げたチャネルを介してコンテンツを販売する“次の一手”を考えると、ECインフラ・サービス以外の分野においても、英語が使えるようにしておいて損はないでしょう。
従って同社の場合は、事業全体にわたって英語の重要性が高まったことから、英語の公用語化の持つ意味は大きいと言うことができます。
とはいえ、その必要性が社内に対して十分説明されているかというと、“中のヒト(といっても在米子会社出向中の方)”のblogを拝見すると、必ずしもそうでない状況が見てとれます。
三木谷社長ご自身は、とても優秀な方であることが、各種メディアにおける露出から推測されます。
しかし、もうちょっと社内全体に戦略ベースの共通認識を“下ろして”いかないと、社員の反発による求心力低下を招きかねないリスクがあります。
結果として同社の場合は、英語公用語化は必要であったけれども、その実施の有り様が拙速に過ぎたと言えるでしょう。
いずれにせよ、日本国内の市場が縮小傾向(≒デフレ傾向)にある限り、非製造業においても、企業による海外への拡大を求める動きは続くでしょう。
ワタシ自身も、もうちょっと英語力を上げないといけないと思ってはいるのですが…(汗











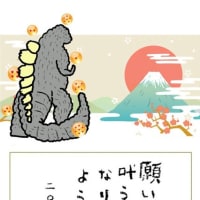
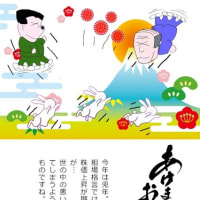

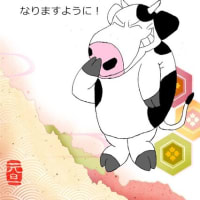
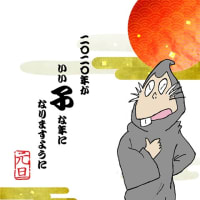

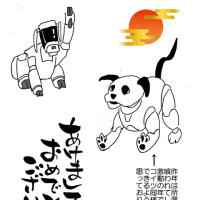
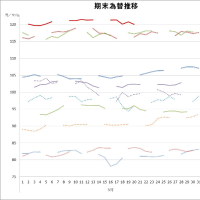
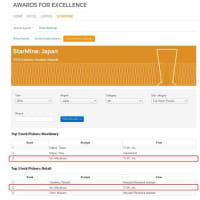
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます