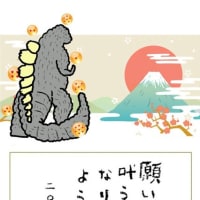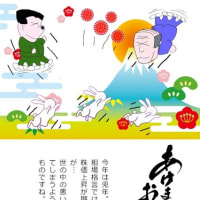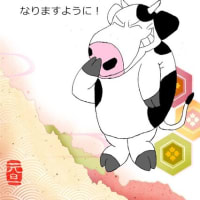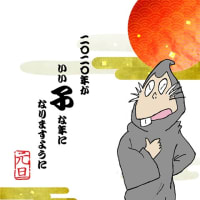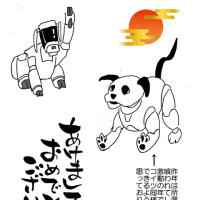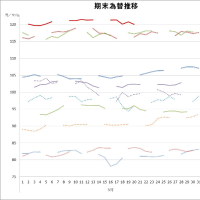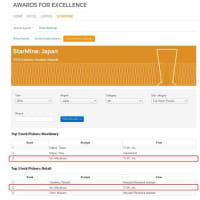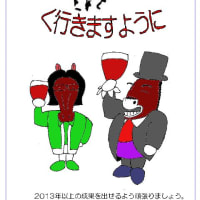米国における地銀の破綻が止まりません。今年に入って既に9件の地銀が破綻し、2008年以来の地銀破綻件数は174となりました。(WSJが見られない方はコチラをどうぞ)
これは、ウォルマートですらリストラせざるを得ない実体経済の状況、特に地方におけるそれが未だ回復しないことを現す、典型的な事象であると言えるでしょう。
足下の経営状況こそ弱含みなものの、2009年を通じて大きな利益を上げたウォール・ストリートの大銀行とは対照的な状況です。
これと比べると、日本の地銀が直面する危機は“ぬるま湯”的ですらあります。
バブル崩壊後、彼らが不良債権の増加に苦慮してきたのは確かです。経済状況に変化が生じるたびに「地銀再編、加速か」との声が再三再四、上がりました。
しかし、“共倒れ”を恐れてか日本の地銀各行は、完全に統合して合理化するような手段を取らず、“ゆるやかな提携”や“持株会社化”によって既存の組織を極力生かす道を選択しました。
その結果、多くの地方で「なんとかホールディングス」「かんとかフィナンシャルグループ」が林立することになったのです。
そうこうしているうちに、2006~2007年頃には不良債権問題も一段落し、同時に英米系ファンドの出資を受けて財務状況が改善されてしまい、根本的な経営改革を行う機を逸してしまいました。
信用バブル崩壊によって再度、不良債権が拡大する局面を迎え、不良債権をグループ内の有力銀行に集中して処理するスキームを通じてグループ内の各地銀の統合強化に繋がる動きもありました。
しかしそれも一部で終わってしまい、全国に拡がることはありませんでした。信用保証協会の保証枠拡大などによって、抱えるリスクは極小化されることになったのです。
米国における状況は、金融機能を大銀行に集中させようとの、ウォール・ストリートの“思惑”が現れている側面があるものと思われます。
それに対して日本は、地域における既得権益者の“思惑”が交錯することで、根本的な改革が出来なくなっている状況にあるのでしょう。
危機的な状況にあるときこそ、金融システムの抜本的な再設計を行う好機なのですが…
 ランクアップにご協力下さい。貴方の1日1クリックを是非。
ランクアップにご協力下さい。貴方の1日1クリックを是非。
これは、ウォルマートですらリストラせざるを得ない実体経済の状況、特に地方におけるそれが未だ回復しないことを現す、典型的な事象であると言えるでしょう。
足下の経営状況こそ弱含みなものの、2009年を通じて大きな利益を上げたウォール・ストリートの大銀行とは対照的な状況です。
これと比べると、日本の地銀が直面する危機は“ぬるま湯”的ですらあります。
バブル崩壊後、彼らが不良債権の増加に苦慮してきたのは確かです。経済状況に変化が生じるたびに「地銀再編、加速か」との声が再三再四、上がりました。
しかし、“共倒れ”を恐れてか日本の地銀各行は、完全に統合して合理化するような手段を取らず、“ゆるやかな提携”や“持株会社化”によって既存の組織を極力生かす道を選択しました。
その結果、多くの地方で「なんとかホールディングス」「かんとかフィナンシャルグループ」が林立することになったのです。
そうこうしているうちに、2006~2007年頃には不良債権問題も一段落し、同時に英米系ファンドの出資を受けて財務状況が改善されてしまい、根本的な経営改革を行う機を逸してしまいました。
信用バブル崩壊によって再度、不良債権が拡大する局面を迎え、不良債権をグループ内の有力銀行に集中して処理するスキームを通じてグループ内の各地銀の統合強化に繋がる動きもありました。
しかしそれも一部で終わってしまい、全国に拡がることはありませんでした。信用保証協会の保証枠拡大などによって、抱えるリスクは極小化されることになったのです。
米国における状況は、金融機能を大銀行に集中させようとの、ウォール・ストリートの“思惑”が現れている側面があるものと思われます。
それに対して日本は、地域における既得権益者の“思惑”が交錯することで、根本的な改革が出来なくなっている状況にあるのでしょう。
危機的な状況にあるときこそ、金融システムの抜本的な再設計を行う好機なのですが…