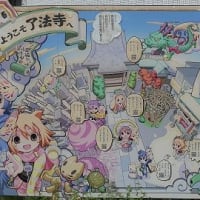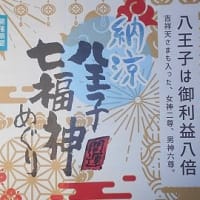前回、内藤新宿から歩いてきて下高井戸宿の入口まで到着しました。それではその続き、高井戸宿のご案内です。
その前に、高井戸宿について概要をさらっと。
高井戸宿は、甲州街道の江戸から2番目の宿場町。内藤新宿ができる前は江戸から最初の宿場町でした。甲州街道ではいくつかの宿場が宿駅業務を交代で担当する場合があり、これを合宿(あいじゅく)と呼びました、高井戸も上高井戸宿・下高井戸宿が半月交替で宿駅業務をこなす合宿でした。
江戸に近い方が下高井戸宿でその先に上高井戸宿。
1843(天保14)年の「甲州道中宿村大概帳」によると、宿場の様子は次のような感じでした。
【下高井戸宿】
・本陣…1軒
・脇本陣…なし
・旅籠屋…3軒
・宿場の家数…183軒※
・宿場の人口…890人※
※加宿の久ケ山村を含む
【上高井戸宿】
・本陣…1軒
・脇本陣…なし
・旅籠屋…2軒
・宿場の家数…168軒
・宿場の人口…787人
内藤新宿の旅籠屋57軒、茶屋50軒と比べると、その規模の小ささがわかるかと思います(内藤新宿が宿場町と遊興の地の両方の性格を持っていたこともありますが)。
【上高井戸宿模型(杉並区立郷土博物館)】

上高井戸宿の模型からもわかるように、宿場町というよりも農村の雰囲気が色濃かったようです。実際、街道沿いに厠を設置して旅人に利用してもらい、下肥を肥料として使ったそうです。
それでは、下高井戸宿を歩いていきましょう。
【下高井戸駅入口の交差点】

前回はここ、甲州街道の下高井戸駅入口の交差点まででした。この辺りが下高井戸宿の入口にあたるようです。当時を偲ぶものが何も残されていないので、推測するしかありません。
宿場の境界には棒杭が建っていたようですが、もちろん痕跡なしです。
【玉川上水跡に架かる橋】

杉並区教育委員会発行の「甲州道中高井戸宿」には、高井戸宿の復元鳥瞰図が収録されていますが、それによると、下高井戸宿に入ってすぐのところに玉川上水を渡る橋が描かれています。この橋(都道427号線)がそれかな?
【不動跡のバス停】

かつて、下高井戸宿の北側に沿って流れる玉川上水の向こう側に、修験道本覚院の不動堂がありました。1872(明治5)年に廃寺となりましたが、バス停にその名を遺しています。バス停に使用されるということは、この辺りでは不動堂跡はメジャーなのでしょうか?
【竹細工のお店】

創業から100年以上たつ竹細工のお店です。2階の竹で編んだ象がシンボル。甲州街道を歩いた人たちのブログには、たびたび登場します。
今回、一緒に歩いた会社の先輩は、麦わら帽子(竹で編んだ帽子かな?)を買いました。
【本陣・問屋場跡】

下高井戸宿の本陣、問屋場がどこにあったかは、はっきりしないようです。「甲州道中宿村大概帳」には宿の中程とだけ記されています。
杉並区教育委員会の「甲州道中高井戸宿」では、古老の話なども参考に、本陣「富吉屋」、問屋場ともに覚蔵寺の参道前のやや東側と推定しています。それに従うと、現在の甲州街道の桜上水駅北交差点辺りになるかと。
本陣は宗源寺の隣にあったというネットでの記事もよく目にしますが、出処がイマイチはっきりしないので、今回は覚蔵寺前、やや東寄り説を採りました。なお、高札場もこの辺りだったようで、この一帯が宿場の中心だったのでしょうね。
【覚蔵寺】

下高井戸宿の中ほどにある覚蔵寺は日蓮宗のお寺です。創建年代は不明ですが、もともとは真言宗の寺院だったものを、江戸時代の初期(慶長年間)に、日蓮宗に改めたそうです。
【覚蔵寺山門】

山号「清月山」の扁額がかかる山門。
覚蔵寺は日蓮上人が自ら彫ったとされる鬼子母神像が有名です。「江戸名所図会」にも由来が紹介されています。
「日蓮が処刑されそうになった時、ひとりの老女が餅を差し上げた。日蓮は大いに喜び、処刑を免れたあと自ら鬼子母神像を彫り、この老女に与えた。像は老女の末裔に伝えられてきたが、1733(享保15)年に鎌倉妙法寺の日曜に預けられた。その後、日曜はこの像ともども覚蔵寺に遷り…」
そして今に至るとのこと。
【覚蔵寺本堂】

その鬼子母神を拝めるかどうかはわかりません。お寺の方にお願いすれば拝観させていただけるのかな?
この日はそれを確認することなく、静かな境内でひと休みして、覚蔵寺を後にしました。
【宗源寺】

覚蔵寺を出て数分歩くと宗源寺です。日蓮宗のお寺で江戸時代初期、慶長年間の創建と伝わります。
【宗源寺不動堂】

先に、下高井戸宿の玉川上水の向こう側には明治に廃寺になった本覚院があり、バス停に不動堂という名前が遺っている…と書きましたが、その不動堂が、ここ宗源寺に移されています。
この不動堂、実は高井戸の地名のもとになったとも言われています。いわく、高い場所にあったお堂だから高井堂と呼ばれ、それが高井戸に転じたと。あるいは高井氏が宮司を務める神宮寺(本覚院)のお堂なので高井堂と呼ばれ、それが高井戸に転じた云々。
【不動堂前の台座・前面】

不動堂の前には、古い台座が残っています。お堂と一緒に本覚院から移されたものと思われますが、高井山と刻まれています。高井山は本覚院の山号のようです。高井山の不動堂だから高井堂。それが転じて高井戸。最初のふたつの説とほぼ同じですが、まぁ、そんな感じで高井戸の地名ができたのでしょうか。高いところにあった井戸が地名の起こりという説もあるようですが…。
【不動堂前の台座・後面】

台座の裏側には、奉納したと思われる人物の名前が刻まれています。「下高井戸宿世話人」とあります。この宿場町の有力者たちなのでしょうね。
【宗源寺前の甲州街道】

宿場の中心から、西側になります。のどかな半農半宿(?)的な風景が広がっていたのでしょうね。
現在は、ここでもまだ新宿からの高速道路が上空を覆い続けています。
【高井戸の一里塚跡】

宗源寺を出たら、街道の左側へ渡りましょう。ほどなく一里塚跡の案内板があります。
この一里塚は笹塚の一里塚の次で、江戸から4番目。案内板があるだけで、もちろん塚の痕跡は残っていません。
そしてこの一里塚をもって、下高井戸宿を出ることになります。当時の上北沢村との境界。
上高井戸宿は上北沢村の向こう側になります。
ということで、下高井戸宿散策は終了。次回は上高井戸に舞台を移します。