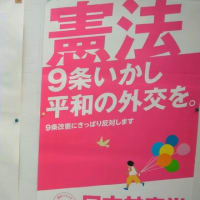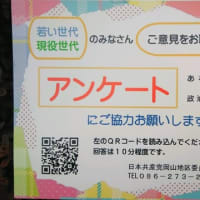今日、建部町公民館で開かれている自然農の講座(全3回の第2回目)に参加し、参考になる話が聴けました。
今日、建部町公民館で開かれている自然農の講座(全3回の第2回目)に参加し、参考になる話が聴けました。講師は、福島県でやまなみ農園をやっていて、原発事故後に建部町にやってきた佐藤和夫さんで、今回の題は「自然農の稲作り」でした。佐藤さんの話で印象に残ったのは、次のようなことです。
・田んぼは耕さず、農薬や化学肥料は使わず、有機肥料もほとんどやらないのが自然農。草刈り機とチエンソー以外の農機は使わない。
・品種は、コシヒカリ、コガネモチ、黒米。
・最初、田んぼの水を切るために、5mおきにスコップの幅(上部30cm、下部20cm、深さ25cm)の溝を切る。
・溝と溝の間の地面には藁や草を敷く。
・播く前に種籾を水選する(消毒はしない。1000粒位なので手で選別することもある)。
・秋に準備していた苗床は、藁をはずして表面のぬかと土を混ぜる。
・4月10日、苗床に1~2cm間隔でモミ(10a当り250g)を播く。苗が1.5~2葉になるまで、ビニールトンネルで保温する。苗床は、周りに溝をきって水を入れるが、浸さないで、乾いたときだけ水を入れる。
・田植えの1週間前に畦草を刈り、田んぼはセリだけを刈る。
・田植えの前日に、たまらない程度に水を入れ、田植え後の1か月は1~2cmで浅水管理する。
・6月1日、籾播きから50日~60日経って5.5葉(3分けつ)の成苗ができた頃、株間30cm・条間40cmで田植えをする。古い鎌を田んぼに刺して横に振って穴をあけて苗を入れ、上の土をつまんで寄せる。手植えで10aに4日間程度かかる(約8300本植える)。
・7月1日(7~8本に分けつしている)から、田んぼ全体を草刈りし、刈った草は、藁といっしょに所々に丸めて置く。2週間後、丸めた草からセリが伸びているようなら、反転させて置く。草刈り後は10cm程度で水管理する。
・8月1日に25~40本に分けつ。8月12~15日に出穂。9月15日に落水。10月10日から稲刈り、ハザかけ。11月1日に脱穀(反当り5俵だった)。その後、後片付けして、稲藁を戻す。
・苗床も準備し、10a当り1.2m×4mで周りに溝を切り、5kgのぬかを振り、藁をかけておく(飛ばないように)。
・たくさんの失敗を経験して覚えるのが農業。
・田んぼの生き物を大切にしていれば人間も大切にすることになる。