※例によって、私なりに聞き取ったことのメモです。
不正確、不十分な点があるかもしれない点、ご容赦を。
■■東京大学 Future Faculty Program のインパクト(栗田佳代子・東大)
○東大FFPの目的
・学生の学びを喚起する教員になるために必要な知識とスキルの修得
教育者として「も」探求し続ける姿勢
○特徴
・全学でオーソライズ(2年かかった)
おおむね全ての研究科から受講
・教育に特化
大学院共通科目。コンテンツと授業スタイルを学ぶ場。
・大学院生に届ける広報体制
地下鉄の駅も
○評価
・全体としての満足度
・友人に勧めますか 91%が肯定的
・意識や行動に変化があったか
・修了者を対象にしたプログラムに参加したいか 90%が肯定的
~積極的な学生、飢餓感をもったまま終了
・FFPアルムナイ
○IMPACT
・新聞で紹介された
・学内の意識改革、教員がオブザーバ希望
・学外機関への波及
○To Do List
■■名古屋大学における大学教員養成支援(中井俊樹・名古屋大)
○アーネスト・ボイヤー
発見、統合、応用、教育
○佐藤浩章
大学教育資格取得を条件
○話題提供の目的
・大学教員準備講座の実践紹介、議論のきっかけ
○特徴
・高等教育研究センター独自にスタート
・教科書。広い内容をカバー
・授業はワーク中心
・大学院の授業として
セミナーから正規の授業へ(組織的支援、自由度の減少)
・内容の公開
○課題
・どの程度、履修を促すか
博士課程進学者500名強→20~50名程度
・博士課程では遅いか
大学教育職を理解するには遅い?
実際の授業担当まで時間が空く。
・他大学とプログラムの標準化は進めるべきか
つまらないものになるのは困る
教員側の意欲低下にならないように
"ルーチン化"してきたかも
■■大阪大学における大学教員養成と研究者開発の取組み(竹村治雄・大阪大)
○大阪大の教育学習支援センター
・2013年6月から、6年間の時限プロジェクト
・活動開始は、11月頃から
・FDやプレFD、全学的なFD活動のワンストップサービスを実現
・学びのスパイラル
・学びのスパイラル
正規授業の学び
→ 課外(学ぶ喜び:TA機能など)(動機付け:サイエンスショップなど)
・教室整備
・講義自動週力配信システム
講義の数時間後には、CLEで公開可能
○研究者開発
・TLSCのワークショップなど
・大学院生向けの横断プログラム
・2014年度から教員養成プログラム
・2015年度
FD担当者研修
新任教員研修プログラム
(これまでの半日単位のものではなく、教員として云々のもの)
・2014年度
1回生向け基礎セミナーで「大学教員という仕事」
こういうキャリアパスもあるということを知ってもらう。
・2014年度から教員養成プログラム
TA制度との連携
Teaching Fellow も計画中
■■ディスカッション
○PhD取得者、人文系の活躍事例
・吉見
大学の教員以外のアカデミック職業の違い。社会的に確立していない。
ライブラリアン、アーキビスト、キュレーター。PhD取得者が何人いるか。
ライブラリアンもICTや知財のことなども。
「知識基盤社会」では、それらが求められる。
○
・東大では、受講者数 100名というのを戦略的に設定。
しかし、Certification の乱発は避ける。
・吉見: FFPが自己目的化してはいけない。高学歴者のキャリアパスを支える。循環回路に。
・吉見: 疲れ果ててる熱心なシニア教員に、さらにFDもというのは個人的には無理があると考える。それが可能になるようにどうしていくかの条件を整えるべき。
若手教員はこれからキャリアをつかむ立場。FFPの有用性も受け入れられる。
○次世代の教員に求められるものは?
・竹村: アメリカのある新聞、現在の小学生の65%は今にはない職業に就く。
社会の変化のスピード。
変化に適応していく力。
・中原: 閉じないこと;孤独にならないこと
・中井: 大学教員とは何かと考える力。そこを考えないと前に進まない。
・チャダ: Inovation
・ターナー: Leadership, in various situation
・吉見: 大学はどういう能力を育てていくのか。
「宮本武蔵」、二刀流。
複雑化していく社会で、一本の刀ではなく、二本の刀をうまく組み合わせて。
違う分野とつなぐ。
■■情報交換会
○非常に有意義でした。
・TLSCには、主に特任(期限付き)の専任教員が何名かいらっしゃるのは知っていましたが、この席上で何名かとお話しすることができました。紹介をお願いしたり、さらに紹介いただいたり、協働中の教員が紹介してくれたりと。
阪大のTLSCはこれまでFD中心にサービスを組み立ててきましたが、学修支援の事業展開も...
ちょうど来年度の某計画のための"粗"案(今年度の実績を並べた程度)をメモしてて、たまたま手元に持っていました。それをお見せしながら、現状の説明や、ご意見を伺ったり。
・先日キャリア支援課で、これまでキャリア支援担当だった教員が退職され、兼務で4月から新しい教員が来られると聞いていましたが、なんとその方にもお会いすることができました。
・やっぱり、特に新しい事業の場合、新しい組織が立ち上がる時は、人と人のつながりだなぁと思った次第です。インターネットやパソコンが広がりだした時も同じだったでしょう。国立大学の法人化の時も同じでしょうか。
(私はこの仕事をどう引き継いで、どう関わるか。どのようにつなげて、広げるか。)
(3年定期異動≒誰でもできる仕事≒専門性の否定 だと確信しますが(特に中堅以上)、事業や組織の成熟度も関連しますね)
・お世話になったことのある某教員の(声がひっくり返った)転任情報。ただ、ライバル校なので、負けないように。
・学生時代のサークルで講演をお願いしたことのある吉見先生ともお話しできました。
・情報系時代の同僚が現在は研究員になっていましたが、お互いの近況報告も。
・バイトで来ていた学生達とも少し話せました。学務システムへの要望を関係者である教員に言ってもらったり。
要望を言う機会があまりないのはよくないですが、「作ったらいいねん」と初対面の学生に言ってみたり。
学務システムの掲示板には登録者の名前が出るらしく、僕の名前を知っている学生がいたり。やはり、名前を覚えてもらって、顔が覚えられて、あの人に聞いてみたらいいと思ってもらえるのはいいことですね。
不正確、不十分な点があるかもしれない点、ご容赦を。
■■東京大学 Future Faculty Program のインパクト(栗田佳代子・東大)
○東大FFPの目的
・学生の学びを喚起する教員になるために必要な知識とスキルの修得
教育者として「も」探求し続ける姿勢
○特徴
・全学でオーソライズ(2年かかった)
おおむね全ての研究科から受講
・教育に特化
大学院共通科目。コンテンツと授業スタイルを学ぶ場。
・大学院生に届ける広報体制
地下鉄の駅も
○評価
・全体としての満足度
・友人に勧めますか 91%が肯定的
・意識や行動に変化があったか
・修了者を対象にしたプログラムに参加したいか 90%が肯定的
~積極的な学生、飢餓感をもったまま終了
・FFPアルムナイ
○IMPACT
・新聞で紹介された
・学内の意識改革、教員がオブザーバ希望
・学外機関への波及
○To Do List
■■名古屋大学における大学教員養成支援(中井俊樹・名古屋大)
○アーネスト・ボイヤー
発見、統合、応用、教育
○佐藤浩章
大学教育資格取得を条件
○話題提供の目的
・大学教員準備講座の実践紹介、議論のきっかけ
○特徴
・高等教育研究センター独自にスタート
・教科書。広い内容をカバー
・授業はワーク中心
・大学院の授業として
セミナーから正規の授業へ(組織的支援、自由度の減少)
・内容の公開
○課題
・どの程度、履修を促すか
博士課程進学者500名強→20~50名程度
・博士課程では遅いか
大学教育職を理解するには遅い?
実際の授業担当まで時間が空く。
・他大学とプログラムの標準化は進めるべきか
つまらないものになるのは困る
教員側の意欲低下にならないように
"ルーチン化"してきたかも
■■大阪大学における大学教員養成と研究者開発の取組み(竹村治雄・大阪大)
○大阪大の教育学習支援センター
・2013年6月から、6年間の時限プロジェクト
・活動開始は、11月頃から
・FDやプレFD、全学的なFD活動のワンストップサービスを実現
・学びのスパイラル
・学びのスパイラル
正規授業の学び
→ 課外(学ぶ喜び:TA機能など)(動機付け:サイエンスショップなど)
・教室整備
・講義自動週力配信システム
講義の数時間後には、CLEで公開可能
○研究者開発
・TLSCのワークショップなど
・大学院生向けの横断プログラム
・2014年度から教員養成プログラム
・2015年度
FD担当者研修
新任教員研修プログラム
(これまでの半日単位のものではなく、教員として云々のもの)
・2014年度
1回生向け基礎セミナーで「大学教員という仕事」
こういうキャリアパスもあるということを知ってもらう。
・2014年度から教員養成プログラム
TA制度との連携
Teaching Fellow も計画中
■■ディスカッション
○PhD取得者、人文系の活躍事例
・吉見
大学の教員以外のアカデミック職業の違い。社会的に確立していない。
ライブラリアン、アーキビスト、キュレーター。PhD取得者が何人いるか。
ライブラリアンもICTや知財のことなども。
「知識基盤社会」では、それらが求められる。
○
・東大では、受講者数 100名というのを戦略的に設定。
しかし、Certification の乱発は避ける。
・吉見: FFPが自己目的化してはいけない。高学歴者のキャリアパスを支える。循環回路に。
・吉見: 疲れ果ててる熱心なシニア教員に、さらにFDもというのは個人的には無理があると考える。それが可能になるようにどうしていくかの条件を整えるべき。
若手教員はこれからキャリアをつかむ立場。FFPの有用性も受け入れられる。
○次世代の教員に求められるものは?
・竹村: アメリカのある新聞、現在の小学生の65%は今にはない職業に就く。
社会の変化のスピード。
変化に適応していく力。
・中原: 閉じないこと;孤独にならないこと
・中井: 大学教員とは何かと考える力。そこを考えないと前に進まない。
・チャダ: Inovation
・ターナー: Leadership, in various situation
・吉見: 大学はどういう能力を育てていくのか。
「宮本武蔵」、二刀流。
複雑化していく社会で、一本の刀ではなく、二本の刀をうまく組み合わせて。
違う分野とつなぐ。
■■情報交換会
○非常に有意義でした。
・TLSCには、主に特任(期限付き)の専任教員が何名かいらっしゃるのは知っていましたが、この席上で何名かとお話しすることができました。紹介をお願いしたり、さらに紹介いただいたり、協働中の教員が紹介してくれたりと。
阪大のTLSCはこれまでFD中心にサービスを組み立ててきましたが、学修支援の事業展開も...
ちょうど来年度の某計画のための"粗"案(今年度の実績を並べた程度)をメモしてて、たまたま手元に持っていました。それをお見せしながら、現状の説明や、ご意見を伺ったり。
・先日キャリア支援課で、これまでキャリア支援担当だった教員が退職され、兼務で4月から新しい教員が来られると聞いていましたが、なんとその方にもお会いすることができました。
・やっぱり、特に新しい事業の場合、新しい組織が立ち上がる時は、人と人のつながりだなぁと思った次第です。インターネットやパソコンが広がりだした時も同じだったでしょう。国立大学の法人化の時も同じでしょうか。
(私はこの仕事をどう引き継いで、どう関わるか。どのようにつなげて、広げるか。)
(3年定期異動≒誰でもできる仕事≒専門性の否定 だと確信しますが(特に中堅以上)、事業や組織の成熟度も関連しますね)
・お世話になったことのある某教員の(声がひっくり返った)転任情報。ただ、ライバル校なので、負けないように。
・学生時代のサークルで講演をお願いしたことのある吉見先生ともお話しできました。
・情報系時代の同僚が現在は研究員になっていましたが、お互いの近況報告も。
・バイトで来ていた学生達とも少し話せました。学務システムへの要望を関係者である教員に言ってもらったり。
要望を言う機会があまりないのはよくないですが、「作ったらいいねん」と初対面の学生に言ってみたり。
学務システムの掲示板には登録者の名前が出るらしく、僕の名前を知っている学生がいたり。やはり、名前を覚えてもらって、顔が覚えられて、あの人に聞いてみたらいいと思ってもらえるのはいいことですね。















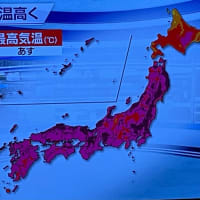
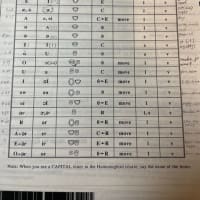









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます