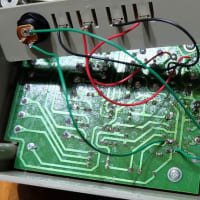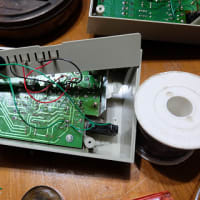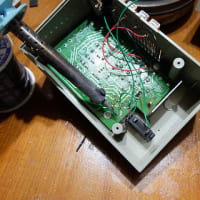★注釈
約15年ほど前に書き始めた記事を数日かけて再検証しなおしてみたもの。
あくまでも自分メモ的なので理解不能な部分もあってしかるべきなのでご容赦を。
札幌市営地下鉄2000系データファイル1
札幌市営地下鉄2000系データファイル2
札幌市営地下鉄2000系データファイル3
札幌市営地下鉄2000系データファイル4
↑長文なのでそれぞれのリンク1から4に沿って読んだほうが解ります。

完成時の1001-1002
室内が一部クロスシートで、タイヤハウスの欠き取りがないため裾が一直線。
(最終姿の画像は持っていないので、WEBなどで確認して)
とてつもないぶっ飛んだデザインの電車がオリンピックにあわせて登場。
この電車の特徴はWIKIでも見れば解るところですが、昭和46年札幌市営地下鉄南北線の一号地下鉄として開業、ゴムタイヤ式案内軌条の高速電車で、連接式に伴う13m級の短い車体、3000mmにも及ぶ幅広い車体に写真を見るだけでエグい軸配置。駆動は車体中心の?軸台車で行い、モーターは車体装架。プロペラシャフトで駆動するキワモノ。
巨大な窓は有名な札幌市電A830(後年の名鉄870型)から引き継いだデザインで、全体イメージをA830から求めたと言いますが、似ても似つかないゲテモノに成り果てたと思うのは自然ではないかと。
アルミ車体の軽量化など贅を尽くした構造ながら、抵抗制御の非冷房。
屋内でしか走らないので、廃車まで一度もリペイントしなかったどころか水洗浄すらしなかった徹底振り。(拭取り清掃はしていた)
日本の色物電車の最右翼ながら、その研究テーマとしては「番号の変遷」に複雑怪奇な歴史あり。
年次増備一覧
試作車(S46・5までの製造)
★1000系は2連、2000系は4連として製造。通番管理で始まり先頭車と中間車の形式分けは行っていない
★1001と1002のみ昭和45年製造扱
★常務員室が狭い
1001~1004 2連×2
2001~2004 4連×1
8両
1次車(S46・12までの製造・試作車含)
★開業にあたり用意された車両
1005~1028 2連×12
2005~2028 4連×6
48両
2次車(S47・7製造)
★1000系としての2連製造を中止。以後全て2000系として製造。先頭車と中間車の形式分けは行っていない
★4連2本8両と1000系への増結中間車8両を製造
★欠番は1次車(1000系先頭車)を改番にて充当(※1)
2029~2036 4連×2
2038・2039・2042・2043・2046・2047・2050・2051
16両
3次車(S49・7製造)
★増結中間車12両を製造
★4連ルールの番号列崩れる
2053~2063(全中間車)
12両
4次車(S50・3までの製造)
★形式内区分けの変更、将来の大改番に備えて末番リセットと百位を編成順列値とする。8連対策で5-6両目を欠番
★形態上、側窓天地が小さくなる。
2101~2104(先頭車)
2201~2204
2301~2304
2401~2404
2701~2704
2801~2804(先頭車)
6連×4
24両
5次車(S51・7までの製造)
★増結中間車12両を製造
★在来車改番の車号整理実施(※2)
2205・2206
2305~2308
2405~2408
2705・2706
12両
6次車(S52・10までの製造)
★増結中間車18両を製造
★在来車改番の車号整理実施(※3)
2209~2211
2309~2311
2409~2411
2509~2511
2609~2611
2709~2711
18両
7・9次車(S53・3までの製造)
★増結中間車22両を製造
★在来車改番の車号整理実施(※4)
★8次車は別形式3000系3001Fのことを称する
2501~2508
2601~2608
2212
2312
2412
2512
2612
2712
22両
製造の終結
■系列と番号概要
・系列概念と車両番号は開業のときの組み換え発生から混乱をきたし、
・構想の「1000系は2連、2000系は4連」の概念は形骸化する。
・途中の編成増加やユニット組み換えの必要が多発して混乱にいっそう拍車が掛かる。
・小改番が都合3度あり、改番基準も時々で異なるため構想は読めるが統一はされなかった。
・昭和53年の大改番・車号整理で矛盾の強制解消
・大改番以後は、系列を2000系に統一。
・千位を系列、百位を編成位置、末2桁を編成番号として整理されるまで、確たる番号と形態の符号は一切しない。
・大改番により、次列と番号順の相対性はなくなる。
・一貫して電気機器メーカー差は、実物が異なるにもかかわらず形式に影響していない
■結果のまとめ
・「全電動車2両ユニット構造で、先頭車と中間車形態があるだけ」なので、1000系や2000系と言ってもスペックには一切変わりがない。
・国鉄流表記でMc、M、M’、M’cの4態しかなく、更には電気品も複数会社に渡って製造されたが、ユニット同メーカーであれば年次を超えたユニット組み替えも自由である。
・外見のマイナーチェンジは4次車からのみである
・内装は試作車で乗務員室仕切り位置が異なるほかはデコラ板デザインは4種ある
・実物は非常にシンプル、かつメーカー間の機器は違っても扱い差もない単純な電車であるのに、番号の府番についてはルールの度重なる設定変更と並行期間があるため、大変わかりにくい。

↑案外ありそうでない、札幌市営2000系の総覧1でした。
WIKIなどは一切読んでません。