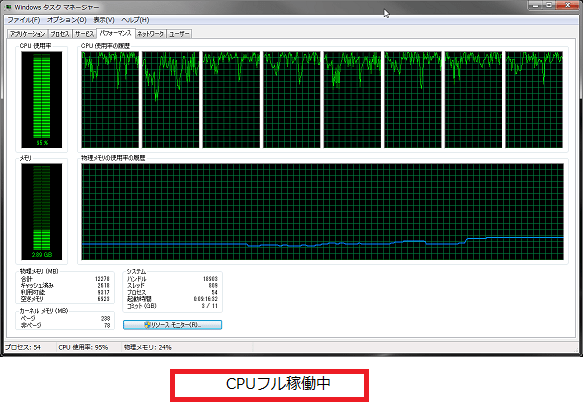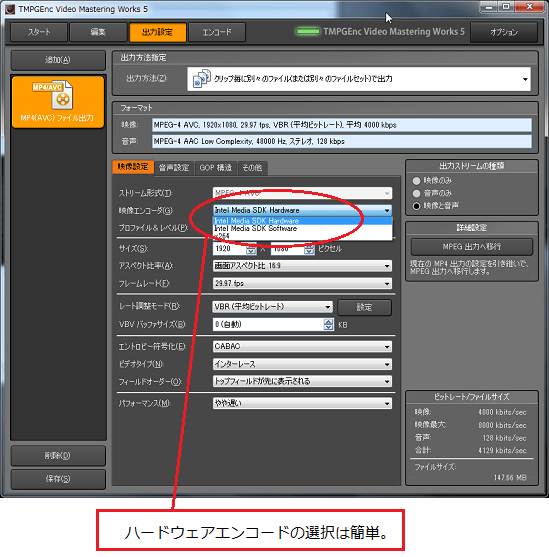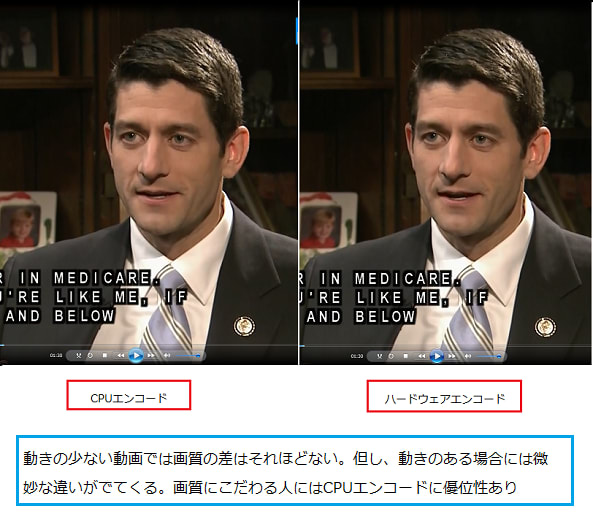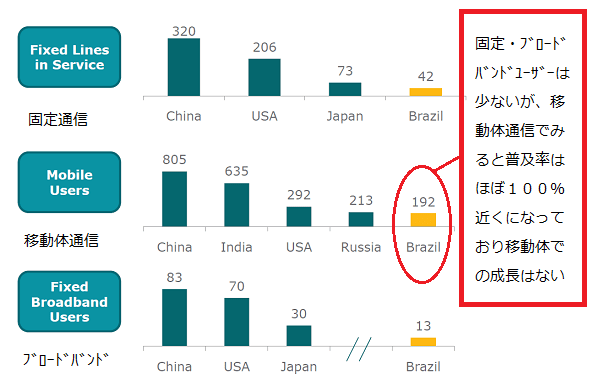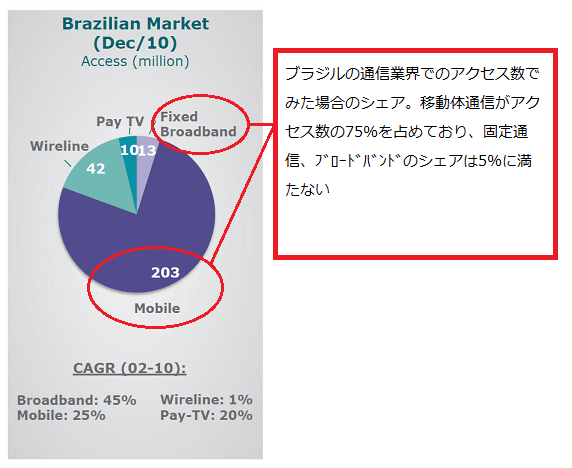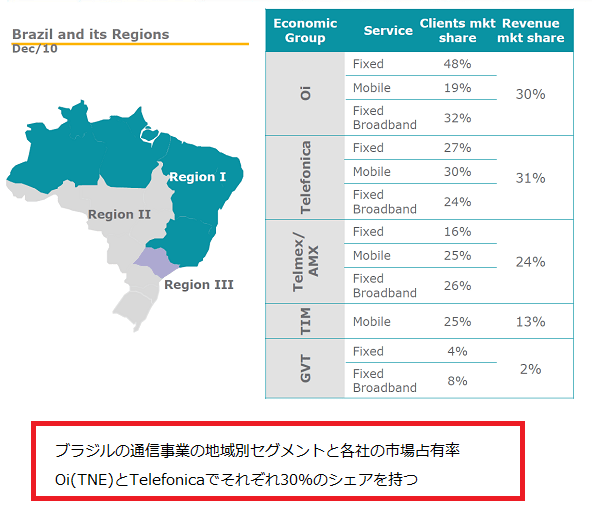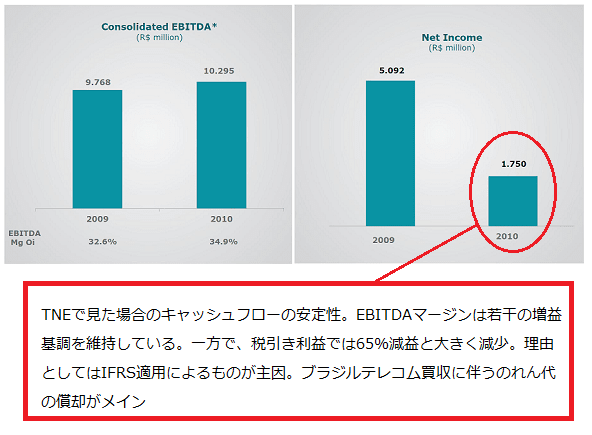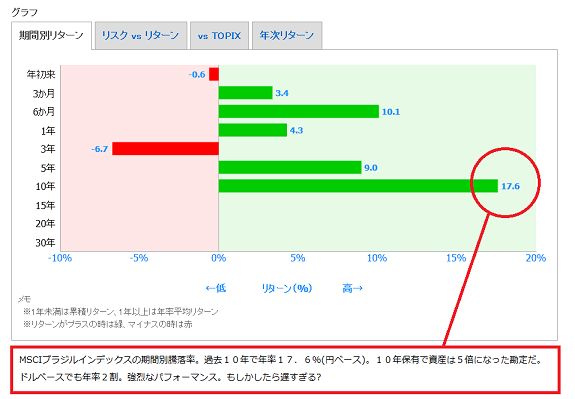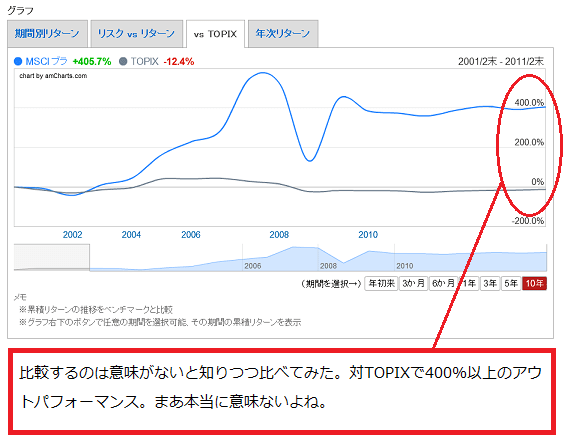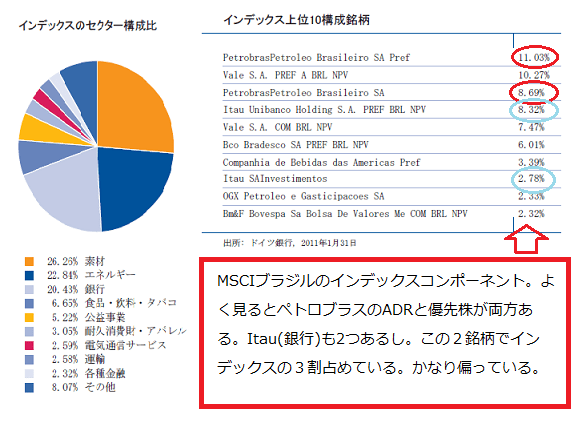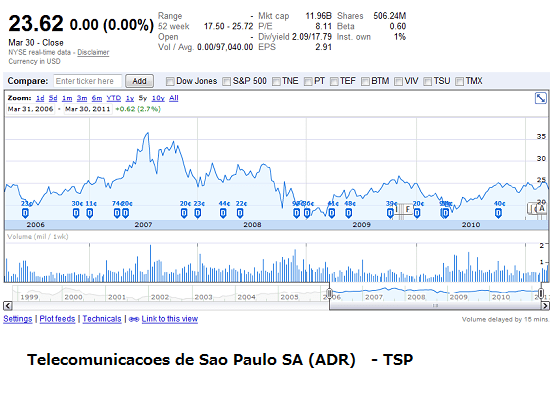投資ツールはネット証券をはじめ各社からいろいろなツールが出されており、現在の個人投資家レベルでも結構いろいろなものが使えるようになってきている。私も時折利用するが、スクリーニングツールなどやチャートツールなどは機関投資家の利用しているものとは異なっているが、それでもそれほど劣ったものではない。むしろトレーディングツールに関して言えば機関投資家用とさほど変わらないものもあるほどだ。但し、トレーディングが主体でなく、中長期投資でバイアンドホールドが基本とする一般投資家にとっては、高度なトレーディングツールは面白そうであっても意外に投資判断に寄与していない。デイトレーディングやチャート分析で売買を行う投資家ならいざしらず普通の投資家はそれほどアクティブであるわけではない。 むしろ材料でもって投資判断を下す人が大半だ。一方で資産運用に関しては全体のポートフォリオ管理を行っている人はほとんどいない。直感的にキャッシュポジションを管理していたり、気分でアセットアロケーションをしている人がほとんどだろう。
私も何社かの証券会社を利用しているがそのうちの1社マネックス証券でポートフォリオ管理ツールが提供されているのでそれを試してみる。このツールの優れているところはマネックスの残高だけでなく、預け入れている他社の投資残高を反映させることができる点だ。登録しておけば、他社に自動ログオンして残高を更新させることができる。Monex Vision βとよばれるプログラムでマネックスの顧客であれば利用することができる。ところが少し困ったことにこのプログラム、マネックス自身があまり宣伝していないのか、マネックス証券の顧客も容易に探せないようになっている。

ログオンして「投資情報」にあるかと思ったら、ない。上の写真のとおりだが、ログオンして「商品・サービス一覧」を選択するとサービスメニューがずらっと並ぶ。その中にMonex Vision βを見つけることができる。ほとんど宣伝していない理由もよくわからないが、まだベータバージョンだからだろうか。ベータが取れれば本格的に利用できるということなんだろうか。それはともかく利用は極めて簡単だ。ログオンすれば自動的に残高がロードされ分析画面がでてくる。

上の図がログインした後にでてくるポートフォリオ分析図だ。まず外部資産の自動更新であるが、国内の金融機関の大半は対象になっている。SBI証券、カブドットコム証券、楽天証券などのオンライン証券はもとより、野村、大和、日興証券などの対面型証券の自動ログオンが可能だ。それに主要な銀行も対応できる。問題となるのは海外の金融機関には対応していない点。マネックスが買収したBOOM証券もできない。恐らく海外金融機関を利用しているユーザーはほとんどいないとの見方をしているのだろう。但し、海外金融機関対応はしていないものの、マニュアルで入力する機能があることから問題は起こらないだろう。参考としてアップした写真だが、すべての証券を登録するのも面倒だったので、私が利用している主要な証券の資産残高を更新している。BOOM証券の残高はマニュアル入力を行った。それと銀行口座は除外した。銀行のキャッシュは資産運用対象外なので問題はないだろう。また実物不動産や匿名組合出資なども除外している。パフォーマンスが計測できないといいうのが理由だ。
ポートフォリオ分析をしてみると面白いことが分かった。ターゲットは積極型のポートフォリオを選択したが、分析結果から得られた最適ポートフォリオは結構異なっている。一方でリスクリターンプロファイルは現状ポートフォリオでも結構近接していることがわかる。REIT資産がオルタナティブ扱いになっていることと、REITのボラティリティが株式のそれと結構にていることがその背景にあるのではないだろうか。適当にやっているわりには意外にいい線言ってんじゃね?

分析の詳細タブを選ぶと現状と目標ポートフォリオの比較ができる。これによればオルタナティブ投資が多いので株式資産を増やせというのがアドバイスの第一、国内資産が多いので新興国株式を含めた外貨建て資産の増加を促すというのが2番目のアドバイスだ。ひとつ前の写真でもわかるとおり、実は最適化ポートフォリオと現状ポートフォリオとではリスクリターンプロファイルが似通っていることから、リバランスによるリスクあたりのリターンの増加が少ない。リバランスに伴う売買コストを考慮すると本当にリバランスをした方がメリットがあるのかは疑問だ。但し、国内資産を減らして外貨建て資産の増加を図るというのは少し賛成だ。

追加購入アドバイスというタブを選択すると何を買えばいいのかというアドバイスが個別資産ごとに金額で示してくれる。私の場合には新興国株式をもっと買い、コモディティ関連にも投資しろという内容だ。このツールのよいところは自分の運用ポートフォリオのリスクリターンプロファイルを計算してくれるところが最大の売りだ。一方、難点はいくらでもあるのだが、まあ簡単にいえばクオンツ運用している投資家ならともかく、アクティブ投資家にとって必ずしもアドバイスに従うインセンティブがほとんどないことだ。私のケースでも外貨建て資産の増加というのは傾聴に値するが、新興国株式・コモディティの投資の増加はあまり素直にしたがえない。第一、REIT、高配当株式をメインに投資している投資家に本当に最適なものかという点だ。確かに期待リターンとリスクで最適化すれば、そうなるだろうが投資家にもいろいろなタイプがおり、数値化できないリスク選好を持つ投資家にとっては馬耳東風となろう。
見た目にもハイテクなツールがでるとなんだかその気になる人が多いのであるが、いくつか注意点を。Monex Vision βは仕様が明らかにされていないが、オプティマイザー(Optimizer)を利用した最適化計算ツールだ。有名どころではパーラモデルが有名だが、それに似たものだと考えていい。問題はオプティマイザーで使用する期待収益率とボラティリティをどのように計算しているかという点だ。通常、簡便なツールであれば、ボラティリティは過去20年とかのヒストリカルボラティリティを利用する。期待収益率も過去の平均リターンを使用する。当モデルでは国内株式の期待収益率が4.8%におき、1980年1月から2010年8月までの30年間の平均リターンで計算しているようだ。しかし、新興国株式とかREITのボラティリティは一体どうやって計算しているのだろうか。最適化プロセスではどの程度のヒストリカルデータを利用するのかという点と、ウェイトづけをするかしないかで最適化結果は大きく変わってくる。
最適化ツールについては書き出すと本ができてしまうくらい奥が深いのでここでは詳述しないが、ヒストリカルデータの扱い方で「最適」かそうでないか、答えが大きく違うという点を意識する必要がある。例えば、ヒストリカルデータを平均するやり方とヒストリカルデータにウェイトづけするやり方では答えが違う。「平均」とはまさに押しなべて平均的に「事象」が発生することを指すが、株式市場の経験則は大昔よりもより直近の「事象」に左右されると考えれば過去20年のデータなら直近5年のデータに50%とか多めのウェイトをつけて算出するという方法もある。分かりやすく言えば東電の株価の動きは15年前-20年前よりも直近5年の動きの方が未来のボラティリティをうまく説明できるという考え方だ。
期待収益率の算出についても留意する必要がある。一般的にはこれもヒストリカルデータを利用するが、これは過去に実現したリターンが将来も「平均的に」実現すると予想したものに他ならない。理屈はそうだが、直感的には疑問が残る算出方法だ。アクティブに期待収益率を予想するという方法もあり、マクロ予想からのトップダウン手法、アナリストの予想収益率を集計したボトムアップ手法など、さらにアクティブ予想に複数シナリオを予想して確率で加重するシナリオ加重といった手法など様々な方法がある。期待収益率が1%異なれば、でてくる最適化結果も大きく異なってくる。
結論からすれば、最適化ツールはあくまでも参考で、「最適化結果」を鵜呑みにして投資判断を下してはならないという当たり前の結論になる。このサービスがあるのはうれしいが、私個人としてはサービスで利用しているオプティマイザーを公開して個人で利用できるようにしてほしい。実はそう思うのは一つ理由があって、最適化ツールであるオプティマイザーにはその機能を利用すると少し変わったことができる。まあ、オプティマイザーの種類やカバーしている機能にもよるが、オプティマイザーで最適ポートフォリオを計算するという一般的な利用方法とは別に、現状ポートフォリオから投資家が期待している資産クラス毎の期待収益率を計算することができる。分かりにくい説明だが、仮にある投資家の現状のアセットアロケーションが「最適」であると仮定した場合、オプティマイザーを利用してその投資家が期待する各資産クラスの期待収益率を計算することができる。これを「逆最適化」と呼ぶ。つまり、仮に現状がベストなポートフォリオと想定するなら自分が保有する国内株式、外国株式等の期待収益率を逆算できることになる。
なにを言いたいかといえば、仮に投資家が自分のポートフォリオに国内株式を30%保有しているとする。そして他の資産クラス、例えば外国株式、債券の比率が分かっており、自分のアセットアロケーションがベストなものであると考えているとする。さらにその投資家が個人的に株式に超強気と考えている。逆最適化により各資産クラスの期待収益率が計算され、仮に国内株式の期待収益率が外国株式のそれを下回ったという結果がでれば、それは本当は自分は国内株式にそれほど強気ではないということが分かるのである。実際のポートフォリオから自分の本当の期待が計算できる。まあ、こんな使い方もできる。

私も何社かの証券会社を利用しているがそのうちの1社マネックス証券でポートフォリオ管理ツールが提供されているのでそれを試してみる。このツールの優れているところはマネックスの残高だけでなく、預け入れている他社の投資残高を反映させることができる点だ。登録しておけば、他社に自動ログオンして残高を更新させることができる。Monex Vision βとよばれるプログラムでマネックスの顧客であれば利用することができる。ところが少し困ったことにこのプログラム、マネックス自身があまり宣伝していないのか、マネックス証券の顧客も容易に探せないようになっている。

ログオンして「投資情報」にあるかと思ったら、ない。上の写真のとおりだが、ログオンして「商品・サービス一覧」を選択するとサービスメニューがずらっと並ぶ。その中にMonex Vision βを見つけることができる。ほとんど宣伝していない理由もよくわからないが、まだベータバージョンだからだろうか。ベータが取れれば本格的に利用できるということなんだろうか。それはともかく利用は極めて簡単だ。ログオンすれば自動的に残高がロードされ分析画面がでてくる。

上の図がログインした後にでてくるポートフォリオ分析図だ。まず外部資産の自動更新であるが、国内の金融機関の大半は対象になっている。SBI証券、カブドットコム証券、楽天証券などのオンライン証券はもとより、野村、大和、日興証券などの対面型証券の自動ログオンが可能だ。それに主要な銀行も対応できる。問題となるのは海外の金融機関には対応していない点。マネックスが買収したBOOM証券もできない。恐らく海外金融機関を利用しているユーザーはほとんどいないとの見方をしているのだろう。但し、海外金融機関対応はしていないものの、マニュアルで入力する機能があることから問題は起こらないだろう。参考としてアップした写真だが、すべての証券を登録するのも面倒だったので、私が利用している主要な証券の資産残高を更新している。BOOM証券の残高はマニュアル入力を行った。それと銀行口座は除外した。銀行のキャッシュは資産運用対象外なので問題はないだろう。また実物不動産や匿名組合出資なども除外している。パフォーマンスが計測できないといいうのが理由だ。
ポートフォリオ分析をしてみると面白いことが分かった。ターゲットは積極型のポートフォリオを選択したが、分析結果から得られた最適ポートフォリオは結構異なっている。一方でリスクリターンプロファイルは現状ポートフォリオでも結構近接していることがわかる。REIT資産がオルタナティブ扱いになっていることと、REITのボラティリティが株式のそれと結構にていることがその背景にあるのではないだろうか。適当にやっているわりには意外にいい線言ってんじゃね?

分析の詳細タブを選ぶと現状と目標ポートフォリオの比較ができる。これによればオルタナティブ投資が多いので株式資産を増やせというのがアドバイスの第一、国内資産が多いので新興国株式を含めた外貨建て資産の増加を促すというのが2番目のアドバイスだ。ひとつ前の写真でもわかるとおり、実は最適化ポートフォリオと現状ポートフォリオとではリスクリターンプロファイルが似通っていることから、リバランスによるリスクあたりのリターンの増加が少ない。リバランスに伴う売買コストを考慮すると本当にリバランスをした方がメリットがあるのかは疑問だ。但し、国内資産を減らして外貨建て資産の増加を図るというのは少し賛成だ。

追加購入アドバイスというタブを選択すると何を買えばいいのかというアドバイスが個別資産ごとに金額で示してくれる。私の場合には新興国株式をもっと買い、コモディティ関連にも投資しろという内容だ。このツールのよいところは自分の運用ポートフォリオのリスクリターンプロファイルを計算してくれるところが最大の売りだ。一方、難点はいくらでもあるのだが、まあ簡単にいえばクオンツ運用している投資家ならともかく、アクティブ投資家にとって必ずしもアドバイスに従うインセンティブがほとんどないことだ。私のケースでも外貨建て資産の増加というのは傾聴に値するが、新興国株式・コモディティの投資の増加はあまり素直にしたがえない。第一、REIT、高配当株式をメインに投資している投資家に本当に最適なものかという点だ。確かに期待リターンとリスクで最適化すれば、そうなるだろうが投資家にもいろいろなタイプがおり、数値化できないリスク選好を持つ投資家にとっては馬耳東風となろう。
見た目にもハイテクなツールがでるとなんだかその気になる人が多いのであるが、いくつか注意点を。Monex Vision βは仕様が明らかにされていないが、オプティマイザー(Optimizer)を利用した最適化計算ツールだ。有名どころではパーラモデルが有名だが、それに似たものだと考えていい。問題はオプティマイザーで使用する期待収益率とボラティリティをどのように計算しているかという点だ。通常、簡便なツールであれば、ボラティリティは過去20年とかのヒストリカルボラティリティを利用する。期待収益率も過去の平均リターンを使用する。当モデルでは国内株式の期待収益率が4.8%におき、1980年1月から2010年8月までの30年間の平均リターンで計算しているようだ。しかし、新興国株式とかREITのボラティリティは一体どうやって計算しているのだろうか。最適化プロセスではどの程度のヒストリカルデータを利用するのかという点と、ウェイトづけをするかしないかで最適化結果は大きく変わってくる。
最適化ツールについては書き出すと本ができてしまうくらい奥が深いのでここでは詳述しないが、ヒストリカルデータの扱い方で「最適」かそうでないか、答えが大きく違うという点を意識する必要がある。例えば、ヒストリカルデータを平均するやり方とヒストリカルデータにウェイトづけするやり方では答えが違う。「平均」とはまさに押しなべて平均的に「事象」が発生することを指すが、株式市場の経験則は大昔よりもより直近の「事象」に左右されると考えれば過去20年のデータなら直近5年のデータに50%とか多めのウェイトをつけて算出するという方法もある。分かりやすく言えば東電の株価の動きは15年前-20年前よりも直近5年の動きの方が未来のボラティリティをうまく説明できるという考え方だ。
期待収益率の算出についても留意する必要がある。一般的にはこれもヒストリカルデータを利用するが、これは過去に実現したリターンが将来も「平均的に」実現すると予想したものに他ならない。理屈はそうだが、直感的には疑問が残る算出方法だ。アクティブに期待収益率を予想するという方法もあり、マクロ予想からのトップダウン手法、アナリストの予想収益率を集計したボトムアップ手法など、さらにアクティブ予想に複数シナリオを予想して確率で加重するシナリオ加重といった手法など様々な方法がある。期待収益率が1%異なれば、でてくる最適化結果も大きく異なってくる。
結論からすれば、最適化ツールはあくまでも参考で、「最適化結果」を鵜呑みにして投資判断を下してはならないという当たり前の結論になる。このサービスがあるのはうれしいが、私個人としてはサービスで利用しているオプティマイザーを公開して個人で利用できるようにしてほしい。実はそう思うのは一つ理由があって、最適化ツールであるオプティマイザーにはその機能を利用すると少し変わったことができる。まあ、オプティマイザーの種類やカバーしている機能にもよるが、オプティマイザーで最適ポートフォリオを計算するという一般的な利用方法とは別に、現状ポートフォリオから投資家が期待している資産クラス毎の期待収益率を計算することができる。分かりにくい説明だが、仮にある投資家の現状のアセットアロケーションが「最適」であると仮定した場合、オプティマイザーを利用してその投資家が期待する各資産クラスの期待収益率を計算することができる。これを「逆最適化」と呼ぶ。つまり、仮に現状がベストなポートフォリオと想定するなら自分が保有する国内株式、外国株式等の期待収益率を逆算できることになる。
なにを言いたいかといえば、仮に投資家が自分のポートフォリオに国内株式を30%保有しているとする。そして他の資産クラス、例えば外国株式、債券の比率が分かっており、自分のアセットアロケーションがベストなものであると考えているとする。さらにその投資家が個人的に株式に超強気と考えている。逆最適化により各資産クラスの期待収益率が計算され、仮に国内株式の期待収益率が外国株式のそれを下回ったという結果がでれば、それは本当は自分は国内株式にそれほど強気ではないということが分かるのである。実際のポートフォリオから自分の本当の期待が計算できる。まあ、こんな使い方もできる。