
★註:天賦人権論とアメリカ合衆国憲法
天賦人権論とアメリカ合衆国憲法は無関係。このことの確認は、1980年初頭から四半世紀あまり続き今も余韻漂うアメリカ連邦憲法を巡る憲法解釈方法論の論争、すなわち、「原意主義:Originalism」と「非原意主義:Non-Originalism」との論争の重要な副産物の一つだと思います。
この論争を通して、天賦人権論を称揚したものとも見える「独立宣言:the Declaration of Independence」(1776年7月)、および、そのプロトタイプでもある「バージニア権利宣言:Virginia Declaration of Rights」(1776年6月)と「アメリカ合衆国憲法:the Constitution of the United States of America」(公布1787年-発効1788年;「修正1条ないし修正10条:権利の章典」は1791年発効)とは、少なくとも、「人権の効力根拠」を巡るロジックに関しては無関係ということが確認された。
・原意主義
憲法の解釈はアメリカ合衆国憲法の立法者である建国の父達がその条規に盛り込んだ<原意>に忠実になされるべきである(よって、例えば、「分離すれども平等:separate but equal」として学校を含む公共施設での人種隔離政策を是認する州法を違憲とした連邦最高裁の判断は、権利の内容からも、また、州の権限を制約する連邦司法部の権限の点からも許されない)
・非原意主義
あたかも「新聞の連載小説」、あるいは、幾人かの作者が一つの作品を書きつないでいく「連作小説:chain novel」(ドゥオーキン)の如く、建国以来の2世紀を超える紆余曲折を経て、現在、憲法が守護すべき正当な価値や権利と捉えられるに至っている、そんな現在の司法審査の原理や基準に沿って憲法は解釈されるべきだ。ならば、憲法典の諸条項が明確に定めている議会や大統領や司法部の構成や権限などは、あたかも、これまで書かれた作品の登場人物や舞台設定の如く、作品の自己同一性を保持する以上現在の解釈もそれに反することは難しいにしても、具体的な権利の内容や権利制限の仕組みなどは憲法の原意にそれほど忠実である必要はない(よって、例えば、公共施設での人種隔離政策を是認する州法を連邦最高裁が違憲と判断したのは当然である)。
▽Excerpt from the Declaration of Independence
・・・We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.— That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed, ・・・
▽アメリカ独立宣言(抜粋)
・・・我々は、次の如き事柄は真っ当であり、かつ、自明であると信ずる。造物主たる神によってすべての人間は平等なる存在として造られていること、生存・自由そして幸福の追求を含むある侵されるべからざる諸権利を神である造物主から認められていることを。また、政府は、これらの権利を保障する目的のために人々の間に組織されるものであって、政府の権力はその政府に統治される人々の同意に由来する限りにおいてのみ正当なものであるということを。・・・ 
その憲法訴訟にご興味があれば下記拙稿をご参照いただくとして、蓋し、独立宣言の中の「their Creator」のフレーズなどを見ると、星条旗に対する「忠誠の誓い:Pledge of Allegiance」に含まれる「神の下に:under God」というフレーズを理由に、「忠誠の誓い」を公立学校で生徒に斉唱させることは、政教分離原則を定めている連邦憲法に違反すると訴えたリベラル派にとっては「独立宣言を教えること」も憲法違反なのかもしれません。更には、日本に特殊な「天賦人権論」もアメリカでは憲法違反、鴨。
・憲法訴訟を巡る日米の貧困と豊饒
☆「忠誠の誓い」合憲判決-リベラル派の妄想に常識の鉄槌(1)~(6)
http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/ec85f638d02c32311e83d3bcb3b6e714
本編記事でも触れたように、誤解や誤差をおそれずに言い切れば、英米の憲法学には「基本的人権」や「人権」なる専門用語は存在しません。よって、上で述べた「憲法解釈方法論争の重要な副産物」なるものは、実は、連邦最高裁の権限を巡る、就中、州法に対する司法審査の権限の範囲を巡るアメリカ合衆国憲法の原意の究明という論争の応酬と帰趨を私なりに<意訳>したもの。
而して、その「副産物」の内容。すなわち、「独立宣言とアメリカ合衆国憲法は無関係」よって「天賦人権論とアメリカ合衆国憲法は無関係」という認識は、①アメリカ合衆国憲法の、「立法事実:legislative facts」や「立法経緯:legislative history」からも、②アメリカ建国後現在に至るまで(少なくとも、経済活動の自由を制約する社会立法を巡る司法審査が連邦最高裁を慌ただしくさせる19世紀の末葉までの建国直後からの1世紀)、アメリカ合衆国とその諸州が正式に継受した、英国の制定法が保障する権利、および、コモンローやエクイティーやらに結晶していると把握される「人間の記憶さえ拒否するほど古から存在する普遍的で不変的な英国臣民の権利そのものを内容とする米国民の権利」とは別の(A)「自然権としての天賦人権」なるものが司法審査の基準とされたことはないと言えることからも自明なのです。
要は、自治権拡大の要求を超えて英国からの独立に向けてルビコンを渡った13植民地の人々にとっては、最早、「人間の記憶さえ拒否するほど古から存在する普遍的で不変的な英国臣民の権利」を大義名分にしては、独立戦争を戦うことも、独立戦争に向けて諸邦の連帯を強化することも、あるいは、諸邦がその各々の社会統合を強化することもできなかったがゆえに、「英国」や「英国臣民」を超える政治的シンボルとして「天賦人権」を持ち出す必要と実益はあったでしょう。
けれども、独立を達成した後の13邦や13州の人々にとって「天賦人権」なるものは無用の長物。端的に言えば粗大ゴミでしかなかった。なぜならば、彼等がその権利をそれの恣意的な権力から守りたい相手は国王から連邦政府に変わったものの、憲法典を使って彼等がそれを守ることを欲した権利の内容自体は「人間の記憶さえ拒否するほど古から存在する普遍的で不変的な英国臣民の権利そのものを内容とする米国民の権利」以外の何ものでもなかったのだろうから。憲法解釈方法論争の経過と帰趨を読み返す度に、益々強くそう私には感じられます。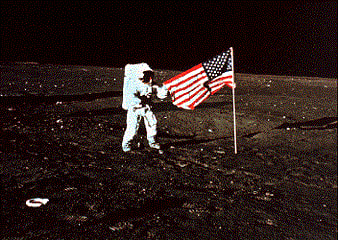
★註:コモンローのヤヌスの貌:自然法としてのコモンローとコモンローの歴史性
最狭義には「コモンロー:common law」とは英国のコモンロー裁判所が紡ぎ上げ編み上げてきた判例法のことですが、時間軸の目盛りを半世紀とか1世紀とか少し長目に設定するとき、それは「普遍妥当・不変不動」と称されながらも、「先例拘束性の原理:doctrine of stare decisis」など歯牙にもかけず、(その硬直性を回避する回路として「エクイティー:equity」が形成されたのですから、確かに、「臨機応変」とまでは言わないけれど、)かなりの変容を経てきたことは今ではよく知られていること。要は、ヤヌスの如くコモンローには二つの貌があるということ。
例えば、「所謂「国会主権の原則:doctrine of Parliamentary Sovereignty」がそれとともに確立したとされる「権利の章典:Bill of Rights」(1689年)以降の、太陽の没することなき大英帝国の版図全体での法の運用を見た場合も、コモンローは普遍的で不変的だったと言えるのか」とか、朝日新聞の安倍ノミックス批判の如きあまり意味のない、かつ、悪趣味な無理難題は控えるとして、
(ⅰa)空間的には大ブリテン島のイングランド地方に限定し、(ⅰb)時間的にも、権利の章典以前の、かつ、(ノルマンコンクエスト(1066年)や(ある慣習が慣習法であるかどうかを裁判所が決める重要な基準時の一つである)「法的記憶:legal memory」の起算点とされるリチャード1世の在位第1年目(1189年)、もしくは、史上有名な最初のマグナカルタ(1215年)ではなく、実は、その後も60回近く更新されたマグナカルタの中でも現在も英国の実定法である版の)マブナカルタ(1297年)以降の、資料も調い/整い、法の運用も比較的安定してきた時期に限ったとしても、(ⅱ)英国の判例法の中でエクイティーから区別される最狭義の意味でのコモンローの内容は、(ⅲ)到底、普遍的や不変的だったとは言えない。
他方、けれども、①正義に適う、②それが法としての効力を持つことには疑問の余地のないものの、その法としての効力根拠を説明することはできない、③人が定めた法(man-made law)よりも高次の(それに反する人定法を無効にできる)、④内容不変の、よって、⑤それを創造するのではなくそれを発見するのが裁判所の役割であるような、⑥人間の記憶さえ拒否するほど古から、⑦英国/米国の社会に普遍的なコモンローが常に存在している。
と、このような法意識が、(ⅰa)(ⅰb)で定義される英国社会どころか、21世紀の英米を含む多くの英米法を継受した社会でもその社会のスタンダードな法意識として存在することも間違いないのだと思います。 
而して、「コモンローと呼ばれる、正しく高次の内容不変の法が我々の社会には普遍的に存在する」という英米法圏の人々の法意識に底礎されてなのでしょうか、英米法圏の人々の善意に悪乗りしてと言うべきでしょうか、世の中には、コモンローを「自然法」と同一視する見解もあります。
ここでは「自然法」の定義は割愛させていただきますけれど、蓋し、確かに、①②③④は自然法の一般的イメージと重なっており、⑥は「ブルジョアジーが「自然法」を錦の御旗に、自分達の要求内容を「自然権」と称してその「自然権」なるものの内容を制定法に盛り込んだ」と評される18世紀-19世紀型自然権の二つの正当化理由(すなわち、理性と伝統)の一つと共通している。
けれども、⑥は「人間理性への信頼」などという(A)「自然権としての天賦人権」がその典型の、18世紀-19世紀型自然権のもう一つの正当化理由とは無縁であり、⑦は自然法の多くが標榜する「人類規模-地球規模」の普遍性の真逆。また、司法機能の正当化の論理の差に着目すれば、実は、⑤においても、そのルールの内容は裁判所が遂行的に形成してきた蓄積の中にこれまた遂行的に確認されるしかないコモンローと、建前上はアプリオリにルールの内容が想定されるフランス革命期に典型的な自然法は似て非なるものと言えるでしょう。
よって、コモンローを「自然法」の一種と呼ぶことは(結局、その議論の是非は「自然法」という用語の定義問題に収斂すのでしょうが)、満更間違いではないけれど、少なくとも、⑤⑥⑦でほぼ真逆な性質を帯びている以上、コモンロー上の権利と(A)「自然権としての天賦人権」とを結びつけることは妥当ではないのです。
<続く>

























