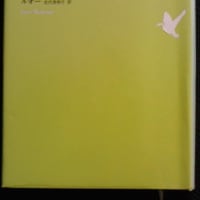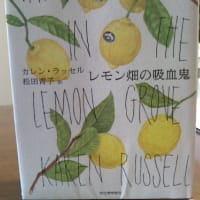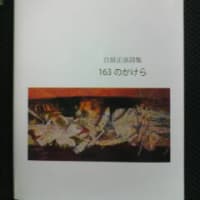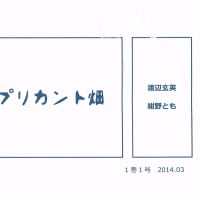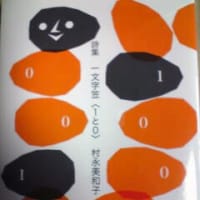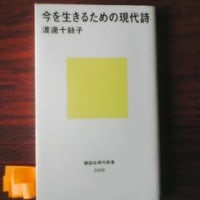言葉の強さに引き寄せられて、言葉の張力に触れてみたくなる詩。
詩は、言葉を衣装とした、様々なる意匠であり、様式であると思う。詩的なるものと詩の距離とは、詩的なるものを詩にする距離である。
で、あれば、中身は? という中身と形式の二分法は、実は、意味をなさない。だが、極端にいえば、中身は空っぽでもいいのかもしれない、逆と比べれば。つまり、伝えたい何かはあるのだが、言葉自体を伝えようとしないものに比べれば。
さらに、で、実際のところ、張りつめた言葉を持っているものは、それ自体で伝えるべき中身を持っているものがほとんどだと思う。これもまた、伝える何かがあると思っているだけのものに比べれば。つまり、表層は、きちんと深層を持っているのだということであり、表層なき深層は、なかなか、これはないということだ。当然といえば、当然。もし、中身という言い方をするのであれば、衣装と意匠と中身とはすでに外に表れて切り離されない状態であるものだ。で、単純な結論に至る。つまり、表層が充実しているものは、それ自体がすでに中身であり、そこに深層があるということだ。そして、強さは、そのあたりに起因する。
藤維夫さんの詩は、その言葉の強さに惹かれてしまう。もちろん、強さにも様々な姿があるのだが、その様々を含めて強さと書く。
詩「遠い場所」は、こう書き出される。第一連、
遠い崖があるかどうかわからずに
むやみに死がさわがしく波だってきた
無茶はわかっていても
どっち付かずの方角を望む
嵐の通り過ぎるのを待つ人のようにじっと考えこんだまま
「崖」に「遠い」という形容詞がつく。「遠い崖」って何だろう、と思ってしまうとつまづくのかもしれない。だが、「遠い崖」がすとんと来る。言葉にベールをかけるのだ。すると、「あるかどうかわからずに」が、そのまま視界のもやのような状態を呼び起こす。「崖があるかどうかわからずに」と書けば、人生の懸崖のようなものだけが意味される(比喩される)のだが、「遠い」が入れば、「遠い」という状態がよぎるのだ。そして、「むやみに死がさわがしく波だってきた」に、この「遠い」が掛かってくる。修飾関係ではないのだ、言葉の残像現象なのだ。認識として不可知ともいえる「死」が、「遠い」はずの認識の彼方から「波だって」くるのだ。つまり、「遠い」が近さに変わっている。寄せる波の距離感が表れる。
で、その先が観念にはいかない。戻ってくる。「無茶はわかっていても」という感慨のような言葉を配置することで、作者に戻る。この「無茶」は前の行の「むやみに」から引き出された音つながりだ。もちろん、意識されてか無意識かはわからない。思考しながら、言葉が言葉として動いているのだ。どちらかだけが走り出すわけではなく、それを聞きとり考えとりながら、言葉が進む。語る人は聞く人だ。いや、聞く人が語れる人なのかもしれない。詩の言葉を作者が聞き分けている。すると、「死」が音のように「波だって」いるのかもしれないとも思えてくる。
そして、行は「どっち付かずの」と、進む。どちらかに決める。あるいは、「どっち付かず」ではない明確な方向を定めればいいのだろうが、人は待機する。待機という実存の延期の時に実存的なのだ。
ここで「どっち」は「無茶」や「わかって」の半角文字の影響を受けている。あるいは「っ」の並び。行は、「無茶は」の「む」から「望む」と閉じる「む」へつながる。立ち止まりを「む」という閉じた音で一瞬完結させる。そして、待機を示す「待つ人」という言葉が書かれ、「考えこんだままだ」に行くときに、また、「っ」の影響を受ける。「じっと」が挿入されているのだ。これらの音を消してしまえば、第一連、実存のためらいは、流れるようなことばの流れで表現されてしまう。藤さんは、そこを聞き分ける。つまり、推敲は、作者の心的状況と言葉の表層を一致させていくようにされているのだ。流麗さをわずかずつ寸断する。そこにいるのは「考え込ん」でいる人である。
この詩は第二連で、明るさに転じるように流れもつくる。
しきりに明るい感覚を思う
行きあう日々の潮騒の痕跡にみちびく
日の終わりから歩むこと
そこでは不在の始まり
うたのこぼれる暗い影は去った
音と形が絡み合う。耳が捉えるものを視覚化しようとするというのだろうか。「行きあう日々」が「潮騒」という音になり、「痕跡」という音の痕跡になる。ところが、この「痕跡」が妙に視覚的なのだ。また、時制がずらされるところで、実体が無化される。「行きあう日々」であって、かつて「行きあった日々」ではないのだ。ここには過去の生きられなかった時間と、将来において生き得ない時間の双方が入り込んでいる。死が身体という実体を連れ去ったとき、意識はそこにとどまるのだろうか。それは、自分自身の生きられなかった時間に残した意識と同じように、死の先にも意識は残り続けるものなのだろうかという問いを可能にする。「日の終わりから歩むこと」という詩句は、そんな思いを想起させる。さらに、「そこでは不在の始まり」なのだ。そして、モーツァルトを訪れた灰色のコートの男のように、未完の「レクイエム」と共に、「うたのこぼれる暗い影は去った」という状態になる時間の到来が記述される。それは「しきりに明るい感覚」として、思われる。
この詩は全四連。このあと、第三連7行のあと、最終連は「音」に触れて、詩を閉じる。音楽は、過去の音を聞いているだけではなく、予想するように、まだ鳴っていない音を聴いているのだと、何かの本で読んだ。そうそう、確認してみると、内田樹が、「〈もう聞こえない音〉を記憶によって、〈まだ聞こえない音〉を先駆的直感によって、現在に引き寄せることで経験している」と、『本は、これから』という岩波新書に書いていた。旋律やリズムと言いながら、人は先取りしながら、やって来る音を捉えているのだろうか。
四季の触手によって生かされた過去はすでに滅びた
須臾の日の強さに保護されたどこにもない場所
音楽の静まるところ たとえばハイドン
ピアノのピッチ
リズムの彷徨う神秘な劇を見たい
音楽は時間であるか。アファナシエフはCDの解説の中で、バッハの空間性を指摘している。「彼の作品に見出すことのできるものは、……人間の宇宙のひろがりの全体なのである」と。うーん、バッハが空間なのだということは何となくわかるような気がする。ハイドンは、どうなのだろう。時間が流れているような気がする。だから、そこには未来の予感が兆すのだろうか。
で、一瞬の中に、立ち止まった時間の中に、現れるのは、空間化された時間の層なのかもしれない。もし、立ち止まった時間というものを設定すれば、時の移ろいである「四季の触手」によって「生かされた過去」という時間は、立ち止まった時間に集積されながら新たな過去を生みだすという営みからは離れ、「滅びた」と言い表されるのかもしれない。四季の循環によって生まれた過去が滅びるとは、無くなることなのだが、それはまた、生み出されないことである。現在の中で蓄積されながら、滅びていく過去。そう、最終連の一行目を少し、ずらすと、二行目にもつながる。
四季の触手によって生かされた、すでに滅びた、過去
こう書くと、時間のねじれを表現してはいないが、文脈はつながる。その立ち止まりの瞬間、「須臾」。すでに滅びた過去が「どこにもない場所」になる。その刹那に、時間が空間的に並び、天体のような姿を現す。その時、星が死滅するときに発するような「日の強さ」の中で「どこにもない場所」が予感される。それは、音楽が終わりながら、さらに音楽が訪れてくる場所であり、意識だけが「日の終わり」から歩み出していく地点なのだ。
詩は、言葉を衣装とした、様々なる意匠であり、様式であると思う。詩的なるものと詩の距離とは、詩的なるものを詩にする距離である。
で、あれば、中身は? という中身と形式の二分法は、実は、意味をなさない。だが、極端にいえば、中身は空っぽでもいいのかもしれない、逆と比べれば。つまり、伝えたい何かはあるのだが、言葉自体を伝えようとしないものに比べれば。
さらに、で、実際のところ、張りつめた言葉を持っているものは、それ自体で伝えるべき中身を持っているものがほとんどだと思う。これもまた、伝える何かがあると思っているだけのものに比べれば。つまり、表層は、きちんと深層を持っているのだということであり、表層なき深層は、なかなか、これはないということだ。当然といえば、当然。もし、中身という言い方をするのであれば、衣装と意匠と中身とはすでに外に表れて切り離されない状態であるものだ。で、単純な結論に至る。つまり、表層が充実しているものは、それ自体がすでに中身であり、そこに深層があるということだ。そして、強さは、そのあたりに起因する。
藤維夫さんの詩は、その言葉の強さに惹かれてしまう。もちろん、強さにも様々な姿があるのだが、その様々を含めて強さと書く。
詩「遠い場所」は、こう書き出される。第一連、
遠い崖があるかどうかわからずに
むやみに死がさわがしく波だってきた
無茶はわかっていても
どっち付かずの方角を望む
嵐の通り過ぎるのを待つ人のようにじっと考えこんだまま
「崖」に「遠い」という形容詞がつく。「遠い崖」って何だろう、と思ってしまうとつまづくのかもしれない。だが、「遠い崖」がすとんと来る。言葉にベールをかけるのだ。すると、「あるかどうかわからずに」が、そのまま視界のもやのような状態を呼び起こす。「崖があるかどうかわからずに」と書けば、人生の懸崖のようなものだけが意味される(比喩される)のだが、「遠い」が入れば、「遠い」という状態がよぎるのだ。そして、「むやみに死がさわがしく波だってきた」に、この「遠い」が掛かってくる。修飾関係ではないのだ、言葉の残像現象なのだ。認識として不可知ともいえる「死」が、「遠い」はずの認識の彼方から「波だって」くるのだ。つまり、「遠い」が近さに変わっている。寄せる波の距離感が表れる。
で、その先が観念にはいかない。戻ってくる。「無茶はわかっていても」という感慨のような言葉を配置することで、作者に戻る。この「無茶」は前の行の「むやみに」から引き出された音つながりだ。もちろん、意識されてか無意識かはわからない。思考しながら、言葉が言葉として動いているのだ。どちらかだけが走り出すわけではなく、それを聞きとり考えとりながら、言葉が進む。語る人は聞く人だ。いや、聞く人が語れる人なのかもしれない。詩の言葉を作者が聞き分けている。すると、「死」が音のように「波だって」いるのかもしれないとも思えてくる。
そして、行は「どっち付かずの」と、進む。どちらかに決める。あるいは、「どっち付かず」ではない明確な方向を定めればいいのだろうが、人は待機する。待機という実存の延期の時に実存的なのだ。
ここで「どっち」は「無茶」や「わかって」の半角文字の影響を受けている。あるいは「っ」の並び。行は、「無茶は」の「む」から「望む」と閉じる「む」へつながる。立ち止まりを「む」という閉じた音で一瞬完結させる。そして、待機を示す「待つ人」という言葉が書かれ、「考えこんだままだ」に行くときに、また、「っ」の影響を受ける。「じっと」が挿入されているのだ。これらの音を消してしまえば、第一連、実存のためらいは、流れるようなことばの流れで表現されてしまう。藤さんは、そこを聞き分ける。つまり、推敲は、作者の心的状況と言葉の表層を一致させていくようにされているのだ。流麗さをわずかずつ寸断する。そこにいるのは「考え込ん」でいる人である。
この詩は第二連で、明るさに転じるように流れもつくる。
しきりに明るい感覚を思う
行きあう日々の潮騒の痕跡にみちびく
日の終わりから歩むこと
そこでは不在の始まり
うたのこぼれる暗い影は去った
音と形が絡み合う。耳が捉えるものを視覚化しようとするというのだろうか。「行きあう日々」が「潮騒」という音になり、「痕跡」という音の痕跡になる。ところが、この「痕跡」が妙に視覚的なのだ。また、時制がずらされるところで、実体が無化される。「行きあう日々」であって、かつて「行きあった日々」ではないのだ。ここには過去の生きられなかった時間と、将来において生き得ない時間の双方が入り込んでいる。死が身体という実体を連れ去ったとき、意識はそこにとどまるのだろうか。それは、自分自身の生きられなかった時間に残した意識と同じように、死の先にも意識は残り続けるものなのだろうかという問いを可能にする。「日の終わりから歩むこと」という詩句は、そんな思いを想起させる。さらに、「そこでは不在の始まり」なのだ。そして、モーツァルトを訪れた灰色のコートの男のように、未完の「レクイエム」と共に、「うたのこぼれる暗い影は去った」という状態になる時間の到来が記述される。それは「しきりに明るい感覚」として、思われる。
この詩は全四連。このあと、第三連7行のあと、最終連は「音」に触れて、詩を閉じる。音楽は、過去の音を聞いているだけではなく、予想するように、まだ鳴っていない音を聴いているのだと、何かの本で読んだ。そうそう、確認してみると、内田樹が、「〈もう聞こえない音〉を記憶によって、〈まだ聞こえない音〉を先駆的直感によって、現在に引き寄せることで経験している」と、『本は、これから』という岩波新書に書いていた。旋律やリズムと言いながら、人は先取りしながら、やって来る音を捉えているのだろうか。
四季の触手によって生かされた過去はすでに滅びた
須臾の日の強さに保護されたどこにもない場所
音楽の静まるところ たとえばハイドン
ピアノのピッチ
リズムの彷徨う神秘な劇を見たい
音楽は時間であるか。アファナシエフはCDの解説の中で、バッハの空間性を指摘している。「彼の作品に見出すことのできるものは、……人間の宇宙のひろがりの全体なのである」と。うーん、バッハが空間なのだということは何となくわかるような気がする。ハイドンは、どうなのだろう。時間が流れているような気がする。だから、そこには未来の予感が兆すのだろうか。
で、一瞬の中に、立ち止まった時間の中に、現れるのは、空間化された時間の層なのかもしれない。もし、立ち止まった時間というものを設定すれば、時の移ろいである「四季の触手」によって「生かされた過去」という時間は、立ち止まった時間に集積されながら新たな過去を生みだすという営みからは離れ、「滅びた」と言い表されるのかもしれない。四季の循環によって生まれた過去が滅びるとは、無くなることなのだが、それはまた、生み出されないことである。現在の中で蓄積されながら、滅びていく過去。そう、最終連の一行目を少し、ずらすと、二行目にもつながる。
四季の触手によって生かされた、すでに滅びた、過去
こう書くと、時間のねじれを表現してはいないが、文脈はつながる。その立ち止まりの瞬間、「須臾」。すでに滅びた過去が「どこにもない場所」になる。その刹那に、時間が空間的に並び、天体のような姿を現す。その時、星が死滅するときに発するような「日の強さ」の中で「どこにもない場所」が予感される。それは、音楽が終わりながら、さらに音楽が訪れてくる場所であり、意識だけが「日の終わり」から歩み出していく地点なのだ。