
まず、この語り口調の平易さにほだされる。
さらに整理のよさと手際の周到さでわかりやすいという気にさせる。それで、この本、一気読みできるわけだが、本来ここにあるものの持っているわかりにくさは、思想というもの自体のわかりにくさであるわけで、さらに思想が政治思想として動く昭和を捉えようとしているものであれば、致し方ないのでは、と思う。ただ、時間軸としての戦前=戦後という区分けではなく、昭和が持っていた「二つの貌」を体現している人物を定点にして論じている本書は、この先を同じ著者の別の本で読みたくさせる魅力を持っていた。
著者は、「理の軸」と「気の軸」を設定する。そして、「理の軸」の右に平泉澄を左に丸山眞男を置く。この「理の軸」は「政治理念によって自己形成することを生の理想とし、理念によって論理的に再構成することを重視」する軸とされる。そして、平泉澄を「皇国史観というものを非常に明晰に、論理的に作り上げた人物」として右に配置する。一方の丸山眞男を「国民主権」にこだわり、「民主主義の理念」を「人間の生の理想としてみんなに身に付けてもらいたい」と考えていると捉え、現実を「遠慮なく批判」していく人物として左に置いている。そして、この二人がそれぞれ右翼左翼の両方から反発されるのは、右翼左翼からの反発というよりも発想方法の違う「気の軸」からの反発だったのではないかと論じている。
では、「気の軸」には誰を持ってきているかといえば、ポジティヴな方向が西田幾多郎、ネガティヴな方向が蓑田胸喜となる。ポジは積極的、創造的、ネガは消極的、否定的と考えてくださいと語られる。「気の軸」の発想方法は、「絶対的なるものを求め、根源からの起動を目指し、流れや勢いに乗って気力を競い合います」とされ、「普通の意味で政治的ではない。この世のもの以外のものを見ている」と「理の軸」の政治性に対比させる。
ところが、昭和の思想は、二〇世紀の思想であり、二〇世紀の思想は、国家と社会が区別しえない関係になっているという点に置いて、政治思想の様相を帯びるということで、いずれもが、「昭和期の引力」に引きつけられ、政治に関与していってしまうとして、著者は「昭和の思想」を俯瞰していくのだ。
この「立体交差する二つの軸」から「昭和の奇妙な精神風土の本質」を解読しようとしている。
平泉澄や蓑田胸喜について、ボクは全く知らなかった。この人物の紹介を受けたというだけでも、この本、面白かった。
さらに、最終章の「二〇世紀思想史としての昭和思想」での、二〇世紀を「政治化の時代」として「国家がトータル」になっていくという論述がなかなかだった。
では、二一世紀は。
植村和秀は「あとがき」で、「グローバル化と情報化の急進展による、歴史的な変動期」に突入していると書いている。であればこそ、昭和の中にあった複数の思想の解読が必要とされるのかも知れない。
さらに整理のよさと手際の周到さでわかりやすいという気にさせる。それで、この本、一気読みできるわけだが、本来ここにあるものの持っているわかりにくさは、思想というもの自体のわかりにくさであるわけで、さらに思想が政治思想として動く昭和を捉えようとしているものであれば、致し方ないのでは、と思う。ただ、時間軸としての戦前=戦後という区分けではなく、昭和が持っていた「二つの貌」を体現している人物を定点にして論じている本書は、この先を同じ著者の別の本で読みたくさせる魅力を持っていた。
著者は、「理の軸」と「気の軸」を設定する。そして、「理の軸」の右に平泉澄を左に丸山眞男を置く。この「理の軸」は「政治理念によって自己形成することを生の理想とし、理念によって論理的に再構成することを重視」する軸とされる。そして、平泉澄を「皇国史観というものを非常に明晰に、論理的に作り上げた人物」として右に配置する。一方の丸山眞男を「国民主権」にこだわり、「民主主義の理念」を「人間の生の理想としてみんなに身に付けてもらいたい」と考えていると捉え、現実を「遠慮なく批判」していく人物として左に置いている。そして、この二人がそれぞれ右翼左翼の両方から反発されるのは、右翼左翼からの反発というよりも発想方法の違う「気の軸」からの反発だったのではないかと論じている。
では、「気の軸」には誰を持ってきているかといえば、ポジティヴな方向が西田幾多郎、ネガティヴな方向が蓑田胸喜となる。ポジは積極的、創造的、ネガは消極的、否定的と考えてくださいと語られる。「気の軸」の発想方法は、「絶対的なるものを求め、根源からの起動を目指し、流れや勢いに乗って気力を競い合います」とされ、「普通の意味で政治的ではない。この世のもの以外のものを見ている」と「理の軸」の政治性に対比させる。
ところが、昭和の思想は、二〇世紀の思想であり、二〇世紀の思想は、国家と社会が区別しえない関係になっているという点に置いて、政治思想の様相を帯びるということで、いずれもが、「昭和期の引力」に引きつけられ、政治に関与していってしまうとして、著者は「昭和の思想」を俯瞰していくのだ。
この「立体交差する二つの軸」から「昭和の奇妙な精神風土の本質」を解読しようとしている。
平泉澄や蓑田胸喜について、ボクは全く知らなかった。この人物の紹介を受けたというだけでも、この本、面白かった。
さらに、最終章の「二〇世紀思想史としての昭和思想」での、二〇世紀を「政治化の時代」として「国家がトータル」になっていくという論述がなかなかだった。
では、二一世紀は。
植村和秀は「あとがき」で、「グローバル化と情報化の急進展による、歴史的な変動期」に突入していると書いている。であればこそ、昭和の中にあった複数の思想の解読が必要とされるのかも知れない。










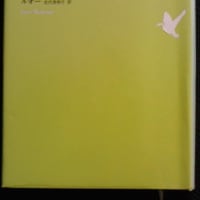
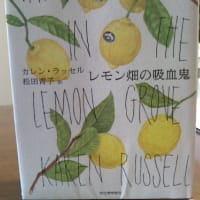
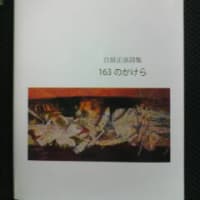
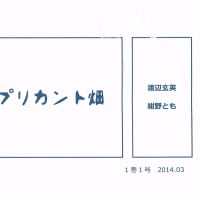
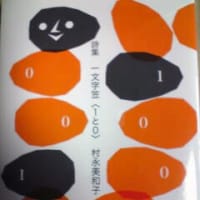
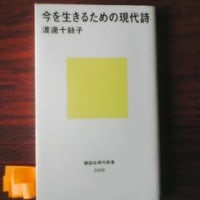









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます