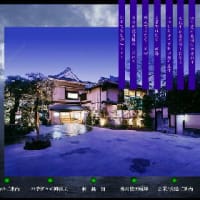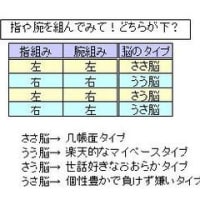自民党の総裁選挙で安倍元幹事長が総裁に選出された。選挙前から「できレース」と揶揄されるほど圧倒的な支持を得ての出馬だったので、そのこと自体はさほど驚くことでもない。しかし、この選挙期間中、総裁候補として名乗りを挙げた3氏がさまざまな場面で主張した内容については驚くべきことや危惧を感じさせられることが多々あった。
私は政治に関してはまったく無知であり、あのドロドロした世界と関わりを持とうなどという気は毛頭ないし、誰が総裁になろうが一向に構わないとも思っている。
しかし、大いに懸念されるのは彼らがそろって「教育問題」を取り上げ、教育基本法の改正をはじめとする教育改革を主張している点である。
そもそも教育の専門職ではないという意味で、教育について深い考えや理解を持っているとは思えない一介の国会議員が、教育についてさも知り尽くしているかのごとく口を差し挟むことについて違和感を覚えるのは私一人であろうか。
彼らの教育に対する考えは、せいぜいが「自分の受けてきた学校教育における経験」にしか基づかないものであり、自分自身が骨身をけずるようにして実践する教育活動の経験に基づいたものでないことは言うまでもない。
特に驚かされたことは、先日の候補者による討論会では、安倍候補が「教育バウチャー」に関する話題の中で『保護者など外部の評価を導入し、選ばれない学校が出てくると、そこはしっかりと乗り込んでいって根本的に問題を是正していく』と思い上がりとしか思えないような発言をしたことである。(傍点筆者)
日本では幸いなことに誰もが平等に教育を受ける権利を有し、そのおかげで誰もが義務教育を受けた経験を持っている。
今日のように「教育問題」がさまざまに論じられ大きく取り上げられる背景には、誰もがそうした「教育を受けた経験」があり、その経験をもとに教育についての自分の考えや意見あるいは感想を持っていることがあるということも否定できない。そして大いに論議を展開し、より望ましい教育をめざすことはよいことに違いない。
しかし、それだからと言ってそれらが的を射ており、問題の解決に役立つものばかりであるかどうかは大いに疑問である。なぜなら、その意見や考えの基準となっているのが、あくまでも「自分の受けた教育」という狭い範囲のものでしかないからである。
決してそうした意見を軽視するわけではないが、それで「教育」を論じ、教育について起きている多様な問題の解決が望めるのであれば、そして望ましい教育活動が一朝一夕に行えるのであれば、教育専門職である教師が日常研究や研修に励まずとも、相応の学校で学んだという経験だけで何の問題もなく教育活動を展開できてしまうはずである。
しかし「教育」とはそう簡単なものではない。
望ましい教育を求め、学校の再生を願い、日夜努力し、問題の解決に向けて苦慮し励む一方で、教育研究にも努めているのは、教育が「生き物」であり、単なる指導技術で片づけることのできない専門性が不可欠だからである。
教育観、子ども観、人間観、指導観などについての深い理解と教育に対する高い志、さらにはそれらに裏付けられた指導技術、教育者として自己の教育活動を振り返り見極めることのできる透徹した目などの資質や能力を高めるために、児童・生徒と真摯に向き合っているのが現場の教師である(はずである)。
学校教育とは無縁の第三者による学校評価を行うとか「教育バウチャー制度」を導入して学校間を競わせ、うまくいかない学校には「乗り込んでいって問題を是正する」などという発言からは、本当に教育について深い理解と考えを持ち『どうすれば真に子どもにとって意味のある教育になるか』という視点で教育問題にあたろうとする姿勢は窺えない。
そのような一夜漬けのように解決できるような問題であれば、学校現場はその対処に苦慮するようなことはなかったはずである。そして、そのように一朝一夕に解決できるのだとすれば、それはいつ剥落しても不思議はないほどの「とってつけたような表面的な解決」でしかない。
問題の根っこの部分、核の部分、本質的な部分を突き止め、それを改善していくには、小手先の安易な手段ではかなわないのは火を見るより明らかである。
モノを生産する活動であれば、均質かつコストパフォーマンスの良い製品を効率的に生産することをめざして方法の改善を図るといったことは可能であろう。そうした場では、他と競争しより高い生産性を生み出すことも可能であろう。それは生み出すものが「モノ」だからである。しかし、「人間の育ち」を期する教育ではそうはいかない。同じ方法で指導を受けても、それが効果的である子どももいるしそうでない子どももいるからである。
子どもはベルトコンベアの上では育たないにもかかわらず、学校を工場と勘違いしているからこそ、必要以上に「競争」を言い立て、成果を求め、均質さを望む発言が後を絶たないのではないか。
そして、こうした発言から窺えるのは、学校で起きている諸問題は、教師の力量不足や努力不足に起因すると考えているのはないかということである。
確かに、一部にはそうした資質や能力に欠ける教師がいることも否定できないが、多くの教師は熱意をもって教育活動に取り組んでいるのである。
それではなぜ成果が目に見えて現れないか、現れないばかりか問題点ばかりが浮き彫りになったり喧伝されてしまうのかと言えば、その多くはこれまでの実践経験や研究の成果では対処しきれないほどに社会が、そして家庭が、さらには子どもが変わってしまっている点にあるのではないかと思われるのだ。
学習意欲の低下の問題にしても校内暴力の低年齢化の問題にしても、これまで社会や家庭が無意図的に行ってきた教育作用が低減し、「人間として育つ」バックボーンが崩壊しつつあることにその原因があるとしか思えないのである。
そこに目を向けず、学校の努力不足や教師力の低下だけを問題の原因として仕立て上げたところで、真の教育改革にはならないことは言うまでもないし、制度をいじりまわしても何の意味もないことは論を待たない。
まずは為政者の「競争させればなんとかなる」という考えを改めること、教育そのものについてより真摯に受け止めようとする心情を持つことこそが望まれる。
安倍政権が誕生したからと言って、かれが提言していることが文教政策として実現可能であるかどうかは定かではないが、そうした安易な考えをもって教育を考え変えようとしていることから目を離すことはできない。
私は政治に関してはまったく無知であり、あのドロドロした世界と関わりを持とうなどという気は毛頭ないし、誰が総裁になろうが一向に構わないとも思っている。
しかし、大いに懸念されるのは彼らがそろって「教育問題」を取り上げ、教育基本法の改正をはじめとする教育改革を主張している点である。
そもそも教育の専門職ではないという意味で、教育について深い考えや理解を持っているとは思えない一介の国会議員が、教育についてさも知り尽くしているかのごとく口を差し挟むことについて違和感を覚えるのは私一人であろうか。
彼らの教育に対する考えは、せいぜいが「自分の受けてきた学校教育における経験」にしか基づかないものであり、自分自身が骨身をけずるようにして実践する教育活動の経験に基づいたものでないことは言うまでもない。
特に驚かされたことは、先日の候補者による討論会では、安倍候補が「教育バウチャー」に関する話題の中で『保護者など外部の評価を導入し、選ばれない学校が出てくると、そこはしっかりと乗り込んでいって根本的に問題を是正していく』と思い上がりとしか思えないような発言をしたことである。(傍点筆者)
日本では幸いなことに誰もが平等に教育を受ける権利を有し、そのおかげで誰もが義務教育を受けた経験を持っている。
今日のように「教育問題」がさまざまに論じられ大きく取り上げられる背景には、誰もがそうした「教育を受けた経験」があり、その経験をもとに教育についての自分の考えや意見あるいは感想を持っていることがあるということも否定できない。そして大いに論議を展開し、より望ましい教育をめざすことはよいことに違いない。
しかし、それだからと言ってそれらが的を射ており、問題の解決に役立つものばかりであるかどうかは大いに疑問である。なぜなら、その意見や考えの基準となっているのが、あくまでも「自分の受けた教育」という狭い範囲のものでしかないからである。
決してそうした意見を軽視するわけではないが、それで「教育」を論じ、教育について起きている多様な問題の解決が望めるのであれば、そして望ましい教育活動が一朝一夕に行えるのであれば、教育専門職である教師が日常研究や研修に励まずとも、相応の学校で学んだという経験だけで何の問題もなく教育活動を展開できてしまうはずである。
しかし「教育」とはそう簡単なものではない。
望ましい教育を求め、学校の再生を願い、日夜努力し、問題の解決に向けて苦慮し励む一方で、教育研究にも努めているのは、教育が「生き物」であり、単なる指導技術で片づけることのできない専門性が不可欠だからである。
教育観、子ども観、人間観、指導観などについての深い理解と教育に対する高い志、さらにはそれらに裏付けられた指導技術、教育者として自己の教育活動を振り返り見極めることのできる透徹した目などの資質や能力を高めるために、児童・生徒と真摯に向き合っているのが現場の教師である(はずである)。
学校教育とは無縁の第三者による学校評価を行うとか「教育バウチャー制度」を導入して学校間を競わせ、うまくいかない学校には「乗り込んでいって問題を是正する」などという発言からは、本当に教育について深い理解と考えを持ち『どうすれば真に子どもにとって意味のある教育になるか』という視点で教育問題にあたろうとする姿勢は窺えない。
そのような一夜漬けのように解決できるような問題であれば、学校現場はその対処に苦慮するようなことはなかったはずである。そして、そのように一朝一夕に解決できるのだとすれば、それはいつ剥落しても不思議はないほどの「とってつけたような表面的な解決」でしかない。
問題の根っこの部分、核の部分、本質的な部分を突き止め、それを改善していくには、小手先の安易な手段ではかなわないのは火を見るより明らかである。
モノを生産する活動であれば、均質かつコストパフォーマンスの良い製品を効率的に生産することをめざして方法の改善を図るといったことは可能であろう。そうした場では、他と競争しより高い生産性を生み出すことも可能であろう。それは生み出すものが「モノ」だからである。しかし、「人間の育ち」を期する教育ではそうはいかない。同じ方法で指導を受けても、それが効果的である子どももいるしそうでない子どももいるからである。
子どもはベルトコンベアの上では育たないにもかかわらず、学校を工場と勘違いしているからこそ、必要以上に「競争」を言い立て、成果を求め、均質さを望む発言が後を絶たないのではないか。
そして、こうした発言から窺えるのは、学校で起きている諸問題は、教師の力量不足や努力不足に起因すると考えているのはないかということである。
確かに、一部にはそうした資質や能力に欠ける教師がいることも否定できないが、多くの教師は熱意をもって教育活動に取り組んでいるのである。
それではなぜ成果が目に見えて現れないか、現れないばかりか問題点ばかりが浮き彫りになったり喧伝されてしまうのかと言えば、その多くはこれまでの実践経験や研究の成果では対処しきれないほどに社会が、そして家庭が、さらには子どもが変わってしまっている点にあるのではないかと思われるのだ。
学習意欲の低下の問題にしても校内暴力の低年齢化の問題にしても、これまで社会や家庭が無意図的に行ってきた教育作用が低減し、「人間として育つ」バックボーンが崩壊しつつあることにその原因があるとしか思えないのである。
そこに目を向けず、学校の努力不足や教師力の低下だけを問題の原因として仕立て上げたところで、真の教育改革にはならないことは言うまでもないし、制度をいじりまわしても何の意味もないことは論を待たない。
まずは為政者の「競争させればなんとかなる」という考えを改めること、教育そのものについてより真摯に受け止めようとする心情を持つことこそが望まれる。
安倍政権が誕生したからと言って、かれが提言していることが文教政策として実現可能であるかどうかは定かではないが、そうした安易な考えをもって教育を考え変えようとしていることから目を離すことはできない。