
昌益が読んだと思われる書物は実に膨大な冊数にのぼると推察される。「大学」「中庸」「論語」「孟子」「易経」「書経」「詩経」「礼記」「河図・洛書」「春秋左氏伝」「孝経」「呂氏春秋」「渾天記」「白虎通義」「周易正義」「易伝」「周易本義」「太極図説」「性理大全」「朱子語類」「乾坤弁説」「天学指要」「墨子」「楊子」「老子」「荘子」「列子」「准南子」「韓非子」「抱朴子」「山海経」「六韜」「三略」「呉子」「司馬法」「唐太宗李衛公対問」「史記」「商書」「漢書」「後漢書」「晋書」「宋書」「斎書」「唐書」「元書」「明書」「説文」「釈名」「広雅」「字彙」「文迸」「三体唐詩迸」「法華経」「涅槃経」「金剛経」「大般若経」…
昌益は「立拔」(たてうち)という言葉を使っている。この言葉の意味を求めて、多くの研究者が大槻文彦の「大言海」をはじめ、辞書類を当たったが出ていない。現代の「広辞苑」等にも載っていない。やがて昔の鉱山で使われていた専門用語ではないかということになった。
果たせるかな、秋田藩士の黒沢元重が書いた「鉱山至宝要録」に「立拔」という言葉が発見されたのである。どのような意味かは、現代の鉱山技師でも分からぬそうだが、江戸時代の鉱山専門用語らしい。昌益が「鉱山至宝要録」を読んだか、鉱山技師から話を聞いた可能性が高い。
昌益は関心領域が非常に広い人であった。彼が「自然心営道」「統道真伝」で触れたことを、現代の学問の範疇で言えば、哲学、倫理学、社会学、政治・経済学、軍事学、歴史学、宗教学、地理学、暦学、数学、天文学、気象学、医学、薬学、農学、動植物学、文字学、音韻学に及ぶ。まさに百科全書派である。
昌益はフランスの百科全書派の人々と同世代人である。百科全書派とはディドロ、ダランペール等が企てた「百科全書」の編纂・出版事業と、彼らとその執筆者の関心領域の広大さを表現した呼称である。
この百科全書の出版事業に反対する強大な抵抗勢力がいた。日本でもなじみ深い「イエズス会」である。イエズス会は、ディドロやダランペールたちが王権の破壊と無信仰を勧めているとして国王に働きかけ、様々な妨害工作をして発禁処分に追い込んだ。
ディドロはこの非合法となった編纂事業を二十一年間かけて続け、ついに出版化した。執筆者はヴォルテール、モンテスキュー、ケネー、テュルゴー、ルソーらである。
注目したいのはフランソワーズ・ケネーである。彼は医師であった。しかも国王の侍医である。ケネーは1758年、一国の経済循環の総体を一枚の大きな紙に数学的に表現して見せた。これが「経済表」である。
彼は重商主義によって疲弊したフランスを立て直すために農業を重視し、国家の繁栄は農業の発展の上にのみ実現することを表明した。我々は高校時代、ケネーを重農主義・農本主義と教えられたものである。
ケネーは世界で初めて「一国の経済循環の総体=国家の経済力」「経済力=国家の力」であると示したのである。アダム・スミスと共に経済学の父と呼ばれる由縁である。ちなみにA・スミスとケネー、ヴォルテール、テュルゴー等は親しかった。
それにしても、この百科全書派と呼ばれる総合知の人々がヨーロッパに出現した同時代、彼らと何ら交渉もなく知識の流入も影響もなかった鎖国時代の日本に、安藤昌益のような総合知の思想家が出現した不思議を思わざるを得ない。これが世界の同時的共振性なのであろう。昌益とルソーが共振し、昌益とケネーが共振した…。
ところで、昌益の一、二世代あとに、加賀の浪人・本多利明が出た。狩野亨吉が本多を発掘したことは先に触れた。本多もまた、数学、天文学、暦学、経済学という広範な知の人であった。彼は「日本国」の総体としての「経済力」を最初に提唱・把握した人なのである。その上で、国産増強、北方開発、対外交易すなわち開国を説いた。現代に通じる経済学者と言える。
さて、刊本「自然真営道」前編が三冊発見されたことは先に触れた。この版元は京都の書肆・小川屋源兵衛である。この刊本には二種類ある。奥付の初刷が「宝暦三癸酉三月 江戸 松葉清兵衛 京都 小川屋源兵衛」となったものである。これは村上寿秋氏の家から発見されたことから「村上本」と呼ばれている。これと全く同じ日付でありながら、松葉清兵衛の名前が削られた小川屋源兵衛の単独刊行の後刷ものを「慶応本」という。慶応義塾大学の所蔵本である。
松葉清兵衛は江戸の書肆で屋号は万屋松葉軒といい、上方書籍の取次で知られた。また彼は江戸書物屋仲間の行司を務める江戸出版界の有力者であった。「江戸書物仲間行司」とは、江戸出版業界の自己検閲制度である。
「書肆が書籍を刊行上梓せんとする時は、それに先って草稿を添へて、仲間行司に開板願を差し出すのである。行司は御法度、禁制に抵触することなき哉、…類板に非ざるか等を吟味し…なんら支障なき時に始めて行司はその願書に奥印証明をなし、町奉行所にその開板許可を申請、…奉行所においてさらに之を検閲した上、開板を許可するのである。…草稿が脱稿されてから刷り上がるまでには五年とか八年を要することも珍しくなかった」(蒔田稲城「京阪書籍商史」)
八戸の昌益が、京都の小川屋源兵衛に草稿を送る。三百部くらいでも二百両くらいかかるという。狩野亨吉が草稿の表紙を剥がした反故紙の中に、昌益の借金の申し込みに対する断りの手紙を発見している。おそらく出版のための金策だったのだろう。この刊本の費用は神山親子が捻出したのかも知れない。
小川屋源兵衛は出版リスクの軽減と江戸・関東・関東以北の流通を考えて、有力書肆で仲間行司の万屋松葉軒・松葉清兵衛に合版(あいばん)を持ちかけた。そして見本刷りを松葉軒に送ったのである。この三巻本は哲学批判が主で、激越な社会批判は書かれていない。しかし何度も読み返した松葉清兵衛は「幕府出版条目」に抵触する記述を見つけた。
それは「暦道の自然論」の部分である。幕府の暦制に対する公然たる批判の論述である。清兵衛は小川屋源兵衛に異議と訂正を求めたのであろう。この部分の削除か、かなりの書き直しを求めたのだ。その上で合版も取次もを降りたものと思われる。小川屋は京都書物屋仲間行司にこの本の販売を停止する旨伝え、昌益に「暦道の自然論」を「国々、自然の気行論」に書き改めさせたのである。「国々、自然の気行論」では暦という文字も暦制批判も消えた。
このように初刷本は著者の昌益と、小川屋源兵衛と松葉清兵衛が秘匿し(このいずれかが村上家に入ったのだ)、改めて宝暦四年の六月に出版された(慶応本)のである。
また、この本で予告された「自然真営道」後編と「孔子一世弁記」は、今もって発見に至っておらず、おそらく出版は立ち消え、未刊行となったものと思われている。
この三巻の刊本を、狩野亨吉も、その後の昌益研究者の三枝博音、服部之聡、丸山真男らも、完成しつつあった百巻本から公にすることが可能な部分を抄出したものと見ている。しかし西尾陽太郎は、先ず三巻本が完成し、小川屋が予告した後編と「孔子一世弁記」はその後に書かれる予定だったもので、後編とは百巻本のことではないかとしている。…
ところでこの刊本は、ほとんど読まれ影響を与えた形跡がない。おそらく読みづらく、手にした者を呆れさせたのだ。
近年、尾崎まとみが、小川屋の出版から一月後に北越の中岡一二斎が読後感を批判的に書いていることを発見している。たしかに読者はいたのである。そしてなにより、小川屋源兵衛の寺町通六角下ると、門人となった明石龍映、有来静香の住居はご近所なのである。
大坂の森映確、志津貞中は道修町の人間であることから薬種屋と思われる。おそらく彼らは、昌益を京都の味岡三伯の下での修業時代から見知っていたのではなかろうか。修業中の青年医師昌益は、薬種屋、医師仲間、書肆たち(有名書肆・小川屋多左衛門一族)からも注目されていたのではないか。
川原衛門が三井家の顧客と同一人物ではないかと推理している大塚屋鐵次郎も薬種屋であることから、もしかすると大坂道修町の人かも知れない。
さて、江戸書物屋仲間行司の万屋松葉軒・松葉清兵衛を慌てさせた、昌益の「暦道の自然論」の暦制批判、暦道批判が、なぜ幕府批判とされて発禁・お縄になるものだったのか、後述したい。これは一時ブームとなった陰陽道の安倍清明からつながる実に興味深い歴史話なのである。
昌益の「暦道の自然論」は〈暦の自り然なるあり方〉の論である。暦の「ひとりすなる」あり方と読む。万屋松葉軒・松葉清兵衛は、この論述のどこが「幕府出版条目」に抵触すると見たのだろうか。安永寿延によれば、清兵衛はその第一条「みだりに異説を成すの儀」を恐れたのだと言う。
ちなみに安永は、後々これで取締の手が昌益に伸びはじめ、彼はその危険を察知して、八戸を逃れて二井田移住を決意したのだと推察しているが、私はこれを信じられない。
暦は古代中国以来、昌益の認識通り「天下の大事、万国の大本」である。だから、国家の施政者からすれば不可侵の権利なのである。昌益が「暦道の自然論」を書いた頃、貞享暦はその採用からすでに六十年ほど経っていた。
その暦法は地方の農業生産の現場では全く現実的でない。それは自然のリズムに沿う直耕の現場を、混乱させるばかりである。「暦道の自然論」は、農業の生産現場、直耕の現場の農事暦、自然(ひとりすなる)のリズム、気行のリズムとは齟齬があることを指摘したものだ。幕府の貞享(じょうきょう)暦統制は私法であると、昌益は批判したのだ。
さて、古代より明治以前まで、暦の編暦権と出版権は国家的な権益であり、国家の統制力を推し量るものであったことは確かである。これは現代の我々では想像もつかぬことだ。もっとも明治五年十一月、政府が突然太陰暦から太陽暦へと改暦したのは、財政難のためであったらしい。これは余談である。
三年ごとに閏年(一年が十三ヶ月ある)がやって来ると、その年は官吏に十三ヶ月分の給料を支払わねばならない。閏年の明治元年、三年は官吏の給料は年俸制であったが、それ以後月給制となっていた。ところが来る明治六年は閏年である。明治政府に十三ヶ月分の給料を支払う財政的余力はなかったのだ。政府は突然、明治五年の十二月三日をもって太陽暦の明治六年一月一日とした。十二月が二日しかないことから、「十二月分の給料は支払わなくてもよかろう」と、まんまと二ヶ月分の官吏の給料を浮かしたのである。(岡田芳郎「暦ものがたり」)
貞亨元年(1687年)五代将軍綱吉の時世に、幕府は八百年以上続いた中国渡来の「宣明暦(せんみょうれき)」を廃し、「貞享暦」を採用した。改暦は政治的・文化的・国家的な大事業である。幕府の威信がかかっている。
宣明暦は唐の暦法で、九世紀半ばに日本に渤海大使が伝えたものである。しかし実際の季節の移り変わりと齟齬を生じて、暦としての信頼性を失っていた。渋川春海が、誤りが大きい宣明暦から、日本の風土に合った新しい暦法に改暦するよう幕府に建言した。春海は土御門神道を安倍泰福に学んだ人である。彼の建言は受け入れられて、幕府天文方を命じられた。幕府は春海が創案した大和暦を、「貞享暦」として改暦に踏み切ったのである。
しばらく、暦の歴史について逸脱してみたい。
先ず賀茂氏の話からである。古代、鴨族は葛族と共に最も早い時期の三、四世紀頃に、韓半島から古代日本に渡来した一族と考えられている。おそらく天皇家よりずっと早く渡来し、土着した。鴨族と葛族は同根で、その後住んだ集落として別れたものであろう。共に奈良の葛城地方を一大本拠として勢力を誇った。葛氏は当時の大王だったのである。
鴨氏は占術・祈祷・呪術を得意とした。鴨氏が大国主神の裔を祀ったものが賀茂神社である。その後一族は、山城や京など各地に移り住み、鴨、賀茂、加茂、蒲生などを名乗った。その名を加茂川、上賀茂神社、下賀茂神社などに留めること枚挙にいとまがない。七世紀、天武帝の朝臣となり、賀茂忠行に始まる陰陽道を世襲している。忠行の子、賀茂保憲が子の光栄に暦道を、弟子の安倍清明に天文道を伝えた。以来、賀茂氏と安倍氏は陰陽道の家として、暦博士と陰陽寮官人を独占した。
安倍家も渡来一族で、もともと下級官人の家であった。安倍清明が出て、藤原道長や一条帝に重用され出世していく。現代の我々にはなかなか理解しがたいが、暦の流入以来、その編暦権と出版権は、まさに国家(朝廷)の一大事業、一大権益なのである。その権益は朝廷のもので、これを陰陽寮・陰陽頭が差配するのである。安倍家は陰陽寮の陰陽頭(おんようのかみ)、天文博士として「暦の編暦権」の管掌を握った。これが下級公家の安倍家の家職である。…
さて鎌倉期に話が飛ぶ。鎌倉前期に勢力をふるった公家の源道親の家を、子の定通が継ぐと、土御門家を名乗った。後鳥羽帝、北条泰時と姻戚関係があり、その血縁から土御門帝に影響力をふるい、やがて後嵯峨帝も実現させた。しかしその後衰退し断絶したが、戦国の下克上の時代、安倍清明の末裔がその土御門家を名乗った。名門の家名を乗っ取ったわけである。その名で、あたかも天皇家や源家、北条家と縁があるかの如く振る舞ったが、商売は本来の家職である陰陽道と、朝廷から委嘱された「暦の編暦権」である。
天和三年に泰福(やすとみ)が陰陽頭になり、霊元帝より諸国陰陽道支配の綸旨を受け、徳川綱吉がこれを追認した。土御門家は朝廷から祓いや天文・暦の御用をつとめ、諸国の陰陽師からの職札料、貢納料の収入を得ていた。
安倍家以来、土御門家は暦の朝廷御用を果たし「編暦権」を握り続けた。やがて幕府は土御門泰福の弟子・渋川春海の建言を入れ、土御門家の既得権をそのままに、朝廷から遍歴権と出版権を奪ったのである。土御門家は、幕府天文方から毎年の貞享暦の原稿を提供され、既得権は安堵されたのだ。
こうして幕府は編暦・出版を通し、改めて全国の統制を図り、さらに出版全体の統制に乗り出したのである。
昌益の自然観は元々易学に始まる。彼の自然思想は五行説(論)から、やがて四行説(論)に移行していく。しかし、当然の話だが、これらでは自然は上手く説明できていない。そんなもので自然が正しく把握・理解できるわけがない。私は昌益のそのこじつけや屁理屈には全く関心がない。
彼は易学、陰陽論の中に差別の思想、二別の思想を見出した。易の考え方に二別、上下差別の根源がある。天は貴く地は卑しいという天尊地卑の宇宙観、上下貴賤の差別思想から、君は貴く、臣は賤しという君臣、父子、夫婦、兄弟 社会関係を上下関係で律しようとする政治・法・道徳思想、そして人間の生理を陰陽で説明する医学理論を、昌益は鋭く批判するのである。天地に高低卑尊の別なし、全宇宙・自然に上下善悪の二別なし、陰陽・陽陰の二別、清濁、天地の二別なし、宇宙・自然・天地は無始無終である…。
まさに昌益に見るべきは、思想哲学批判、社会批判(制度批判)の苛烈さ激越さである。平等思想、不合理な宗教や施政者側の思想哲学を斬り捨てた唯物思想、平和思想、労働感と革命思想の峻烈さである。
昌益の「自然真営道」は、医者であった彼が、当時の医学の基礎にある儒学、易学・陰陽論、諸哲学に疑問を持ち始めたことから出発したものと考えられる。こうして彼は、中国の医書、医論批判をこころみ、自然哲学・思想批判に至り、やがてその目は、様々な社会の不合理や、悲惨な大飢饉を目の当たりにして、社会の制度・法、それを支える全ての思想哲学批判へと、そして施政者批判へと、激越化していったのだ。
















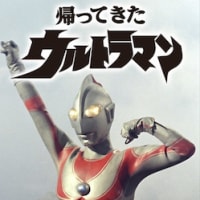
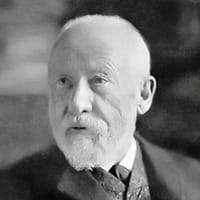
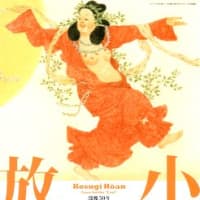








数の言葉の自然数を創生するのは、
≪…天尊地卑の宇宙観…≫を
[円]と『自然比矩形』に観る。
この自然数は、
[絵本]「もろはのつるぎ]で・・・