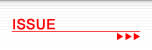メイキング・オブ『死刑執行』(※『現代プレミア』より)
青木 理・ジャーナリスト

徹底した密行主義
そのことについて語り始めると、しばしば感情ばかりが先に立ち、場合によっては「思想性」や「人間性」まで問われかねないようなテーマがある。死刑問題をめぐる議論はその一つだろう。
国家の名の下に人間の生命を奪い去る死刑は、究極かつ絶対不可逆の刑罰である。現在の日本において被告人に死刑が宣されるケースのほとんどは殺人事件であり、メディアが伝える犯行の陰惨や被害者遺族の激烈な悲憤等に接すれば、「ああ、死刑もやむを得ないだろう」と多くの人が考える。特に最近の日本の刑事司法は厳罰化のベクトルへと急傾斜しており、世論調査では実に約8割が死刑制度を容認する考えを示している。
一方、世界的には──少なくとも“先進諸国”では──死刑廃止が圧倒的趨勢{すせい}であるのは疑いない。欧州連合(EU)は死刑制度の廃止を加盟条件とするに至っているし、07年12月には国連総会で死刑制度の廃止を視野に死刑執行の一時停止(モラトリアム)を求める決議が大多数の加盟国の賛成によって採択された。「暴力の連鎖を暴力で断ち切ることはできない」と訴えるEUの理念を読めば、人類社会の目指すべき崇高な理想がそこにある、と痛切に思う。
しかし、「凶悪」と評される犯罪は無くならず、被害への悲嘆と加害への憎悪という人間の根源的情念が一方の極に重く横たわる。他方、人類社会の理想が彼方の極に立ち聳{そび}えている。人間の抜き難い根源的情念と、目指すべき崇高な理想の間でせめぎ合うからこそ、死刑をめぐる議論はしばしば二項対立的となり、両極の狭間で激しく感情ばかりがもつれ合う。
ただ、私たちは死刑についてしばしば感情的に語る割に、その足下の実態をあまりに知らないのではないか。死刑をめぐる議論は多くの場合、酷{ひど}く表層的で、情念的で、時に理念的だ。特に絞首によって執行される日本の死刑は世界でも類例を見ないほど徹底した密行主義の壁に覆われており、一体に刑場でどのように執行されているのか、それ自体が闇の奥に隠されている。
言うまでもないことだが、例えば死刑という刑罰の執行に直接関わらざるを得ない人がいる。刑務官。教誨師{きょうかいし}。検察官。医務官。国家が主宰する死刑執行という究極の営為に幾人もの人々が「職務」として携わっている。彼らは果たして、どのような思いを抱えながら執行に当たっているのか。
あるいは被害者。加害者。その遺族や家族。弁護人。メディアが血も涙もない極悪人であるかのように盛んに描きたてる死刑囚らは、果たしてそれほどに徹底的な極悪人なのか。時に事件から何十年も勾留され続けることもある彼らは、自らの罪について、いまどのような感情を抱くに至っているのか。深い悲嘆に沈む被害者遺族は、事件から何年も経って加害者が死刑に処せられることを、心中でどう捉えているのか。
是非を考える前提として
抽象的な「死刑」という単語の向こう側に、数多くの人々の苦悩と煩悶が渦を巻いているはずだ。ある時、『月刊現代』の編集者だった片寄太一郎君とそんなことを語り合った。
直截{ちょくせつ}に記してしまえば、私と片寄君の死刑問題に関する「立ち位置」は随分と異なっていた。私は腹が立ち、片寄君を批判した。片寄君も憤ったのか、強い疑義と反論を口にした。ただ、死刑が究極の刑罰であるにもかかわらず、その実相と関係者の心の奥底はあまりに知られていない、という点では同じ想いを共有していた。
確かに死刑問題を語った文献や書物は過去にいくつもある。しかし、多くは法律や理念的な観点からの死刑制度論であったり、被害者遺族の立場や死刑廃止運動の立場に寄り添って「是非」の姿勢を明確にした上で紡がれたものだった。もちろん、読み応えのあるノンフィクションや良質なルポルタージュ作品が皆無なわけではないし、死刑に携わった経験を持つ元刑務官の手記なども出版されてはいる。
ただ、死刑に関わる人々──執行にあたる人々はもちろん、死刑囚や被害者遺族までを含む──の心中に渦巻く感情の深淵を、現場取材で多角的に、包括的に描いたノンフィクションやルポルタージュはほとんど見当たらなかった。
だから私たちは、死刑制度の是非を考える前提としての事実を、さまざまな立場から死刑に関わらざるを得なくなった人々の心の襞{ひだ}を、現場取材によって提示できないかと考えた。表層的な情念や理念に流されることなく、可能な限り多くの関係者に会い、死刑という究極の刑罰を取り巻く人々の、恐らくは千々に乱れているであろう心象風景を描いてみたいと思ったのだ。
取材ルートを手繰る作業
大抵のノンフィクション作品は、書き手と編集者の共同作業で成り立つ。取材と執筆を担うのはもちろん書き手だが、編集者は同じ目標に向かって二人三脚で歩み、書き手を支え、原稿を完成形に近づけてくれる。書き手にとって編集者とは、かけがえのない羅針盤だ。
ところが今回は、書き手である私と編集者である片寄君の「立ち位置」が随分異なっていた。しかし、それはむしろ好都合だと思った。私たちが提示したいのは、制度としての死刑論でもなければ、その是非をめぐる二頂対立的な議論でもない。究極の刑罰に直面せざるを得なかった人々の心の奥に分け入り、それを描く作業だったのだから。
「もしかしたら、取材を進めていく過程で、私たちの立ち位置が変わるかもしれませんね」
そんな風に言う片寄君と取材に取りかかったのは、07年の春頃だったと記憶している。
こうした「苦労話」を披瀝するのは趣味ではないし、本稿を書くにあたっては正直なところ戸惑いもあった。ただ、実相に迫るのに困難がつきまとう死刑というテーマを描く作業の裏側をお伝えすることは、ノンフィクションにおける「取材」とは何かを説明するのに適しているのかもしれない。
実際、取材は随分と難航した。中でも執行に携わった刑務官や教誨師に話を聴く作業は、酷く難儀だった。細い糸を手繰っても、その糸はしばしば途中で切れてしまったし、ようやく会えた刑務官や教誨師も、事細かに執行の様子を聴く私たちに対し、ある人は声を荒らげて怒り、別の人は押し黙って不快を露{あらわ}にした。
加害者である死刑囚や被害者の遺族への取材も同様だ。確定死刑囚との面会はほぼ不可能だし、確定前の被告人にしても、杓子定規な法務当局の対応によって1回の面会で与えられる時間は15分ほどに過ぎず、何度も面会を積み重ねるほかなかった。当たり前の話だが、被害者遺族の多くも「そっとしておいてください」とつぶやくだけで、心の奥底などなかなか吐露してはくれなかった。
結局、取材で訪れた先は、北は北海道から南は九州まで全国に及んだ。ようやく連載第1回の原稿を書き上げたときには、片寄君と最初に議論を交わしてから優に1年が過ぎていた。
Profile
あおき おさむ
1966年生まれ。慶應義塾大学卒。90年、共同通信社入社。大阪社会部などを経て、本社社会部の警視庁警備・公安担当に。その経験を基に『日本の公安警察』(講談社現代新書)を執筆。06年よりフリー。近著に『国策捜査』(金曜日)がある。なお、『月刊現代』の連載と本稿をまとめ、死刑についての単行本を近く刊行する予定
My Bookmark
■G-Search
■国会会議録検索システム
■聯合ニュース(韓国の通信社)
| Trackback ( 0 )
|