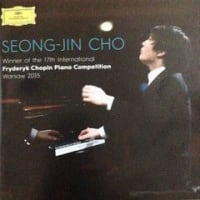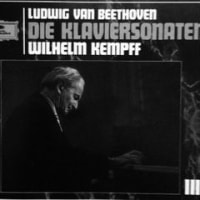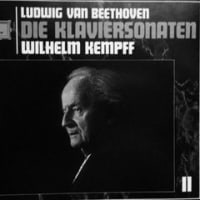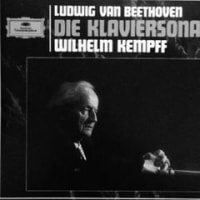コース順路:コース満足度★★★ 3月28日~3月29日
常陸国分寺跡 → 常陸国分尼寺跡 → 弘道館 → 水戸城跡 → 水戸東照宮 → 偕楽園 → 徳川博物館 ~ 県立歴史館


常陸国分寺は寺料が稲束6万束で全国の最高位、定住僧30名、寺域60町歩という規模だったが、現在は礎石を残すのみ。
伽藍配置は東大寺式で、一直線上に南大門、中門、金堂、講堂が並ぶ。
常陸国分尼寺には、10人の尼僧が在籍し、寺の運営は10町の水田によって賄なわれていたというが、現在は往時を偲ぶ礎石が散在しているのみ。


弘道館は水戸藩の藩校として、第9代藩主・徳川斉昭により天保12年(1841)に創設された。
武芸一般はもとより、医学・天文学・蘭学など、幅広い学問をとり入れた、当時の藩校としては国内最大規模のものだったという。
第15代将軍となった徳川慶喜も、5歳の時から弘道館において英才教育を受けている。
水戸城の歴史をたどると、鎌倉時代に馬場氏により建てられた館が最初で、それが江戸氏・佐竹氏と渡り、慶長14年(1609)には徳川家康の11男・徳川頼房が水戸徳川家の城主となっている。




徳川光圀の生誕地に立つ神社を訪れる。
光圀は寛永5年(1628)、水戸藩初代藩主頼房の三男として、家臣三木家の屋敷で生まれている。
身分を隠し、4歳までここで育ったという。
偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ「日本三大公園」のひとつだが、天保13年(1842)に第九代藩主徳川斉昭によって造られたもの。
見事な梅の花を見ようと、多くの人々が絶え間なく訪れている。
常陸国分寺跡 → 常陸国分尼寺跡 → 弘道館 → 水戸城跡 → 水戸東照宮 → 偕楽園 → 徳川博物館 ~ 県立歴史館


常陸国分寺は寺料が稲束6万束で全国の最高位、定住僧30名、寺域60町歩という規模だったが、現在は礎石を残すのみ。
伽藍配置は東大寺式で、一直線上に南大門、中門、金堂、講堂が並ぶ。
常陸国分尼寺には、10人の尼僧が在籍し、寺の運営は10町の水田によって賄なわれていたというが、現在は往時を偲ぶ礎石が散在しているのみ。


弘道館は水戸藩の藩校として、第9代藩主・徳川斉昭により天保12年(1841)に創設された。
武芸一般はもとより、医学・天文学・蘭学など、幅広い学問をとり入れた、当時の藩校としては国内最大規模のものだったという。
第15代将軍となった徳川慶喜も、5歳の時から弘道館において英才教育を受けている。
水戸城の歴史をたどると、鎌倉時代に馬場氏により建てられた館が最初で、それが江戸氏・佐竹氏と渡り、慶長14年(1609)には徳川家康の11男・徳川頼房が水戸徳川家の城主となっている。




徳川光圀の生誕地に立つ神社を訪れる。
光圀は寛永5年(1628)、水戸藩初代藩主頼房の三男として、家臣三木家の屋敷で生まれている。
身分を隠し、4歳までここで育ったという。
偕楽園は金沢の兼六園、岡山の後楽園とならぶ「日本三大公園」のひとつだが、天保13年(1842)に第九代藩主徳川斉昭によって造られたもの。
見事な梅の花を見ようと、多くの人々が絶え間なく訪れている。