以前、自然公園に外来種を植樹すべきではないと書きましたが、在来種でも苗木を遠く離れた地域に植えるべきではないと森林総合研究所が警告しています。例えば、北海道で育てたミズナラの苗木を京都府の山地に植樹してはいけないと言うのです。
今年3月に発表した『広葉樹の種苗の移動に関する遺伝的ガイドライン』によると、10種類の広葉樹で実態調査し、そのうちのミズナラ、ブナ、ヤマザクラ、ウダイカンバ、イロハモミジ、オオモミジの6種について境界線を定め、それを越えて移動させないように注意しています。
たとえば、ミズナラは石川県~岐阜県~長野県南部~山梨県~神奈川県を境にした東西2地域、イロハモミジは福井県~滋賀県~三重県を境にした東西2地域、ヤマザクラは山口県~九州とそれ以西の2地域というように樹種ごとにエリアを分けています。

西日本と東日本で移動制限されたミズナラ(栃の森の巨木)
同じ種類でも地域よって遺伝的な差異があり、異なる集団を人為的に混ぜると、それまでに自然が長い年月をかけて築いた遺伝構造を破壊する可能性がある。その結果、一定の地域で適応してきた集団が死滅したり、遺伝的な多様性が損なわれ、種の衰退につながる…。森林総研はそう警告しているのです。
指定した6種のうち、ブナだけは日本海側(北海道~鳥取県)、太平洋側(宮城県~和歌山県)、西日本(中国~四国~九州)の3地域に分かれています。

3地域で移動制限されたブナ(春の芽吹き)
実は、うちの庭をつくるとき、植木屋さんにカシワを注文しましたが、関西には苗木がないので栃木県から取り寄せました。森林総研はカシワの調査をしていませんが、ミズナラと近縁なので移動制限すべき樹種かも知れません。

庭のカシワ
主要な針葉樹(スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ)についてはすでに林業種苗法という法律で苗木の移動制限がされているそうです。それを広葉樹にまで拡大しようというのが今回の提言の狙い。
実行するには、地域ごとの種の確保、苗木産地の分散化、苗木の産地表示などさまざまな課題があるようですが、長いスパンで考えれば立法化するべきですね。
森林総研の資料はこちら

















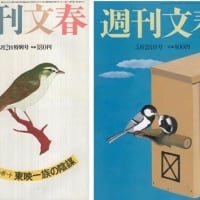
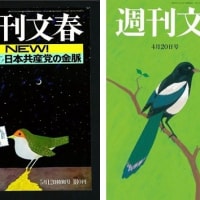





書き込みが遅れました・・・
この問題について以前札幌のA公園再整備の際にミズナラを植樹するならどの辺りの樹木までは遺伝子的に問題なさそうですかと北大の先生に聞いたところ石狩低地帯なら大丈夫かなと言われました。
また別の大学では山から採取した種子を苗木に育てて植樹をする活動を支援していて一度そこに参加させてもらったところ、札幌市内の豊平川河岸に植える樹木でいちばん遠いのは札幌の50kmほど北西の美唄市で採取されたものでした。
私は少し不安になって先生に(大胆にも)聞いてみたところ石狩川水系だから大丈夫と説明され納得しました。
私はそれら自らの体験から、この問題を考えるにおいては例えば札幌ならどこのものなら大丈夫か、何km圏内とか水系とか、それをデータとして蓄積してゆけないものかと思います。
現状ではそういう意識は広がってきているので反対という声はあまりないかなと思いますが、一般の人と業者を納得させた上で動いてもらうのはまだまだ先のことかなと感じています。
遺伝的な配慮すれば、狭い範囲の方がいいですもんね。
ただ、苗木業者が事業として育てることを考えると、細かく地域を限定すると難しいでしょう。
私はこの情報に接するまで、苗木を地域限定すべきとは考えたことはありませんでした。自然はデリケートということですね。