昔、カッコウの托卵を扱ったNHKの番組で、孵ったばかりで羽毛も生えていない、目も見えないヒナが宿主の卵を巣の外に放り出すシーンを見て衝撃を受けました。
ホトトギスやツツドリ、ジュウイチも同様の托卵をするわけですが、人間はいつごろからこの生態を知っていたのでしょう?
私は双眼鏡などの光学機器が発明されて以降だろうと思っていましたが、驚くべきことに、『万葉集』に托卵を詠んだ歌があります。
うぐいすの生卵(かいこ)の中に ほととぎすひとり生まれて
己(な)が父に似ては鳴かず 己が母に似ては鳴かず…
「ウグイスの巣の中でホトトギスが1羽生まれたが、父親に似た声では鳴かないし、母親に似た声でも鳴かない」という歌です。作者は高橋虫麻呂(たかはしのむしまろ)。
『万葉集』が編纂されたのは6~7世紀。双眼鏡も望遠鏡もカメラもないのにホトトギスの托卵を知っていたわけです。
ただ、この歌の前には「霍公鳥を詠める一首」というイントロダクションがあり、「霍公鳥」はカッコウを意味するそうです。イントロで「カッコウ」と紹介しながら、歌の中では「保登等藝須(ホトトギス)」と表記しているのです。当時はカッコウとホトトギスを同一種と認識していたからではないかという人もいます。
いずれにしても、万葉人はトケン類の托卵行動を知っていたわけですが、驚くのはまだ早くて、世界的にはもっと昔、紀元前4世紀にアリストテレスが『動物誌』の中でカッコウの托卵について書いています。
カッコウも卵を産むには産むが、巣を作らずに産むのであって、ときには自分よりも小さいいろいろな鳥の巣の中に、その鳥の卵を食ってから、卵を産むこともあるが、特にモリバトの巣の中に、やはりその卵を食ってから、産むのである。(第6巻 第7章 カッコウとその産卵習性)(岩波文庫版)
肉眼でしか鳥の行動を見られなかった当時、こんな細かいところまでよく観察できたものだと感心します。
それに引き替え、双眼鏡や望遠鏡、さらには1000mmのレンズ付きカメラで鳥の動きを記録していながら、いまだにカッコウとホトトギスの区別がつかない私は何なんでしょう(笑)。
ホトトギスやツツドリ、ジュウイチも同様の托卵をするわけですが、人間はいつごろからこの生態を知っていたのでしょう?
私は双眼鏡などの光学機器が発明されて以降だろうと思っていましたが、驚くべきことに、『万葉集』に托卵を詠んだ歌があります。
うぐいすの生卵(かいこ)の中に ほととぎすひとり生まれて
己(な)が父に似ては鳴かず 己が母に似ては鳴かず…
「ウグイスの巣の中でホトトギスが1羽生まれたが、父親に似た声では鳴かないし、母親に似た声でも鳴かない」という歌です。作者は高橋虫麻呂(たかはしのむしまろ)。
『万葉集』が編纂されたのは6~7世紀。双眼鏡も望遠鏡もカメラもないのにホトトギスの托卵を知っていたわけです。
ただ、この歌の前には「霍公鳥を詠める一首」というイントロダクションがあり、「霍公鳥」はカッコウを意味するそうです。イントロで「カッコウ」と紹介しながら、歌の中では「保登等藝須(ホトトギス)」と表記しているのです。当時はカッコウとホトトギスを同一種と認識していたからではないかという人もいます。
いずれにしても、万葉人はトケン類の托卵行動を知っていたわけですが、驚くのはまだ早くて、世界的にはもっと昔、紀元前4世紀にアリストテレスが『動物誌』の中でカッコウの托卵について書いています。
カッコウも卵を産むには産むが、巣を作らずに産むのであって、ときには自分よりも小さいいろいろな鳥の巣の中に、その鳥の卵を食ってから、卵を産むこともあるが、特にモリバトの巣の中に、やはりその卵を食ってから、産むのである。(第6巻 第7章 カッコウとその産卵習性)(岩波文庫版)
肉眼でしか鳥の行動を見られなかった当時、こんな細かいところまでよく観察できたものだと感心します。
それに引き替え、双眼鏡や望遠鏡、さらには1000mmのレンズ付きカメラで鳥の動きを記録していながら、いまだにカッコウとホトトギスの区別がつかない私は何なんでしょう(笑)。

















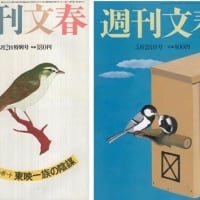
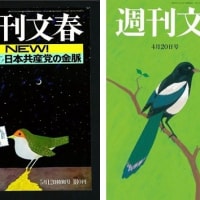





万葉集は、和歌への興味とは別に、昔の日本人の動物や植物とのつながりが分かりそうなのでいつか真面目に読みたいと思いつつ、まだです。
ブックオフで万葉集に出てくる植物を扱った本をたまたま見つけて買いましたが、鳥でもそのような本が出ているとありがたい、と思いました。
怠慢ですね、私は・・・(笑)。
こちらホトトギスは基本的にいないのですが、もしかしてあと20年もすれば夏に普通にいるようになるかもしれません。
少し南の黒松内にはいました。
植物の本は私も図書館で見つけましたが、鳥の本はまだないようです。断片的には出て来るようですが。
ホトトギスの北限は黒松内ということなんですね。先ほど図鑑を見たら、カッコウ、ツツドリ、ジュウイチは北海道まで渡ることになっていました。
私も以前、そちらでカッコウを見たことがあります。
なぜホトトギスは北海道まで渡らないのか、興味が出てきました。温度? 餌? それとも托卵相手?
ウグイスはたくさん生息しているんですよね?
不思議ですね。