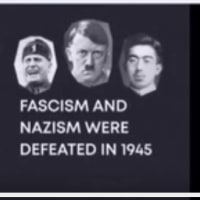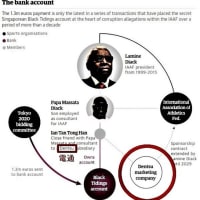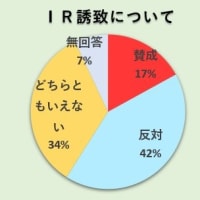小泉「構造改革」によって格差社会と貧困の広がりという事態が加速したという非難に対し、国会開会を控えた19日、内閣府は「見かけ上の問題だ」として、格差拡大論を否定する見解を公表しました。早速、小泉首相や竹中総務相ら、「構造改革」首謀者は、これを根拠に「格差拡大というのは誤解だ」と声高に反論しています。小泉「構造改革」は、本当に格差社会と貧困の広がりとは無縁と言えるのでしょうか。
小泉「構造改革」は、従来の成長第一の開発主義型国家システムをグローバル資本主義のもとで多国籍企業の競争力第一システムに各分野を「改革」することです。多国籍企業の競争力第一のために、税金等の負担の軽減、企業の利潤追求の障害物の除去、規制緩和、労働雇用の自由化、相互競争の徹底などが推進されてきました。
労働雇用の自由化、相互競争の徹底とは、現代の雇用者をマルクスが『資本論Ⅰ』第23章「資本主義的蓄積の一般的法則」で明らかにした「産業予備軍」(不安定雇用者、待機労働者、失業者のこと)の運命に引戻すことです。「この予備軍が現役の労働者軍と比べて大きくなればなるほど、固定的過剰人口、すなわち彼らの労働苦に反比例して貧困が増大していく労働者層が、それだけ大量的となる。最後に、労働者階級中の貧民層と産業予備軍とが大きくなればなるほど、公認の受救貧民(慈善事業的な援助で生活している貧民層のこと)がそれだけ大きくなる。これこそが資本主義的蓄積の絶対的・一般的な法則である」
先の内閣府の報告書は、所得格差の拡大を示す指標(ジニ係数)は上昇していることは確かだが、年齢別の係数分析や単身世帯を含まない所得統計の分析をしてみると、それは、元来所得格差が大きい高年齢層世帯の増加や、核家族化の進行で所得の少ない単身者世帯が増えたのが原因であって、“所得格差の拡大は見かけ上のもの”だと主張します。これにたいしては、たとえば橘木俊詔・京都大教授が「家族の人数を考慮して調整した所得を使い、核家族化の影響を除外しているOECDのジニ係数上昇データを、内閣府はどう説明するのだろうか。また高齢化が原因というが、高齢の貧困者が増えている問題をどうするつもりなのかと問いたい」と反論しています(「朝日」インターネット06.1.19)。
一般的にどこの資本主義国でも、市場原理に任せたまままでは拡大する所得格差を是正するため、政府は社会保障給付および税による所得格差の縮小策をとります。小泉「構造改革」は、明らかにこの再分配システムを縮小しようとする企てであるから、統計数字をどのようにいじくろうとも、格差拡大、貧困化は必然の成り行きです。資本主義的蓄積の絶対的・一般的な法則なのだから。1997年と比較して生活保護世帯は六十万から百万世帯に、教育扶助・就学援助を受けている児童・生徒は6・6%から12・8%に、貯蓄ゼロの世帯は10%から23・8%に、どれも激増しているという統計もあります。
同じ内閣府経済社会総合研究所 の太田清氏は、「フリーターの増加と労働所得格差の拡大」と題する論文で「1990 年代後半から最近にかけて、個人間の労働所得格差が拡大していることがわかった。いずれの年齢層でも格差は拡大しているが、特に若年層でその拡大テンポが速い。この若年層内における格差の拡大は、フリーター化など非正規雇用の増大の影響が大きい。若年層の間での格差拡大は、日本社会の将来の姿を先取りしたものである可能性もある。」としています(05年5月)。確かに、若年時の所得格差は生涯にわたっての格差につながる可能性が高いと思われます。政治が若者に希望格差社会を強制することは、若者の将来の夢を奪うことです。堀江社長のように手段を選ばず稼ぐことに励めとでもいうのでしょうか。
小泉「構造改革」は、従来の成長第一の開発主義型国家システムをグローバル資本主義のもとで多国籍企業の競争力第一システムに各分野を「改革」することです。多国籍企業の競争力第一のために、税金等の負担の軽減、企業の利潤追求の障害物の除去、規制緩和、労働雇用の自由化、相互競争の徹底などが推進されてきました。
労働雇用の自由化、相互競争の徹底とは、現代の雇用者をマルクスが『資本論Ⅰ』第23章「資本主義的蓄積の一般的法則」で明らかにした「産業予備軍」(不安定雇用者、待機労働者、失業者のこと)の運命に引戻すことです。「この予備軍が現役の労働者軍と比べて大きくなればなるほど、固定的過剰人口、すなわち彼らの労働苦に反比例して貧困が増大していく労働者層が、それだけ大量的となる。最後に、労働者階級中の貧民層と産業予備軍とが大きくなればなるほど、公認の受救貧民(慈善事業的な援助で生活している貧民層のこと)がそれだけ大きくなる。これこそが資本主義的蓄積の絶対的・一般的な法則である」
先の内閣府の報告書は、所得格差の拡大を示す指標(ジニ係数)は上昇していることは確かだが、年齢別の係数分析や単身世帯を含まない所得統計の分析をしてみると、それは、元来所得格差が大きい高年齢層世帯の増加や、核家族化の進行で所得の少ない単身者世帯が増えたのが原因であって、“所得格差の拡大は見かけ上のもの”だと主張します。これにたいしては、たとえば橘木俊詔・京都大教授が「家族の人数を考慮して調整した所得を使い、核家族化の影響を除外しているOECDのジニ係数上昇データを、内閣府はどう説明するのだろうか。また高齢化が原因というが、高齢の貧困者が増えている問題をどうするつもりなのかと問いたい」と反論しています(「朝日」インターネット06.1.19)。
一般的にどこの資本主義国でも、市場原理に任せたまままでは拡大する所得格差を是正するため、政府は社会保障給付および税による所得格差の縮小策をとります。小泉「構造改革」は、明らかにこの再分配システムを縮小しようとする企てであるから、統計数字をどのようにいじくろうとも、格差拡大、貧困化は必然の成り行きです。資本主義的蓄積の絶対的・一般的な法則なのだから。1997年と比較して生活保護世帯は六十万から百万世帯に、教育扶助・就学援助を受けている児童・生徒は6・6%から12・8%に、貯蓄ゼロの世帯は10%から23・8%に、どれも激増しているという統計もあります。
同じ内閣府経済社会総合研究所 の太田清氏は、「フリーターの増加と労働所得格差の拡大」と題する論文で「1990 年代後半から最近にかけて、個人間の労働所得格差が拡大していることがわかった。いずれの年齢層でも格差は拡大しているが、特に若年層でその拡大テンポが速い。この若年層内における格差の拡大は、フリーター化など非正規雇用の増大の影響が大きい。若年層の間での格差拡大は、日本社会の将来の姿を先取りしたものである可能性もある。」としています(05年5月)。確かに、若年時の所得格差は生涯にわたっての格差につながる可能性が高いと思われます。政治が若者に希望格差社会を強制することは、若者の将来の夢を奪うことです。堀江社長のように手段を選ばず稼ぐことに励めとでもいうのでしょうか。