カウンターの横にある白い券売機は、薄暗い店内で変に目立っていた。
リアンは、券売機に一万円札を差し込むと、一番左端のボタンを素早く押した。
「ウィーン、ガちょん!」
店内の雰囲気をぶち壊すような音が、券売機から響き渡る。
「うはははは、佐野さん、マジで券売機なんだ!」
「な、そうだべ!」
続けざまにリアンは、六枚のチケットを買うと、三つのテーブルにチケットを二枚ずつ置いて回った。
私は白いチケットを手に取ると、内容を確認した。
「んーと、60分セット、2,500円、19:25ね、なるほど。それにしても凄いシステムだね」
リアンもサリーも、客の反応には慣れっこなのか、特に気にする様子も無かった。
「ところでさ、この店、マスターとかママは居ないの?」
入店時から気になっていたのだが、店内にはフィリピン人の女の子が居るだけで、日本人のスタッフが一人も居なかった。
「ん?ママはリアンだよな」
佐野が、笑いながらリアンを顎でしゃくる。
「えー?リアンが経営者なの?」
リアンは軽い苦笑いをしながら、手を胸の前でヒラヒラとさせる。
「ワタシワ、『チーママ』みたいなモノだよ。コノ店ワ、パパの店ネ」
佐野の話によると、この店の経営者は日本人で、営業時間内に適当にふらりと現れて、券売機につり銭を補充するのが仕事らしかった。
「という事は、この店のママは券売機なの?」
私の言葉に、佐野とリアンとサリーが頷いた。
「ソウソウ、ソウナルヨ」
どうやらこのフィリピンパブは、一人の信用できるフィリピン人ホステス兼チーママと、絶対に会計をごまかさない『券売機』のママによって、運営されている様だった。
「佐野さん、ある意味、物凄い店舗運営ですね」
「そうだろう、笑えるだろ。俺も最初に入った時は、本気で笑ったからな」
このフィリピンパブ、一見、奇抜な店に見えるのだが、店内には独特の空気が流れていた。
それは、日本人の管理スタッフが居ないせいなのか、女の子たちが、実に自由な雰囲気で働いている事だ。イメージ的には、客が、女の子たちのサークル活動にお邪魔しているような感じだ。
女の子同士の会話は、ほとんどがタガログ語なのだが、なぜか嫌な感じが少しもしない。店によっては、客の悪口を、目の前でタガログ語で話している場合もあるのだが、この店にはそういう陰険な雰囲気が感じられないのだ。
「佐野さん、なんか楽しい店ですねぇ!」
「そーだべぇ、キーちゃんならきっと気に入ると思ってたよ」
現場が終わった開放感もあってか、私は急激にご機嫌になり始めていた。
「そーれ!そーれぇ!」
「がはははは!うわっ、やめろハル!」
「ナニシテルのよォ、ドウシテお菓子を入れるノヨォ!」
「っちゃあ、何だよ、ハルちゃんスペシャルに文句があんのかぁ?」
「がはははは、お前が作ったんだから、お前が飲め!」
後のボックスでは、小磯とハルが大騒ぎをしている。
「カラオケ、歌ウ?ナニカ歌ってクダサイ!」
サリーが、分厚いカラオケの本を私の膝の上に置いた。
「キーちゃん、じゃあ俺が選曲してやるよ」
佐野はニヤリと笑うと、私からカラオケ本を受け取り、リアンに曲番を伝えた。
こういう時の佐野は、何か必ず仕掛けがあるはずなので、私は素直に従うことにした。
リアンは、券売機に一万円札を差し込むと、一番左端のボタンを素早く押した。
「ウィーン、ガちょん!」
店内の雰囲気をぶち壊すような音が、券売機から響き渡る。
「うはははは、佐野さん、マジで券売機なんだ!」
「な、そうだべ!」
続けざまにリアンは、六枚のチケットを買うと、三つのテーブルにチケットを二枚ずつ置いて回った。
私は白いチケットを手に取ると、内容を確認した。
「んーと、60分セット、2,500円、19:25ね、なるほど。それにしても凄いシステムだね」
リアンもサリーも、客の反応には慣れっこなのか、特に気にする様子も無かった。
「ところでさ、この店、マスターとかママは居ないの?」
入店時から気になっていたのだが、店内にはフィリピン人の女の子が居るだけで、日本人のスタッフが一人も居なかった。
「ん?ママはリアンだよな」
佐野が、笑いながらリアンを顎でしゃくる。
「えー?リアンが経営者なの?」
リアンは軽い苦笑いをしながら、手を胸の前でヒラヒラとさせる。
「ワタシワ、『チーママ』みたいなモノだよ。コノ店ワ、パパの店ネ」
佐野の話によると、この店の経営者は日本人で、営業時間内に適当にふらりと現れて、券売機につり銭を補充するのが仕事らしかった。
「という事は、この店のママは券売機なの?」
私の言葉に、佐野とリアンとサリーが頷いた。
「ソウソウ、ソウナルヨ」
どうやらこのフィリピンパブは、一人の信用できるフィリピン人ホステス兼チーママと、絶対に会計をごまかさない『券売機』のママによって、運営されている様だった。
「佐野さん、ある意味、物凄い店舗運営ですね」
「そうだろう、笑えるだろ。俺も最初に入った時は、本気で笑ったからな」
このフィリピンパブ、一見、奇抜な店に見えるのだが、店内には独特の空気が流れていた。
それは、日本人の管理スタッフが居ないせいなのか、女の子たちが、実に自由な雰囲気で働いている事だ。イメージ的には、客が、女の子たちのサークル活動にお邪魔しているような感じだ。
女の子同士の会話は、ほとんどがタガログ語なのだが、なぜか嫌な感じが少しもしない。店によっては、客の悪口を、目の前でタガログ語で話している場合もあるのだが、この店にはそういう陰険な雰囲気が感じられないのだ。
「佐野さん、なんか楽しい店ですねぇ!」
「そーだべぇ、キーちゃんならきっと気に入ると思ってたよ」
現場が終わった開放感もあってか、私は急激にご機嫌になり始めていた。
「そーれ!そーれぇ!」
「がはははは!うわっ、やめろハル!」
「ナニシテルのよォ、ドウシテお菓子を入れるノヨォ!」
「っちゃあ、何だよ、ハルちゃんスペシャルに文句があんのかぁ?」
「がはははは、お前が作ったんだから、お前が飲め!」
後のボックスでは、小磯とハルが大騒ぎをしている。
「カラオケ、歌ウ?ナニカ歌ってクダサイ!」
サリーが、分厚いカラオケの本を私の膝の上に置いた。
「キーちゃん、じゃあ俺が選曲してやるよ」
佐野はニヤリと笑うと、私からカラオケ本を受け取り、リアンに曲番を伝えた。
こういう時の佐野は、何か必ず仕掛けがあるはずなので、私は素直に従うことにした。


















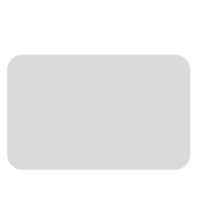

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます