次の本を読む。
「『武士道』解題 ノーブレス・オブリージュとは」(著者:李登輝氏、出版社:小学館、出版日:2006/05/01)(単行本 - 出版社:小学館、出版日:2003/04)
キリスト者(クリスチャン)である著者の元・中華民国(台湾)総統・李登輝氏。優秀な事で有名な、「東洋のユダヤ人」と呼ばれる「客家」でもある。西洋や日本の数多くの先人の哲学書を読み熟されて来たが故の教養と知識の豊かさ・深さと、イエスキリストへの信仰心をベースにした独自の視点からの捉え方により、同じキリスト者である新渡戸稲造氏の著した「武士道」を、本書にて読み解き明かし述べている。日本の明治維新後の近代化において、特に西欧列強諸国に日本の理解を深めてもらう為の海外への発信材料として、当時、英語で「武士道」が出版された。
その「武士道」を著した新渡戸稲造氏は、イエス・キリストと武士道をセットにして、「キリスト武士道」を唱えた。著書「武士道」は正に、止揚(アウフヘーベン)した「キリスト武士道」の内容となっている。しかし元々から、不文律の武士道や陽明学には、新約聖書的な内容が含まれていると、著書「武士道」の中で述べる。また、札幌農学校で同期生として共に学び、同じくキリスト者である内村鑑三氏も、「代表的日本人」を英語で著し、同じく海外に発信した。そして内村氏は、「愛国は人性の至誠なり」と唱えて、イエス・キリスト(Jesus)と日本国(Japan)の「二つのJ」をセットにした、「キリスト愛国」を唱えた。また、内村氏は新渡戸氏と同様に、「キリスト武士道」を次の様に表現した。
「武士道の台本に基督教を接いだ物、其物は世界最善の産物であって、之に日本国のみならず全世界を救ふ能力がある」(内村鑑三氏著「英和独語集」より、本書経由)
「キリスト武士道」精神の下、第一次世界大戦後のパリ講和会議にて、日本は「人種差別撤廃法案」を国連に提出した。11対5の賛成多数で可決されたものの、アメリカのウィルソン議長(米大統領)が全会不一致を理由にして、採決を無効とし、法案を成立させなかった。また大東亜戦争によって、白人欧米列強の白人至上主義によって差別的・奴隷的植民地とされていたアジア各国を解放して独立させ、その上での大東亜会議において、大東亜共同宣言「相互協力・独立尊重」を、アジア各国と共に宣言した。また、日韓合邦(日韓併合)時代に、日本が朝鮮半島に学校、病院、裁判所、橋梁、発電ダム等を建造し、鉄道を敷き、港湾や道路を整備して、朝鮮半島のインフラを近代化した。日本は朝鮮を一応形としては植民地として統治したが、白人の西欧列強諸国によるアジアやアフリカにおける搾取・掠奪・奴隷化の植民地政策とは全く異なり、日本は朝鮮に対して投資するばかり、与えるばかりで、日本は朝鮮に対しては赤字収支であり、却って日本の方こそが犠牲となっていた。
内村鑑三氏は「無教会主義」を唱え、新渡戸稲造氏も祭司無く装飾も無い極めて質素で小さな集会所でのクエーカー派であった。キリスト者である両者は共に、特に西欧の大きく組織化しているキリスト教団体とは距離を置き、堕落し世俗化しリベラル化しているキリスト教界を否定し批判した。
著者・李登輝元総統の2歳年上の兄は、日本軍に従軍して戦死し、靖国神社に合祀されているのだが、キリスト者である著者は、当然にして靖国参拝を希望していたのだが、日中関係を優先する日本政府の方針から日本への公式訪問も儘ならなかった事から、実現する事が出来ないでいた。しかし、本書の文庫版発行の翌年2007年に、観光目的で来日した際に靖国神社参拝を実現させ、「兄の霊を守ってくれることに感謝している」(ウィキペディア「李登輝」より)と、神社に対し謝礼を述べた。
靖国神社参拝について、昭和54年(1979年)に同じくキリスト者である大平正芳首相(当時)が、総理大臣として靖国神社公式参拝を行った。大平首相は、「『A級戦犯』及び大東亜戦争に対する審判は歴史が下すのに任せる、人がどう見ようと私は私の気持ちで参拝に行く」と延べ、慰霊の為、慰謝の為、世俗目的の為に、周囲の人にどの様に思われようとも、自分の気持ちに素直に、自分の信念に則って、堂々と公式参拝を果たした。そして大平首相は、日本の後世の人達による正しい歴史認識による日本の歴史修正によって、この参拝がはっきり認められる時が来る事を信じ期待していた。その公式参拝について、支那(中国)からの抗議は、当時は全く無かった。
因みに、政教分離について憲法に明確に定義されておらず、また最高裁判所において「目的効果基準」を基に、靖国神社の公式参拝は慰霊・慰謝の世俗目的の為であり、宗教的意義は希薄であり、それによる効果で特定宗教を利する事にはならないと判断して、「合憲」を示されている。欧米各国は、国家と宗教組織・団体を分離し、国家と宗教そのものとは分離していない。つまり、state(国家)である政府や権力機関が特定の宗教組織と結びつく事を禁止する事に留まり、nation(国家)である国民、共同体は宗教を排除する必要は無い(参考:百地章氏著「憲法の常識 常識の憲法」(文藝春秋))。
本書出版当時、アメリカ同時多発テロ事件(911)、米国によるアフガニスタン侵攻とイラク侵攻、新世界秩序(NWO)、金融至上主義と金融グローバル化、また日本の金融規制緩和や金融改革、国際金融資本・外資系・多国籍企業参入、構造改革、ゆとり教育、フェミニズム、リベラリズムが在り、更に支那(中国)や韓国からの靖国参拝や教科書検定等に対する内政干渉、領土問題、反日・歴史認識等における外交敗北、国内のマスコミ等による反日・スパイ活動、米国の圧力等と、日本がグローバリズムの波に呑まれかけ、外圧に抑えられ様とし、国家の存亡も危機に瀕していた。
その危機的状況を乗り越えて、日本国と日本人が生き残る為に必要なものとして、日本の伝統的精神「武士道」を、親日家で却って一般的な日本人よりも日本の事を理解しておられる著者が、警世の意味も込めて勧められている。自虐史観による対外的に媚び諛う外交や、政治家や官僚の慇懃無礼で卑屈な態度、国民の愛国心や自尊心、誇りの希薄さと、戦後の日本人が精神的に堕落してしまい、唯心論から唯物論に、拝物・拝金主義に陥ってしまった事に、その危機的状況を招いた原因が有る。武士道は、世界的なグローバリズムに対抗して、日本独自の歴史・伝統・文化・日本精神・大和魂・愛国心・民族的自尊心と自信、それらを守る為の規範・精神・土台となるものである。
現在の困難な時代に「いかに生くべきか」という問いに対し、日本の伝統的精神「武士道」を道徳規範として今一度、日本人が見直すべき事を強調する。そして、著者、新渡戸稲造氏、内村鑑三氏が共有する、イエス・キリストの教えとキリストへの信仰を併せた、「キリスト武士道」と「キリスト愛国」の精神が、大東亜共同宣言「相互協力・独立尊重」を、世界での各国間の関係に於いて実現されうる事を思う。
「道は天地自然のものにして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛したもう故、我を愛する心をもって人を愛するなり。人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして己を尽し人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」(西郷隆盛氏著「西郷南洲遺訓」より、本書中「武士道」経由)
著者は戦前の日本の教養教育を受ける中で思索し、読書を通じて公義や死生観を学んだと言う。日本の禅を含めた多くの先哲から学び、精神的な涵養・内省を行ったと言う。数多くの形而上学的哲学を学び、イマニュエル・カントの「純粋理性批判」や「実践理性批判」を判断指針にしていたが、やがてその「批判哲学」から、陽明学の「知行合一」や「実践躬行」へと変わっていったと言う。
「武士道」の「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義・克己」、「自害・切腹・仇討ち(復仇)」、武士と武家の婦人の教育等について熟読して解いておられる。
「義」は、公の為に用いるべく「公義」を意味し、私利私欲の無いものと言う。「公義」は「公的義務」、「義務」は「義の務め」、「義理」・「道義」は「正義の道理」が、本来の意味であると言う。
「勇」は、「敢為堅忍」がセットになっていない場合には、容易く卑怯な行為に用いられうると言う。自衛の為、大切なものを守る為、自害・切腹、仇討ち等、忍耐・我慢を伴った末の「やむにやまれぬ」気持ちに至った上で、一矢報いる命懸けの気概の勇気であると言う。
「仁」は、惻隠の心で弱者に共感・同情し、敵に塩を送り、相手の立場になって考える事であると言う。「誠」は「言が成る」という意味で、二言・二枚舌・虚言遁辞を否定し、信実・名誉・高い地位を表す。「克己」は、運命を受け入れ、感情を抑制し、実践道徳下、ストイックに、反省を伴うものと言う。「忠義」は公の為の忠であり、決して媚び諂い卑屈になって従うのでは無く、「勇」を持って諫言・忠告する事も必要であると言う。また迎合する事は、「名誉」に反するものと言う。
「武士は食わねど高楊枝」と言われた様に、武士は非経済的身分であった。高貴な身分故に、霊的勤労と清貧、道徳を旨とし、一般大衆よりも高い道徳が求められて大衆の模範となり、自分を律した。外見的ストイックで無表情となり、やせ我慢であったと言う。また死を恐れず、命や金に執着せず、現世の生死を超越した永遠の魂を見据えたと言う。
「餅は餅屋」と言う様に、女性は家事や家庭を守る事が役割であり、男性と女性を比較しての値打ちの違いと言うものは無く、差別でも無く、差異であり区別であると言う。そして、現在世界的に流布されているフェミニズムについて、悪平等と批判する。
本書より(著者の言葉)
「また、王陽明の言う『行』の概念は幅が広く、人間の心の働き、たとえば好悪の情や心に兆す意欲・思念なども『行』に含まれる、と主張しました。『行』は当然、道徳的規範に合致していなければならず、そこでは行動として外に表れた不善だけでなく、心内の思念の不善をも克服する厳しさが求められます。これらを実現する心が、王陽明の言う『良知』なのです。」
「新渡戸稲造先生は、陽明学の中にある短所には十分に配慮しながらも、その根本精神がキリスト教に根ざした新しい西欧の思潮にさまざまな点で合致している部分に着目し、『武士道』を世界に宣布する上での大きな理論的根拠を提供したのです。」
「『封建制の政治は武断主義に堕落しやすい』
という新渡戸先生が最も懸念していた“悪例”・・・…(後略)」
「弱者、劣者、敗者に対する仁は、特に武士に適わしき徳として賞讃せられた。」
「(前略)……新渡戸稲造先生は、
『武士道は非経済的である』
と直截に明言しています。なぜならば、『武士』という身分は報酬や金など全く期待しない、いや期待してはいけない仕事に身を捧げた人々だととらえているからです。……(後略)」
本書より(著者の言葉と「武士道」引用文)
「《女子がその夫、家庭ならびに家族のために身を棄つるは、男子が主君と国とのために身を棄つると同様に、喜んでかつ立派になされた。…(中略)…
女子が男子の奴隷でなかったことは、彼女の夫が封建君主の奴隷でなかったと同様である。女子の果たしたる役割は、内助すなわち『内側の助け』であった。奉仕の上昇階段に立ちて、女子は男子のために己を棄て、これにより男子をして主君のために己を棄つるをえしめ、主君はまたこれによって天に従わんがためであった。
私はこの教訓の欠陥を知っている。またキリスト教の優越は、生きとし生ける人間各自に向かって創造者に対する直接の責任を要求する点に、最も善く現われていることを知る。
しかるにもかかわらず、奉仕の教義に関する限り ― 自己の個性をさえ犠牲にして己よりも高き目的に仕えること、すなわちキリストの教えの中最大であり彼の使命の神聖なる基調をなしたる奉仕の教義 ― これに関する限りにおいて、武士道は永遠の真理に基づいたのである》
これは、女性を大事にしろ、という意味ではありません。婦人には婦人の役割、男性には男性の役割がある。婦人が役割を果たすべきところは『キッチン』である。『台所』である。それから、男が役割を果たすところは『戦場』である。それぞれのところで自分に課せられた役割を果たすのだから、どちらが偉いなどという問題ではない。それぞれの役割を果たしているという意味において『平等』である、ということを言っているのであって、何でもかんでも一緒くたにして『差別』だなどと皮相なスローガンを叫び立てていた戦後の『悪平等』論などとは似て非なるものなのです。
《もし私の言が武士道の下における婦人の地位に関し甚だ低き評価を人にいだかしめたとすれば、私は歴史的真理に対し大なる不正を冒すものである。
私は女子が男子と同等に待遇せられなかった、と述べるに躊躇しない。しかしながら、吾人が差異と不平等との区別を学ばざる限り、この問題についての誤解を常に免れないであろう》」
新渡戸稲造氏著「武士道」より(本書経由。尚、著者による本文中の( )内の註解は省略)
「まず、仏教から始めよう。
運命に任すという平静なる感覚、不可避に対する静かなる服従、危険災禍に直面してのストイック的なる沈着、生を賤しみ死を親しむる心、仏教は武士道に対してこれらを寄与した。」
「西洋の読者は、王陽明の著述の中に『新約聖書』との類似点の多いことを容易に見いだすであろう。特殊なる用語上の差異さえ認めれば、
『まず、神の国と神の義とを求めよ、さらばすべてこれらの物は汝らに加えらるべし』という言は、王陽明のほとんどいずれのページにも見いだされうる思想である」
(※「まず、神の国と・・・・・・」:新約聖書・マタイの福音書6章33節)
「(前略)・・・・・・或る著名の武士はこれを定義して決断力となした、曰く、『義は勇の相手にて裁断の心なり。道理に任せて決心して猶予せざる心をいうなり。死すべき場合に死し、討つべき場合に討つことなり』」
(※「或る著名の武士」:林子平、1738~1793、江戸後期の経世家)
「・・・(前略)・・・我が国民の大衆教育上しばしば引用せられる四十七人の忠臣は、俗に四十七義士として知られているのである。
ややともすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代にありて、この真率正直なる男らしき徳は、最大の光輝をもって輝いた宝石であり、人の最も高く賞讃したるところである。
義と勇とは双生児の兄弟であって、共に武徳である。…(中略)…義理という文字は『正義の道理』の意味であるが、…(中略)…その本来の純粋なる意味においては、義理は単純明瞭なる義務を意味した…(中略)…
何となれば、義務とは『正義の道理』が我々になすことを要求し、かつ命令するところ以外の何ものでもないではないか。『正義の道理』は我々の絶対命令であるべきではないか。・・・…
…(中略)…
・・・…自然の情愛はしばしば恣意的人工的なる習慣に屈服しなければならなかったような、人為的社会の諸条件から生まれでたものである。
正にこの人為性の故に義理は時をへるうちに堕落して、・・・…
…(中略)…
もし鋭敏にして正しき勇気感、敢為堅忍の精神が武士道になかったならば、義理はたやすく卑怯者の巣と化したであろう」
(※「絶対命令」:カント倫理学における「定言命令」。『善を行うのに条件付きではなく無条件に、ただ道徳法則の命令のままに断行する』)
「勇気は、義のために行われるのでなければ、徳の中に数えられるにほとんど値しない。・・・…
…(中略)…
・・・…水戸の義公も、
『戦場に掛け入りて討死するはいとやすき業にていかなる無下の者にてもなしえらるべし。生くべき時は生き死すべき時にのみ死するを真の勇とはいうなり』
と言っている。
西洋において道徳的勇気と肉体的勇気との間に立てられた区別は、我が国民の間にありても久しき前から認められていた。・・・…
…(中略)…
我慢と勇気の話はお伽ばなしの中にもたくさんある。しかし少年に対し敢為自若の精神を鼓吹する方法は、決してこれらの物語に尽きなかった。時には残酷と思われるほどの厳しさをもって、親は子供の胆力を練磨した。
『獅子はその児を千仞の谷に落す』
と彼らは言った。武士の子は艱難の嶮しき谷へ投ぜられ、…(中略)…時としては食物を与えず、もしくは寒気に曝すことも、忍耐を学ばしむるに極めて有効なる試練であると考えられた。・・・…(後略)」
(※「水戸の義公」:徳川光圀、1628~1700、水戸藩・二代藩主、「水戸黄門」)
「日本において武士階級の間に優雅の風が養われたのは、薩摩だけのことではない。白河楽翁公が心に浮かぶままを書き記せる随筆の中に、次のような言葉がある。
『枕に通うとも咎なきものは花の香り、遠寺の鐘、夜の虫の音はことに哀れなり』。
また曰く、
『憎くとも宥すべきは花の風、月の雲、うちつけに争う人はゆるすのみかは』
これらの優美なる感情を外に表現するため、否むしろ内に涵養するがため、武士の間に詩歌が奨励せられた。それ故に、我が国の詩歌には悲壮と優雅の強き底流がある』
(※「白河楽翁公」:松平定信、1758~1829、白河藩主、幕府老中、「寛政の改革」)
「虚言遁辞は、ともに卑怯と看做された。武士の高き社会的地位は、百姓町人よりも高き信実の標準を要求した。
…(中略)…
武士は然諾を重んじ、その約束は一般に証書にとらずして結ばれ、かつ履行せられた。証文を書くことは、彼の品位に適わしくないと考えられた。
『二言』すなわち『二枚舌』をば、死によって償いたる多くの物語が伝わっている。
信実を重んずることかくのごとく高く、したがって真個の武士は、誓いをなすをもって彼らの名誉を引き下げるものと考えた。
この点、一般のキリスト教徒が彼らの主の『誓うなかれ』という明白なる命令を、絶えず破っているのとは異なる。
…(中略)…
言を強めるためにしばしば文字通り血をもって判した。・・・…(後略)」
(※「誓うなかれ」:新約聖書・マタイの福音書5章34節
「しかし、わたしはあなたがたに言います。決して誓ってはいけません。すなわち、天をさして誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。」)
「武士道は、我々の良心を主君の奴隷となすべきことを要求しなかった。・・・…
…(中略)…
主君の気紛れの意思、もしくは妄念邪想のために自己の良心を犠牲にする者に対しては、武士道は低き評価を与えた。
かかる者は、「佞臣」すなわち腹黒き阿諛をもって気に入ることを求むる奸徒として、或いは「寵臣」すなわち卑屈なる追従によりて主君の愛を盗む嬖臣として賤しめられた。
…(中略)…
臣が君と意見を異にする場合、彼の取るべき忠義の途は、リア王に仕えしケントのごとく、あらゆる手段をつくして君の非を正すにあった。
容れられざる時は、主君をして欲するがままに我を処置せしめよ。かかる場合において、自己の血を濺いで言の誠実を表わし、これによって主君の明智と良心に対し最後の訴えをなすは、武士の常としたるところであった。
生命は、これをもって主君に仕うべき手段なりと考えられ、しかしてその理想は名誉に置かれた。したがって、武士の教育ならびに訓練の全体は、これに基づいて行なわれたのである」
(※「リア王に仕えしケント」:シェイクスピア「リア王」の「無類の忠臣」。「主君に諫言するときは命がけで忠告する勇気も持ち合わせていた」)
「武士の教育において守るべき第一の点は、品性を建つるにあり、思慮、知識、弁論等の知的才能は重んぜられなかった」
「かくのごとく金銭と金銭慾とを力めて無視したるにより、武士道は金銭に基づく凡百の弊害から久しく自由であることをえた。これは我が国の公吏が久しく腐敗から自由であった事実を証明する十分なる理由である。しかしああ!現代における拝金思想の増大何ぞそれ速やかなるや。
・・・(中略)…
知識でなく品性が、頭脳でなく霊魂が琢磨啓発の素材として選ばれる時、教師の職業は神聖なる性質を帯びる。
・・・(中略)…
あらゆる種類の仕事に対し報酬を与える現代の制度は、武士道の信奉者の間には行なわれなかった。金銭なく価格なくしてのみなされうる仕事のあることを、武士道は信じた。
僧侶の仕事にせよ、教師の仕事にせよ、霊的の勤労は金銀をもって支払わるべきでなかった。価値がないからではない、評価しえざるが故であった」
「武士が感情を面に現わすは男らしくないと考えられた。『喜怒色に現わさず』とは、偉大なる人物を評する場合に用いらるる句であった。
最も自然的なる愛情も抑制せられた。・・・(中略)…私室においてはともかく、他人の面前にてこれをなさなかったのである」
「克己の修養はその度を過ごしやすい。それは霊魂の潑剌たる流れを抑圧することがありうる。それはすなおなる天性を歪めて偏狭畸形となすことがありうる。それは頑固を生み、偽善を培い、情感を鈍らすことがありうる。……(後略)」
「(前略)……娘としては父のために、妻としては夫のために、母としては子のために、女子は己を犠牲にした。」
「(前略)……父や夫が戦場に出て不在なる時、家事を治むるはまったく母や妻の手に委ねられた。幼者の教育、その防衛すらも、彼らに託された。私が前に述べたる婦人の武芸のごときも、主として子女の教育を賢しく指導するをえんがためであった」
本ブログ過去の関連記事
・2016/07/21付:「クリスチャン内村鑑三・新渡戸稲造は愛国者であった・・・『三つのJ』、武士道精神、契約の民の末裔、歴史修正の必要性、慰霊・慰謝の靖国公式参拝の正当性」
・2017/04/23付:「『一億総町人化』『護憲の軍隊』、死を賭す覚悟の無さ、後の永遠を軽視、独立自尊精神の欠如、国家存亡危機、……自分の命を犠牲にし日本精神・魂を遺した三島由紀夫氏の警世・・・『若きサムライのために』を読む」
・2017/05/11付:「武士道・自害・切腹に見る日本の伝統的精神性と神道による宗教性、『男系男子』を貫く日本の皇室とユダヤの祭司の血統・・・『驚くほど似ている 日本人とユダヤ人』を読む」
「『武士道』解題 ノーブレス・オブリージュとは」(著者:李登輝氏、出版社:小学館、出版日:2006/05/01)(単行本 - 出版社:小学館、出版日:2003/04)
キリスト者(クリスチャン)である著者の元・中華民国(台湾)総統・李登輝氏。優秀な事で有名な、「東洋のユダヤ人」と呼ばれる「客家」でもある。西洋や日本の数多くの先人の哲学書を読み熟されて来たが故の教養と知識の豊かさ・深さと、イエスキリストへの信仰心をベースにした独自の視点からの捉え方により、同じキリスト者である新渡戸稲造氏の著した「武士道」を、本書にて読み解き明かし述べている。日本の明治維新後の近代化において、特に西欧列強諸国に日本の理解を深めてもらう為の海外への発信材料として、当時、英語で「武士道」が出版された。
その「武士道」を著した新渡戸稲造氏は、イエス・キリストと武士道をセットにして、「キリスト武士道」を唱えた。著書「武士道」は正に、止揚(アウフヘーベン)した「キリスト武士道」の内容となっている。しかし元々から、不文律の武士道や陽明学には、新約聖書的な内容が含まれていると、著書「武士道」の中で述べる。また、札幌農学校で同期生として共に学び、同じくキリスト者である内村鑑三氏も、「代表的日本人」を英語で著し、同じく海外に発信した。そして内村氏は、「愛国は人性の至誠なり」と唱えて、イエス・キリスト(Jesus)と日本国(Japan)の「二つのJ」をセットにした、「キリスト愛国」を唱えた。また、内村氏は新渡戸氏と同様に、「キリスト武士道」を次の様に表現した。
「武士道の台本に基督教を接いだ物、其物は世界最善の産物であって、之に日本国のみならず全世界を救ふ能力がある」(内村鑑三氏著「英和独語集」より、本書経由)
「キリスト武士道」精神の下、第一次世界大戦後のパリ講和会議にて、日本は「人種差別撤廃法案」を国連に提出した。11対5の賛成多数で可決されたものの、アメリカのウィルソン議長(米大統領)が全会不一致を理由にして、採決を無効とし、法案を成立させなかった。また大東亜戦争によって、白人欧米列強の白人至上主義によって差別的・奴隷的植民地とされていたアジア各国を解放して独立させ、その上での大東亜会議において、大東亜共同宣言「相互協力・独立尊重」を、アジア各国と共に宣言した。また、日韓合邦(日韓併合)時代に、日本が朝鮮半島に学校、病院、裁判所、橋梁、発電ダム等を建造し、鉄道を敷き、港湾や道路を整備して、朝鮮半島のインフラを近代化した。日本は朝鮮を一応形としては植民地として統治したが、白人の西欧列強諸国によるアジアやアフリカにおける搾取・掠奪・奴隷化の植民地政策とは全く異なり、日本は朝鮮に対して投資するばかり、与えるばかりで、日本は朝鮮に対しては赤字収支であり、却って日本の方こそが犠牲となっていた。
内村鑑三氏は「無教会主義」を唱え、新渡戸稲造氏も祭司無く装飾も無い極めて質素で小さな集会所でのクエーカー派であった。キリスト者である両者は共に、特に西欧の大きく組織化しているキリスト教団体とは距離を置き、堕落し世俗化しリベラル化しているキリスト教界を否定し批判した。
著者・李登輝元総統の2歳年上の兄は、日本軍に従軍して戦死し、靖国神社に合祀されているのだが、キリスト者である著者は、当然にして靖国参拝を希望していたのだが、日中関係を優先する日本政府の方針から日本への公式訪問も儘ならなかった事から、実現する事が出来ないでいた。しかし、本書の文庫版発行の翌年2007年に、観光目的で来日した際に靖国神社参拝を実現させ、「兄の霊を守ってくれることに感謝している」(ウィキペディア「李登輝」より)と、神社に対し謝礼を述べた。
靖国神社参拝について、昭和54年(1979年)に同じくキリスト者である大平正芳首相(当時)が、総理大臣として靖国神社公式参拝を行った。大平首相は、「『A級戦犯』及び大東亜戦争に対する審判は歴史が下すのに任せる、人がどう見ようと私は私の気持ちで参拝に行く」と延べ、慰霊の為、慰謝の為、世俗目的の為に、周囲の人にどの様に思われようとも、自分の気持ちに素直に、自分の信念に則って、堂々と公式参拝を果たした。そして大平首相は、日本の後世の人達による正しい歴史認識による日本の歴史修正によって、この参拝がはっきり認められる時が来る事を信じ期待していた。その公式参拝について、支那(中国)からの抗議は、当時は全く無かった。
因みに、政教分離について憲法に明確に定義されておらず、また最高裁判所において「目的効果基準」を基に、靖国神社の公式参拝は慰霊・慰謝の世俗目的の為であり、宗教的意義は希薄であり、それによる効果で特定宗教を利する事にはならないと判断して、「合憲」を示されている。欧米各国は、国家と宗教組織・団体を分離し、国家と宗教そのものとは分離していない。つまり、state(国家)である政府や権力機関が特定の宗教組織と結びつく事を禁止する事に留まり、nation(国家)である国民、共同体は宗教を排除する必要は無い(参考:百地章氏著「憲法の常識 常識の憲法」(文藝春秋))。
本書出版当時、アメリカ同時多発テロ事件(911)、米国によるアフガニスタン侵攻とイラク侵攻、新世界秩序(NWO)、金融至上主義と金融グローバル化、また日本の金融規制緩和や金融改革、国際金融資本・外資系・多国籍企業参入、構造改革、ゆとり教育、フェミニズム、リベラリズムが在り、更に支那(中国)や韓国からの靖国参拝や教科書検定等に対する内政干渉、領土問題、反日・歴史認識等における外交敗北、国内のマスコミ等による反日・スパイ活動、米国の圧力等と、日本がグローバリズムの波に呑まれかけ、外圧に抑えられ様とし、国家の存亡も危機に瀕していた。
その危機的状況を乗り越えて、日本国と日本人が生き残る為に必要なものとして、日本の伝統的精神「武士道」を、親日家で却って一般的な日本人よりも日本の事を理解しておられる著者が、警世の意味も込めて勧められている。自虐史観による対外的に媚び諛う外交や、政治家や官僚の慇懃無礼で卑屈な態度、国民の愛国心や自尊心、誇りの希薄さと、戦後の日本人が精神的に堕落してしまい、唯心論から唯物論に、拝物・拝金主義に陥ってしまった事に、その危機的状況を招いた原因が有る。武士道は、世界的なグローバリズムに対抗して、日本独自の歴史・伝統・文化・日本精神・大和魂・愛国心・民族的自尊心と自信、それらを守る為の規範・精神・土台となるものである。
現在の困難な時代に「いかに生くべきか」という問いに対し、日本の伝統的精神「武士道」を道徳規範として今一度、日本人が見直すべき事を強調する。そして、著者、新渡戸稲造氏、内村鑑三氏が共有する、イエス・キリストの教えとキリストへの信仰を併せた、「キリスト武士道」と「キリスト愛国」の精神が、大東亜共同宣言「相互協力・独立尊重」を、世界での各国間の関係に於いて実現されうる事を思う。
「道は天地自然のものにして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は人も我も同一に愛したもう故、我を愛する心をもって人を愛するなり。人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして己を尽し人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし」(西郷隆盛氏著「西郷南洲遺訓」より、本書中「武士道」経由)
著者は戦前の日本の教養教育を受ける中で思索し、読書を通じて公義や死生観を学んだと言う。日本の禅を含めた多くの先哲から学び、精神的な涵養・内省を行ったと言う。数多くの形而上学的哲学を学び、イマニュエル・カントの「純粋理性批判」や「実践理性批判」を判断指針にしていたが、やがてその「批判哲学」から、陽明学の「知行合一」や「実践躬行」へと変わっていったと言う。
「武士道」の「義・勇・仁・礼・誠・名誉・忠義・克己」、「自害・切腹・仇討ち(復仇)」、武士と武家の婦人の教育等について熟読して解いておられる。
「義」は、公の為に用いるべく「公義」を意味し、私利私欲の無いものと言う。「公義」は「公的義務」、「義務」は「義の務め」、「義理」・「道義」は「正義の道理」が、本来の意味であると言う。
「勇」は、「敢為堅忍」がセットになっていない場合には、容易く卑怯な行為に用いられうると言う。自衛の為、大切なものを守る為、自害・切腹、仇討ち等、忍耐・我慢を伴った末の「やむにやまれぬ」気持ちに至った上で、一矢報いる命懸けの気概の勇気であると言う。
「仁」は、惻隠の心で弱者に共感・同情し、敵に塩を送り、相手の立場になって考える事であると言う。「誠」は「言が成る」という意味で、二言・二枚舌・虚言遁辞を否定し、信実・名誉・高い地位を表す。「克己」は、運命を受け入れ、感情を抑制し、実践道徳下、ストイックに、反省を伴うものと言う。「忠義」は公の為の忠であり、決して媚び諂い卑屈になって従うのでは無く、「勇」を持って諫言・忠告する事も必要であると言う。また迎合する事は、「名誉」に反するものと言う。
「武士は食わねど高楊枝」と言われた様に、武士は非経済的身分であった。高貴な身分故に、霊的勤労と清貧、道徳を旨とし、一般大衆よりも高い道徳が求められて大衆の模範となり、自分を律した。外見的ストイックで無表情となり、やせ我慢であったと言う。また死を恐れず、命や金に執着せず、現世の生死を超越した永遠の魂を見据えたと言う。
「餅は餅屋」と言う様に、女性は家事や家庭を守る事が役割であり、男性と女性を比較しての値打ちの違いと言うものは無く、差別でも無く、差異であり区別であると言う。そして、現在世界的に流布されているフェミニズムについて、悪平等と批判する。
本書より(著者の言葉)
「また、王陽明の言う『行』の概念は幅が広く、人間の心の働き、たとえば好悪の情や心に兆す意欲・思念なども『行』に含まれる、と主張しました。『行』は当然、道徳的規範に合致していなければならず、そこでは行動として外に表れた不善だけでなく、心内の思念の不善をも克服する厳しさが求められます。これらを実現する心が、王陽明の言う『良知』なのです。」
「新渡戸稲造先生は、陽明学の中にある短所には十分に配慮しながらも、その根本精神がキリスト教に根ざした新しい西欧の思潮にさまざまな点で合致している部分に着目し、『武士道』を世界に宣布する上での大きな理論的根拠を提供したのです。」
「『封建制の政治は武断主義に堕落しやすい』
という新渡戸先生が最も懸念していた“悪例”・・・…(後略)」
「弱者、劣者、敗者に対する仁は、特に武士に適わしき徳として賞讃せられた。」
「(前略)……新渡戸稲造先生は、
『武士道は非経済的である』
と直截に明言しています。なぜならば、『武士』という身分は報酬や金など全く期待しない、いや期待してはいけない仕事に身を捧げた人々だととらえているからです。……(後略)」
本書より(著者の言葉と「武士道」引用文)
「《女子がその夫、家庭ならびに家族のために身を棄つるは、男子が主君と国とのために身を棄つると同様に、喜んでかつ立派になされた。…(中略)…
女子が男子の奴隷でなかったことは、彼女の夫が封建君主の奴隷でなかったと同様である。女子の果たしたる役割は、内助すなわち『内側の助け』であった。奉仕の上昇階段に立ちて、女子は男子のために己を棄て、これにより男子をして主君のために己を棄つるをえしめ、主君はまたこれによって天に従わんがためであった。
私はこの教訓の欠陥を知っている。またキリスト教の優越は、生きとし生ける人間各自に向かって創造者に対する直接の責任を要求する点に、最も善く現われていることを知る。
しかるにもかかわらず、奉仕の教義に関する限り ― 自己の個性をさえ犠牲にして己よりも高き目的に仕えること、すなわちキリストの教えの中最大であり彼の使命の神聖なる基調をなしたる奉仕の教義 ― これに関する限りにおいて、武士道は永遠の真理に基づいたのである》
これは、女性を大事にしろ、という意味ではありません。婦人には婦人の役割、男性には男性の役割がある。婦人が役割を果たすべきところは『キッチン』である。『台所』である。それから、男が役割を果たすところは『戦場』である。それぞれのところで自分に課せられた役割を果たすのだから、どちらが偉いなどという問題ではない。それぞれの役割を果たしているという意味において『平等』である、ということを言っているのであって、何でもかんでも一緒くたにして『差別』だなどと皮相なスローガンを叫び立てていた戦後の『悪平等』論などとは似て非なるものなのです。
《もし私の言が武士道の下における婦人の地位に関し甚だ低き評価を人にいだかしめたとすれば、私は歴史的真理に対し大なる不正を冒すものである。
私は女子が男子と同等に待遇せられなかった、と述べるに躊躇しない。しかしながら、吾人が差異と不平等との区別を学ばざる限り、この問題についての誤解を常に免れないであろう》」
新渡戸稲造氏著「武士道」より(本書経由。尚、著者による本文中の( )内の註解は省略)
「まず、仏教から始めよう。
運命に任すという平静なる感覚、不可避に対する静かなる服従、危険災禍に直面してのストイック的なる沈着、生を賤しみ死を親しむる心、仏教は武士道に対してこれらを寄与した。」
「西洋の読者は、王陽明の著述の中に『新約聖書』との類似点の多いことを容易に見いだすであろう。特殊なる用語上の差異さえ認めれば、
『まず、神の国と神の義とを求めよ、さらばすべてこれらの物は汝らに加えらるべし』という言は、王陽明のほとんどいずれのページにも見いだされうる思想である」
(※「まず、神の国と・・・・・・」:新約聖書・マタイの福音書6章33節)
「(前略)・・・・・・或る著名の武士はこれを定義して決断力となした、曰く、『義は勇の相手にて裁断の心なり。道理に任せて決心して猶予せざる心をいうなり。死すべき場合に死し、討つべき場合に討つことなり』」
(※「或る著名の武士」:林子平、1738~1793、江戸後期の経世家)
「・・・(前略)・・・我が国民の大衆教育上しばしば引用せられる四十七人の忠臣は、俗に四十七義士として知られているのである。
ややともすれば詐術が戦術として通用し、虚偽が兵略として通用した時代にありて、この真率正直なる男らしき徳は、最大の光輝をもって輝いた宝石であり、人の最も高く賞讃したるところである。
義と勇とは双生児の兄弟であって、共に武徳である。…(中略)…義理という文字は『正義の道理』の意味であるが、…(中略)…その本来の純粋なる意味においては、義理は単純明瞭なる義務を意味した…(中略)…
何となれば、義務とは『正義の道理』が我々になすことを要求し、かつ命令するところ以外の何ものでもないではないか。『正義の道理』は我々の絶対命令であるべきではないか。・・・…
…(中略)…
・・・…自然の情愛はしばしば恣意的人工的なる習慣に屈服しなければならなかったような、人為的社会の諸条件から生まれでたものである。
正にこの人為性の故に義理は時をへるうちに堕落して、・・・…
…(中略)…
もし鋭敏にして正しき勇気感、敢為堅忍の精神が武士道になかったならば、義理はたやすく卑怯者の巣と化したであろう」
(※「絶対命令」:カント倫理学における「定言命令」。『善を行うのに条件付きではなく無条件に、ただ道徳法則の命令のままに断行する』)
「勇気は、義のために行われるのでなければ、徳の中に数えられるにほとんど値しない。・・・…
…(中略)…
・・・…水戸の義公も、
『戦場に掛け入りて討死するはいとやすき業にていかなる無下の者にてもなしえらるべし。生くべき時は生き死すべき時にのみ死するを真の勇とはいうなり』
と言っている。
西洋において道徳的勇気と肉体的勇気との間に立てられた区別は、我が国民の間にありても久しき前から認められていた。・・・…
…(中略)…
我慢と勇気の話はお伽ばなしの中にもたくさんある。しかし少年に対し敢為自若の精神を鼓吹する方法は、決してこれらの物語に尽きなかった。時には残酷と思われるほどの厳しさをもって、親は子供の胆力を練磨した。
『獅子はその児を千仞の谷に落す』
と彼らは言った。武士の子は艱難の嶮しき谷へ投ぜられ、…(中略)…時としては食物を与えず、もしくは寒気に曝すことも、忍耐を学ばしむるに極めて有効なる試練であると考えられた。・・・…(後略)」
(※「水戸の義公」:徳川光圀、1628~1700、水戸藩・二代藩主、「水戸黄門」)
「日本において武士階級の間に優雅の風が養われたのは、薩摩だけのことではない。白河楽翁公が心に浮かぶままを書き記せる随筆の中に、次のような言葉がある。
『枕に通うとも咎なきものは花の香り、遠寺の鐘、夜の虫の音はことに哀れなり』。
また曰く、
『憎くとも宥すべきは花の風、月の雲、うちつけに争う人はゆるすのみかは』
これらの優美なる感情を外に表現するため、否むしろ内に涵養するがため、武士の間に詩歌が奨励せられた。それ故に、我が国の詩歌には悲壮と優雅の強き底流がある』
(※「白河楽翁公」:松平定信、1758~1829、白河藩主、幕府老中、「寛政の改革」)
「虚言遁辞は、ともに卑怯と看做された。武士の高き社会的地位は、百姓町人よりも高き信実の標準を要求した。
…(中略)…
武士は然諾を重んじ、その約束は一般に証書にとらずして結ばれ、かつ履行せられた。証文を書くことは、彼の品位に適わしくないと考えられた。
『二言』すなわち『二枚舌』をば、死によって償いたる多くの物語が伝わっている。
信実を重んずることかくのごとく高く、したがって真個の武士は、誓いをなすをもって彼らの名誉を引き下げるものと考えた。
この点、一般のキリスト教徒が彼らの主の『誓うなかれ』という明白なる命令を、絶えず破っているのとは異なる。
…(中略)…
言を強めるためにしばしば文字通り血をもって判した。・・・…(後略)」
(※「誓うなかれ」:新約聖書・マタイの福音書5章34節
「しかし、わたしはあなたがたに言います。決して誓ってはいけません。すなわち、天をさして誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。」)
「武士道は、我々の良心を主君の奴隷となすべきことを要求しなかった。・・・…
…(中略)…
主君の気紛れの意思、もしくは妄念邪想のために自己の良心を犠牲にする者に対しては、武士道は低き評価を与えた。
かかる者は、「佞臣」すなわち腹黒き阿諛をもって気に入ることを求むる奸徒として、或いは「寵臣」すなわち卑屈なる追従によりて主君の愛を盗む嬖臣として賤しめられた。
…(中略)…
臣が君と意見を異にする場合、彼の取るべき忠義の途は、リア王に仕えしケントのごとく、あらゆる手段をつくして君の非を正すにあった。
容れられざる時は、主君をして欲するがままに我を処置せしめよ。かかる場合において、自己の血を濺いで言の誠実を表わし、これによって主君の明智と良心に対し最後の訴えをなすは、武士の常としたるところであった。
生命は、これをもって主君に仕うべき手段なりと考えられ、しかしてその理想は名誉に置かれた。したがって、武士の教育ならびに訓練の全体は、これに基づいて行なわれたのである」
(※「リア王に仕えしケント」:シェイクスピア「リア王」の「無類の忠臣」。「主君に諫言するときは命がけで忠告する勇気も持ち合わせていた」)
「武士の教育において守るべき第一の点は、品性を建つるにあり、思慮、知識、弁論等の知的才能は重んぜられなかった」
「かくのごとく金銭と金銭慾とを力めて無視したるにより、武士道は金銭に基づく凡百の弊害から久しく自由であることをえた。これは我が国の公吏が久しく腐敗から自由であった事実を証明する十分なる理由である。しかしああ!現代における拝金思想の増大何ぞそれ速やかなるや。
・・・(中略)…
知識でなく品性が、頭脳でなく霊魂が琢磨啓発の素材として選ばれる時、教師の職業は神聖なる性質を帯びる。
・・・(中略)…
あらゆる種類の仕事に対し報酬を与える現代の制度は、武士道の信奉者の間には行なわれなかった。金銭なく価格なくしてのみなされうる仕事のあることを、武士道は信じた。
僧侶の仕事にせよ、教師の仕事にせよ、霊的の勤労は金銀をもって支払わるべきでなかった。価値がないからではない、評価しえざるが故であった」
「武士が感情を面に現わすは男らしくないと考えられた。『喜怒色に現わさず』とは、偉大なる人物を評する場合に用いらるる句であった。
最も自然的なる愛情も抑制せられた。・・・(中略)…私室においてはともかく、他人の面前にてこれをなさなかったのである」
「克己の修養はその度を過ごしやすい。それは霊魂の潑剌たる流れを抑圧することがありうる。それはすなおなる天性を歪めて偏狭畸形となすことがありうる。それは頑固を生み、偽善を培い、情感を鈍らすことがありうる。……(後略)」
「(前略)……娘としては父のために、妻としては夫のために、母としては子のために、女子は己を犠牲にした。」
「(前略)……父や夫が戦場に出て不在なる時、家事を治むるはまったく母や妻の手に委ねられた。幼者の教育、その防衛すらも、彼らに託された。私が前に述べたる婦人の武芸のごときも、主として子女の教育を賢しく指導するをえんがためであった」
本ブログ過去の関連記事
・2016/07/21付:「クリスチャン内村鑑三・新渡戸稲造は愛国者であった・・・『三つのJ』、武士道精神、契約の民の末裔、歴史修正の必要性、慰霊・慰謝の靖国公式参拝の正当性」
・2017/04/23付:「『一億総町人化』『護憲の軍隊』、死を賭す覚悟の無さ、後の永遠を軽視、独立自尊精神の欠如、国家存亡危機、……自分の命を犠牲にし日本精神・魂を遺した三島由紀夫氏の警世・・・『若きサムライのために』を読む」
・2017/05/11付:「武士道・自害・切腹に見る日本の伝統的精神性と神道による宗教性、『男系男子』を貫く日本の皇室とユダヤの祭司の血統・・・『驚くほど似ている 日本人とユダヤ人』を読む」
 | 「『武士道』解題 ノーブレス・オブリージュとは」 (著者:李登輝氏、出版社:小学館、出版日:2006/05/01) (単行本 - 出版社:小学館、出版日:2003/04) |










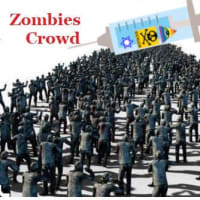
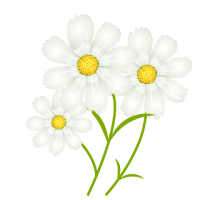
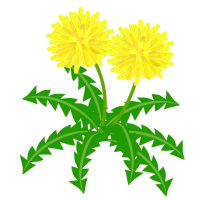
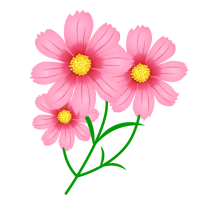
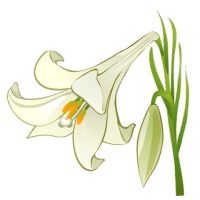
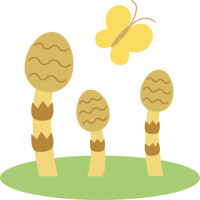
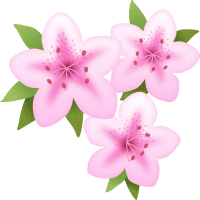

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます