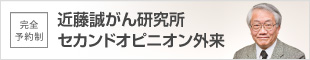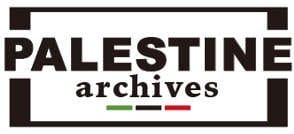哲学者・西田幾多郎氏(1870年(明治3年)6月17日 ~ 1945年(昭和20年)6月7日)は京都大学教授・名誉教授、京都学派の創始者で、研究分野は禅と倫理学、今から100年程前の著書「善の研究」によって世代を超えて現代社会の空虚さに対する示唆を与えています。
上田閑照氏(西田氏の孫弟子、専攻はドイツ哲学・宗教哲学、京都大学名誉教授)は、「空虚である事に疑問を感じた場合に、自分が何処に足を置いて立つべきかを問い直す上での指針・道を示す現代人への哲学として存在」、「自分の足で立つ、その限りにおいて、人と人との交わりもリアルになると言うのが西田氏の思想の根幹を成す」、「自立し、人間の基本的な在り方に返る事を重視している」。
その西田氏の特集番組を視聴してのレポートです。
「日本人は何を考えてきたのか・第11回『世代を超えて~西田幾多郎と京都学派~』」(2013年1月20日(日)22:00~23:30、NHK・Eテレ)。
根源、純粋主義、直接。
全体主義と個人主義。
東洋と西洋の哲学を自分のものにして、新たな思想形態を生み出す。
青年時代の参禅と幅広い西洋哲学書の読書の蓄積が根底に存在。
「善の研究」…1911年、西田氏40歳時の最初の著作。
軍の理論化…「大東亜共栄圏」。
人生の問題=哲学。…自己の悩みが哲学の動機に。
ギャップに身を置いて逃れず、統一の在り方を成り立たせる。
座禅…悟りの境地。じっとして自分と外との仕切り・区別が解けて、限りない開きを経験する。「心月孤円光香万象」…「円相図」。「○」の月・円の心、無限なものに根源を内包、その内の空・無から(自分を)出発。
「純粋経験」=「直接経験」。…同類のものを主観によって判断して種類に分ける前の段階。思慮分別が加わる前の意識状態。…「自己の細工を捨てて事実に従うて知る」。事実そのままに知るの意。主観へのこだわりを捨てよと訴える。「自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主も無く客も無い知識とその対象とが全く合一している、此れが経験の最酵(最純)」。
「自覚に於ける直観と反省」(大正6年著)。…純粋経験=直接的経験=直観から自覚へ。それから主客二元論(主観と客観)、思慮分別=反省へ。自覚においては認識の連続。図と地。
絶対的価値の喪失から、悩み・哲学へ。その哲学を時世への反映、方向付け、思想、本性そのもの、普遍性になるものとしようとする。絶対的価値=理想。
「日本文化の問題」著。…「矛盾的自己同一」、矛盾・対立そのままに、全体的な同一性を保っている状態。生命は多と一(多くの細胞と一つの身体)、全体主義と個人主義との結び付き。物事を根源的に捉える事に加えて、自己の意識からのみでは無く、現実の世界の構造からも考える。心境的な面で確信を得ても、心境的で形・表現の無さは歴史を動かせないと。
戦時、「最も戒むべきは日本を主体化する事」と。…日本を主体化した帝国主義・全体主義に於いて、大義名分は成立しない。ブレーントラスト(政策に助言する学識経験者。知能顧問団)を務め、「東亜新秩序」。
昭和研究会が新日本の思想原理・新文化の創造。陸軍と海軍其々にブレーンが存在し、西田氏はその両方の幹部のブレーントラストとなった。海軍の秘密会合に京都学派(京都帝国大学での西田氏に師事)、その会合の大島康正メモが残る。「近代の超克」(京都学派、文学会著)は、当時若者や知識人に流行。西田氏と陸軍幹部による国策研究会(昭和18年5月)にて、「世界新秩序の原理」。「大東亜共栄圏」の理論化…日本の「盟主」(日本が東アジアでのイニシアチブ(主導権)を握る事)と他国との「共栄」(共存共栄)の矛盾を如何に結び付けるか。歴史哲学の確立。実際は、軍政には他者の視点が無かった。
西田氏の弟子の三木清氏(兵庫県たつの市出身、霞城館に資料)は、昭和17年に陸軍宣伝員として「東亜解放の真義の徹底」を任務としてフィリピンに10ヶ月従軍。「日本が当面している厳しい現実は、甘い観念論、浪漫的な形而上学で乗り切れるものでは無い」と、従軍前の己を含めた日本の知識人への根本からの批判をする。
陸軍幹部宛て「要領理解の参考に供する」にて、昭和18年6月の東条英機首相演説への西田氏の助言、「各国家・民族が各自の世界的使命に自覚して、地域伝統に従って一つの特殊的世界を構成しなければならない。これが共栄圏の原理」。一方では、「その中心となって之を担うものがなければならない。東洋に於いては我が日本の他には無い」と矛盾した事と、日本の責任を述べている。しかし、実際の演説には西田氏の理念は反映されずに失望された。
「古来、武力のみにて栄えた国は有りません。永遠に栄える国は、立派な道徳と文化とが根底になければなりません。我が国民全て此の根底から大転換をせねばならぬ時」(昭和20年西田氏)。
「西田哲学」のアンダーカレント(底流)、デタッチメント(関わり無く)からコミットメント(参加)・積極性・義務感・語りへと遷移した事。
上田閑照氏、「何となくはっきりとしない事でもこうだと決めていく事によって学問が成立し、その学問を基礎にして実践や政策になる。しかし哲学はその逆で、決められた事、決まった様に見える事、それらが全てでは無い。もっと別の事が有り、その外があるというそのセンス、それが非常に大切」。
西田氏は、己とは何か、世界とは何かを生涯問い続けた。「私が書いたものが何にもならないものかもしれない。或いは、後の何人かの立場になるものかも知れない。私には唯、私の道を進み行く外ないのです」(昭和11年)。
自分・人間の考え・打算・計り事(謀り事)が生じる前に、神様から与えられた経験・運命に対して元々生まれ持っている良心から生じて来る純粋な気持ちが大事であり、西田氏の言う主観を捨てた「純粋主義」と共通する様に思います。又、イエス・キリストにあってイエス・キリストを信じる全ての者が一つになる事は、西田氏の「矛盾的自己同一」に似ている様にも思います。
旧約聖書・詩編12章6節「主のみことばは混じりけのないことば。」。
同・箴言30章5~6節「神のことばは、すべて純粋。神は拠り頼む者の盾。神のことばにつけ足しをしてはならない。神が、あなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。」。
新約聖書・ローマ人への手紙12章4~8節「一つのからだには多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器官なのです。私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行なう人は喜んでそれをしなさい。」。
同・コリント人への手紙 第一12章4~27節「さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、みなの益となるために、おのおのに御霊の現われが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵のことばが与えられ、ほかの人には同じ御霊にかなう知識のことばが与えられ、またある人には同じ御霊による信仰がが与えられ、・・・。しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、みこころのままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですから、ちょうど、からだが一つでも、それに多くの部分があり、からだの部分はたとい多くあっても、その全部が一つのからだであるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちはみな、ユダヤ人もギリシヤ人も、奴隷も自由人も、一つのからだとなるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべての者が一つの御霊を飲む者とされたからです。・・・もしからだ全体が聞くところであったら、どこでかぐのでしょう。しかしこのとおり、神はみこころに従って、からだの中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし、全部がただ一つの器官であったら、からだはいったいどこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、からだは一つなのです。・・・からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。また、私たちは、からだの中で比較的に尊くないとみなす器官を、ことさらに尊びます。・・・神は、劣ったところをことさらに尊んで、からだをこのように調和させてくださったのです。それは、からだの中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです。」。
上田閑照氏(西田氏の孫弟子、専攻はドイツ哲学・宗教哲学、京都大学名誉教授)は、「空虚である事に疑問を感じた場合に、自分が何処に足を置いて立つべきかを問い直す上での指針・道を示す現代人への哲学として存在」、「自分の足で立つ、その限りにおいて、人と人との交わりもリアルになると言うのが西田氏の思想の根幹を成す」、「自立し、人間の基本的な在り方に返る事を重視している」。
その西田氏の特集番組を視聴してのレポートです。
「日本人は何を考えてきたのか・第11回『世代を超えて~西田幾多郎と京都学派~』」(2013年1月20日(日)22:00~23:30、NHK・Eテレ)。
根源、純粋主義、直接。
全体主義と個人主義。
東洋と西洋の哲学を自分のものにして、新たな思想形態を生み出す。
青年時代の参禅と幅広い西洋哲学書の読書の蓄積が根底に存在。
「善の研究」…1911年、西田氏40歳時の最初の著作。
軍の理論化…「大東亜共栄圏」。
人生の問題=哲学。…自己の悩みが哲学の動機に。
ギャップに身を置いて逃れず、統一の在り方を成り立たせる。
座禅…悟りの境地。じっとして自分と外との仕切り・区別が解けて、限りない開きを経験する。「心月孤円光香万象」…「円相図」。「○」の月・円の心、無限なものに根源を内包、その内の空・無から(自分を)出発。
「純粋経験」=「直接経験」。…同類のものを主観によって判断して種類に分ける前の段階。思慮分別が加わる前の意識状態。…「自己の細工を捨てて事実に従うて知る」。事実そのままに知るの意。主観へのこだわりを捨てよと訴える。「自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主も無く客も無い知識とその対象とが全く合一している、此れが経験の最酵(最純)」。
「自覚に於ける直観と反省」(大正6年著)。…純粋経験=直接的経験=直観から自覚へ。それから主客二元論(主観と客観)、思慮分別=反省へ。自覚においては認識の連続。図と地。
絶対的価値の喪失から、悩み・哲学へ。その哲学を時世への反映、方向付け、思想、本性そのもの、普遍性になるものとしようとする。絶対的価値=理想。
「日本文化の問題」著。…「矛盾的自己同一」、矛盾・対立そのままに、全体的な同一性を保っている状態。生命は多と一(多くの細胞と一つの身体)、全体主義と個人主義との結び付き。物事を根源的に捉える事に加えて、自己の意識からのみでは無く、現実の世界の構造からも考える。心境的な面で確信を得ても、心境的で形・表現の無さは歴史を動かせないと。
戦時、「最も戒むべきは日本を主体化する事」と。…日本を主体化した帝国主義・全体主義に於いて、大義名分は成立しない。ブレーントラスト(政策に助言する学識経験者。知能顧問団)を務め、「東亜新秩序」。
昭和研究会が新日本の思想原理・新文化の創造。陸軍と海軍其々にブレーンが存在し、西田氏はその両方の幹部のブレーントラストとなった。海軍の秘密会合に京都学派(京都帝国大学での西田氏に師事)、その会合の大島康正メモが残る。「近代の超克」(京都学派、文学会著)は、当時若者や知識人に流行。西田氏と陸軍幹部による国策研究会(昭和18年5月)にて、「世界新秩序の原理」。「大東亜共栄圏」の理論化…日本の「盟主」(日本が東アジアでのイニシアチブ(主導権)を握る事)と他国との「共栄」(共存共栄)の矛盾を如何に結び付けるか。歴史哲学の確立。実際は、軍政には他者の視点が無かった。
西田氏の弟子の三木清氏(兵庫県たつの市出身、霞城館に資料)は、昭和17年に陸軍宣伝員として「東亜解放の真義の徹底」を任務としてフィリピンに10ヶ月従軍。「日本が当面している厳しい現実は、甘い観念論、浪漫的な形而上学で乗り切れるものでは無い」と、従軍前の己を含めた日本の知識人への根本からの批判をする。
陸軍幹部宛て「要領理解の参考に供する」にて、昭和18年6月の東条英機首相演説への西田氏の助言、「各国家・民族が各自の世界的使命に自覚して、地域伝統に従って一つの特殊的世界を構成しなければならない。これが共栄圏の原理」。一方では、「その中心となって之を担うものがなければならない。東洋に於いては我が日本の他には無い」と矛盾した事と、日本の責任を述べている。しかし、実際の演説には西田氏の理念は反映されずに失望された。
「古来、武力のみにて栄えた国は有りません。永遠に栄える国は、立派な道徳と文化とが根底になければなりません。我が国民全て此の根底から大転換をせねばならぬ時」(昭和20年西田氏)。
「西田哲学」のアンダーカレント(底流)、デタッチメント(関わり無く)からコミットメント(参加)・積極性・義務感・語りへと遷移した事。
上田閑照氏、「何となくはっきりとしない事でもこうだと決めていく事によって学問が成立し、その学問を基礎にして実践や政策になる。しかし哲学はその逆で、決められた事、決まった様に見える事、それらが全てでは無い。もっと別の事が有り、その外があるというそのセンス、それが非常に大切」。
西田氏は、己とは何か、世界とは何かを生涯問い続けた。「私が書いたものが何にもならないものかもしれない。或いは、後の何人かの立場になるものかも知れない。私には唯、私の道を進み行く外ないのです」(昭和11年)。
自分・人間の考え・打算・計り事(謀り事)が生じる前に、神様から与えられた経験・運命に対して元々生まれ持っている良心から生じて来る純粋な気持ちが大事であり、西田氏の言う主観を捨てた「純粋主義」と共通する様に思います。又、イエス・キリストにあってイエス・キリストを信じる全ての者が一つになる事は、西田氏の「矛盾的自己同一」に似ている様にも思います。
旧約聖書・詩編12章6節「主のみことばは混じりけのないことば。」。
同・箴言30章5~6節「神のことばは、すべて純粋。神は拠り頼む者の盾。神のことばにつけ足しをしてはならない。神が、あなたを責めないように、あなたがまやかし者とされないように。」。
新約聖書・ローマ人への手紙12章4~8節「一つのからだには多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大ぜいいる私たちも、キリストにあって一つのからだであり、ひとりひとり互いに器官なのです。私たちは、与えられた恵みに従って、異なった賜物を持っているので、もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまず分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行なう人は喜んでそれをしなさい。」。
同・コリント人への手紙 第一12章4~27節「さて御霊の賜物にはいろいろの種類がありますが、御霊は同じ御霊です。奉仕にはいろいろの種類がありますが、主は同じ主です。働きにはいろいろの種類がありますが、神はすべての人の中ですべての働きをなさる同じ神です。しかし、みなの益となるために、おのおのに御霊の現われが与えられているのです。ある人には御霊によって知恵のことばが与えられ、ほかの人には同じ御霊にかなう知識のことばが与えられ、またある人には同じ御霊による信仰がが与えられ、・・・。しかし、同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、みこころのままに、おのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。ですから、ちょうど、からだが一つでも、それに多くの部分があり、からだの部分はたとい多くあっても、その全部が一つのからだであるように、キリストもそれと同様です。なぜなら、私たちはみな、ユダヤ人もギリシヤ人も、奴隷も自由人も、一つのからだとなるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべての者が一つの御霊を飲む者とされたからです。・・・もしからだ全体が聞くところであったら、どこでかぐのでしょう。しかしこのとおり、神はみこころに従って、からだの中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし、全部がただ一つの器官であったら、からだはいったいどこにあるのでしょう。しかしこういうわけで、器官は多くありますが、からだは一つなのです。・・・からだの中で比較的に弱いと見られる器官が、かえってなくてはならないものなのです。また、私たちは、からだの中で比較的に尊くないとみなす器官を、ことさらに尊びます。・・・神は、劣ったところをことさらに尊んで、からだをこのように調和させてくださったのです。それは、からだの中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分がともに喜ぶのです。あなたがたはキリストのからだであって、ひとりひとりは各器官なのです。」。