ハリウッドの代表的映画監督オリバー・ストーン氏は、映画を武器に政治や権力と闘っています。ストーン監督が、第二次大戦前夜の1930年代から現代までのアメリカ史を独自の視点で語り綴った、「オリバー・ストーンが語るアメリカ史(原題:The Untold History of the United States)」を制作しました。脚本は監督とアメリカン大学(ワシントンDC)歴史学科のピーター・カズニック准教授との共同執筆により、アメリカの外交・軍事の軌跡を検証し、大量の核兵器を保有するアメリカは、世界の人々とどう向き合ってきたのか、そして核兵器削減の機会はなかったのかを問いかけます。教科書には書かれていない歴史の中で、アメリカの辿った道を変えられたかも知れない人物にも焦点を当てて、アメリカ人の歴史認識を大きく揺さぶっているそうです。この作品はBS世界のドキュメンタリーの時間枠で、全10本からなるシリーズ番組として、これまで2度にわたり放送されました。貴重な歴史的映像を含む衝撃的内容で、歴史の重みに圧倒される作品でした。ストーン監督は作品の冒頭で、アメリカが第二次大戦以後に犯してきた深刻な過ちを正すことを願い、そのチャンスはあると語っています。
8月第2週から、BS1で00:00-00:50(24時間表記)のBS世界のドキュメンタリーでシリーズの再々放送が始まります。全てを視聴するのは大変な時間と労力を要しますが、5日(月)の同じ時間帯のBS1スペシャルで、シリーズの放送に先立ち、見どころが一挙に御覧になれます。それ以降の放送予定と番組の概要を以下に示します。
8月6日(火)「第1回 第二次世界大戦の惨禍」。
第二次世界大戦前夜から1942年のスターリングラードの攻防までが描かれます。ストーン監督は番組冒頭で、「未来を生きる子供たちのためにも、新たな視点を提示し、歴史に関心を持つ眼を育んでもらいたい。このために、忘れられた歴史上のヒーローにも焦点をあて、語られなかった歴史を見ていく」とシリーズ制作の意図を説明します。
第二次世界大戦は、ヒトラー、ムッソリーニのファシスト政権と日本の帝国主義を打ち砕いたという意味で、多くのアメリカ人にとって「正しい戦争」だったと言われます。しかしドキュメンタリーは、実際にはおびただしい数の死者を出した「最悪の戦争」であり、アメリカはこの戦争で“深刻な過ち”を犯したとしています。
日本、ドイツ、フランコが勝利するスペイン内戦、スターリンのソビエトなどの様相が挿入されているほか、アメリカのルーズベルト大統領の「大陸への戦争には関与しない」という公約が、ドイツの快進撃の中でどう覆されるのかが紐解かれています。また、当時としては異例の黒人農業技術者を登用したウォレス農務長官を副大統領に据えたことにも焦点をあてています。
8月7日(水)「第2回 ルーズベルト、トルーマン、ウォレス」。
第二次世界大戦後半、スターリングラード攻防でナチス・ドイツが敗北して以来、独ソ戦の形勢はソビエト有利に傾きました。この形勢逆転で英米はスターリン単独での対ドイツ和平を恐れました。これを防ぐためルーズベルトは、1943年11月にテヘランでスターリン、チャーチルと会談。更にルーズベルトは、チャーチルを外してスターリンと個別に数日間交渉を行い、東ヨーロッパの戦後処理にソビエトが関与することを事実上認め、ナチスとの戦争終了後にソビエトが対日戦争を開始することが極秘に確認されました。
また、内政面では、圧倒的な支持を得ていた副大統領候補のヘンリー・ウォレス(当時、副大統領)にスポットを当てています。ウォレスは歴史上で忘れられたような存在ですが、1942年に“the century of the common man(市民の世紀)”を訴える演説を行い、全米で最も人気のある政治家でした。しかし、彼のリベラルな姿勢(男女平等、黒人解放的思考、反植民地主義など)が民主党内で危険視され、トルーマンが一転して副大統領候補となる「歴史の分かれ目」となるような変化が起きました。その後、ルーズベルト大統領の死によって大統領となったトルーマンは、日本への原爆投下を決断することになるのです。
8月8日(木)「第3回 原爆投下」。
広島と長崎への原爆投下に至るアメリカ政府内の“知られざる論争”に焦点があてられます。ニミッツ、アイゼンハワー、マッカーサー、キング、アーノルド、レイヒーという6人の主要な将軍も、原爆投下は「道徳的にも非難されるべきであり、軍事的にも必要ない」としていました。そして、戦後に原爆の破壊力の凄まじさから、核兵器の国際共同管理、あるいはソビエトの研究中止確約によるアメリカの核兵器破棄という選択肢が政権内で多数派を占めながらも、トルーマン大統領、バーンズ国務長官が否定していくことも描かれます。そして、トルーマン路線と対立したウォレス商務長官の突然の辞任につながります。ニューディールの中心的な存在で、ルーズベルト政権の農務長官、副大統領、そしてトルーマン政権の商務長官と政権内にいた彼の存在は大きかったとするストーン監督は、「彼がもし、シカゴの党大会で引き続き副大統領候補に指名されていれば、ルーズベルトの死後、大統領になっていた。そうなれば、原爆の投下はあっただろうか?戦後の核開発競争もあっただろうか。人種隔離や女性の権利向上は数十年早く実現しただろうか?」と問いかけます。
当ブログ掲載の広島原爆投下前の米政権内の意見対立と、ポツダム会議の裏側もご参照ください。
8月9日(金)「第4回 冷戦の構図」。
第二次世界大戦直後の5年間、トルーマン政権時代に進む反共戦略に焦点を当てられ、アメリカが核兵器を保有し、世界に君臨する反共産主義国家へと変わっていく経緯が明らかにされます。アメリカでは戦前に比べ輸出額が倍増し、工業生産は年に15%の伸びを示すなど、大きな経済成長を遂げていました。一方、戦争の甚大な被害を被ったヨーロッパ各国では、社会不安から共産主義勢力が拡大していました。ドイツと日本の侵略を恐れたスターリンはアメリカとの協力関係を望みましたが、アメリカはメディアを使ってソビエトが共産主義による世界征服をもくろんでいると国民に信じさせることに成功し、世界は冷戦へと向かいました。
アメリカが1947年のトルーマン・ドクトリンで冷戦の構図を作りあげたことがターニングポイントとなり、その後の核開発競争と朝鮮半島やインドシナ半島への介入へとつながったとオリバー・ストーン監督は主張しています。
8月12日(月)「第5回 アイゼンハワーと核兵器」
冷戦構造が確定し、核開発競争が激化するアイゼンハワー大統領の1950年代を見る。アメリカは「力の外交」を展開し、自由主義陣営の構築を目指す。その屋台骨をダレス国務長官やポール・ニッツェなどの反共産主義者が担い、CIA長官のアレン・ダレス、FBIに君臨したエドガー・フーバーが権謀術数を張り巡らす。外交面では、パーレビ国王を復位させたアメリカはイランを中東最強の同盟国に仕立て上げるなど、政権転覆も含め、アメリカの陣営に入れようと様々な“工作”が行われた。こうした“外交”は、第三世界でのアメリカの評判を落としていったと、ストーン監督は指摘する。米ソによる対立が激しくなる中、エジプト、インド、インドネシア、ユーゴなどの国々は、「非同盟中立路線」を掲げて、アメリカと距離を取っていく。一方、対共産圏では、中国、北ベトナム、ラオスなど、アメリカは核兵器使用を検討する事態があったことに光をあてている。国内的には、軍需産業が隆盛となり、経済的繁栄を謳歌したが、海外に目を向けると朝鮮戦争やハンガリー動乱、スエズ動乱、インドシナ戦争など、ベトナムへの軍事介入の伏線が張られていく時代でもあった。
8月13日(火)「第6回 J. F. ケネディ ~全面核戦争の瀬戸際~」。
1961年1月に大統領に就任した若きケネディは、冷戦と反共主義で弱体化した民主党にあっては希望の星だった。しかし、前年の大統領選でニクソンとの一騎打ちを僅差で勝利したケネディは、アイゼンハワー共和党政権時代の問題対処に迫られる。その一つが、CIAが立案し、亡命キューバ人を使ったカストロ転覆計画(ピッグス湾事件、1961年4月)。米軍の出動を懇願した亡命キューバ人と制服組の声をケネディは拒否。これがきっかけとなって、第三世界や共産主義圏への工作を続けるCIAやペンタゴンとの内なる闘いが生まれていく。そして、1962年キューバ危機。米ソの全面核戦争一歩手前までいく事態となった。結果的に危機を回避したケネディ。しかし、強硬策を取らなかったケネディは、フルシチョフ・ソ連首相と同じで、国内の強硬派、ミリタリー、インテリジェンスのコミュニティーから強い怒りを買うことになったとストーン監督は指摘する。それでも全面戦争の深淵を見た米ソ首脳は、部分的核実験禁止条約をまとめ、米上院で批准をみる。そして、1963年6月のアメリカン大学(AU)の卒業式。ストーン監督が「20世紀の歴史的な演説」と呼んだケネディ演説が行われた。ペンタゴン、国務省、CIAからの見解を受けず、20世紀を生きるアメリカの採るべき姿勢を青年たちに訴えた。その後に暗殺されるケネディ。冷戦の路線修正を狙った試みは潰えていく。
8月14日(水)「第7回 ベトナム戦争 運命の暗転」。
ケネディの後を継いだジョンソンは、ベトナム戦争への関与を深めていく。そして、第二次世界大戦で投下された爆弾の三倍以上という夥しい量を、北ベトナムを中心に投下する。多くの戦場でモラルが低下し、現場指揮官が大規模な空爆でも状況が好転しないと進言する中、ジョンソンは強硬路線を取り続けた。やがて、国防長官のマクナマラとの対立が顕在化し、マクナマラは世界銀行総裁に転出させられた。国内ではベトナム反戦運動が高まり、FBIはこの背後に共産主義者が扇動しているとみて、大がかりな電話盗聴や諜報活動を展開。対象には黒人公民権運動のリーダー、キング牧師もいた。
戦争が泥沼化する中、何度が核兵器使用について検討された。やがて、ジョンソンは再選を求めず、共和党のニクソンが大統領になった。それでもキッシンジャーたちは、徹底爆撃を指令した。ベトナム世代のストーン監督は、この時代に起きたことを様々な言葉で総括している。「ワシントンにあるベトナム戦争記念碑には58000人余の米兵に捧げられている。そのメッセージは、米国兵の損失が悲劇の中核であって、その背後に380万人以上のベトナム、カンボジアやラオスの人々がいることではない」。ベトナム戦争でアメリカは負け、アメリカ社会は大きく分断された。しかし、こうした過去の教訓は、保守層のみならず、多くのアメリカの政治家が“組織的に美化し”、大義のある戦争だったと喧伝したとする。"
8月19日(月)第8回「レーガンとゴルバチョフ」。
ソビエトのブレジネフ書記長死後の混乱を経て、若きゴルバチョフが登場し、レーガン大統領との間で一連の米ソ首脳会談を行っていく過程を描く。
第二次世界大戦後に世界各地で米軍を駐留させることになったアメリカは、分厚い産軍複合体を形成し、おびただしい数の核兵器を配備してきた。こうした国家のあり様を少しでも変えることはできたのではないか・・・。オリバー・ストーン監督ら制作者は、ここで1986年にアイスランドのレイキャビクで開かれたレーガン・ゴルバチョフによる米ソ首脳会談と、それに至る過程を「大きな歴史の分岐点だったとする。
レーガンは、基本的には核軍縮に前向きとされたが、一方で核抑止を確実にするためにSDI(戦略防衛構想)を打ち上げていた。しかし、ペンタゴンや軍のインナーサークルはSDIが“たわいない夢物語”であることも分かっていた。この構想に危機感を抱くゴルバチョフは、「アメリカがSDIを断念すれば、ソビエトは核兵器全廃に踏み出す・・・」という“大胆かつ明確な提案”をしてきた。ここでレーガンは逡巡する。最後まで受け入れを迫るゴルバチョフは、会談終了後の車寄せでレーガンを見送る時にも再考を促した。しかし、歴史の歯車は核兵器の大幅削減へとは向かわなかった。
8月20日(火)第9回「“唯一の超大国”アメリカ」。
レーガンの後を継いだのが、副大統領のジョージ・H.W.・ブッシュ。彼の4年間には、東欧社会主義圏で体制転換が起き、ベルリンの壁も崩壊。やがてソビエト連邦が解体して冷戦が終結する“激動の時代”だった。湾岸戦争も天安門事件も起きた。
この激変の時期にあって、アメリカは、世界との関係を再構築できるチャンスと捉え、寛容な外交姿勢に転じることはできなかったのか・・・。オリバー・ストーン監督ら制作者たちは鋭く問いかける。そして、湾岸戦争で勝利したブッシュが再選を阻まれ、民主党のクリントンが登場した時にもそのチャンスは訪れる。しかし、クリントンは保守派の圧力を受け、結局のところ軍事増強を推し進めることになった。「この時代、差し迫った脅威がアメリカには少なかったにも関わらず、共和党に輪をかけてクリントンは軍事支出を増やしてしまった」とストーン監督は指摘する。
1990年代は、“アメリカの一人勝ち”と言われた時代で、経済のグローバル化が進み、その蓄積された富もまたアメリカに向かった。“唯一の超大国”のアメリカは従来の外交姿勢を崩さず、結果的に「資本主義の正当性」を強調するだけであった。
8月21日(水)第10回「テロの時代 ブッシュからオバマへ」
“唯一の超大国”となり、経済的繁栄を謳歌していたアメリカだが、21世紀に入るとその光景が一変する。2001年9月11日の同時多発テロ事件である。ニューヨークとワシントン郊外の国防総省を襲った前代未聞の民間航空機テロ後に、長く続くことになったのが「テロの時代」である。
アメリカは「愛国法」をもとに、テロ容疑者への尋問、拘束、電話の盗聴など、あらゆる手段を用いてイスラム過激派勢力の封じ込めを狙う。アフガンだけでなく、イラクへの戦争も仕掛ける。しかしイラクの場合、大量破壊兵器は見つからず、軍事介入の正当性に疑問符が付けられることになった。アメリカの大義は大きく揺らぎ、その威信を回復すべく登場したのがバラク・オバマだった。
「アメリカン・エンパイアー」と呼ばれ、主要国の軍事費の合計を遥かにしのぐ軍事費を支出するアメリカは、21世紀を経てもなお“大国”として存続しうるだろうか・・・。オリバー・ストーン監督は、シリーズ最終作を締めくくるあたり、第二次世界大戦から70年近くなるアメリカの軍事・外交戦略が全てにおいて正しいものだったのか、根本的な問いかけを行っている。そして、自らの歴史を正当化、美化している状況にも警鐘を鳴らす。












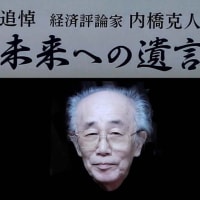


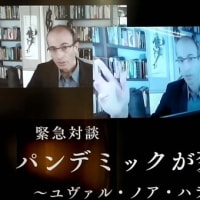









※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます