会の概要報告については「―1」を参照(写真を含めた会の様子はこちらにあります)。
なにぶんにも多彩なメンツであったので、死刑制度をめぐる問題点の言及も多岐に渡った。それは予想していたことでもあり、同時に話の多くは僕が書籍やWebサイトなどで読んであらかじめ知っていた情報であることが多かった。もちろん会場には死刑について学び始めたばかりという人だってたくさんいただろうから、そうした話が無駄であるはずもない。ただ、僕の聞きたかったことは他にあったのも事実である。
最初に司会者から指名を受けて発言を求められたパネリストは亀井静香だった。それで、会の滑り出しとしては「終身刑導入と引き換えの死刑廃止」という道筋、つまりはどちらかと言えば政治的な解決の道筋が、ここ日本でも端緒を開きつつあるという情勢の確認から始まったわけである(裁判員制度との兼ね合いという新たな難題と絡み合いつつも)。
僕のした質問は、その話の流れと、主催者・司会者を含めてイタリア人が多いことをふまえてのものだった。つまり、これまで非常に困難だった廃止への道筋が、本当に今度こそ端緒を開けるのだろうか──ちなみにイタリアでは相当昔に廃止されているから、ここに今日来ている人でも、その時の状況を詳しく語れる人はいないかも知れないけれど、イタリア人から見て「日本にはまだ死刑を廃止する条件がない」と思えることはあるのだろうか。仮にあるとしたら、それは政治的な条件なのか、宗教的な条件なのか、その他なのか・・・・別にイタリア人に質問というわけでなく、誰が答えてくださってもかまわないのだけど・・・・という、やや冗長な質問。
これについて、直接「それでは僕が」と答えてくれたのは民主党の山花郁夫氏だ。ありがたかったけれど、正直に言えば、それは僕がすでに知っている話だった。つまり、イタリアではかなり昔の話になってしまうので難しいけれど、同じヨーロッパでも比較的遅めに廃止した国、フランスの例が日本には参考になるのではないか──ということで、ミッテラン政権が多数派世論を押し切って廃止にこぎつけた話などを、わかりやすく解説してくれたのである。
その流れの中で、日本でも世論は大多数が死刑存置ということになっているが、アンケートの誘導の仕方に問題があるのであって、本当に積極的に存置という人はそう多くはない、「終身刑」という選択肢があればおさらだ──山花氏は、だから日本でも死刑廃止は「結局は政治の側の意識の問題」と、はっきり言ってのけた。それに続けて(だったと思う)亀井氏も、実は自民党の議員の間ですら、「終身刑導入なら死刑存置にはこだわらない」のが昔から多数なんだよ──票を落とすのが怖いから口には出さないけどね、というような話をかぶせてきた(ただし、法務官僚の意識はまったく別物)。
僕はもちろん、そうした話を聞いてホッとするところもあるのだけれど、同時に「そう甘くはないはずだ・・・」という、悲観的な見方から抜け出せないところもある。前回のエントリーで書いた「遺族感情」にまつわる見解が、当然その主要な根拠である。だから僕は、時間があればもう一度質問したいと思っていた──あるいは、こちらを先に聞くべきだったのかも知れない。欧州などでは被害者遺族への社会補償はどうなっているのか?あるいは死刑の廃止と引き換えに、遺族への対応をより手厚くする何らかの施策を導入したということはないのか?ということを(それこそ自分で勝手に調べろという話もあるが)。
対して、僕の質問に直接答える形ではないのだけれど、結果として僕には「ああ!」と腑に落ちたり、あるいは「へえ・・・」と考えさせられる話を、他のパネリストの口から聞くことができたのは収穫だった。
たとえば森達也氏は日本人の「帰属意識」について触れた。人間誰しも、どこの国の人でも、帰属意識はある。特定の集団、特定の共同体に属していることの安心感を求める心理はある。ただはっきり言えることは、外国に比べ、日本人はそれがやや強いということ。大きなものに守られたいという意識が強い。それは、大きな恐怖の裏返しではないのか。守られなければ不安だという恐怖の強さの。
これはまさに僕が(死刑の問題以前に)数年来考え続けていることでもあるので、大いに腑に落ちた。僕らの最大の敵は、ずばり言って恐怖だろう。だからこそ、それがどこからやってくるのか、出所と正体を暴き続けることが、切実に必要とされるのだ。
一方、あまり考えたことのなかった視点が二つほど出てきた。
一つは、上智大学の元学長であるヨゼフ・ピッタウ大司教が、「新しいヨーロッパ」という概念を説明していた中にあった。二度の悲惨な大戦をピークとする戦争の歴史の後で、ヨーロッパ人の意識は変わった、もういい加減こんな争いはやめよう、もうお互いを許そうと。つまり、戦勝国・敗戦国の区別なしに、どちらの側でも「もうたくさん」という気持ちがヨーロッパ中を押し包んだ。それが現在にいたる「新しいヨーロッパ」の下地になり、死刑のような残虐な刑罰を禁止するコンセンサスもそうした下地があってこそだ、というのである(ご高齢ゆえか、日本語がかなりたどたどしかったので、僕の聞き違い・記憶違いも含まれているかも知れないが)。
戦争の惨禍を受けたということなら、日本だって同じだ。というか、ヨーロッパを上回る破壊を被っている。では日本ではなぜ、ヨーロッパのような道筋を辿らなかったのだろう?
そんなもの、戦争/復興という文脈以前に、日本と欧州じゃ細々とした条件が元々いろいろ違いすぎて、簡単に比較できるわけないだろうが、という考えもあるだろう。でも僕は、それは頭の片隅で同意しつつも、ピッタウ司教の言ったことにも、何か引っかかるものがある。それはたとえば、比較的近い時代まで、軍事政権のくびきの下にあって、日本並みの「民主化」には遅れていた韓国、台湾などが、死刑のモラトリアムではあっさり日本をリードしてしまう現実とも、どこか相通ずる話のような気がするのだが・・・・まだいろいろ勉強しなければいけないことが多い。
もう一つは、それとつながるところもある話なのだが、パネリストの一人、冤罪死刑囚だった免田栄氏の獄中体験が語られる中で、日本の警察・司法と天皇制の結びつきがしつこく言及されるのに絡んで、である。
正直僕はその話に乗り気でなかった。そうした問題があるのはわかるけれど、それと死刑廃止の問題とは別だろうと思っていたからである。しかし、司会のピオさんがそれを補足する形で紹介した、彼の友人の島田雅彦の言葉を聞いて、「あっ」と思った。──日本では死刑は廃止されないだろう、なぜならもしも天皇が暗殺された時、犯人を死刑にできないと困る人達がいるから・・・・。
確かに、荒唐無稽な考えかも知れない。いかにも島田雅彦らしい、ひねくれたユーモアだとも言えるかも知れない。だが、僕は笑えない。笑えない現実が、日本という国の背骨に巣食っている。天皇制が廃止されない限り、死刑廃止もない──これはもしかしたら、かなりな程度真実を含んでいるかも知れない。であるなら、この国では「廃止」にこだわるだけでなく、制度は残したままでの「一時停止」「停止」も、十分評価されるべきかも知れない。人命がかかっている以上、「実質」を得ることを優先しても、決して妥協といわれるべき筋合いのものではない、と。
いずれにしろ、このあたりのことは自分としてまだ消化しきれず、突っ込んだことをこれ以上書くことができない。
ピオさんが最後の方に言った言葉も記しておきたい。「死刑を廃止するのに、(本当は)たいそうな理由なんか要りません。それはただやめるべきこと、です。死刑を廃止するか否か、それは政治の問題でも、宗教の問題でもありません。ただ、文明の問題です」。これについてはいろいろ反論したい人がいるだろう。実は僕もその一人だ。だが、すぐに答えを出しておしまいにできるような事柄ではない。これからじっくり自分の問題として考えていきたい。
最後にアンジェロさんをはじめ、会の設営に尽力したLo Studioloの皆さんに、お疲れ様。来年はピオさんの宣言の通り、イタリア文化会館でやれるといいな。
なにぶんにも多彩なメンツであったので、死刑制度をめぐる問題点の言及も多岐に渡った。それは予想していたことでもあり、同時に話の多くは僕が書籍やWebサイトなどで読んであらかじめ知っていた情報であることが多かった。もちろん会場には死刑について学び始めたばかりという人だってたくさんいただろうから、そうした話が無駄であるはずもない。ただ、僕の聞きたかったことは他にあったのも事実である。
最初に司会者から指名を受けて発言を求められたパネリストは亀井静香だった。それで、会の滑り出しとしては「終身刑導入と引き換えの死刑廃止」という道筋、つまりはどちらかと言えば政治的な解決の道筋が、ここ日本でも端緒を開きつつあるという情勢の確認から始まったわけである(裁判員制度との兼ね合いという新たな難題と絡み合いつつも)。
僕のした質問は、その話の流れと、主催者・司会者を含めてイタリア人が多いことをふまえてのものだった。つまり、これまで非常に困難だった廃止への道筋が、本当に今度こそ端緒を開けるのだろうか──ちなみにイタリアでは相当昔に廃止されているから、ここに今日来ている人でも、その時の状況を詳しく語れる人はいないかも知れないけれど、イタリア人から見て「日本にはまだ死刑を廃止する条件がない」と思えることはあるのだろうか。仮にあるとしたら、それは政治的な条件なのか、宗教的な条件なのか、その他なのか・・・・別にイタリア人に質問というわけでなく、誰が答えてくださってもかまわないのだけど・・・・という、やや冗長な質問。
これについて、直接「それでは僕が」と答えてくれたのは民主党の山花郁夫氏だ。ありがたかったけれど、正直に言えば、それは僕がすでに知っている話だった。つまり、イタリアではかなり昔の話になってしまうので難しいけれど、同じヨーロッパでも比較的遅めに廃止した国、フランスの例が日本には参考になるのではないか──ということで、ミッテラン政権が多数派世論を押し切って廃止にこぎつけた話などを、わかりやすく解説してくれたのである。
その流れの中で、日本でも世論は大多数が死刑存置ということになっているが、アンケートの誘導の仕方に問題があるのであって、本当に積極的に存置という人はそう多くはない、「終身刑」という選択肢があればおさらだ──山花氏は、だから日本でも死刑廃止は「結局は政治の側の意識の問題」と、はっきり言ってのけた。それに続けて(だったと思う)亀井氏も、実は自民党の議員の間ですら、「終身刑導入なら死刑存置にはこだわらない」のが昔から多数なんだよ──票を落とすのが怖いから口には出さないけどね、というような話をかぶせてきた(ただし、法務官僚の意識はまったく別物)。
僕はもちろん、そうした話を聞いてホッとするところもあるのだけれど、同時に「そう甘くはないはずだ・・・」という、悲観的な見方から抜け出せないところもある。前回のエントリーで書いた「遺族感情」にまつわる見解が、当然その主要な根拠である。だから僕は、時間があればもう一度質問したいと思っていた──あるいは、こちらを先に聞くべきだったのかも知れない。欧州などでは被害者遺族への社会補償はどうなっているのか?あるいは死刑の廃止と引き換えに、遺族への対応をより手厚くする何らかの施策を導入したということはないのか?ということを(それこそ自分で勝手に調べろという話もあるが)。
対して、僕の質問に直接答える形ではないのだけれど、結果として僕には「ああ!」と腑に落ちたり、あるいは「へえ・・・」と考えさせられる話を、他のパネリストの口から聞くことができたのは収穫だった。
たとえば森達也氏は日本人の「帰属意識」について触れた。人間誰しも、どこの国の人でも、帰属意識はある。特定の集団、特定の共同体に属していることの安心感を求める心理はある。ただはっきり言えることは、外国に比べ、日本人はそれがやや強いということ。大きなものに守られたいという意識が強い。それは、大きな恐怖の裏返しではないのか。守られなければ不安だという恐怖の強さの。
これはまさに僕が(死刑の問題以前に)数年来考え続けていることでもあるので、大いに腑に落ちた。僕らの最大の敵は、ずばり言って恐怖だろう。だからこそ、それがどこからやってくるのか、出所と正体を暴き続けることが、切実に必要とされるのだ。
一方、あまり考えたことのなかった視点が二つほど出てきた。
一つは、上智大学の元学長であるヨゼフ・ピッタウ大司教が、「新しいヨーロッパ」という概念を説明していた中にあった。二度の悲惨な大戦をピークとする戦争の歴史の後で、ヨーロッパ人の意識は変わった、もういい加減こんな争いはやめよう、もうお互いを許そうと。つまり、戦勝国・敗戦国の区別なしに、どちらの側でも「もうたくさん」という気持ちがヨーロッパ中を押し包んだ。それが現在にいたる「新しいヨーロッパ」の下地になり、死刑のような残虐な刑罰を禁止するコンセンサスもそうした下地があってこそだ、というのである(ご高齢ゆえか、日本語がかなりたどたどしかったので、僕の聞き違い・記憶違いも含まれているかも知れないが)。
戦争の惨禍を受けたということなら、日本だって同じだ。というか、ヨーロッパを上回る破壊を被っている。では日本ではなぜ、ヨーロッパのような道筋を辿らなかったのだろう?
そんなもの、戦争/復興という文脈以前に、日本と欧州じゃ細々とした条件が元々いろいろ違いすぎて、簡単に比較できるわけないだろうが、という考えもあるだろう。でも僕は、それは頭の片隅で同意しつつも、ピッタウ司教の言ったことにも、何か引っかかるものがある。それはたとえば、比較的近い時代まで、軍事政権のくびきの下にあって、日本並みの「民主化」には遅れていた韓国、台湾などが、死刑のモラトリアムではあっさり日本をリードしてしまう現実とも、どこか相通ずる話のような気がするのだが・・・・まだいろいろ勉強しなければいけないことが多い。
もう一つは、それとつながるところもある話なのだが、パネリストの一人、冤罪死刑囚だった免田栄氏の獄中体験が語られる中で、日本の警察・司法と天皇制の結びつきがしつこく言及されるのに絡んで、である。
正直僕はその話に乗り気でなかった。そうした問題があるのはわかるけれど、それと死刑廃止の問題とは別だろうと思っていたからである。しかし、司会のピオさんがそれを補足する形で紹介した、彼の友人の島田雅彦の言葉を聞いて、「あっ」と思った。──日本では死刑は廃止されないだろう、なぜならもしも天皇が暗殺された時、犯人を死刑にできないと困る人達がいるから・・・・。
確かに、荒唐無稽な考えかも知れない。いかにも島田雅彦らしい、ひねくれたユーモアだとも言えるかも知れない。だが、僕は笑えない。笑えない現実が、日本という国の背骨に巣食っている。天皇制が廃止されない限り、死刑廃止もない──これはもしかしたら、かなりな程度真実を含んでいるかも知れない。であるなら、この国では「廃止」にこだわるだけでなく、制度は残したままでの「一時停止」「停止」も、十分評価されるべきかも知れない。人命がかかっている以上、「実質」を得ることを優先しても、決して妥協といわれるべき筋合いのものではない、と。
いずれにしろ、このあたりのことは自分としてまだ消化しきれず、突っ込んだことをこれ以上書くことができない。
ピオさんが最後の方に言った言葉も記しておきたい。「死刑を廃止するのに、(本当は)たいそうな理由なんか要りません。それはただやめるべきこと、です。死刑を廃止するか否か、それは政治の問題でも、宗教の問題でもありません。ただ、文明の問題です」。これについてはいろいろ反論したい人がいるだろう。実は僕もその一人だ。だが、すぐに答えを出しておしまいにできるような事柄ではない。これからじっくり自分の問題として考えていきたい。
最後にアンジェロさんをはじめ、会の設営に尽力したLo Studioloの皆さんに、お疲れ様。来年はピオさんの宣言の通り、イタリア文化会館でやれるといいな。


















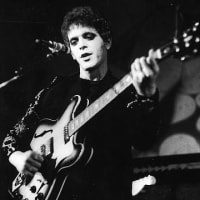

ヨーロッパと日本の文化の違いは大きいのでしょうね。作家の村上龍が
「日本は長い間鎖国をしており、リアルに海外に接していない。大戦でも空爆や原爆で多大な被害をこうむったが、他国の兵士が家族や友人を直接殺すところやレイプするところを見ていない(沖縄をのぞく)だから日本は海外に対して排他的」
と小説で語らせておりました。
一理あるな、と思いました。海外で起きた出来事もどこか「対岸の火事」な雰囲気だし。島国、という地形も大きいのでしょうか?
御紹介の「死刑制度についての討論会」ですが、パネリストの面々を拝見する限り存置派の人は含まれていないようですね。当然と言えば当然なのでしょうが。会場の参加者もやはり廃止派の方がほとんどだったのでしょうか。
存置派との「不毛」(?)な議論を避けようとの配慮だったのかも知れませんが、できれば支持する側の参加者もいた方がなお良かったと思います。
>端的に言えば、終身刑の導入をめぐる法案が、「犯罪被害者救済(新)法」とセットであったら、どんなにかよいだろう・・・ということなのだけど。
>ただどうしても、廃止派の人達が遺族感情と距離を置きたがる、距離があいていなければ廃止論が成り立たないかのようにビクビクしている、・・・・
犯罪被害者の救済に関わると、「廃止するためのパフォーマンス、アリバイ作り」と思われるのではないか、と危惧するからではないでしょうか。
本来この問題は存置派、廃止派を問わず取り組むべきものだと思うのですが、現実は残念ながらそうはなっていません。
例えば代表的な廃止団体であるアムネスティにしても「犯罪被害者の救済は別個の問題。廃止と併置するのは妥当ではない」として一切関知しようとはしていません(但し、廃止の立場に立つ遺族とは協調的な関係にあるようです)。このあたりの姿勢が廃止論から一般市民を逆に遠ざける結果になっているように思います。
島田氏の天皇制云々ですが、わざわざそのような論を持ち出す意図がわかりません。本来かなりデリケートな死刑問題に、それに輪をかけてデリケートな問題を結びつけるのは廃止を実現する上で障害になるだけだと思います。
天皇や皇族に親しみを感じる人々の中にも廃止派がいるのですから。(存置派の人間がこんなことを言うのは大きなお世話かも知れませんね(笑)
>天皇が暗殺された時、犯人を死刑にできないと困る人達がいるから
考えてみたこともありませんでしたが、ある種の「真実」を衝いていると思います。そしておそらくこれは日本人の「帰属意識」とも絡んでいるのでしょう。そんな気がします。
>大きなものに守られたいという意識が強い。それは、大きな恐怖の裏返しではないのか
大きなものに守られたいが、その「大きなもの」への信頼感が希薄になった。それが現代の日本の姿ではないでしょうか。信頼感が希薄になるから恐怖を抱く。それが国家組織や軽薄なスピリッチュアルまがいのものへの依存症になって現れているように感じます。死刑制度の存続を望む者に国家依存症が多いのは、その所為ではないのか思っています。人間の生殺与奪の権限を国家に与えることで、国家を「大きなもの」だと思い込みたがっている、と。
レンランダーさんのおっしゃる事はよく分かります。「死刑制度廃止(停止)」の正当性を訴えられたとしても、遺族の気持ちは割り切れるものではないでしょう。そこを考えてなければ「死刑廃止」はどんなに正しくても未熟なままではないでしょうか?
フランスの新聞に「日本は遺族に対する救済措置がなっていない。だからせめて「死刑」にして加害者に復讐したいのではないか」と、日本がいつまでも「死刑廃止」しない理由として考察していました。
だとすると、「国」の怠慢ではないでしょうか?(年金にしろ薬害にしろ日本の政治は怠慢と傲慢が多すぎるのでは?)
愚樵様:
>死刑制度の存続を望む者に国家依存症が多い
私もその中の1人ということになりますが(苦笑)、具体的にはどのような「症状」なのでしょう?「個人の価値観を無批判に(無邪気に)国家の価値観と同一視する」というような意味なのですか。自分自身のことは案外わからないものですから、御教示賜れば幸甚です。
遅れちゃったので、前のコメントと併せてレスさせていただきます。ご容赦を。
今回の討論会のレポートが、何がしかのお役に立てれば幸いです。ただ、僕のレポートは僕の狭い関心の幅に沿った「拾い食い」のものに過ぎませんから、かなり抜けてる話もあります。主催者のページで紹介されてますが、JANJANの記者がまとめたレポートは網羅的で、当日の話の流れをうまくつかんでいるのでお勧めです。
http://www.news.janjan.jp/government/0803/0803052056/1.php
犯罪被害者遺族に対する救済措置については、これからぼちぼち自分で調べていこうと思ってますが、何か有用な資料などがありましたら、教えていただけると嬉しいです。なんとなく欧州の場合、死刑廃止に伴ってというより、もともと補償が充実してた(日本に比べて)んじゃないかという気がするんですが。その意味で確かに、
>(年金にしろ薬害にしろ日本の政治は怠慢と傲慢が多すぎるのでは?)
すべて一緒くたに言うわけにはいかないかも知れませんが、共通したものはありそうですね。「終身刑などとんでもない!我々の税金で犯罪者を一生養えっていうのか!」なんていう、社会性の乏しい国民が多いことが、そうした怠慢をしっかり支えているとも。
>愚樵さん
僕も「ある種の真実」を衝いてる、あくまで「ある種」だけど、と思います。島田雅彦は、右翼の脅迫で皇室がらみの小説の出版をお蔵入りにした経験もある作家です。だからといって、こうした「右からの力」について知り尽くしている、とまでは言えないにしても。
端的には「天皇が暗殺された時、犯人を死刑にできないと困る人達」というのは、財界や保守政治家の一部、法務官僚、警察・司法のトップクラス、なんかだろうと思うんです。でもなぜ困るのかと言えば、それは彼らの思いがどうこうより前に、彼らの手なづけた国民が、死刑にしないことを彼らに許さないからでしょう。
ありていに言ってしまえば、「守られたい」というのはこの場合、「騙されたい」と同義かも。天皇制という依存性薬物が切れて、日本流「国家」の夢から覚めるのを拒絶したい。人間としての芯の部分を、そこにあずけておきたい人は(自覚的にしろ、無自覚にしろ)、やはり結構な割合でいるでしょうから。
網野善彦という歴史家が、いずれ将来、日本人は天皇制を必要としなくなる日が来る、その時には「日本」という国号も考え直さなければならなくなる、と言ってからだいぶ経つんですが、──まさかその日まで死刑廃止もおあずけ、というのは勘弁してもらいたいもんです。
>DHさん
僕が答える筋合いではないのは承知で、一応僕の診たても書いておきます。
国家依存症かどうかは知りませんが(知りたくもないですが)、自意識肥大症だとは思いますよ。
>自意識肥大症だとは思いますよ。
うーん、キツイですね。愚樵さんのことは以前から存じ上げているので、お尋ねしただけなのですが。
国家依存症についてですね。では、少しだけ。
人間はひとりでは人間でいられません。人間が人間であるためには、その人を受容してくれる共同体が必要です。人間は、その共同体への無意識下での「帰属意識」があって初めて、情緒的に安定した人間でいられる。ところが現在の日本では、帰属すべき共同体が解体されつつある。でも、人間はどこかに帰属したい。その方向性が国家へ向かうのを「国家依存症」と言ったのです。
レイランダーさんは自意識肥大と仰いましたが、人間は帰属意識が希薄になると自意識過剰になるんでしょうね。現代人はみな自意識過剰で、その過剰を解消するところを探している。「自分探し」なんてのもそのひとつでしょう。「人権信仰」も過剰な自意識解消の一方法でしょう。
死刑廃止論者さんよ。金川君を守る記事書けよ。殺された人たちは愚か者だと書けよ。絶対書けよ。金川の人権擁護しろよ。被害者の人権は無視しろよ。死刑廃止論者さんよ。