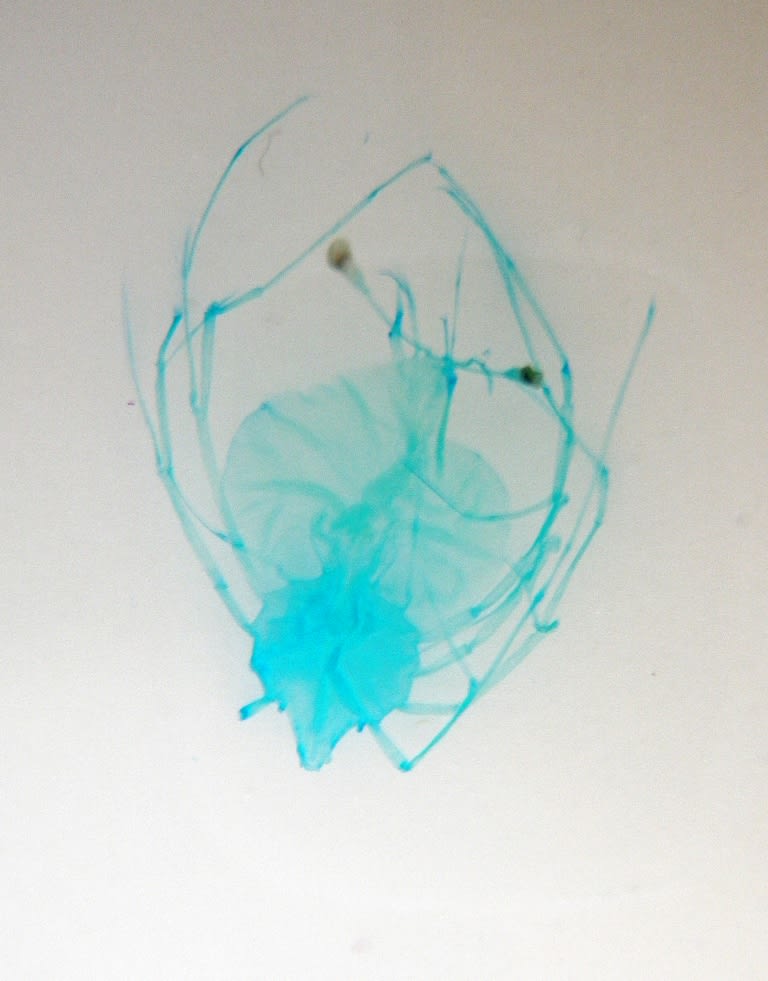
イセエビ類のフィロソーマ幼生(フィロゾーマ幼生; phyllosoma; phyllo:葉状+soma:体)。
節足動物門 Arthropoda
甲殻亜門 Crustacea
軟甲綱 Malacostraca
真軟甲亜綱 Eumalacostraca
ホンエビ上目 Eucarida
十脚目(エビ目) Decapoda
抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata
イセエビ下目 Palinuridea
シラスから採取したもの。所謂、"チリモン"。
そのまんまじゃつまんねぇかなぁとアルシアンブルーで染色し、透明化してみたが、
…特にどうにもならんねぇ。
プランクトンネットなどでもよく引っ掛かります。
19世紀初頭からすでにプランクトンの一種として、数多くのフィロソーマの記載が見られるが、
その親と似ても似つかない形態から、他の多くの動物の幼生と同じく、
フィロソーマたちも当初はこれが成体であり、
未だ知られざる新種なのだと思われていた。
これらがイセエビ類の幼生であることが判明したのは、
水生生物を室内で繁殖させる手法が確立されてきた、20世紀に入ってから。
イセエビはご存知の通り、岩礁などに生息している動物だが、
卵から孵化したフィロソーマ幼生は、種によって様々だが、約1年もの間浮遊生活を送る。
この間脱皮を繰り返して成長するが、
ある時脱皮すると、突然プエルルス幼生(puerulus; puer:子供+ ulus:小さい)と呼ばれる、
よりエビっぽい形態をとり、
岩礁に向けて猛烈な勢いで泳ぎ始める。
このプエルルス、実は顎などの摂食・消化に係る器官が著しく退化しており、
何も食わず、ほとんど体内に蓄えた脂肪だけで生きるという。
岩礁にたどり着くと、稚エビに変態し、見慣れたエビの姿になる。
いくつかの甲殻類のグループについて発生のプロセスをザクッと纏めると、
イセエビ: 「卵→ノープリウス→フィロソーマ→プエルルス→稚エビ」
カニ: 「卵→ノープリウス→ゾエア→メガロパ→稚ガニ」
クルマエビ:「卵→ノープリウス→ゾエア→ミシス→稚エビ」
フジツボ: 「卵→ノープリウス→キプリス→稚フジツボ」
ザリガニ: 「卵→稚エビ」
みたいな感じになる。
クルマエビさんとイセエビさんは、エビとは申せど、下のように異なる亜目に属す。
Dendrobranchiata 根鰓亜目{クルマエビ亜目; 羽毛状の根鰓(Dendrobranch)を持つ}
クルマエビ下目(Penaeidea)
サクラエビ下目(Sergestoidea)
Pleocyemata 抱卵亜目{エビ亜目;葉鰓(Phyllobranch)/毛鰓(Trichobranch)を持ち、♀は腹部で抱卵する傾向}
オトヒメエビ下目(Stenopodidea)
コエビ下目(Cardiea)
短尾下目(カニ下目; Brachyura)
異尾下目(ヤドカリ下目; Anomura)
イセエビ下目(Palinuridea)
ザリガニ下目(Astacidea)
アナジャコ下目(Thalassinidea)
詳しくは記事:ハルマンスナモグリで。
フィロソーマちゃんが泳ぐ動画はコチラ↓
イセエビの赤ちゃんフィロソーマ
可愛いでしょ♥


BLOG外LINKS:
・セミエビまたはヒメセミエビ(たぶん)のフィロゾーマの色々 by.『見て、見て、チリメンモンスター(チリモン)』
<weblog内-関連記事LINKS:>
・specimens: うちの収蔵標本。
・Tetraclita japonica: クロフジツボ。同じ甲殻類の誼。
・Nihonotrypea harmandi: ハルマンスナモグリ。同じ甲殻類の誼。
・Ovalipes punctatus: ヒラツメガニ。同じ甲殻類の誼。
節足動物門 Arthropoda
甲殻亜門 Crustacea
軟甲綱 Malacostraca
真軟甲亜綱 Eumalacostraca
ホンエビ上目 Eucarida
十脚目(エビ目) Decapoda
抱卵亜目(エビ亜目) Pleocyemata
イセエビ下目 Palinuridea
シラスから採取したもの。所謂、"チリモン"。
そのまんまじゃつまんねぇかなぁとアルシアンブルーで染色し、透明化してみたが、
…特にどうにもならんねぇ。
プランクトンネットなどでもよく引っ掛かります。
19世紀初頭からすでにプランクトンの一種として、数多くのフィロソーマの記載が見られるが、
その親と似ても似つかない形態から、他の多くの動物の幼生と同じく、
フィロソーマたちも当初はこれが成体であり、
未だ知られざる新種なのだと思われていた。
これらがイセエビ類の幼生であることが判明したのは、
水生生物を室内で繁殖させる手法が確立されてきた、20世紀に入ってから。
イセエビはご存知の通り、岩礁などに生息している動物だが、
卵から孵化したフィロソーマ幼生は、種によって様々だが、約1年もの間浮遊生活を送る。
この間脱皮を繰り返して成長するが、
ある時脱皮すると、突然プエルルス幼生(puerulus; puer:子供+ ulus:小さい)と呼ばれる、
よりエビっぽい形態をとり、
岩礁に向けて猛烈な勢いで泳ぎ始める。
このプエルルス、実は顎などの摂食・消化に係る器官が著しく退化しており、
何も食わず、ほとんど体内に蓄えた脂肪だけで生きるという。
岩礁にたどり着くと、稚エビに変態し、見慣れたエビの姿になる。
いくつかの甲殻類のグループについて発生のプロセスをザクッと纏めると、
イセエビ: 「卵→ノープリウス→フィロソーマ→プエルルス→稚エビ」
カニ: 「卵→ノープリウス→ゾエア→メガロパ→稚ガニ」
クルマエビ:「卵→ノープリウス→ゾエア→ミシス→稚エビ」
フジツボ: 「卵→ノープリウス→キプリス→稚フジツボ」
ザリガニ: 「卵→稚エビ」
みたいな感じになる。
クルマエビさんとイセエビさんは、エビとは申せど、下のように異なる亜目に属す。
Dendrobranchiata 根鰓亜目{クルマエビ亜目; 羽毛状の根鰓(Dendrobranch)を持つ}
クルマエビ下目(Penaeidea)
サクラエビ下目(Sergestoidea)
Pleocyemata 抱卵亜目{エビ亜目;葉鰓(Phyllobranch)/毛鰓(Trichobranch)を持ち、♀は腹部で抱卵する傾向}
オトヒメエビ下目(Stenopodidea)
コエビ下目(Cardiea)
短尾下目(カニ下目; Brachyura)
異尾下目(ヤドカリ下目; Anomura)
イセエビ下目(Palinuridea)
ザリガニ下目(Astacidea)
アナジャコ下目(Thalassinidea)
詳しくは記事:ハルマンスナモグリで。
フィロソーマちゃんが泳ぐ動画はコチラ↓
イセエビの赤ちゃんフィロソーマ
可愛いでしょ♥
BLOG外LINKS:
・セミエビまたはヒメセミエビ(たぶん)のフィロゾーマの色々 by.『見て、見て、チリメンモンスター(チリモン)』
<weblog内-関連記事LINKS:>
・specimens: うちの収蔵標本。
・Tetraclita japonica: クロフジツボ。同じ甲殻類の誼。
・Nihonotrypea harmandi: ハルマンスナモグリ。同じ甲殻類の誼。
・Ovalipes punctatus: ヒラツメガニ。同じ甲殻類の誼。



















