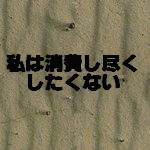
最近少々疲れ気味で乗り物の中では居眠りしていることが多いのだが、今日は久しぶりに電車の中で本を1冊読んだ。駅前の書店で買った、佐高信『城山三郎の昭和』(角川文庫)。「本の旅人」に掲載されて3年ほど前に単行本として発刊されたもので、先頃……おそらく城山三郎死去に伴って文庫になったものである。とっくに読まれた方も多いと思うが、私はまとめて読んだのは今回が初めてである。
作家論ではないし作品論でもないし、強いて言えば人物論か。城山を熱く評価している佐高信が彼の文章の原点について自分の思うところを語ったもので、雰囲気としては随想に近い。興味を抱かれたら一読をお勧めするが、さっと読める文章なので立ち読みでも充分読み通せると思う。
私自身は、城山三郎の小説は一部の代表作?しか読んでいない。これは別に他意あってのことではない。城山は綿密に取材し、膨大な資料を集め分析して書くというタイプの作家で、彼の小説の多くはいわゆる伝記小説である。たとえば東京裁判におけるA級戦犯の中で唯一の文官であり、「軍人のほかに文官の死も要求されているのなら、私はそれを受け入れる。あの戦争を止められなかったという点だけにおいても私は有罪である」という意味のこと(字句として正確かどうかはわからない。いつもの通りうろ覚えのまま書いているのだが、ニュアンスとしては間違っていないはず)を言って絞首刑に処せられた広田弘毅を主人公にした『落日燃ゆ』はその代表だろう。つまりはフィクションというよりジャーナリズムの仕事に近く、その世界の片隅で飯食ってる私にはちょっと食傷ぎみだった……というに過ぎない。私は元来が、どちらかといえば「荒唐無稽な幻想の世界」が好きなのだ……。
もうひとつ。たしか『落日燃ゆ』だったと思うが、天皇に「……と言われた」といった類の(軽い)敬語が使われていた。それが微かな違和感につながったのかも知れない。読んだのはもう随分前のことだから、確信をもって言えるわけではないけれども。むろん城山三郎には彼なりの判断があってのことだと思うが、私はノンフィクションおよびそれに近い文章で特定の登場人物に敬語を使うのは嫌いなので、何となく読みづらい感じがしたのだろう。(完璧なフィクションの世界で、一種の雰囲気作りとして敬語を使うのは話が別。たとえば『源氏物語』であれば、光君が○○とおおせられた、みたいな表現があっても「ア、ソウ」ですむのだが……)
前置きが長くなった。それはそれとして――。私が同著のなかでもっとも心揺さぶられたのは、城山三郎の『旗』という詩を全文まともに読んだことだろう。城山は昭和2年に生まれて軍国主義教育を受け、敗戦の直前に未成年で海軍に志願した。そのことを終生の痛みとして抱え、「こんなことを二度と繰り返してはいけない」「人が、人の上に立ってはいけない」「思想信条の自由は守られねばならない」と死ぬまで叫び続けた彼の、原理原則を訴えた詩である。冒頭部分は非常に有名で、よくさまざまな文章に引用されるのでさすがに知っていたけれども、詩の全文を通してちゃんと読んだのは初めてだった。
熱に浮かされたように旗を振り、その下に集うことを、城山三郎は嫌悪し続けた。カリスマも英雄も大嫌いで、数にもならぬ身としてしたたかに生きたいとだけ願い、最後のひとりになっても国のためになど死にたくないと思っている私は、少なくともその点には涙ぐむほどに共感できる。
全部紹介したいところだが、それだと改めて「城山三郎とは何者か」「言論の自由とは何か」などを考えるさいの手掛かりになりにくいだろう。第一、長いから全部書き写すのはしんどい。……というわけで、この詩の冒頭だけを紹介しておく。少しでも関心を持たれたら、ぜひ立ち読みしてくだされ。あ、むろん買って行かれてもいいですよ。
――城山三郎『旗』より――
旗振るな/旗振らすな/旗伏せよ/旗たため
社旗も 校旗も/国々の旗も/国策なる旗も/運動という名の旗も
ひとみなひとり/ひとりには/ひとつの命





















衝撃的だった。
以前同様の衝撃は金子みすずの「大漁」を読んだとき以来だ。
国家権力への壮絶な闘いの詩だ。
皆が読むといい。
旗の馬鹿馬鹿しさを読んで欲しい。
人は人を殺すといふ、馬鹿馬鹿しさを読んで欲しい。
祖父の無罪を晴らそうといふ、とんでもない首相が辞めてもまだまだ国家権力の本質は変わっていない。