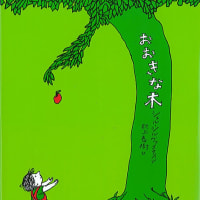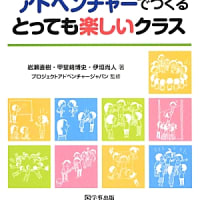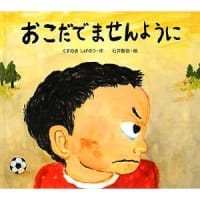本当は振り替え休日だっただけれど、出勤。金曜日、休みをもらうから。
本当は振り替え休日だっただけれど、出勤。金曜日、休みをもらうから。
教室行くなり、子供たちと会うなり、いろいろと報告が来る。
やっぱり2日教室を開けると、開けた分、何かはあるのは当たり前だ。しかも、まだクラスがスタートして、50日ちょっと。
クラスは、3日で崩れるって、ボクの師匠の先生から若いころ、よく聞いていたけれど、今も実感する話だ。
ただ、報告された(笑)内容は、クラスの課題的なものはゼロ。委員会のことやら、忘れ物の話。
休んだ分の振り返りジャーナルを見ても、すごくよい2日間だったよう…。
ある男の子は、こう書いてあった。「『自分たちの教室は自分たちでつくる』ということが少しずつでき始めたことを実感した。やっぱり大野先生にまだまだ引っ張ってもらってるんだなぁと思った。でも、こういうチャンスを使って、成長していきたい。」
なかなか立派なことを書いていらっしゃる。
明日も教室を開けることになる。そういうチャンスをぜひ使ってほしいなぁと思う。
夜、仕事をしながら、テレ朝の「テレビ朝日「トリハダ[秘]スクープ映像100科ジテン」という番組を見た。
日体大女子の集団行動(実演会)を取り上げていた。以前も取り上げていたようだが、ボクは初めて見た。
集団行動には、いろいろな思い、見方をする人がいる。
でも、その取り組みの価値のインストラクションをどうするかが大切だと思う。
どんな価値をどう伝えて、その価値をどう実感させるかが大事であって、あらためて言うことじゃないかもしれないけれど、集団行動自体が問題なんじゃないなぁと思う。
凄腕…とキャプションが入っていた監督さんは、特に「お~、なるほど、こういう指導をすればよいのか!」ということを感じる技術屋ではなかったように思う。
どちらからと言えば、根性論、精神論(テレビが映し出されたところだけで判断しているので、それ以外のところでは、それなりに指導のポイントはあるのだろうけど)で指導していた感がある。しかも、まちがいなく今の若者には通用するのが難しいものだ。
でも、それでも女子大生はついてくる。なぜか。
それは、堀さんがいつも言っているが、「『何を言ったかよよりも、誰が言ったか』だ!」ということとつながっているなと思う。
監督は、71歳。代々の先輩たちが崇拝してきた監督だ。もちろん言っていることは大切なことだし、まねできないような愛情の持ち方も感じ取れた。でも、やっぱり「何を言ったかよよりも、誰が言ったか」というところがおおきいのではないだろうか。
でも、監督が技術というより、そういう存在(指導)だからこそ、自分たちで考えて、自分たちでやっていかなければ、それ以上のものは作れないという状態に気づくのではないかと思う。
彼女たちは、最後、自分たちで自分たちの演技を作り上げていく。その監督もそれがねらいだったという。
うまく表現できなくて、悔しいのだけれど、これは、教室の中でも、言える部分もあるかなと考えたりもする。
何かも上手に教えちゃう先生のクラスの子供たちは、ある程度までは上達するけれど、それ以上のものは難しいのではないか?
だとしたら、先生が考えなければならないそのバランスは難しいなぁと思う。今回の監督さんが意識的にやっていたように、ボクたちは、こうした部分に自覚的にならなければならないと思う。
いや、そうではなく、女子大生では、そういう流れができるけれど、発達段階的に、小学生では、そういう流れを作るのは難しいかもれしれない。だから、基本的には、上手に教えることができなければいけないということという見方もあるだろう。
いろいろ考えさせられた番組だった。