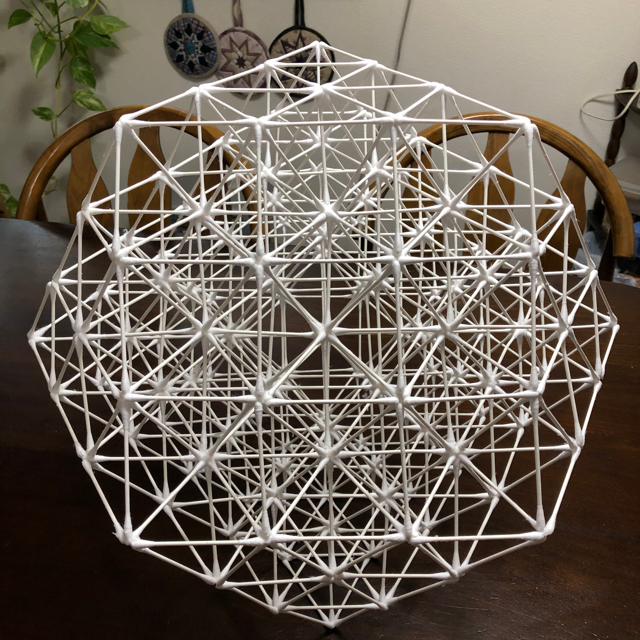目次の「たましい」の発見と言う言葉にひかれて
河合隼雄氏の“「子どもの目」からの発想”を読み返えしている。
忘れもしない小学生のある夏休み。
退屈さのあまりふと手に取った本が
エーリヒ・ケストナーの「エミールと探偵たち」だった。
(家に届いたばかりの岩波世界少年少女文学全集。
読書好きではない私のために密かに両親が用意したものだ。)
退屈さのあまりふと手に取った本が
エーリヒ・ケストナーの「エミールと探偵たち」だった。
(家に届いたばかりの岩波世界少年少女文学全集。
読書好きではない私のために密かに両親が用意したものだ。)
ぎっしり詰まった小さい文字にいささか閉口しながらも
何とか読み進むうちその興味深い面白さにどんどんはまっていった・・・
それから常にいろいろなジャンルの新しい「本」を4・5冊
脇に置いた生活が今に続いているのが何とも言えない。
(決してオタク的読書家ではないけれど。)
脇に置いた生活が今に続いているのが何とも言えない。
(決してオタク的読書家ではないけれど。)
出会った最初の本がケストナーなんて何と言う幸運だろう。
彼から始まった読書生活はやはり児童文学とは切り離せない。
現在まで折にふれて読みそれなりに研究も続けてきた。
その時から「作家読み」も始まり
リンドグレーン、メアリー・ノートン、アーサー・ランサム等々・・・
フィリパ・ピアス、ガニスバーグ等々と続いている。
もちろん「ハリー・ポッター」だって読んでいる。
リンドグレーン、メアリー・ノートン、アーサー・ランサム等々・・・
フィリパ・ピアス、ガニスバーグ等々と続いている。
もちろん「ハリー・ポッター」だって読んでいる。
岩波の全集も小学生の頃にもちろん読破。
訳者も素晴らしく子どもに媚びていない。
今から思っても本当に「質の高い」全集だ。
(現在にも受けつがれているけれど。)
幼い瑞々しい感性に世界への窓口が開かれたことは
大きいと今更ながらに気づく。
(読み応えのあるあらゆるジャンルが結構網羅されていた。
いわゆるその頃の流行ではなかったところがよかった。)
訳者も素晴らしく子どもに媚びていない。
今から思っても本当に「質の高い」全集だ。
(現在にも受けつがれているけれど。)
幼い瑞々しい感性に世界への窓口が開かれたことは
大きいと今更ながらに気づく。
(読み応えのあるあらゆるジャンルが結構網羅されていた。
いわゆるその頃の流行ではなかったところがよかった。)
優れた児童文学(大人の文学には負けずとも劣らない質を持ち
子どもでも読むことができる)には
もう一人の自分が描かれることが多い。
大人の文学やドラマ等ではそれは
ブラックな自分であることが多いが
児童文学では魂の声(ハイヤーセルフ)的要素を持つ。
子どもでも読むことができる)には
もう一人の自分が描かれることが多い。
大人の文学やドラマ等ではそれは
ブラックな自分であることが多いが
児童文学では魂の声(ハイヤーセルフ)的要素を持つ。
またファンタジーと言う形をとることにより
異次元での「真実」が興味深く面白く描かれる。
やさしい言葉や分かりやすい表現で著わされることにより
知らず知らずのうちに感性や「たましい」の奥深くに響く。
それに何よりベクトルが光の方向へ
向かっている文学であるということ。
(形を子どもに向けていることが大きいのだろうけれど。)
この時代において私は「修羅」や「不条理」を描くことが
優れた芸術だとは思わない。
形の多様性はあってしかるべきだが
それのみに終わることはかえって「甘さ」や「甘え」
ではないのかとこの頃感じている。
優れた芸術だとは思わない。
形の多様性はあってしかるべきだが
それのみに終わることはかえって「甘さ」や「甘え」
ではないのかとこの頃感じている。
次の宮崎駿のスタジオ・ジブリ作品が
ノートンの「床下の小人たち」を原作にしているらしい。
あのシリーズも子供の頃ワクワクしながら読んだ。
どんな風に描かれるか楽しみだ。
ノートンの「床下の小人たち」を原作にしているらしい。
あのシリーズも子供の頃ワクワクしながら読んだ。
どんな風に描かれるか楽しみだ。
「たましい」の発見は自分の奥深い「たましい」へ
の問いかけから始まる。
そういった意味で知らず知らずに導かれる
「児童文学の世界」は深遠で輝きに満ちた
何より面白く楽しい世界だ。
この時代、もっと多くの人にその扉を開いて欲しい。




の問いかけから始まる。
そういった意味で知らず知らずに導かれる
「児童文学の世界」は深遠で輝きに満ちた
何より面白く楽しい世界だ。
この時代、もっと多くの人にその扉を開いて欲しい。