
『生誕250年 酒井抱一-琳派の華』 畠山記念館
サイト※前期:2月17日(木)まで、後期:2月19日(土)~3月21日(月・祝)
京都の話題もまだ残ってはいるのだけど、とりあえず(茶道のために)巡ったところの報告は終わったので、
晴れ晴れとした気持ちで東京の美術館めぐりを再開
1月に出光でも鑑賞したけど、気になるのは酒井抱一サン。
今回の展覧会では、前期後期合わせて畠山における抱一コレクションを全て見せてくれるらしい。
併せて、琳派の流れもわかる趣向。
もちろん、光悦や乾山をはじめ琳派の方々の茶道具も鑑賞できる
前も展示解説を聴いて、とても有意義だったので、今回もそうした。(やはり盛況だった)
本阿弥光悦の扇面月兎図は金がとても効果的に使われていてキレイ。
「扇の骨の後がないなー」と思っていたら、実際は扇面にはならなかったようで。
抱一の“とても美人な”お多福の乙御前図。表層(中廻しだったかな?)に花兎の裂地が使われていて、可愛かった。
光琳の小督図はちょっと意外な感じ。(描写の技術は見事なんだけど、色使いがキラキラしてなかったので)
そして、抱一の弟子・鈴木其一の曲水宴図は一人ひとりの心情が丁寧で、それが烏帽子でわかる面白さ。
(解説を聴いて、後から見直した)
そして、抱一の富士見業平図屏風。
もとは光琳の描いた対の掛け軸を写して、自分流の表現を屏風に表したものという。
前日、光琳と抱一は時代的に一世紀近い差があることに気がついたんだけど、→こちら
抱一にとって、光琳は“前の時代の憧れの人”だったみたい。
現代のワタシたちが上村松園や横山大観に傾倒するようなものだったのかしらん。
(ワタシ自身は全く絵は描けないケド )
)
同じように風神雷神図屏風も。
光琳は宗達に憧れ、抱一は光琳に憧れて同じ構図で屏風絵を描いた。(そして其一も)
ただ、抱一の場合は屏風のみならず、対の掛け軸としても構図をアレンジして描いている。
これは後期の展示なので、再訪必至
そして、抱一といえば花鳥図。
四季花木図屏風。一つの屏風の中に桜もあれば朝顔もススキも水仙も描かれてあって、不思議だったけれど、美しかった。
抱一が花々や木を写生した上で描いたのが伺える、とてもリアルなきれいさがわかる。
そして、十二ヶ月花鳥図も。
以前、とびとびで湯木美術館で見た? 短冊だったかな。
他にも三の丸尚蔵館にもあるらしいけど、描かれている花鳥(の種類)が違うんだって。
例えば、6月の花といえば紫陽花が思い浮かぶけど、葵と百合で「え?」って印象。
個人的には1月の構図が「椿、梅、鶯」だったのとか意外。(←梅と鶯は2月か3月かと思ってたので)
2月は「菜の花と雲雀」、3月は「桜と瑠璃鳥」と現代よりも季節が先取りされているような?
旧暦と新暦の違いだろうか。
でも、そういえばこの前、土手に菜の花が咲いているのが視界に入ったような。(←電車 内から見えた)
内から見えた)
季節感に敏感になることは、茶人の素養として必要だな、って思った。
それにしても、大名家の次男坊ということで、上等の絹地に質のいい絵の具を使って描いているから、
200年経ってもきれいだなぁ。
工芸は光悦の赤楽茶碗「李白」が印象に残った。
オレンジのような、ピンクのようなほんのりした明るい赤。
(銘は酒飲みだった李白をイメージして原三渓がつけた)
乾山の器(鉢、向付、香合、黒楽茶碗)、光琳の茶杓、本阿弥光甫の茶杓もよかった。
(工芸は全期を通じての展示なので、後期でもみよう)
今回の展覧会、畠山としては初めてクリアファイルを作った。
2種類あって、1枚250円。
とーーーってもいい。(写真、リアルに撮りすぎちゃったので、ココで紹介するのはパスさせていただきます)
展覧会の前後、茶室というか露地も見学する。


先日の茶室見学のフリーク効果で露地や飛び石がやたら気になる。
現在、茶道文化検定の公式テキストを読み返しながら勉強し直してる。
改めて「おぉっ 」って思うこと多し。
」って思うこと多し。
でも、飛び石のところは文章中心だし、詳しいような、物足りないような、、難しい。
もっと読み深めておかねばなと思う。

にほんブログ村
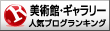 人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ
応援ヨロシク 致しマス
致しマス
※参考 過去の畠山記念館
2010年11月→→『織部が愛した茶碗 高麗・割高台』その2
2010年10月→『織部が愛した茶碗 高麗・割高台』その1
2010年8月→『涼を愉しむ-書画・茶器・懐石道具-』
2010年5月→『茶の湯の美-数寄のかたちと意匠-』
2010年2月→『懐石のうつわ -向付と鉢を中心に-』
2009年10月→『戦国武将と茶の湯 -信長・秀吉ゆかりの品々-』
2009年4月→『畠山記念館名品展 季節の書画と茶道具』
2009年2月→『冬季展 日本の春-華やぎと侘び』
2008年10月→『益田鈍翁 -心づくしの茶人-』
2008年8月→『夏季展 夏のやきもの -金襴手・万暦赤絵・古赤絵・南京赤絵』
2008年4月→『細川井戸と名物茶道具』
2008年3月→『花によせる日本の心 -梅・桜・椿を中心に』
2007.12月→『茶の湯の美 -利休から宗旦へ-』後期
2007.11月→『茶の湯の美 利休から宗旦へ』前期
サイト※前期:2月17日(木)まで、後期:2月19日(土)~3月21日(月・祝)
京都の話題もまだ残ってはいるのだけど、とりあえず(茶道のために)巡ったところの報告は終わったので、
晴れ晴れとした気持ちで東京の美術館めぐりを再開

1月に出光でも鑑賞したけど、気になるのは酒井抱一サン。
今回の展覧会では、前期後期合わせて畠山における抱一コレクションを全て見せてくれるらしい。
併せて、琳派の流れもわかる趣向。
もちろん、光悦や乾山をはじめ琳派の方々の茶道具も鑑賞できる

前も展示解説を聴いて、とても有意義だったので、今回もそうした。(やはり盛況だった)
本阿弥光悦の扇面月兎図は金がとても効果的に使われていてキレイ。
「扇の骨の後がないなー」と思っていたら、実際は扇面にはならなかったようで。
抱一の“とても美人な”お多福の乙御前図。表層(中廻しだったかな?)に花兎の裂地が使われていて、可愛かった。
光琳の小督図はちょっと意外な感じ。(描写の技術は見事なんだけど、色使いがキラキラしてなかったので)
そして、抱一の弟子・鈴木其一の曲水宴図は一人ひとりの心情が丁寧で、それが烏帽子でわかる面白さ。
(解説を聴いて、後から見直した)
そして、抱一の富士見業平図屏風。
もとは光琳の描いた対の掛け軸を写して、自分流の表現を屏風に表したものという。
前日、光琳と抱一は時代的に一世紀近い差があることに気がついたんだけど、→こちら
抱一にとって、光琳は“前の時代の憧れの人”だったみたい。
現代のワタシたちが上村松園や横山大観に傾倒するようなものだったのかしらん。
(ワタシ自身は全く絵は描けないケド
 )
)同じように風神雷神図屏風も。
光琳は宗達に憧れ、抱一は光琳に憧れて同じ構図で屏風絵を描いた。(そして其一も)
ただ、抱一の場合は屏風のみならず、対の掛け軸としても構図をアレンジして描いている。
これは後期の展示なので、再訪必至

そして、抱一といえば花鳥図。
四季花木図屏風。一つの屏風の中に桜もあれば朝顔もススキも水仙も描かれてあって、不思議だったけれど、美しかった。
抱一が花々や木を写生した上で描いたのが伺える、とてもリアルなきれいさがわかる。
そして、十二ヶ月花鳥図も。
以前、とびとびで湯木美術館で見た? 短冊だったかな。
他にも三の丸尚蔵館にもあるらしいけど、描かれている花鳥(の種類)が違うんだって。
例えば、6月の花といえば紫陽花が思い浮かぶけど、葵と百合で「え?」って印象。
個人的には1月の構図が「椿、梅、鶯」だったのとか意外。(←梅と鶯は2月か3月かと思ってたので)
2月は「菜の花と雲雀」、3月は「桜と瑠璃鳥」と現代よりも季節が先取りされているような?
旧暦と新暦の違いだろうか。
でも、そういえばこの前、土手に菜の花が咲いているのが視界に入ったような。(←電車
 内から見えた)
内から見えた)季節感に敏感になることは、茶人の素養として必要だな、って思った。
それにしても、大名家の次男坊ということで、上等の絹地に質のいい絵の具を使って描いているから、
200年経ってもきれいだなぁ。
工芸は光悦の赤楽茶碗「李白」が印象に残った。
オレンジのような、ピンクのようなほんのりした明るい赤。
(銘は酒飲みだった李白をイメージして原三渓がつけた)
乾山の器(鉢、向付、香合、黒楽茶碗)、光琳の茶杓、本阿弥光甫の茶杓もよかった。
(工芸は全期を通じての展示なので、後期でもみよう)
今回の展覧会、畠山としては初めてクリアファイルを作った。
2種類あって、1枚250円。
とーーーってもいい。(写真、リアルに撮りすぎちゃったので、ココで紹介するのはパスさせていただきます)
展覧会の前後、茶室というか露地も見学する。


先日の茶室見学のフリーク効果で露地や飛び石がやたら気になる。
現在、茶道文化検定の公式テキストを読み返しながら勉強し直してる。
改めて「おぉっ
 」って思うこと多し。
」って思うこと多し。でも、飛び石のところは文章中心だし、詳しいような、物足りないような、、難しい。
もっと読み深めておかねばなと思う。
にほんブログ村
応援ヨロシク
 致しマス
致しマス
※参考 過去の畠山記念館
2010年11月→→『織部が愛した茶碗 高麗・割高台』その2
2010年10月→『織部が愛した茶碗 高麗・割高台』その1
2010年8月→『涼を愉しむ-書画・茶器・懐石道具-』
2010年5月→『茶の湯の美-数寄のかたちと意匠-』
2010年2月→『懐石のうつわ -向付と鉢を中心に-』
2009年10月→『戦国武将と茶の湯 -信長・秀吉ゆかりの品々-』
2009年4月→『畠山記念館名品展 季節の書画と茶道具』
2009年2月→『冬季展 日本の春-華やぎと侘び』
2008年10月→『益田鈍翁 -心づくしの茶人-』
2008年8月→『夏季展 夏のやきもの -金襴手・万暦赤絵・古赤絵・南京赤絵』
2008年4月→『細川井戸と名物茶道具』
2008年3月→『花によせる日本の心 -梅・桜・椿を中心に』
2007.12月→『茶の湯の美 -利休から宗旦へ-』後期
2007.11月→『茶の湯の美 利休から宗旦へ』前期


























