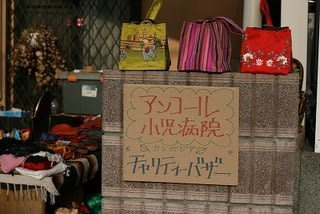すぐにできるソーシャルアクションの一つです。
日本在住の皆様へ,
 Avaaz の代理として、佐野美博に署名を届けるアイリーン・美緒子・スミス(グリーン・アクション) |
すばらしい結果です!わずか3日間で12万もの人々が団結し、福島の子供たちを救うため抗議の声を上げました。そして先週金曜日、私たちのメッセージは日本の非政府組織グリーン・アクションによって総理大臣に届けられました。大きな第一歩を踏み出しましたが、道のりはまだまだ先です。
政府は未だに、緊急避難支援を実施しません。その間にも、人々は日一日と放射能にさらされ続け、それは現在そして今後何十年にもわたり、深刻な健康被害を助長していくのです。今なお高レベル汚染地区に閉じ込められ、そこからの避難を切望している福島市の子供たちや渡利の住民にとって、最後の希望の源は人々の力です。
http://www.avaaz.org/jp/japan_reportback_and_poll/?vl
AVAAZについて
Avaaz.orgは世界の人々の声や価値観が政策決定に反映されるよう世界規模でキャンペーンを行う非営利団体です(Avaazは様々な言語で「声」を意味します)。Avaazは政府や企業から一切資金援助を受けず、ロンドン、リオデジャネイロ、ニューヨーク、パリ、ワシントンDC、そしてジュネーブを拠点とするスタッフにより運営されています。