
先日BS世界のドキュメンタリーで放送された「未来への提言:エマニュエル・トッド」は大変参考になった。
エマニュエル・トッド氏はフランスの人口統計学者。人口統計学を用いてソビエト連邦崩壊を予言したばかりか、2002年の著書『帝国以後』においてアメリカの衰退、アメリカ型システムの崩壊をも予言し、世界的に注目を集めている。
このフランスを代表する知性の洞察力に満ちた言葉は非常に興味深かったので、よく頭に入れるためにスクリプトを作成した。以下その内容。
未来への提言 エマニュエル・トッド
【アメリカは世界の問題】
厳密に言えば、2002年に「帝国以後」を書いたとき、私はアメリカの崩壊を予言したわけではない。むしろアメリカの弱体化、いわば正常な規模の国に戻るのではないかと指摘したのだ。しかし、今、ブッシュ政権時代に起きた金融スキャンダル、軍事力の衰退を見るにつけ、アメリカはソビエト連邦のように崩壊の瀬戸際にいるのではないかと考え始めている。でもそのスピードは分からない。オバマの当選がアメリカというシステムの寿命を延ばしたことは明らかだ。
最近のアメリカは世界の問題を解決する役割をやめてしまっただけでなく、自らが世界の問題になってしまった。金融に過度に依存するだけでなく、世界中に不安定と戦争をもたらした。彼らはイラクを荒廃させた。そして今もアフガニスタンでの無益な戦争を続けようとしている。アメリカはヨーロッパとロシアの関係も悪化させた。
私はかつてアメリカの社会はとても柔軟で弾力性があり、ソビエト連邦のように崩壊するなどあり得ないのではと思っていた。弱体化するにしてもむしろ普通の国に戻るだけだと。しかし現実をよく見てみると貿易赤字の果てしない膨張、ブッシュ政権時代の愚かで好戦的な振る舞いなど、私を悲観的な予測へ向かわせるものばかりだったのだ。
決定的なのはアメリカ人の自分自身に対する無知だ。何もかもうまくいっていると自分に言い聞かせるあの能力は異常なものだといえるだろう。サブプライムローンのメカニズムを冷静に分析すれば、常軌を逸したものだとわかるはずだ。ソビエト連邦の崩壊のような重大な危機というのは、政権幹部が問題を解決しようとせず、先送りしようとしたときに起こる。いまだにアメリカには活力がある、自動車産業の崩壊はたいしたことない、サブプライムローンなんてたいしたことない、イラク戦争なんてたいしたことないなどと言っている人は、私に言わせれば無責任だ。
裸の王様という童話がある。取り巻きは王様の服をほめそやしているが、実際には王さまは何も着ていない。そこへ子供が現れ「王様は裸だ」というのだ。私もいわば子供だ。私の頭のなかは自由だから本当のことを言える。
【乳児死亡率の意味するもの】
ソビエト連邦で何が起きていたのか説明しよう。当時私は24歳の学生だった。私は国立人口統計学研究所の図書館で、偶然WHOの統計の中に、ソビエト連邦の1歳以下の乳児死亡率の増加をみつけた。私は人口統計学を学んでいたので、すぐにその重要性に気づいた。さらにソビエトは1974年以降この統計を発表していなかった。おかしいなと直感した。乳児死亡率というのはその国の経済力や、親がどれくらい子供を注意して見てやれるか、医療システムなど、他の様々な要因と密接に結びついている。つまり国の力を示す総括的な指標なのだ。
アメリカは、乳児死亡率が先進諸国の中で最も高い国の1つだ。最近も前年より上昇してしまったこともある。ポーランドとほぼ同じレベルだ。だからみんなが興奮して「アメリカは超大国だ!」などと言うとき、「いやいや、この数字をご覧なさい」というのだ。
【オバマ大統領をどう見る】
私がもしアメリカ人だったら、やはりオバマに投票しただろう。ブッシュよりずっと好感が持てるのは確かだ。ブッシュ政権時代、私は、アメリカは極右化しているのではないかと懸念していたので、オバマの当選を喜んでいる。グアンタナモ収容所の閉鎖は良いことだし、オバマは自分にできることはすべてやるだろう。
熱狂的なオバマファンが増えていることからも明らかなように、実は、同盟国はアメリカに隷属したいと願っているのだ。つまり、アメリカに世界の中心であり続けて欲しいのだ。しかしご存知のように今アメリカは空っぽの貝殻のようなものだ。GMが崩壊していくのが見える。とはいえ、もしアメリカがリーダーシップをとり続ける気があるのならまだ余力が残っている。何より最終的な強みは、同盟国がアメリカの消滅を恐れていることだ。リーダー不在の世界は不安だから、人々にはいわば幻想が必要なのだ。
しかしアメリカが抱えているシステム不全は、ブッシュ政権だけの問題ではなく、とても根深いものだ。例えばエンジニアが育たないといって教育システムの欠陥だ。アメリカは金融に頼り切ってしまった。8,000億ドルもの貿易赤字を抱え、株と国債をばらまいて凌いでいる。これは生産するのではなく消費する社会だ。
もちろんオバマはこうした状況を変えたいと思っているだろうが、非常に困難だ。教育システムを根本から再構築し、学生達が金融マンや弁護士になるよりも科学や工学を学ぶように導かなけれならない。でも、これは大統領の仕事ではない。モラルの向上の問題だ。黒人が政治の壁を超えたのは素晴らしいことだ。しかし、オバマのスローガン“Yes, we can!”を聞きながら、つい私は呟いてしまった。“Sub-prime, Yes, we can!”と。つまりオバマも手品を続けるだけなのでないか。ちょっと皮肉が過ぎるか。
これは直観だが、アメリカがいわゆる帝国のように振る舞い始めたのは、クリントン政権の時代だ。1996年から1998年頃、民主党政権下でのことだ。オバマの側近にはクリントン政権の古株が揃っている。だからアメリカが世界のリーダーシップを取るという流れは、脈々とオバマ政権にもつながっている。いずれにせよ、歴史上帝国と呼ばれた国家が正常な国家に戻ることもあった。しかし、歴史家としての教育を受けた者として言わせてもらえば、アメリカはまだあまりにも若く、再生する能力があると実証していない国なのだ。オバマが希望をばらまきすぎなければよいのだが。
おそらくアメリカは産業を復興するよりも金融に頼って生き続けるころだろう。そしていつか軍部が崩壊するだろう。産業なしに軍部は維持できないからだ。オバマに対して過剰な幻想は抱かないことだ。
【自由貿易の問題点】
アメリカ発の経済危機が明らかにしたのは、これが自由貿易のなれの果てだということだ。自由貿易という言葉はとても美しく響く。何しろ「自由」という単語が使われているから。もちろん自由貿易は有益なものになり得る。しかし今はすべての人を巻き込む激しいビジネス競争となっている。保護主義は平和だといっても信じてもらえないかもしれないが、自由貿易は戦争だということは信じてもらえるはずだ。
企業は外国市場向けの生産を始めた途端、労働者の賃金を単なるコストだと考える。従来の内需を中心とする経済では、企業は賃金の引き上げが生産性を高め、利潤を生むことを知っていた。輸出においては、賃金は単なるコストとなり、絶対的な競争原理のもと、コストの引き下げ圧力がかかる。もし世界中の企業が賃金をただのコストでしかないと考え抑制したら、世界規模で需要不足が起きるのは明からだ。
現在アメリカの消費はすさまじく、アメリカは8,000億ドルの貿易赤字を抱えている。不道徳かもしれないが、これが地球規模の需要を生んでいたのだ。アメリカは消費し続けることで、自滅するだろうが役には立つ。
産業と経済の復興には需要の喚起が必要だ。ヨーロッパの場合は、保護主義を基本とするブロック経済に戻るべきだと、私は考える。保護主義という言葉がタブーなのは私もよく知っている。しかし、もしヨーロッパが地元贔屓に戻れば、賃金を回復し、グローバルな需要を増やすことにもつながる。
保護主義の危険性については、フランスでも常に議論を呼んでいる。保護主義は外国人の排斥や外国敵視につながるという意見は確かにある。しかし、私の言う保護主義は全くそうではない。あくまでも需要を増やし、貿易を健全な形に再活性化するツールに過ぎないのだ。むしろ自由貿易は、世界の工場中国を破滅へと向かわせている。例え保護主義を導入しなくても、欧米の需要が崩壊すれば中国も崩壊する。
【中国の危機】
つい最近まで、中国はグローバル化と自由貿易の多大な恩恵を受けて発展してきた。しかし今、GDPに占める輸出の割合の大きさを考えると、中国は今回の経済危機で最も脅かされている国だといえる。
中国を救うには国際的な協力が必要だ。私が関税で保護されたブロック経済による世界経済の再編を唱えているのは、需要を増やしていためであり、どこかの国を攻撃したいからでは決してない。例えばヨーロッパは中国の輸出に対して予告なしに門戸を閉じるようなことがあってはならない。段階的に徐々に進めることが大切だ。その間に、中国が自国の製品を国内市場に展開できるよう援助しなければならない。
私は、中国はもっと内需を増やす方向に進んで行けると思っている。もちろん内需のみというわけにはいかないが、それを優先するということだ。ご存じのように、中国は革命国家だ。歴史上何人もの皇帝が倒され、共産革命が起こった。そして現在、すさまじい社会的緊張がある。私は今、中国共産党の幹部は恐怖に怯えていると思う。彼らは輸出が減り失業が広がっているのを理解しているし、中国の格差が行き着くとどんな事態が起きるか知り抜いている。中国が抱える問題を意識し、この非常に困難な事態を乗り越えるためには、彼らを支援しなければならないと強く訴えたい。
【人類学者になった理由】
私が人類学者になったのは、私の家族の中に多様な文化があったことが影響しているかもしれない。私の先祖はフランス・ブルターニュ地方の農民と、フランス東部のユダヤ人、イギリス人、そしてオーストリアのユダヤ人だ。家族の歴史の中に3つの宗教がある。イギリスに留学したのも大きい。私は最初にフランスとの文化の違いを目撃したのはイギリスだ。高校時代、パリ郊外のインターナショナルスクールで学んだことも影響している。それからヨーロッパ中を旅行した。私はいわゆるフィールでワークは行わないが、文化の多様性を分析することに強い興味を持っている。
【日本の取るべき態度】
日本は、心理的、文化的にアメリカのリーダーシップからもっと解放されるべきだと私は思う。日本は世界の中で唯一、その技術の高さに驚かされる国だ。平均寿命の長さや乳児死亡率の低さも世界でトップだ。いわば、世界で最も進んだ国なのだ。オートメーション化やロボット工学など、未来界を切り開く分野で日本はリーダーだ。
しかし、日本は、政治システム上は民主主義だが、国民はアメリカの依存から脱却することを望まず、大人になることさえ嫌がっているように見える。つまり、能力もあり、いつかは独り立ちしなければならない子供が、パパが年老いていくことを信じたがらないといった風だ。おそらく第二次大戦のトラウマもあるのだろう。日本が独自に行動した時代の思い出は良いものではない。
私はそれに加えて文化的、人類学的側面もあるものと見ている。上下関係を重んじ、権威に阿るモデルとでも言おうか、日本人は率直に物を言うことが苦手だ。それが国際社会で他の国々と対等の関係を築いていくことのネックになっている。
あなた方は平等な世界にいるのだ。真の成熟というものは、人間も国家も互いに平等なシステムの中でこそ到達できるものだ。もし本当に世界の再構築を考えているのなら、日本はヨーロッパと直接対話すべきだ。この2つの地域は本物の産業ゾーンなのだから。そして日本はアジア経済の立て直しでももっと責任を果たすべきだ。私も取るに足らないフランス人だが、日本には大人になって欲しいと願っている。
【日本が抱える最大の課題】
日本が本当に恐れるべきはアメリカの影響ではない。それは出生率の低下だ。最近日本の人口減少についての長期的な分析を読む機会があり、本当に驚いた。日本ではもう何年も女性が一生の間に産む子供の人数が1.3人という状態が続いている。少子化は人口の減少を引き起こす。
もうひとつ恐れなければならないことは、日本が移民の受け入れがあまり得意ではないということだ。伝統的に外国人と関わるのが苦手だということもあるのだろう。私は日本の人々がロボット研究に熱狂しているのを見て時々自問する。日本の戦略は移民よりもとにかくロボットなのかと。でもそれだけではうまくいかない。
国家というものは人口減少や高齢化を受け入れてしまったら、もはや大国であり続けることはできない。だから世界経済の問題以上に、日本の本当の問題は人口問題なのだ。
【人類の希望】
グローバル化が進んでも、世界には文化的な多様性がある。我々はその多様性を受け入れなければならない。唯一のシステムを押し付けようとすれば、フランス革命のような戦争を引き起こすか、もっと奇妙な事態となるだろう。中東に対するアメリカの攻撃を覚えているか。軍事力でまだ民主化の準備ができていないアラブ諸国に民主主義を押し付けようとした。アラブ諸国は独自の民主化を遂げるだろうが、今すぐにではない。
私は歴史の中心線は教育の発展にあると思っている。まずは識字化すること、そして中等教育、高等教育の発展だ。識字化についていえば、もうすぐ世界中の人々が読み書きできる時代が来るだろう。欧米や日本と同様に、中国やインドで、そしてアラブ世界やアフリカ、ラテンアメリカでも識字化に成功するだろう。経済危機のせいで今は誰もが悲観的になっているが、実際には2030年には世界中の人々が読み書きできるようになる。
本当のグローバル化は経済ではない。皆が読み書きできる世界が現れるという意味では、グローバル化は素晴らしいことだ。歴史の続きは興味深いものになるだろう。
私は夢見ている。この経済危機の解決策を見出すことのできる世界的な指導者達が現れることを。そして我々をこの制御不能な自由貿易という罠から抜け出させてくれることを。
私は市場経済が唯一妥当な経済だと信じている。ただ、経済的基盤の大きさはそれぞれの地域で決めるべきで、国家もある程度関与すべきだと思う。私にはユートピアや資本主義を超えた全く新しい経済モデルを発明することはできそうにない。だから人類がこれ以上つまらない失敗をやり過ぎないよう期待するばかりだ。
【未来を切り開くキーワード:「知的正直さとリアリズム」】
「知的正直さとリアリズム」これは現在の状況に最も欠けているものだと私は思う。経済を議論しながら今動いているシステムのどこに問題があるのかを考えようとしない人々が多すぎる。現実を直視できず、現状に即した行動を取れないのだ。
私は知的正直さとリアリズムを心がけるよう努力している。問題を理解し、危機と向き合い、その合理的な解決策を受け入れるのだ。たとえそれが胸躍るような策でなくても。
エマニュエル・トッド氏はフランスの人口統計学者。人口統計学を用いてソビエト連邦崩壊を予言したばかりか、2002年の著書『帝国以後』においてアメリカの衰退、アメリカ型システムの崩壊をも予言し、世界的に注目を集めている。
このフランスを代表する知性の洞察力に満ちた言葉は非常に興味深かったので、よく頭に入れるためにスクリプトを作成した。以下その内容。
未来への提言 エマニュエル・トッド
【アメリカは世界の問題】
厳密に言えば、2002年に「帝国以後」を書いたとき、私はアメリカの崩壊を予言したわけではない。むしろアメリカの弱体化、いわば正常な規模の国に戻るのではないかと指摘したのだ。しかし、今、ブッシュ政権時代に起きた金融スキャンダル、軍事力の衰退を見るにつけ、アメリカはソビエト連邦のように崩壊の瀬戸際にいるのではないかと考え始めている。でもそのスピードは分からない。オバマの当選がアメリカというシステムの寿命を延ばしたことは明らかだ。
最近のアメリカは世界の問題を解決する役割をやめてしまっただけでなく、自らが世界の問題になってしまった。金融に過度に依存するだけでなく、世界中に不安定と戦争をもたらした。彼らはイラクを荒廃させた。そして今もアフガニスタンでの無益な戦争を続けようとしている。アメリカはヨーロッパとロシアの関係も悪化させた。
私はかつてアメリカの社会はとても柔軟で弾力性があり、ソビエト連邦のように崩壊するなどあり得ないのではと思っていた。弱体化するにしてもむしろ普通の国に戻るだけだと。しかし現実をよく見てみると貿易赤字の果てしない膨張、ブッシュ政権時代の愚かで好戦的な振る舞いなど、私を悲観的な予測へ向かわせるものばかりだったのだ。
決定的なのはアメリカ人の自分自身に対する無知だ。何もかもうまくいっていると自分に言い聞かせるあの能力は異常なものだといえるだろう。サブプライムローンのメカニズムを冷静に分析すれば、常軌を逸したものだとわかるはずだ。ソビエト連邦の崩壊のような重大な危機というのは、政権幹部が問題を解決しようとせず、先送りしようとしたときに起こる。いまだにアメリカには活力がある、自動車産業の崩壊はたいしたことない、サブプライムローンなんてたいしたことない、イラク戦争なんてたいしたことないなどと言っている人は、私に言わせれば無責任だ。
裸の王様という童話がある。取り巻きは王様の服をほめそやしているが、実際には王さまは何も着ていない。そこへ子供が現れ「王様は裸だ」というのだ。私もいわば子供だ。私の頭のなかは自由だから本当のことを言える。
【乳児死亡率の意味するもの】
ソビエト連邦で何が起きていたのか説明しよう。当時私は24歳の学生だった。私は国立人口統計学研究所の図書館で、偶然WHOの統計の中に、ソビエト連邦の1歳以下の乳児死亡率の増加をみつけた。私は人口統計学を学んでいたので、すぐにその重要性に気づいた。さらにソビエトは1974年以降この統計を発表していなかった。おかしいなと直感した。乳児死亡率というのはその国の経済力や、親がどれくらい子供を注意して見てやれるか、医療システムなど、他の様々な要因と密接に結びついている。つまり国の力を示す総括的な指標なのだ。
アメリカは、乳児死亡率が先進諸国の中で最も高い国の1つだ。最近も前年より上昇してしまったこともある。ポーランドとほぼ同じレベルだ。だからみんなが興奮して「アメリカは超大国だ!」などと言うとき、「いやいや、この数字をご覧なさい」というのだ。
【オバマ大統領をどう見る】
私がもしアメリカ人だったら、やはりオバマに投票しただろう。ブッシュよりずっと好感が持てるのは確かだ。ブッシュ政権時代、私は、アメリカは極右化しているのではないかと懸念していたので、オバマの当選を喜んでいる。グアンタナモ収容所の閉鎖は良いことだし、オバマは自分にできることはすべてやるだろう。
熱狂的なオバマファンが増えていることからも明らかなように、実は、同盟国はアメリカに隷属したいと願っているのだ。つまり、アメリカに世界の中心であり続けて欲しいのだ。しかしご存知のように今アメリカは空っぽの貝殻のようなものだ。GMが崩壊していくのが見える。とはいえ、もしアメリカがリーダーシップをとり続ける気があるのならまだ余力が残っている。何より最終的な強みは、同盟国がアメリカの消滅を恐れていることだ。リーダー不在の世界は不安だから、人々にはいわば幻想が必要なのだ。
しかしアメリカが抱えているシステム不全は、ブッシュ政権だけの問題ではなく、とても根深いものだ。例えばエンジニアが育たないといって教育システムの欠陥だ。アメリカは金融に頼り切ってしまった。8,000億ドルもの貿易赤字を抱え、株と国債をばらまいて凌いでいる。これは生産するのではなく消費する社会だ。
もちろんオバマはこうした状況を変えたいと思っているだろうが、非常に困難だ。教育システムを根本から再構築し、学生達が金融マンや弁護士になるよりも科学や工学を学ぶように導かなけれならない。でも、これは大統領の仕事ではない。モラルの向上の問題だ。黒人が政治の壁を超えたのは素晴らしいことだ。しかし、オバマのスローガン“Yes, we can!”を聞きながら、つい私は呟いてしまった。“Sub-prime, Yes, we can!”と。つまりオバマも手品を続けるだけなのでないか。ちょっと皮肉が過ぎるか。
これは直観だが、アメリカがいわゆる帝国のように振る舞い始めたのは、クリントン政権の時代だ。1996年から1998年頃、民主党政権下でのことだ。オバマの側近にはクリントン政権の古株が揃っている。だからアメリカが世界のリーダーシップを取るという流れは、脈々とオバマ政権にもつながっている。いずれにせよ、歴史上帝国と呼ばれた国家が正常な国家に戻ることもあった。しかし、歴史家としての教育を受けた者として言わせてもらえば、アメリカはまだあまりにも若く、再生する能力があると実証していない国なのだ。オバマが希望をばらまきすぎなければよいのだが。
おそらくアメリカは産業を復興するよりも金融に頼って生き続けるころだろう。そしていつか軍部が崩壊するだろう。産業なしに軍部は維持できないからだ。オバマに対して過剰な幻想は抱かないことだ。
【自由貿易の問題点】
アメリカ発の経済危機が明らかにしたのは、これが自由貿易のなれの果てだということだ。自由貿易という言葉はとても美しく響く。何しろ「自由」という単語が使われているから。もちろん自由貿易は有益なものになり得る。しかし今はすべての人を巻き込む激しいビジネス競争となっている。保護主義は平和だといっても信じてもらえないかもしれないが、自由貿易は戦争だということは信じてもらえるはずだ。
企業は外国市場向けの生産を始めた途端、労働者の賃金を単なるコストだと考える。従来の内需を中心とする経済では、企業は賃金の引き上げが生産性を高め、利潤を生むことを知っていた。輸出においては、賃金は単なるコストとなり、絶対的な競争原理のもと、コストの引き下げ圧力がかかる。もし世界中の企業が賃金をただのコストでしかないと考え抑制したら、世界規模で需要不足が起きるのは明からだ。
現在アメリカの消費はすさまじく、アメリカは8,000億ドルの貿易赤字を抱えている。不道徳かもしれないが、これが地球規模の需要を生んでいたのだ。アメリカは消費し続けることで、自滅するだろうが役には立つ。
産業と経済の復興には需要の喚起が必要だ。ヨーロッパの場合は、保護主義を基本とするブロック経済に戻るべきだと、私は考える。保護主義という言葉がタブーなのは私もよく知っている。しかし、もしヨーロッパが地元贔屓に戻れば、賃金を回復し、グローバルな需要を増やすことにもつながる。
保護主義の危険性については、フランスでも常に議論を呼んでいる。保護主義は外国人の排斥や外国敵視につながるという意見は確かにある。しかし、私の言う保護主義は全くそうではない。あくまでも需要を増やし、貿易を健全な形に再活性化するツールに過ぎないのだ。むしろ自由貿易は、世界の工場中国を破滅へと向かわせている。例え保護主義を導入しなくても、欧米の需要が崩壊すれば中国も崩壊する。
【中国の危機】
つい最近まで、中国はグローバル化と自由貿易の多大な恩恵を受けて発展してきた。しかし今、GDPに占める輸出の割合の大きさを考えると、中国は今回の経済危機で最も脅かされている国だといえる。
中国を救うには国際的な協力が必要だ。私が関税で保護されたブロック経済による世界経済の再編を唱えているのは、需要を増やしていためであり、どこかの国を攻撃したいからでは決してない。例えばヨーロッパは中国の輸出に対して予告なしに門戸を閉じるようなことがあってはならない。段階的に徐々に進めることが大切だ。その間に、中国が自国の製品を国内市場に展開できるよう援助しなければならない。
私は、中国はもっと内需を増やす方向に進んで行けると思っている。もちろん内需のみというわけにはいかないが、それを優先するということだ。ご存じのように、中国は革命国家だ。歴史上何人もの皇帝が倒され、共産革命が起こった。そして現在、すさまじい社会的緊張がある。私は今、中国共産党の幹部は恐怖に怯えていると思う。彼らは輸出が減り失業が広がっているのを理解しているし、中国の格差が行き着くとどんな事態が起きるか知り抜いている。中国が抱える問題を意識し、この非常に困難な事態を乗り越えるためには、彼らを支援しなければならないと強く訴えたい。
【人類学者になった理由】
私が人類学者になったのは、私の家族の中に多様な文化があったことが影響しているかもしれない。私の先祖はフランス・ブルターニュ地方の農民と、フランス東部のユダヤ人、イギリス人、そしてオーストリアのユダヤ人だ。家族の歴史の中に3つの宗教がある。イギリスに留学したのも大きい。私は最初にフランスとの文化の違いを目撃したのはイギリスだ。高校時代、パリ郊外のインターナショナルスクールで学んだことも影響している。それからヨーロッパ中を旅行した。私はいわゆるフィールでワークは行わないが、文化の多様性を分析することに強い興味を持っている。
【日本の取るべき態度】
日本は、心理的、文化的にアメリカのリーダーシップからもっと解放されるべきだと私は思う。日本は世界の中で唯一、その技術の高さに驚かされる国だ。平均寿命の長さや乳児死亡率の低さも世界でトップだ。いわば、世界で最も進んだ国なのだ。オートメーション化やロボット工学など、未来界を切り開く分野で日本はリーダーだ。
しかし、日本は、政治システム上は民主主義だが、国民はアメリカの依存から脱却することを望まず、大人になることさえ嫌がっているように見える。つまり、能力もあり、いつかは独り立ちしなければならない子供が、パパが年老いていくことを信じたがらないといった風だ。おそらく第二次大戦のトラウマもあるのだろう。日本が独自に行動した時代の思い出は良いものではない。
私はそれに加えて文化的、人類学的側面もあるものと見ている。上下関係を重んじ、権威に阿るモデルとでも言おうか、日本人は率直に物を言うことが苦手だ。それが国際社会で他の国々と対等の関係を築いていくことのネックになっている。
あなた方は平等な世界にいるのだ。真の成熟というものは、人間も国家も互いに平等なシステムの中でこそ到達できるものだ。もし本当に世界の再構築を考えているのなら、日本はヨーロッパと直接対話すべきだ。この2つの地域は本物の産業ゾーンなのだから。そして日本はアジア経済の立て直しでももっと責任を果たすべきだ。私も取るに足らないフランス人だが、日本には大人になって欲しいと願っている。
【日本が抱える最大の課題】
日本が本当に恐れるべきはアメリカの影響ではない。それは出生率の低下だ。最近日本の人口減少についての長期的な分析を読む機会があり、本当に驚いた。日本ではもう何年も女性が一生の間に産む子供の人数が1.3人という状態が続いている。少子化は人口の減少を引き起こす。
もうひとつ恐れなければならないことは、日本が移民の受け入れがあまり得意ではないということだ。伝統的に外国人と関わるのが苦手だということもあるのだろう。私は日本の人々がロボット研究に熱狂しているのを見て時々自問する。日本の戦略は移民よりもとにかくロボットなのかと。でもそれだけではうまくいかない。
国家というものは人口減少や高齢化を受け入れてしまったら、もはや大国であり続けることはできない。だから世界経済の問題以上に、日本の本当の問題は人口問題なのだ。
【人類の希望】
グローバル化が進んでも、世界には文化的な多様性がある。我々はその多様性を受け入れなければならない。唯一のシステムを押し付けようとすれば、フランス革命のような戦争を引き起こすか、もっと奇妙な事態となるだろう。中東に対するアメリカの攻撃を覚えているか。軍事力でまだ民主化の準備ができていないアラブ諸国に民主主義を押し付けようとした。アラブ諸国は独自の民主化を遂げるだろうが、今すぐにではない。
私は歴史の中心線は教育の発展にあると思っている。まずは識字化すること、そして中等教育、高等教育の発展だ。識字化についていえば、もうすぐ世界中の人々が読み書きできる時代が来るだろう。欧米や日本と同様に、中国やインドで、そしてアラブ世界やアフリカ、ラテンアメリカでも識字化に成功するだろう。経済危機のせいで今は誰もが悲観的になっているが、実際には2030年には世界中の人々が読み書きできるようになる。
本当のグローバル化は経済ではない。皆が読み書きできる世界が現れるという意味では、グローバル化は素晴らしいことだ。歴史の続きは興味深いものになるだろう。
私は夢見ている。この経済危機の解決策を見出すことのできる世界的な指導者達が現れることを。そして我々をこの制御不能な自由貿易という罠から抜け出させてくれることを。
私は市場経済が唯一妥当な経済だと信じている。ただ、経済的基盤の大きさはそれぞれの地域で決めるべきで、国家もある程度関与すべきだと思う。私にはユートピアや資本主義を超えた全く新しい経済モデルを発明することはできそうにない。だから人類がこれ以上つまらない失敗をやり過ぎないよう期待するばかりだ。
【未来を切り開くキーワード:「知的正直さとリアリズム」】
「知的正直さとリアリズム」これは現在の状況に最も欠けているものだと私は思う。経済を議論しながら今動いているシステムのどこに問題があるのかを考えようとしない人々が多すぎる。現実を直視できず、現状に即した行動を取れないのだ。
私は知的正直さとリアリズムを心がけるよう努力している。問題を理解し、危機と向き合い、その合理的な解決策を受け入れるのだ。たとえそれが胸躍るような策でなくても。















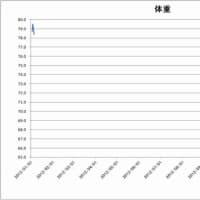
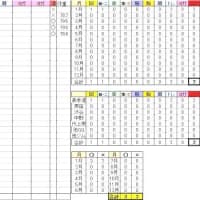



以前お話していた通り、リンク先のページで引用させていただきました。引用というよりは、ほとんど借用のような形になってしまい申し訳ないくらいなのですが、その分、自分の感想を踏み込んで書いてみました。
『マネーが止まった』についても入手しましたので、読了次第書評を書きます。
読書ブログも読ませていただきます。