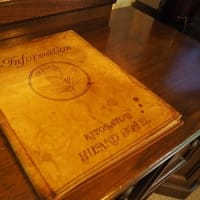「湯布院の良さは田舎者にはわからない」という言い回しがあります。
「湯布院のよかとこは、田舎もんには分からんにー」(適当)
みたいな感じですかね。
その意味は、湯布院が田舎だからだそうです。
田舎の人間には田舎の良さがわかりにくいと云うことでしょう。
バブル後の不況の中で苦戦していた地方の女将さんが視察に来た時に「なんだ、ただの田舎じゃない」と驚いて帰ったという話もあるようです。
その「田舎」を一反一億円と言われるほど土地の跳ね上がったバブルの時代に、開発の勢いから湯布院を守るため苦労をしてきた話はNHKでも番組になったので有名ですね。
結果、湯布院は湯量だけは豊富な寂れた湯治場から全国区ブランドへと展開したようで、行きたい温泉地(オンライン総合旅行サービス「DeNAトラベル」)のアンケートでも東の草津に並んで西の湯布院に選ばれています。江戸時代の温泉番付は圏外ですから大躍進です。
でも首都圏の人間だからと言って田舎の良さがわかるとは限らない。自分はどうなんだろう、と思い立った訳です。
取り合えず湯布院で検索してたまたま最初に現れたのが亀の井別荘でしたので選びました(高そうだけど)。
ただこの御三家と言われる宿の経営者が湯布院を守るための一翼を担ったともありましたので、せっかくだからということで。
ところが行く直前になってつらつらこの宿を検索していたら4年ほど前にUPされた結構な辛口のブログ記事があって、それがまた上手な写真とともに読むと頷ける内容でしたので、期待値のテンションが大分下がっていました。
「亀の井別荘に泊まった人のブログの感想 」の内の一つで、「亀の井別荘 私的生活日記」で検索できますが、いやすごい。
たしかに料理の写真をみると美味しそうには見えないものもいくつかありましたから、そうなのかなぁと。
亀の井別荘を褒める記事ならプロらしき人も含めてたくあん、いやタクサンありますが、この女性ブログ主は厳しい。
どこかで少し褒めるのかと思いきや、一気に突き抜けています。
指摘する一つ一つには確かに問題点もあると思うのですが、なにか一段深いところで勘に障ったところがあるのじゃなかろうかと、思います。
自分には「ほかの客の感想」という点でとても参考になって何回も読んだし、たぶん宿にとってもこの記事は逆に良いのではないのかな、とも思います。
宿に対する指摘は役に立ちそうですし、読んだ人が訪れてみれば「思ったよりも良かった」という事にもなりそうですしね。
勝手な詮索ですが記事を読む限りでは、この女性が普段利用しているレベルの宿からすると普通すぎるサービスの割にちゃんと出来ていないところが多く、その割に当たり前のことをいかにもサービスがましくされたように受け取り、片腹痛いような感じになったのかもしれない。見当違いかもしれませんけど。
そんなんで、過度の期待を持つこともなく泊まってみたのですが、それが良かったのか、事細かにチェックできる能力が無いせいなのか知りませんが、自分はこの宿が気に入りましたし、また泊まってもいい宿だなと思いました。
前置きが長くなりましたが行き方です。大分空港からバスで湯布院の駅まで行きました。そこから20分ほど歩いて韓国語が飛び交う賑やかな湯の坪通りを抜けて、奥に折れると亀の井別荘へ入る石橋あります。先に目をやるとロータリーになっていて、左が天井桟敷や土産物の鍵屋。右に周るとよく写真でみる小さな茅葺の門があります。





着いたのが2時ころで、少し早かったから宿のスタッフに荷物を預け、鍵屋、食堂の湯の岳庵をみて、天井桟敷へ。


湯の岳庵のメニュー、そんなに高くない?

天井桟敷のコーヒーは一口飲んだところ口当たりがマイルドで美味しいと思いました。これはコーヒーよりも水ですね。水がいいんだと思います。コーヒーも売っていますが、持ち帰って淹れても同じ味にはならないよ、たぶん。
その後天井桟敷を出てから金鱗湖周辺を歩いて宿に戻りました。
門をくぐって玄関までの前庭は敷き詰めた砂利になっているのですが、その砂利を枯山水の波のように掃いて打ち水がしてありました。荷物を預けた時との変化にきちんと迎えられたような気がして心地よく、遠からず、近からずの玄関までの程よい距離を波を崩しながら歩きました。結局この印象が宿の大部分を占めることになりました。

時間をつぶした割には少し早めに入ったので、ロビーで茶でも出るのかなと待っていたらすぐに部屋まで案内してくれました。ちょっと焦ったけど。

離れでも8畳と6畳の部屋にするか8畳と9畳にするか迷ったのですが、安いほうの8畳と6畳にしました。8畳はちょっと狭いかなとも思ったのですが全然そんなことはなくて、畳も一枚一枚が大きく板の間もあるので2人では十分な広さでした。

逆にこれ以上部屋が広いと自分は嫌です。
角のスペースに広縁が取ってあり冷蔵庫に手が伸ばしやすく良いのですが、庭を眺めるという場所ではないかな。
洗面所は普通ですがタオルを乾かすヒーターのようなものがありました。これは要るか?と思いましたが冬は寒くて乾きにくいのかな。

タオルはさすがの今治タオル。

でもこのタオルは厚いからあまり好きじゃなくて。
宿の持って帰ってもいいタオルを置いてくれるとありがたかったりします。
でもこんなこともあるので、実はタオル持参してます。今回は仙壽閣で貰ったタオル。まあ、自分の都合です。
普段は使わないのですが、たまたま髭を剃った顎がヒリヒリしたときアフターシェーブローションを探したけど、そういうアメニティーは部屋には置いて無いようです。
こういうのは他人とは共用したくないので無くてもよいですが、使い捨てのクリームかなんかが置いてあったらと、少しですが思いました。
洗面所が部屋風呂の脱衣所にもなっていて、部屋風呂を覗いてみると木枠の湯船に温泉が注ぎ込まれていました。ちょっとテンションが上がりましたね。好きなんですよ、これ。

ざっと室内を見回してみると、ちょっとした既視感。

そう、伊豆長岡の三養荘の新館の部屋にかなり似ていますね。三養荘は好きでかれこれ5回程泊まっているので、同じタイプのこの宿にもすぐに慣れることが出来ました。
三養荘も内風呂が源泉かけ流しでいつも湯船から溢れていてお気に入りなのですが、ここはさらにドアがあり、外に出ると木のチェアーが置いてあるので(ちょっと汚れてるっぽいけど)ノボせても涼めます。結構気持ちよかった。
いままでで内風呂に入ったのはこの二つの宿だけです。
全体的に居心地の不満はありませんでした。
ちなみにこの宿は金鱗湖のすぐそばなので、1人で出てみました。


湖というより「池」ですよ。
宿の方に金鱗湖は外国の方が多いですねと言ったら「名所というほどのものではないんですけど」と笑っておりました。

その脇に下ん湯という共同浴場があります。200円。
もちろん入りました。





一部露天になっていて、しかも混浴なので女性はおりませんでしたが、最高です。
隙間から池、いや金鱗湖がみえるので、向こうからもみえるかも・・。
味のある共同浴場でした。
問題の料理です、先のブログでコテンパンの。
ブログから4年は経ってるものの配膳はやっぱ遅くなるのかなぁと覚悟していましたが、そんなことは全くなくむしろスムーズに流れたので驚きました。結構改善しているのかもしれません。
給仕部屋付属の離れなので、厨房との距離はそれほどは関係はないような気もがします。配膳が遅かった時はなにかしらのトラブルがあったのかも。

突然思い出しましたけど、大昔にタイのパタヤにあるロイヤルクリフというホテルのロッシーニという名のイタリアンレストランで、夕食を取った時に料理が出てこず1、2回催促はしたものの、結局最初の料理まで2時間待ったことがありました。友人と話が盛り上がっていたせいもあったのですが、それにしてもすごいでしょ、2時間。すげーな俺たちって、なんか誇らしげな気分になった気がします。
まあ、そんなことはともかく、ここは日本ですよね。
料理の内容を一品づつ。細かい説明はいたしませんが、どうでしょうか。



この薄くて軽いグラスですが、最近よく見かけます。
昔福島の野口英世博物館の前にあるガラス館みたいなところで買った記憶があります。意外に割れにくかったです。


このおすましですが、出汁の香りが少し弱く若干ぬるめでした。
しかし、帰りがけに玉の湯の「葡萄屋」でランチをとりましたが、そこでもホボホボ同じようだったので、そういうもんなのかな。

見た目はちょっとと思いますが、茄子のほうは味付けが薄かったので茄子の味自体が感じられました。
焼き魚は太刀魚です。ゴボウの乗せ方があれですが、この魚は好きなので肉厚ですし、よしとします。

豊後牛。ヒレとロースを選べ焼き方も聞いてくれます。これはロース。
ただこのワサビはだめです。
自分は肉にワサビは必須なのですが、このワサビ、色も悪く量もオカシイと思いました。
実際全く効いておらず、自分みたいな素人でも見た瞬間わかるのにどうしたのでしょうか。
肉は脂が強いようです。これは先ほどの玉の湯、葡萄屋でも食べましたが、やはり同じなので豊後牛自体がそういう食感なんだと思います。



朝食。
なんと「のどぐろ」が。
肉厚でおいしいと思いました。九州でも獲れるんですね。時期はどうなのでしょう。
のどぐろというと日本海側のイメージがあるのですけど、そういえば亀の井別荘のそもそもは加賀のほうの出身らしく、土産物の鍵屋になぜか加賀の棒茶がありましたから、なにかしら繋がっているのかもしれません。


確かに3万円前後の宿ならともかく、5万円近くになる宿としてはお客さんの期待も高くなるので見方も厳しくなるのかもしれないですね。
ただ海もそう離れていないとはいえ山ですからね、ここは。
大浴場については、露天の岩風呂を建物で囲ったような内風呂があってプールのような綺麗な水色が記憶に残ります。庭に張り付いたような露天風呂は浸かった時の低い目線の位置からか、その庭と一体化した印象があり、嫌いではないです。日帰り入浴施設といわれればそうかな、とも思いますが、それは言わないで、というところ。




もちろんファイスタオル、バスタオルは常備ですが、フェイスタオルが2種類あります。厚めの今治タオルとワッフルタイプ。ワッフルが好み。マッサージ機が一台。
男女入れ替えあり。
泊まった部屋の正面に談話室があって、コーヒーとかセルフでいただけます。こういうやり方は星野グループの「界」と同じですね。どちらが先か知りませんが。



辛口ブログでは「勝手にやって飲み物」という面白い言い回しをしてましたけど、実はこれ、好き。
「勝手にやって梅酒」が無くなっていたので相方は残念がっていました。
面白いことに、辛口ブログの方と同じように感じたところもいくつかありました。思いつくままに言うと、玄関の靴ベラ、これいいと思いましたし、タオルを乾かすヒーターは珍しい、ですが自分は厚ぼったい機械よりも普通のタオルかけの方が好みですけどね。スタッフの方の対応が少し硬い。内風呂は気持ちが良い。すまし汁が少しぬるい。こんなところでしょうか。
宿の方の対応が少し硬いと書きましたが、皆さん立ち止まって笑顔で挨拶してくれますし、問題があるとは感じませんでした。一生懸命さからくる硬さのような気がします。うちの相方も中居さんと辻馬車の馬の名前がユキちゃんであるとか、金鱗湖の靄の話とかで盛り上がっていましたし、楽しく接客してもらったと思います。
初めてのお客さんだし、そこそこ硬さがあるのは仕方ないと思うんですよね。これが無かったのはやはり熱海小嵐亭のしずかさん。もうね、プロ。
相方がファンになったくらいで、なんなら握手をしてもらいたいくらいの勢いでしたね。そんな方もいました。
でもどうしても日本旅館の場合はそこに至るには何かしらの修行を経ないと難しいと思います。
またこれがホテルマンだと事情は違うと思うんですけどね。
ホテルというのはこちらが要求したことには完璧に応えるけど、なにも求めなければ何もしない。日本旅館はこちらが言う前に揃える、という印象ですけど。
ホテルはマニュアルに沿って個々人の要求を過不足なく、そのマニュアル感を出さずに満たしていく、旅館は客の動きに沿った環境をコントロールするというところが、もてなし方の違いかもしれないなぁと思う。
だからホテルの方がマニュアル化しやすい分プロ化もしやすい感じがする。
泊まってみれば結局、例えば、浴衣は目で測ってもらったようで大と特大を用意していただきましたが、できれば同じサイズを2枚置いてほしいなぁとか、灰皿が溜まれば取り換えてほしいとか、部屋で清算する宿もあるので何処でするか最初に教えてほしいとか、まあどうでもいいワガママはありますが、やはり全ては茅葺(かやぶき)の門から玄関までの気持ちの良い最初の印象、これが滞在時間全般を支配したように思います。
帰り際に友人に渡すためパンフレットとマッチをお願いしたのですが、頂いたその足で門まで見送っていただきました。
宿はそんな感じでしたけど、湯布院の町自体もユキちゃんの引っ張る辻馬車に乗って回ってきました。
知らない方、写ってますけどごめんなさい。

湯布院ってなにがあるの?と聞かれると温泉?由布岳?、大自然の中というわけでもないので答えにくいんですが、テーマパークもなく、歓楽街もなく、大規模旅館もないけれど、ただ道端にはコスモスの花が咲いているという、関東なら中央線のどっかの駅で降りたようなどこにでもある、まさしく「田舎」だったですね。







湯の坪通という賑やかな通りはありますが、どこの町でもメインストリートくらいはあり、無い方がむしろ不自然かもしれないです。そのかわりこの町は交差点でも信号がありません。
いろいろ問題を解決しながらこの田舎を守ってきたのでしょうけれど帰る時に乗った辻馬車の御者さんが、案内の話の中で「何とかやっていければいい(生活)」と言っていたことが印象に残りました。
ただ「田舎を守る」という戦略的な考えだけで湯布院の町づくりを行うのは、人の居ることですし、やはりそうは言っても難しかったのではないだろうかと思っていたのですが、なるほど、と腑に落ちました。
例えば一反一億円で土地を売ればその時は儲かるけれど、一億とはいえお金ですからいずれ無くなってしまうものです。そして田舎は戻ってこないわけです。
もちろん湯布院にもお金持ちは沢山いるはずですが、そういった経済力にかかわらずそれぞれの町の人が田舎を守りつつ「何とかやっていければいい」と暮らしていくことで、長い目でみれば一億円では足りないほど遠い先まで生活を続けていけるということになるのかもしれません。
そんなことを考えながら帰路に着くバスに乗り大分空港へ向かった、秋の夕暮れ。