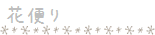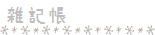ハイキング・旅行の記録
Mi diario
ペラリ山(新ひだか町) 2022年12月25日
天気予報が良くない週末はモチベーションがあがりませんが、希望を捨てず、じっくり見てゆくと天気の良い地域が見つかることがあります。週末が近づくにつれて日高地方や夕張辺りは晴れ予報になっていきました。どうしても行きたい山はこの時期にはなく、夕張の未踏の低山にしようと思っていましたが、静内のペラリ山を再訪したいとの話がありました。最近はすっかりご無沙汰の山域ですが、愛着のある山なの自分も行きたくなりました。”日高晴れ”を期待して新ひだか町へ。
道央自動車道を走り、苫小牧付近へ入ると、日高方面が明るくなっているのが確認できます。道央はどんよりとしていても、太平洋沿岸線は晴れている、冬季はこういうことが多い印象です。日高自動車道へ入ると、夕張岳が綺麗に見えるようになり、そして日高幌尻岳など北日高の山々も見えてきました。現地の青空だけでもいいと思っていましたが、山頂からは日高山脈の名峰を拝めるかもしれないと分かると、テンションが上がります。
新冠は街の手前でサラブレット銀座(道道209号線)へ入り、高江、朝日、大富、そして道道71号線(平取静内線)を走って新ひだか町静内豊畑地区へ。どんよりとした天気が続いてた札幌とは違い、新ひだか町は清々しい青空が広がり、気持ちがいい。新ひだか町に住んだ頃を思い出し、「そうそう、冬の日高はこうなんだ!」・・・と。

林道を歩きだす。
この地域にしては結構な積雪があります。

ペラリ山登山口。

登山口のあるコルから504m標高点へ向かって登る。

樹氷で白っぽくなったペラリ山が見えてきました。
標高536m付近、西尾根には一部作業道が付いている。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。

新ひだか町静内の街や太平洋が見えています。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
ペラリ山登山口への林道入り口に車を止めて出発です。以前はさらに車で入れましたが、すぐ先で倒木があり、道にも大きな雨裂が出来ています。これでは車は無理だろうと、ところが!今朝のものらしいタイヤの跡が付いています。倒木は斜めに倒れているので、背の低い車なら通れそうです。雨裂の方は普通車では無理ですが、ジムニーのようなものならいけるといえば行けるかも・・・?
積雪がありますが、おかげでタイヤの跡を歩いて楽ちん。昨日のものと思われる数名の足跡もあります。以前は登る人が滅多にいない山でしたが、登山ブームでこんな地味な山にも結構登山者が訪れるようになりました。
林道は364m標高点と400mポコを巻いて、370mコルが登山口。タイヤのあとは右の林道を進んでいるので、登山者のものではないようです。
トレースはほぼ夏道通りに付いているようですが、トラバース部分が滑りそうで嫌な感じです。急登を耐えて登った504m標高点から少し下りてコルからペラリ山の西尾根に取り付きます。あとはこのまま尾根に沿って登って行くだけですが、途中で作業道のようなものと合流します。この作業道は山頂付近までつづらについているようでが、夏道が付けられたこの山では使う必要もありません。
尾根を登り詰めると記憶にある大岩があり、そこからわずかに登ればペラリ山の山頂です。見上げると真っ青な空と樹氷が美しく、登頂の喜びが倍増されます。

これを登ったら山頂直下。

青空が美しい山頂へ。

天測点と山頂標識のあるペラリ山山頂。

天測点と遠景に輝く太平洋。

山頂標識と一等三角点の標石。
ペラリ山 719m 一等三角点 点名:比裸騾山(ぺららやま)

山頂標識より少し先に進むと日高山脈が見えます。
まずはスマホで景色全体。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。

ペラリ山山頂から北東方向、ピセナイ山とルベツネ山。ペテガリ岳はピセナイ山に隠れています。
ペラリ山がもう少し高かったら見えるのに・・・。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真

望遠で中ノ岳(1519m)
今日は鳥見の時に使うカメラ・レンズを背負ってきました。だから広角はスマホで。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。

1493m峰(ニシュオマナイ岳)、ピリガイ山(1167m)
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真

東方向へ目向けると、神威岳、ソエマツ岳、ピリカヌプリが見えます。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真

少しズームでソエマツ岳、神威岳。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真

もう少し視線を右にやると、トヨニ岳も見えてきました。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真

さらに右を見ると、南日高の山々が見えてきました。
トヨニ岳~広尾岳まで。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真

望遠でトヨニ岳。
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。

ピンネシリ、アポイ岳、さらに遠景に豊似岳(えりも町)
※画像をクリックすると別ウィンドウが開き大きなサイズで表示されます。
山名入りの写真
日高山脈は登ったことのある山より、登ったことのない山、私ではもう登れない山の方が多く、憧れの山域。こうして眺めだけでもワクワクしてきます。体調を整えて、登れる日が来るといいなぁ~と淡い期待を持ってはいますが、どうなるかな?
景色にとらわれてすっかり忘れていましたが、この山は一等三角点と天測点のある山です。Eさんが雪に埋まった標石を探しあてました。一等三角点の標石は上面の辺の長さが18センチ、二等・三等が15センチなのに対してひと回り大きいのです。見えている部分はわずかですが、この柱石は埋まっている部分の方がはるかに大きく重さは90キロ、そしてさらにその下には盤石があり重さは45キロにもなるそうです。どうやってここまで持ち上げたのでしょうね。というか、もっと高山の一等三角点はどうやって?
天測点は改めて調べてみると、道内に6ヶ所あるそうです。馬追山(長沼町)、篦射峰(稚内市)、和寒山(和寒町)、冠色樹山(足寄町)、社万部山(黒松内町)、当別丸山(北斗市)、そしてこのペラリ山。
天測点は一等三角点の傍に設けられた天文測量を実施するための基準点で、コンクリート製の観測台は機材を置くためにしっかりした作りになっているようです。
風のない暖かい場所で昼食を済ませて、下山します。
西尾根を下りていると、2名の登山が登ってきました。目立たない低山でしたが、割とメジャーな山になったようです。
西尾根は景色が開けている部分が多く、太平洋まで続く景色を楽しみながら良い気分。さらにもう1名の登山者とすれ違います。
登山口を過ぎて林道へ入ると、朝見たタイヤの跡が広がっています。どうやら車は今朝この林道を走り、私達が山へ登っている間に戻ってきて下りて行ったようです。崩れている部分もありなかなかスリルのあるドライブだと思いますが、林道を走り慣れているのでしょう。お互い無事に下山できたようで、良かった。
登山後の温泉は新冠温泉レコードの湯。ゆっくり温まって帰途に就く。
思いがけずの好天に恵まれ、楽しい山行でした。
*備忘録*
登り 約2時間半
下り 約1時間10分
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )
| « 買い物好き? | 野帳-お正月... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |