数年前、日本語の授業中に生徒にどんな本が好きかを聞いた。
一人の男子生徒は「指輪物語」と答えた。そして、彼はその本をもう5、6回読んだと言った。
当時、僕はなぜ同じ本を何度も読むのか、その行動の意味が全く理解できなかった。なぜなら、1回読んだら、ストーリーのほとんどが頭に入り、2回目に読む際に面白くないんじゃないかと思ったからである。
でも、今考えると、その考えは間違っていたと思う。
なぜなら、人間は僕が思っていたほど賢くないからである。人間は1回読んだら、内容やストーリーがすべて把握できるほど頭も良くないし、それほど記憶力が優れている訳ではない。
何回も何回も繰り返し読んで、初めてそのストーリーや内容が少しずつ頭に蓄積・記憶されていく。
そして、読む度に、見る度に、新しい発見をするものである。
だから、いい作品・著書は何度読んでも読み足りないのだ。何回も何回も読んで、その作品・ストーリー・内容を味わい、その作風・テーマを自分のものとして、習得していくのである。
そして、もし小説家になりたいのだったら、今度はその作品を読むだけでなく、真似して実際に書いてみることが大事である。また、漫画家になりたいのなら、自分の好きな漫画家の作品を模倣して描いてみる必要があるし、プロのバンドとして成功したいなら、好きなバンドのコピーバンドから始めるべきである。
とにかく、何になるにしても、好きな人の好きな作品を何度も何度も見たり読んだり聞いたりし、それ以後はとにかく模倣して自分でやってみる。
人を真似することは決して恥ずかしい事ではない。また、芸術は決して「無」から生まれる訳ではない。
昔読んだ『「超」発想法』(講談社、野口悠紀雄著)にも発想に関する基本5原則が書いてあった。
- 発想は既存のアイディアの組み換えで生じる。模倣なくして創造なし。
- アイディアの組み換えは頭の中で行われる。
- データを頭に詰め込む作業(勉強)がまず必要。
- 環境が発想を左右する。
- 強いモチベーションが必要。
骨の髄まで自分が好きな人の作品を真似し、そこに自分なりのプラスアルファーを付け加えれば、それで十分なのである。
これはポルトガル語の勉強でも同じである。人が書いている文章をたくさん読み、それを良い模範にしてひたすらその憧れの文章を真似て書く。
最初は猿まねでもいい。ずっと真似ていると、何か自分らしいものが「カタチ」として出てくるはずである。
乱読と精読。
この2つをうまく組み合わせてこそ、その人の個性が生まれるんだと思う。
何かを創造したい。











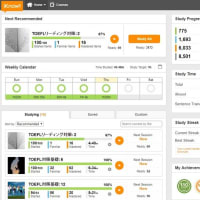



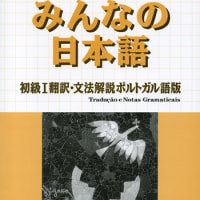
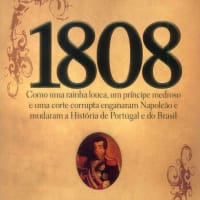
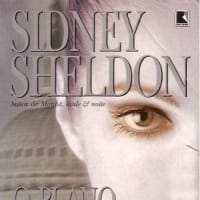



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます