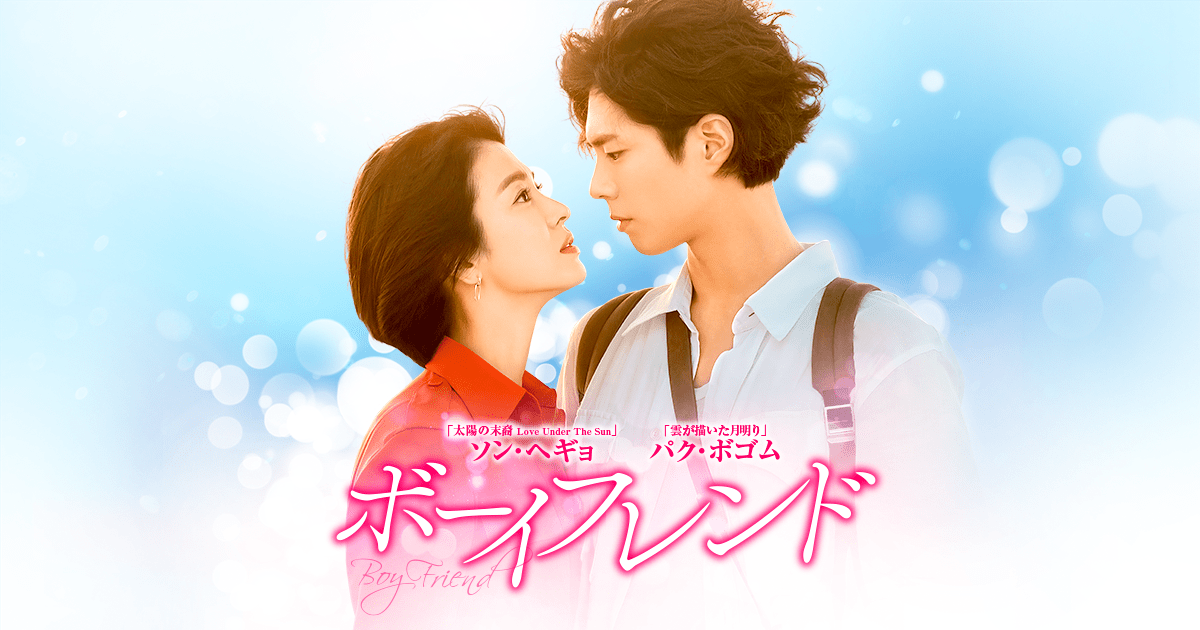どうして、そんなに騒ぐのだろう? 自分に直接関わりがない人たちのことを、ああだ、こうだ、言わなくてもいいのでは?。
週刊誌やテレビのワイドショーで、皇族やその関係者の動向が取り上げられる度、そんなふうに思っていた。
最近は、秋篠宮の長女・真子さんと結婚した小室氏の話題が週刊誌やネットで取り上げられることが多く、 小室さんの母親の金銭問題、小室さん自身の髪型や振る舞い、ニューヨーク州の司法資格試験の合否などの話題があった。皇室に対してそれほど関心が高いわけではない私でさえ、これらのニュースを目にして記憶している。
直接関わりのない一般の人が、自分や家族の動向について、ネット上でああだ、こうだと好き勝手に発言する状況を、ご本人たちはどんなふうに受けとめているのか?
不快だったり、嫌になることもあるのではないか? 皇族やその関係者として注目されることを「辞めたい」と考えた場合には、本人の選択で辞められる仕組みをつくることはできないのだろうか? そんなことを考えたこともあった。
高山文彦著の「ふたり 皇后美智子と石牟礼道子」(講談社文庫)は、前の天皇・皇后(現在の上皇・上皇后)が、熊本・水俣を訪れる機会に、当初予定になかった胎児性水俣病患者との対面を実現したことに注目し、その舞台裏を取材してまとめたノンフィクションだ。
母親のお腹の中にいる時に、水俣病の原因となる毒(メチル水銀)にさらされた胎児性水俣病患者は、生まれても長く生きられなかったり、重度の障害を抱えていたりする。彼らの親や家族も水俣病の症状に苦しんでいたり、差別を受けた経験のある人も少なくない。
当時の天皇・皇后が、どのような思いや考えを持って、胎児性水俣病患者に対面したのか。それは、その機会を調整した関係者や、実際にお二人に会った人々の話から、推し量るしかない。
本書に登場する水俣病患者や彼らを支える人々は、当時の天皇・皇后の言葉や行動に「救い」を感じている。
水俣病の症状に苦しみ、差別に苦しむ人生を生きてきた自分たちの存在を、「ずっと心の中に置いている」「忘れてなどいない」というメッセージをお二人の言葉や行動から読み取り、受けとめている。
私は、本書で紹介されているエピソードを通して、当時の天皇・皇后の言葉や行動が、法律や制度、補償などでは行き届かないところで苦しんでいる人々にとって「救い」や「支え」「力」になったことを知った。
皇族」といっても、天皇・皇后とその他の立場では役割が異なる点があるだろう。また、当時の天皇・皇后の人柄や考え方に依るものもある気はする。 私にとって「皇族」はワイドショーや週刊誌によるバッシングの対象という印象が強かったが、「皇族」という存在の意義や、彼らの役割について考えさせられる1冊になった。
ふたり 皇后美智子と石牟礼道子 (講談社文庫) | 髙山 文彦 |本 | 通販 | Amazon