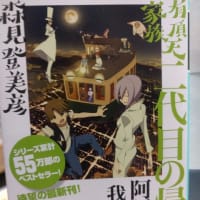| オルフ:カルミナ・ブラーナヨッフム(オイゲン),ヤノヴィッツ(グンドゥラ),シュトルツェ(ゲルハルト),フィッシャー=ディースカウ(ディートリッヒ),ベルリン・ドイツ・オペラ合唱団,シェーネベルク少年合唱団ポリドールこのアイテムの詳細を見る |
オイゲン・ヨッフム(1902-1987)は
「正当なドイツ音楽の継承者の一人」だと評されている。
最も得意なレパートリーはブルックナーとされ、
2度にわたって交響曲全集を録音し、
演奏会でも精力的に取り上げていたようである。
ドイツ音楽といえば比較しやすい個性は、
ベルリン・フィルの常任だったフルトヴェングラーとカラヤンであろうか。
たまたま、ブルックナーの8番の交響曲のディスクをそれぞれ所有している。
私の独断で簡単な感想を述べると、
フルトヴェングラーは遅くないが深く重く、爆発力は群を抜く。
カラヤン慎重なテンポで規模が大きく、幅が広い。
そしてヨッフム は、刺がなくスルスルときれいに流れて美しい。
三者三様で個性は違うけれど、ドイツ音楽の勘所というのか、
どの盤を聴いても引き込まれながらもゆったり聴けるものである。
ヨッフムで「美しい」としたのは、三者を比べて述べた特徴である。
それにしてもブルッ8(ぶるっぱち)はそれ自体美しい。
ヨッフムのブルックナーは、弦が力強く刻む上に乗っかって、
金管がきれいな和音を「ワー!」とやり、木管が裏で隠し味的に地味だ、
というような、それぞれがそれぞれの主張の仕方ではなくて、
「tuttiですよ~」という感じがしてくる。
全体で出てこようというときは、フォルテでもピアノでも、
みんな仲良く渾然一体となってポーンとボールを投げられるような感覚で
耳の中に入ってくる、とでも言えば分かって頂けるだろうか。
そんな「ブルックナーと言えば」と言われるヨッフムの録音で、
私が以前出遭って強い印象を受けたのが、オルフ「カルミナ・ブラーナ」 である。
この曲のディスクで人気がある(というか、有名である)のは、
フィリップスから出てる小沢征爾 の演奏かもしれない。
私はディスクは持っていないが、ベルリン・フィルのジルベスターコンサートの
番組録画を持っているので何度も聴いた。
小澤の演奏はよく完成されたというか洗練されたいうに相応しい。
ベルリンのジルベスターといえば、
近年に演奏されたラトルの演奏もよい演奏だと思う。
これもディスクはないが、録画がある。
小澤のようにテンポも音色も全体の構想もよく整っているというのでもないし、
あとで述べるヨッフムのとも違う味がある。
映像を見ればわかるが、音楽に間を置くとき、テンポを数えているというより、
完全に自分の間で静止しているように見える。
しかし、全体の秩序を損なうものでは決してなく、
むしろ音楽全体の面白みを出しているように思う。
さて、ヨッフムの盤は、変な意味ではなく土くさい感じがする。
きれいな旋律は言うまでもなくきれいだし、
ガチャガチャした部分はとてもガチャガチャしているし、
滑稽に遊ばせるようなところも、テクニックで満足に聴かせようとはせず、
とても自由に聴こえる。
とにかく素朴である。
ラトルのも自由な感じはするが、印象としてはラトルが自由である。
オルフの音楽はリズムを重視した原始主義が特質とよくいわれる。
この録音には、そのオルフ自身が監修しているということで、
そういう情報も頭に入れて考えれば、作品を最もよく理解した演奏かも知れない。
 | オルフ:カルミナ・ブラーナグルベローバ(エディタ),ベルリン・シュターツ&ドム少年合唱団,ハンプソン(トーマス),エイラー(ジョン)マーキュリー・ミュージックエンタテインメントこのアイテムの詳細を見る |
 | オルフ:カルミナ・ブラーナラトル(サイモン),マシューズ(サリー),ブラウンリー(ローレンス),ゲルハーヘル(クリスティアン),ベルリン放送合唱団,ベルリン州立及び教会児童合唱団EMIミュージック・ジャパンこのアイテムの詳細を見る |