老後資金7000万が早々に半減…青ざめる80歳前の親が月7万円も献上するしかない「働かない50歳長女」の浪費先2025/03/22 10:15PRESIDENT Online 掲載<
7000万円超あった両親の老後資金が13年間で半減してしまったのはなぜか。家計相談を受けたFPの畠中雅子さんは「原因は浪費家計にある。食費の次に支出額が大きいのは同居する50歳の長女への月5万〜7万円のこづかい。このままでは80歳手前の両親が他界する前に貯蓄は底を突き、同居する2人の働かない娘は生活保護を受けることになる」という――。
■アラフィフの娘2人が働けず、未来が描けない
関東地方に住む米田家には、働くことのできない2人の娘がいる。
次女(47)は双極性障害と診断され、障害年金(2級)を受給しているが、長女(50)は若いときから病院の受診を拒み続け、今までに診断を受けたことがない。
父親(78)が退職した65歳の時点では、米田家には7000万円を超える貯蓄があった。それが、退職してからの13年間で、半分くらいにまで減ってきている。毎月の赤字が10数万円で、車の維持費や固定資産税、家電の買い替え費用などの特別支出を加えると、年間の赤字額は200万円を超えている。年間赤字の多さが、貯蓄が速いペースで減ってきている原因である。
【米田家の家族構成】
父親・78歳
母親・77歳
長女・50歳(無職)
次女・47歳(無職)障害年金受給中
【米田家の資産状況】
現在の貯蓄
父親 2800万円
母親 800万円
計 3600万円
自宅は持ち家(築33年)
【米田家の収入】
年金額
父親 月16万円
母親 月5万円
世帯計 月21万円
※次女の障害年金(月6万8000円)は本人がこづかいなどに充当
【米田家の支出】
(生活費 内訳)
食費 13万円
日用品 2万円
電気・ガス・水道代 3万円
通信費(スマホ3人分+Wi-Fi) 2万円
こづかい(夫) 2万円
こづかい(妻) 2万円
こづかい(長女) 5万〜7万円
医療費 2万円
交通費 1万円
ガソリン代 1万円
教養娯楽費(新聞代、NHK代含む) 2万円
月約35万〜37万円
赤字の原因のひとつは、月5万〜7万円の長女のこづかいにある。長女は、韓国のヴォーカルグループに傾倒しており、推しグッズを集めたり、イベントに参加したりするために、年に2回ほど、訪韓している。長女は無職なので、推し活の原資は親からのこづかいだ。月のこづかいを貯めて、訪韓費用に充てているそうだが、追加で無心されることもある。
結婚を親に反対されたから、私の人生はおかしくなった
米田家の赤字の原因となっている長女のこづかいについては、「金額を減らすべき」というアドバイスをするのは簡単なことだし、まっとうなことだろう。しかし、長期間働いていない女性の場合、一筋縄ではいかないケースが多い。米田家においても、長女はある理由から親を恨んでおり、親を苦しめることで、自分自身の精神を保っている面があるからだ。
長女の成育歴をご紹介しよう。高校までは、ごく平均的な女性だったらしい。社交的ではないものの、友達もいる、どこにでもいるような学生だったという。高校卒業後は、短大に進学。短大卒業後は、食品メーカーで4年ほど働いた。
食品メーカーで働いているとき、「結婚したい」と思える男性と出会って、交際。長女は結婚を強く望んだが、その相手は定職を持たないフリーターであった。「結婚しても、生活が成り立たないのではないか」と心配した両親は長女の結婚を反対し、結果として破局してしまった。
両親の反対だけが破局の原因ではなかったかもしれないが、「両親が結婚を反対したせいで、私の人生はここまでこじれてしまった」と、長女は今でも感じている。フリーターの彼と別れた後、長女は精神的に不安定となり、仕事に行けなくなった。数カ月、休職をした後に退職。その後3年くらいは自室にひきこもり、両親との接触も避けて暮らしてきたそうだ。
親として、定職を持たない相手との結婚を反対するのは、ほめられた行いでないかもしれないが、理解できる部分もあるように思う。だが、結婚まで考えていた相手との破局が、長女の人生を大きく変えてしまった。その原因はすべて親にあると、長女は考えている。
「親を心の底から強く恨む」。これは米田家のケースに限らず、女性のひきこもりでは、よく見受けられるケースといえる。
次女は双極性障害と診断され、障害年金を受給中
次は、米田家のもう一人の娘。次女に話を移そう。次女は小さいころから内気で、学校になじめなかった。中学生のときは不定期に学校に通うなど、不登校気味であった。高校には進学したものの、2年生の夏休み明けに退学した。高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)を受ける話もあったが、実際には試験を受けずに現在に至っている。
高校を中退したあとしばらくは、自宅から出られない時期もあったが、病院の受診にはつながっていた。病院を受診した結果、20代前半に双極性障害と診断されて、障害年金の受給につながった。障害年金がもらえてからは、自分のためにお金を使えるようになったので、今では外出ができるようになっている。ただし次女は、人生で一日も働いた経験がなく、今後も働く意思はないという。
■「老後破産が起こりかねない」リタイア後の13年で、貯蓄が半減
ここからは少し、両親との相談の一部をご紹介していく。
【畠中】次女さんは、障害年金を貯蓄されていますか?
【母親】それほどお金を使う子ではないので、ある程度は口座に残していると思います。
【畠中】できれば、次女さんの口座にいくらくらい障害年金が残っているのかを確認してほしいのですが、可能でしょうか?
【母親】今まで、次女とお金の話をしたことがないので難しいのですが、タイミングを見計らって聞いてみます。
【畠中】次女さんは障害年金をある程度貯めておいてもらわないと、親亡き後の生活が厳しいと思います。自由に使わせるのは、将来のリスクにつながることを認識してもらう必要がありますね。そして、次女さんより問題が大きい長女さんのことですが、長女さんとは、話をしたり、食事を一緒にしたりすることはできていますか?
【母親】この10年くらいは、多少の会話はできていますし、食事も一緒に取っています。ただ、結婚や彼氏など、長女が嫌う話題がテレビから流れてきたりすると、いきなりキレて部屋に戻ったりしていますので、一般的なご家庭とは関係性が異なると感じています。
【畠中】長女さんにとっての地雷を踏まないように、ビクビクしながら暮らされているわけですね。ただ、今のままの暮らしを続けていると、あと13〜15年くらいで貯蓄が底を突いてしまいます。ご両親とも現在70代後半ですが、どちらかがご存命のうちに、老後破産が起こりかねない状況です。そのあたりの危機感について、ご夫婦ではどのように認識されていますか?
「食費はなぜ、13万円もかかっているんですか?」
【父親】60歳で退職金を受け取り、65歳まで働いていたので、そこそこ貯蓄もできたと思っていました。そのため年金生活に入ってから、これほど早く、貯蓄が減るとは思ってもいませんでした。長女のこづかいを減らしたいのはやまやまですが、行動を改めてもらうような話をしようとすると、いきなり別人のようになってキレてしまうので、なかなか話を進められない状況で困っています」
【畠中】長女さんと話し合うとしても時間は相当かかるはずですので、まずは親側ができる節約を実行しましょう。食費はなぜ、13万円もかかっているんですか?
【母親】長女も次女も偏食でして、親とは別メニューにすることが多いんです。また、スイーツなどをある程度冷蔵庫に入れておかないと、長女の機嫌が悪くなるので、つい多めに買ったりしています。
【畠中】食費が多い理由はわかりましたが、親亡き後は今のようにはいかないですよね。2人とも、たとえばひとり2万5000円などのお金を食費予算として渡して、自分たちで食事を賄ってもらうように促してはいかがでしょう。お子さんたちの顔色をうかがわず、「もう決めたことだから、親はご飯を作りません」と強く言い聞かせることも大切です。
■ご飯作らないと言ったら…「娘たちがキレたりしないでしょうか」
【母親】そんなことをしたら、娘たちがキレたりしないでしょうか。
【畠中】キレるかもしれませんが、キレることに怯えて、いつまでも言いなりになっているほうが、娘さんたちにとっては良くない状況です。たとえば食費は娘さん2人で5万円、ご両親は2人で4万円の合計9万円に減らすことから始めてもらえませんか。年金暮らしのご家庭で、夫婦の食費予算が4万円というのは、よくあるケースですので。
【母親】そのほかの費目で、減らしたほうが良いものはありますか?
【畠中】日用品の月2万円も、年金暮らしでは多いですね。この金額の中には、長女さんの支出も含まれていますか。
【母親】はい、長女がお皿やら、カトラリーといった生活用品をよく買ってきます。買うたびに請求されていますが、お皿などはこれ以上増えても困るので、買わないようには言っているんですが。
【畠中】今さらお皿やカトラリーを増やしても、仕方がないと思うんです。もしほしい生活用品があるのなら、「食費の中でやりくりして買ってね」というのが、順当ですね。そして、1日でも早く、何とかしたいのが長女さんのおこづかいですが、(現状の5万〜7万円から)1万〜1万5000円くらいに減らせると、貯蓄が減るペースがかなり緩やかになります。その話し合いは不可能でしょうか。
【父親・母親】…………。
娘たちの理解を得るか、生活保護の道を模索するか
米田家のように、親に対して強い恨みを持っている場合、残念ながら常識的なアドバイスが通用しないのが通例だ。米田家は、食費や日用品の金額も多いので、まずは生活費の見直しから着手してもらえるように促した。
食費の見直しや長女のこづかいの減額が実現しない場合、親が存命中に貯蓄が底を突く可能性もあるし、最悪、お葬式代すら残らないかもしれない。両親といろいろ話していても、長女と向き合う覚悟が持てるようには思えなかったため、米田家の将来は生活保護の受給も検討しなければならないだろう。
【畠中】今のまま、何も手を打たないと、娘さんたちは生活保護の申請をしなければならないかもしれません。米田さんはご自宅をお持ちですが、米田さんのご自宅の評価額であれば、自宅に住んだまま、生活保護の受給は可能だと思われます。ただ、家賃に当たる住宅扶助はもらえないという仕組みですが、生活保護がスタートすると、固定資産税は免除されます。
【父親】家を持っていても、生活保護は受給できるんですか。
【畠中】居住地の自治体ごとに、家を保有しても良い基準価格(評価額)が決まっているので、その金額以下であれば、生活保護の受給は可能です。ただし、家が基準以下であっても、畑など、他の不動産がある場合は、自宅以外は売却して、そのお金をしばらく生活費に充てることになりますが。
■「長女も次女も、働くのは無理だと思います」
【父親】娘たちが家に住み続けられるのは、安心材料です。
【畠中】安心材料かもしれませんが、築年数を考えますと、今の家に娘さんたちの人生の終わりまで、今の家に住み続けられるかはわかりませんし、次女さんが障害年金を受給されているので、その分は生活保護費から差し引かれます。また、障害年金を受給されている次女さんの場合は、それほど厳しく言われないと思いますが、障害年金をもらっていない長女さんの場合、生活保護の受給はできても、65歳頃までは働くことを促されます。働くことを拒否し続けると、生活保護が途中で停止される可能性もあります。「一生、働かずに生活保護で生きる」というのも、実は簡単ではないんです。
【母親】長女も次女も、働くのは無理だと思います。
【畠中】無理だと思うなら、まずは親御さんが、生活保護制度についてきちんと調べることをお勧めします。たとえば全財産が10万円を切ったくらいでないと、生活保護の申請は難しいのですが、米田家の場合、次女さんの口座に障害年金がある程度貯まっていきますよね。その場合、長女さんの貯蓄はゼロだとしても、生活保護の申請はできないんですね。次女さんの口座のお金が底を尽きかねないと申請ができないわけですから、親亡き後は生活保護のお世話になるとしても、まずは親側が正しい知識を得ることが欠かせません。
生活保護を想定するなら、制度の詳細を知る努力が欠かせない
ここ数年、ひきこもり家族からの家計相談を受けていると、生活保護に頼らないと、親亡き後の生活が成り立たないだろうと思われるケースが増えていると肌で感じる。ところが、生活保護の正しい知識を得ようとしない人が多すぎる。親が亡くなった後、「いつか、親切な誰かが、申請を手伝ってくれるだろう」と楽観視する人も少なくない。
米田家の場合、仮に将来は生活保護のお世話になるとしても、現時点で生活コストの大幅な削減が必要である。長女の気分に配慮して、何も策を打たないままだと、10年くらいの時間はあっという間に過ぎてしまうからだ。
働けない子どもが生活保護に頼ることを「良いか悪いか」という二者択一で判断するのは難しい。ただ、明らかに「悪い」のは、子供がいずれかが「生活保護のお世話になるだろう」と考えているのに、親が生活保護の詳細を知ろうとしないことだ。
親の資産だけでは、子どもの生活が成り立たない家庭では、生活保護の正しい知識を身に付けることをお勧めする。それが子供への最後の置き土産でもなるのだから。
畠中 雅子(はたなか・まさこ)氏_ファイナンシャルプランナー
「働けない子どものお金を考える会」「高齢期のお金を考える会」主宰。『お金のプロに相談してみた! 息子、娘が中高年ひきこもりでもどうにかなるってほんとうですか? 親亡き後、子どもが「孤独」と「貧困」にならない生活設計』など著書、監修書は70冊












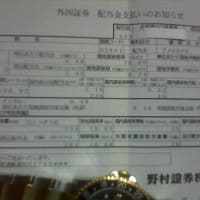

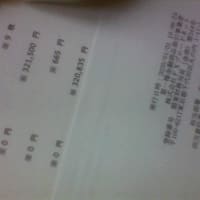
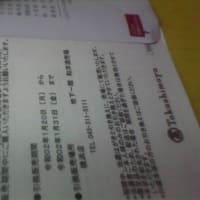

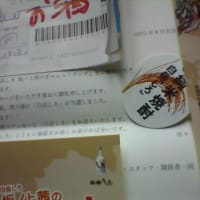

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます