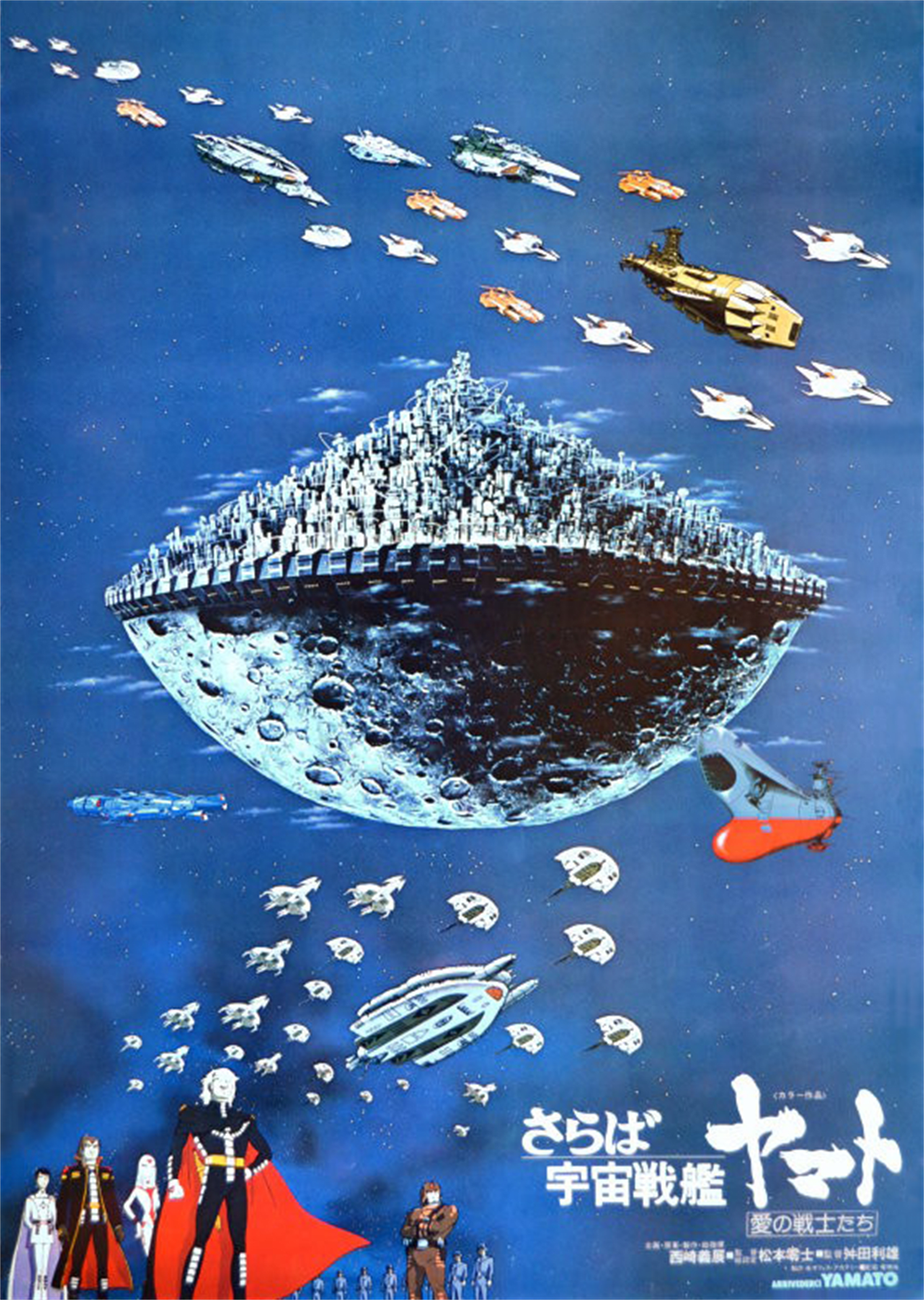[ 2025年07月03日 01時02分 公開 ]
source
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅲ 7/15
2025-05-07 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_z/e/243552adb3d3f60f179c8eed4d679c7c
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 1/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/1d7cf04fa7f71cb9ebac184e9b6d5371
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 2/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/c1ff00d44010e2e1b792d5d326609930
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 3/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/13a3803707ab7bd76eb2c74efa22429b
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 4/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/596daf88e4f0a6b4814c34131bac264e
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 5/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/e010a8b0d30c37a603788b5eedfc5881
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 6/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/967997c2b1c52c752d59014f6f8c0197
https://ja.wikipedia.org/wiki/良忍
〉
良忍(りょうにん、延久5年1月1日(1073年2月10日)? - 天承2年2月1日(1132年2月19日))は、平安時代後期の天台宗の僧で、融通念仏宗の開祖。聖応大師。
-
https://ja.wikipedia.org/wiki/融通念仏宗
〉
融通念仏宗(ゆうずうねんぶつしゅう)は、日本の仏教における宗派の一つ。明治時代に策定された代表的な宗派である十三宗に含まれる。総本山は大念仏寺。
平安時代末期の永久5年5月15日(1117年6月16日)に天台宗の僧侶である良忍が大原来迎院にて修行中、阿弥陀如来から速疾往生(阿弥陀如来から誰もが速やかに仏の道に至る方法)の偈文「一人一切人 一切人一人 一行一切行 一切行一行 十界一念 融通念仏 億百万編 功徳円満」を授かり開宗した。近世には大念仏(だいねんぶつ)といわれた。
総本山
総本山である大念仏寺は、大治2年(1127年)に鳥羽上皇の勅願により、宗祖良忍が開創した。坂上田村麻呂の次男で、平安時代にこの地域を開発したといわれる「平野殿」こと坂上広野の私邸内に建てられた修楽寺が前身と伝わる。日本最初の念仏道場である。
融通念佛宗総本山 大念佛寺
https://www.dainenbutsuji.com
https://www.google.com/maps/place/大念佛寺
https://ja.wikipedia.org/wiki/法然
〉
法然(ほうねん)は、平安時代末期から鎌倉時代初期の日本の僧である。はじめ山門(比叡山)で天台宗の教学を学び、承安5年(1175年)、専ら阿弥陀仏の誓いを信じ「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えれば、死後は平等に往生できるという専修念仏の教えを説き、後に日本浄土宗の宗祖と仰がれた。法然は房号で、諱は源空げんくう、幼名を勢至丸[2]、通称は黒谷上人、吉水上人とも。
諡号は、慧光菩薩・華頂尊者・通明国師・天下上人無極道心者・光照大士である[注釈 2][2]。
-
https://ja.wikipedia.org/wiki/浄土宗
〉
浄土宗(じょうどしゅう)は、大乗仏教の宗派のひとつである。浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で、法然を宗祖とする。鎌倉仏教のひとつ。
本尊は阿弥陀如来(舟後光立弥陀・舟立阿弥陀)。教義は専修念仏を中心とする。浄土専念宗とも呼ばれる。
白旗派を中心とし知恩院を総本山とする現在の浄土宗の他、浄土宗西山派 (西山浄土宗、浄土宗西山禅林寺派、浄土宗西山深草派)もあり、法然の高弟親鸞が開いた浄土真宗も同一系統の宗派である。
浄土宗【公式サイト】
https://jodo.or.jp
https://ja.wikipedia.org/wiki/知恩院
〉
知恩院(ちおんいん)は、京都市東山区林下町にある浄土宗の総本山の寺院。山号は華頂山(かちょうざん)。本尊は法然上人像(御影堂)および阿弥陀如来像(阿弥陀堂)。開山は法然である。正式呼称は華頂山知恩教院大谷寺(かちょうざん ちおんきょういん おおたにでら)[2]。
浄土宗の宗祖・法然が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた寺院で、現在のような大規模な伽藍が建立されたのは江戸時代以降である。徳川将軍家から庶民まで広く信仰を集め、今も京都の人々からは親しみを込めて「ちよいんさん」「ちおいんさん」と呼ばれている。
なお他流で門跡に当たる当主・住職を、知恩院では浄土門主(もんす)と呼ぶ。浄土門主・法主推戴委員会により推戴される。
浄土宗総本山 知恩院
https://www.chion-in.or.jp
総本山 知恩院 Google Maps
https://www.google.com/maps/place/知恩院
https://ja.wikipedia.org/wiki/親鸞
〉
親鸞(しんらん、承安3年4月1日 - 弘長2年11月28日 [注釈 6])は、鎌倉時代前半から中期にかけての日本の僧。親鸞聖人と尊称され、鎌倉仏教の一つ、浄土真宗の宗祖とされる[注釈 7]。
法然を本師と仰いでから生涯に亘り、「法然によって明らかにされた浄土往生を説く真実の教え[1]」を継承し、さらに高めて行く事に力を注いだ。自らが開宗する意志は無かったと考えられる。独自の寺院を持つ事はせず、各地に簡素な念仏道場を設けて教化する形をとる。その中で宗派としての教義の相違が明確となり、親鸞の没後に宗旨として確立される事になる。浄土真宗の立教開宗の年は、『顕浄土真実教行証文類』(以下、『教行信証』)の草稿本が完成した1224年(元仁元年4月15日)とされるが、定められたのは親鸞の没後である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/親鸞#出家
〉
出家
治承5年(1181年)9歳、叔父である日野範綱に伴われて京都青蓮院に入り、後の天台座主・慈円(慈鎮和尚)のもと得度して「範宴」(はんねん)と称する。
-
叡山修学
出家後は叡山(比叡山延暦寺)に登り、慈円が検校(けんぎょう)を勤める横川の首楞厳院(しゅりょうごんいん)の常行堂において、天台宗の堂僧として不断念仏の修行をしたとされる。叡山において20年に渡り厳しい修行を積むが[11]、自力修行の限界を感じるようになる。天台宗は「法華経」を重視した宗派だったが、そもそも「八幡太郎」の嫡流は八幡神社思想が「三つ子の魂」で「法華経」はなじまなかったという学説がある。
建久3年(1192年)7月12日、源頼朝が征夷大将軍に任じられ、鎌倉時代に移行する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/浄土真宗
〉
浄土真宗(じょうどしんしゅう)は、大乗仏教の宗派のひとつで、浄土信仰に基づく日本仏教の宗旨で[1]、鎌倉仏教の一つである。鎌倉時代初期の僧である親鸞が、その師である法然によって明(顕)らかにされた浄土往生を説く真実の教え(顕浄土真実)[2]を継承し展開させる。親鸞の没後に、その門弟たちが教団として発展させた。
https://ja.wikipedia.org/wiki/浄土真宗#宗派
〉
宗派
現在、真宗教団連合加盟の10派ほか諸派に分かれているが、宗全体としては、日本の仏教諸宗中、最も多くの寺院(約22000か寺)、信徒を擁する。
所属寺院数は、開山・廃寺により変動するため概数で表す[注釈 12]。
真宗十派(真宗教団連合)
真宗教団連合は、親鸞聖人生誕750年・立教開宗700年にあたる1923年(大正12年)、真宗各派の協調・連携を図る為に、真宗各派協和会として結成された。加盟団体は以下の10派であり「真宗十派」といわれる。
https://ja.wikipedia.org/wiki/西本願寺
〉
西本願寺(にしほんがんじ)は、京都市下京区本願寺門前町にある浄土真宗本願寺派の本山の寺院。山号は龍谷山(りゅうこくざん)。本尊は阿弥陀如来。正式名称は龍谷山本願寺、宗教法人としての名称は本願寺である。本願寺住職は浄土真宗本願寺派門主を兼務する。真宗大谷派の本山である東本願寺(正式名称「真宗本廟」)と区別するため、両派の本山は通称で呼ばれることが多い。京都市民からはお西さんの愛称でも親しまれている。
文永7年(1272年)、親鸞の廟堂として京都東山の吉水の地に創建された。その後、比叡山延暦寺から迫害を受けるなど場所は転々とし、現在地には天正19年(1591年)、豊臣秀吉の寄進により大坂天満から移転した(詳細は後述「歴史」の項参照)。
2023年より銀杏と御影堂、阿弥陀堂の2つのお堂をモチーフにしたブランドロゴとともに、「人はひとり。だからこそ、ご縁を見つめたい。」をタグラインとして定めている[1]。
お西さん(西本願寺)-本願寺への参拝(参る・知る・観る)
https://www.hongwanji.kyoto
Google Maps
https://www.google.com/maps/place/西本願寺
https://ja.wikipedia.org/wiki/東本願寺
〉
東本願寺(ひがしほんがんじ)は、京都市下京区にある真宗大谷派の本山の寺院[1]。山号はなし。本尊は阿弥陀如来。正式名称は真宗本廟(しんしゅうほんびょう)[2][3]である。東本願寺の名は通称であり、西本願寺(龍谷山本願寺)に対して東に位置することに由来している。愛称は「お東」「お東さん」。2020年(令和2年)7月現在の門首は、大谷暢裕(修如)。
真宗大谷派(東本願寺)
https://www.higashihonganji.or.jp
Google Maps
https://www.google.com/maps/search/東本願寺
https://ja.wikipedia.org/wiki/大谷本廟
〉
大谷本廟(おおたにほんびょう)は、京都市東山区にある浄土真宗本願寺派の本山の本願寺が所有する墓地。浄土真宗の宗祖・親鸞の墓所。通称は、「西大谷[1]」。
大谷本廟は、「日野誕生院」・「角坊」(すみのぼう)とともに「宗教法人 本願寺」が所有する飛地境内である[2]。
概要
大谷本廟は、文永9年(1272年)に東山大谷の地に建立された親鸞の廟堂である「大谷廟堂」(後の大谷本願寺)に由来する。
-
大谷本廟【西大谷】
https://otani-hombyo.hongwanji.or.jp
Google Maps
https://www.google.com/maps/place/大谷本廟
https://ja.wikipedia.org/wiki/一遍
〉
一遍(いっぺん、英語: IPPEN)は、鎌倉時代中期の僧侶。時宗の開祖。全国各地で賦算(ふさん)と呼ばれる「念仏札」を渡し、踊りながら南無阿弥陀仏(念仏)と唱える「踊り念仏」を行った。徹底的に自身の所有物を捨てたことで「捨聖(すてひじり)」とも呼ばれた。
-
https://ja.wikipedia.org/wiki/時宗
〉
時宗(じしゅう)は、鎌倉時代末期に興った浄土教の一宗派の日本仏教。開祖は一遍。鎌倉仏教のひとつ。総本山は神奈川県藤沢市の清浄光寺(通称遊行寺)。
https://ja.wikipedia.org/wiki/時宗#思想
〉
思想
浄土教では阿弥陀仏への信仰がその教説の中心である。融通念仏は、一人の念仏が万人の念仏と融合するという大念仏を説き、浄土宗では信心の表れとして念仏を唱える努力を重視し、念仏を唱えれば唱えるほど極楽浄土への往生も可能になると説いた。 時宗では、阿弥陀仏への信・不信は問わず、念仏さえ唱えれば往生できると説いた。仏の本願力は絶対であるがゆえに、それが信じない者にまで及ぶという解釈である。
時宗(時衆)の語源は、「日常を臨命終「時」(臨終)と心得て、常に念仏を唱える故に「時」宗といわれる」とする説もあるが、時宗総本山の遊行寺のウェブサイトには念仏を中国から伝えた善導大師が時間ごとに交代して念仏する弟子たちを「時衆」と呼んだ事が起源である、と明記されている[2]。
-
時宗総本山 遊行寺
http://www.jishu.or.jp
遊行寺と藤沢
http://www.jishu.or.jp/yugyouji-engi/fujisawa/
〉
-
現在の「遊行寺坂」は、例年1月2日と翌3日の2日間に行われる箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)のコースになっています。選手を応援する方々が沿道に詰めかける様子は、まさにこの浮世絵のようです。
Google Maps
https://www.google.com/maps/place/清浄光寺(遊行寺)
https://ja.wikipedia.org/wiki/題目
〉
題目(だいもく)とは、日蓮系・法華経系の宗教団体などにおいて勤行の際に用いられる南無妙法蓮華経の文句のことである。「お題目」とも言う。元来は題名(だいめい)の意であり、法華経(サッダルマ・プンダリーカ・スートラ)の翻訳題(あて字)である妙法蓮華経(鳩摩羅什による訳)の五字のことを指しているが、南無(帰依するの意)を加えて七字にしても「題目」と呼ぶ。
なお、お題目は、建前の意味で使用されることもある。ここでは、上記いずれについても記載する。
題目とは
「南無」はサンスクリット語のnamoの音写である。「帰命」とも訳される。
「妙法蓮華経」は鳩摩羅什が漢字に翻訳した法華経一部八巻二十八品の題目(題名)の五字である。
「妙法蓮華経」の五字を本仏の名号と見なして南無(帰命)する言葉として、「南無妙法蓮華経」すなわち漢字七字の題目が生まれた。「南無妙法蓮華経」とは、妙法蓮華経(法華経)の法・御教え(みおしえ)に帰依することである。
既に平安時代中期の天台宗では称名念仏の影響で題目も唱える様になっていたが、題目そのものが教義に組み込まれることは無かった。
題目そのものを教義に組み込んだのは日蓮が最初であり、当時流行の称名念仏への対抗策として浮上したものとみられる[1]。
各団体における詳細
連続して「南無妙法蓮華経」と繰り返し唱える修行を「唱題(しょうだい)」という。
法華経系の宗門では、様々な修行の中、この「唱題行」を「正行」と呼び、最も重視している。他に、滝に打たれたり、断食行や無言の行を行ったりしても、それは「助行」と呼ばれ、補助的な修行方法に過ぎない。
https://ja.wikipedia.org/wiki/マントラ
〉
マントラ(मन्त्र Mantra)は、サンスクリットで、本来的には「文字」「言葉」を意味する。真言と漢訳され、大乗仏教、特に密教では仏に対する讃歌や祈りを象徴的に表現した短い言葉を指す。
『愛染明王真言』
不動明王真言108遍 (慈救呪)不動護摩と法楽太鼓アリ 開運厄除け
念仏一会 浄土宗
霊山のつどい(唱題行)令和4年8月27日
https://hi.wikipedia.org/wiki/मन्त्र
Google 翻訳
https://hi-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/मन्त्र
〉
伝統的に、ヴェーダのリチャはマントラと呼ばれています。さらに、インド起源の宗教の古代のテキストに見られる短いフレーズ、文章、または詩はマントラと呼ばれます。グルによって教えられた主な事柄はマントラとも呼ばれます。リグ・ヴェーダ・サンヒターには約 10,552 のマントラが含まれています。「オーム」自体はマントラであり、地球上で最初に生成された音であると信じられています。
-
https://ja.wikipedia.org/wiki/阿吽
〉
阿吽(あうん、サンスクリット語: अहूँ、a-hūṃ)は、仏教の真言の一つ。「阿呍」とも表記する。
意味
古代インドのサンスクリットの悉曇文字(梵字)において、a(阿)は全く妨げのない状態で口を大きく開いたときの音、m(hūṃ、吽)は口を完全に閉じたときの音である[1]。悉曇文字の字母の配列は、口を大きく開いたa(阿)から始まり、口を完全に閉じたm(hūṃ、吽)で終わっており、そこから「阿吽」は宇宙の始まりから終わりまでを表す言葉とされた[1]。宇宙のほかにも、a(阿)を真実や求道心に、m(hūṃ、吽)を智慧や涅槃にたとえる場合もある。
阿吽は宗教的な像にも取り入れられ、口を開けた阿形(あぎょう)と口を閉じた吽形(うんぎょう)の一対の像は、神社の狛犬(本来は獅子と狛犬の一対)などにみられる[1]。また、寺社の金剛力士像(仁王像)や沖縄のシーサーなどにも口を開けた阿形と口を閉じた吽形がみられる。
日本語では2人の人物が呼吸まで合わせるように共に行動しているさまを阿吽の呼吸、阿吽の仲などと呼ぶ。
阿吽 (English 版)
https://en.wikipedia.org/wiki/Om#Japanese_Buddhism
Google 翻訳
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Om Japanese_Buddhism
〉
日本の仏教
阿吽
参照:Om mani padme hum
阿吽(あうん)という用語は、デーヴァナーガリーでअहूँと 書かれる2つの音節「a」と「hūṃ 」の日本語への音訳である。日本語では、しばしば音節「Om」と混同される。元のサンスクリット語は、 デーヴァナーガリー文字のabugidaの最初の文字( अ)と最後の文字( ह )の2つの文字で構成されており、後者には「hūṃ 」の「 -ūṃ 」を示す分音記号(anusvaraを含む)が付いている。これらは一緒になって、すべてのものの始まりと終わりを象徴的に表す。[ 119 ]日本の密教では、文字は宇宙の始まりと終わりを表す。[ 120 ]これはギリシャ語アルファベットの最初と最後の文字であるアルファとオメガに匹敵し、キリスト教ではキリストをすべての始まりと終わりとして象徴するために同様に採用されています。
「阿吽」という用語は、一部の日本語表現で比喩的に「阿吽の呼吸」または「阿吽の仲」として使用され、本質的に調和のとれた関係または非言語コミュニケーションを示します。
仁王と狛犬
詳細は「仁王と狛犬」を参照
この用語は仏教建築や神道においても、日本の宗教的な場でよく見られる一対の像、特に仁王と狛犬を指すのに用いられる。[ 119 ]片方(通常は右側)は口を開けており、仏教徒はこれを「あ」の字を象徴するものとして捉えている。もう片方(通常は左側)は口を閉じており、これは「吽」の字を象徴するものとして捉えている。この二つを合わせると「あ・うん」と発音すると考えられる。口を開けた像は一般に「阿形(あぎょう)」、口を閉じた像は「吽形(うんぎょう)」と呼ばれる。[ 119 ]
日本の仁王像や東アジアの仁王像は、仏教寺院の門や仏塔の前に、2体の恐ろしい守護王(金剛般若)の姿で一対で置かれる。[ 117 ] [ 118 ]
狛犬は日本、韓国、中国に見られ、仏教寺院や公共の場所では一対で置かれており、一方は口を開けており(阿形)、もう一方は口を閉じています(吽形)。[ 121 ] [ 122 ] [ 123 ]
( 阿吽 English 版 )
https://en.wikipedia.org/wiki/Om
Google 翻訳
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Om
〉
Om(またはAum ;聞くⓘ ;サンスクリット語:ॐ, ओम्、ローマ字表記: Oṃ, Auṃ、ISO 15919:Ōṁ) は、ヒンドゥー教における神聖な音、音節、マントラ、祈願を多義的な。 [ 1 ] [ 2 ]その書かれた形は、ヒンドゥー教で最も重要な記号である。 [ 3 ]それは、至高の絶対、 [ 2 ]意識、 [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]アートマン、ブラフマン、または宇宙世界の本質である。 [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]インドの宗教では、オームはヴェーダのの基準救済のの中心的な側面。 [ 10 ]これは、解脱へのヨガの道における瞑想の基本的なツールです。 [ 11 ]この音節は、ヴェーダ、ウパニシャッド、その他のヒンドゥー教のテキストの章の冒頭と末尾によく見られます。 [ 9 ]これはすべてのヴェーダの目標として説明されています。 [ 12 ]
オムはヴェーダ文献から生まれ、サマヴェーダの詠唱や歌を要約した形だと言われています。 [ 1 ] [ 10 ]オムは、霊的テキストの朗誦の前や最中、プージャや個人的な祈りの最中、結婚式などの通過儀礼 (サンスカーラ) の儀式、プラナヴァヨガなどの瞑想的、霊的活動の最中に行われる神聖な霊的呪文です。[ 13 ] [ 14 ]オムは、ヒンズー教、仏教、ジャイナ教、シク教の古代および中世の写本、寺院、僧院、霊的リトリートで見られる図像の一部です。[ 15 ] [ 16 ]ヒンズー教、仏教、ジャイナ教では、音節として、単独で、または霊的朗誦の前や瞑想中によく唱えられます。[ 17 ] [ 18 ]
-
( Om 日本語版 )
https://ja.wikipedia.org/wiki/オーム_(聖音)
〉
オーム(ओम् om、または ॐ oṃ〈オーン〉)は、バラモン教をはじめとするインドの諸宗教において神聖視される呪文。
漢訳仏典では、唵(おん、口偏に奄)と音写される。
なお、日本では「オーム」と表記する事が多いが、oṃは「オーン」と読み[1]、omは「オーム」である。
解釈
バラモン教
ヴェーダを誦読する前後、また祈りの文句の前に唱えられる。 ウパニシャッドにおいては、この聖音は宇宙の根本原理であるブラフマンを象徴するものとされ、特に瞑想の手段として用いられた。
また、この聖音 は「a」、「u」、「m」の3音に分解して神秘的に解釈される。これは、サンスクリット語ではaとuが隣り合うと同化して長母音oになるという音韻法則があるからである。
例えば『ブリハッド・アーラニヤカ・ウパニシャッド』では「a」は『リグ・ヴェーダ』、「u」 は『サーマ・ヴェーダ』、「m」 は『ヤジュル・ヴェーダ』の三ヴェーダを表し、「aum」全体でブラフマンを表すと解釈された。
ヒンドゥー教
さらに後世のヒンドゥー教になると「a」は創造神ブラフマー、「u」は維持神ヴィシュヌ、「m」は破壊神シヴァを表し、全体として三神一体(トリムールティ)の真理を表すものとされ、民間においても浸透しており同教のシンボル的な意匠となっている。
仏教
この聖音は後に仏教にも取り入れられ、密教では真言の冒頭の決まり文句(オン)として、末尾のスヴァーハー(ソワカ)と共に多用された(例えば「オン アビラウンケン ソワカ」で大日如来の真言)。 また、仏教の経典『守護国界主陀羅尼経』では「a」は法身、「u」は報身、「m」は応身の三身を象徴し、すべての仏たちはこの聖音を観想する事によって成仏すると説かれる。
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 8/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/99f1e32d0b5e2b056d4504630fb64d1c

[ 本文 END ]

[ FORM ]
己がよく視聴します、主な地上波TV放送局 & BSデジタル放送局様
NHK Eテレ 日本テレビ テレビ朝日 TBSテレビ テレビ東京 フジテレビ
NHK BS NHK BSP4K BS日テレ BS朝日 BS-TBS BSテレ東 BSフジ BS11 BS12
良い番組の提供、ありがとうございます
関東圏、放送局様 地上波 1/2 関東圏、放送局様 地上波 2/2 BSデジタル放送局様 代表一覧
同上であります

My blog. Whitsunday and Mission Series URL. + Ⅱ
2025-05-28 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_x/d/20250528
〉
お世話になっている古神道の先生 (神官) より 250528版
2025-05-28 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_w/e/1cd15a6be042f19ddf1955e9b4c5ce48
https://dictionary.goo.ne.jp/thsrs/9827/meaning/m0u/
行かないで 070702
2024-12-04 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_x/e/fee37adce256bfb459fc6114228d54cb
世間に出ることを退いた伝説の霊能者が見た史上最悪な未来 &, sequence.. Ⅳ 1/16 - 16/16
2025-07-01 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_four/e/4cdd3f538c6c1d3cc04a0390b5501ca4
ニコニコ動画様が復活して約1か月
2024-09-07 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_y/d/20240907
やす子「LINE NEWS AWARDS 2024」受賞、今年注目を集めた話題の人物
2024-12-10 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_z/d/20241210
blog.goo.ne.jp/whitsunday (series) , mission_ (series) 期間まとめ
2022-08-19 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_x/e/b528ab1ebc5db208db58093413009477
blog.goo.ne.jp/whitsunday (series) , mission_ (series) 期間まとめ Ⅱ b
2023-02-20 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_s/d/20230220
blog.goo.ne.jp/whitsunday (series) , mission_ (series) 期間まとめ Ⅲ b
2023-02-20 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_x/d/20230220
blog.goo.ne.jp/whitsunday (series) , mission_ (series) 期間まとめ Ⅳ 4
2023-05-02 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_five/d/20230502
blog.goo.ne.jp/whitsunday (series) , mission_ (series) 期間まとめ Ⅴ
https://blog.goo.ne.jp/whitsunday_five/d/20230512
blog.goo.ne.jp/whitsunday (series) , mission_ (series) 期間まとめ Ⅵ 〔6〕 [ 240914更新分 ]
2024-06-19 | 日記
https://blog.goo.ne.jp/mission_x/e/bea73c46df6dcb024095d8dcdbb103e1

第43回 真夜中の虹
http://www.rosetta.jp/fu-un/041116.html
〈 " 禁足地、入るべからず " 〉
http://web.archive.org/web/20130410010329/http://youkey.hanagasumi.net/zatudan/zatudanpage/z-09.html
教訓 222. 悪い言動には悪い報いがある
http://www.wa.commufa.jp/~anknak/kyoukun222.htm

https://www.google.co.jp/search?q=神社 ライブカメラ 〔 お寺も入っています 〕
地元 鎮守 〔 挿絵 ( postcard ) 〕

[ 菅原神社 拝殿 / ペン画 上田博昭 様 ] ( 筆者 若干 arrange )

[ 同 鳥居 桜 / ペン画 上田博昭 様 ]
https://blog.goo.ne.jp/mission_v/d/20241119
〉
https://ja.wikipedia.org/wiki/菅原道真
〉
菅原 道真(すがわら の みちざね、承和12年6月25日〈845年8月1日〉- 延喜3年2月25日〈903年3月26日〉)は、日本の平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家。参議・菅原是善の三男。官位は従二位・右大臣。贈正一位・太政大臣。
忠臣として名高く、宇多天皇に重用されて、寛平の治を支えた一人であり、醍醐朝では右大臣にまで上り詰めたが、藤原時平の讒言(昌泰の変)により、大宰府へ大宰員外帥として左遷され現地で没した。死後は怨霊になり、清涼殿落雷事件などで日本三大怨霊の一人として知られる。後に天満天神として信仰の対象となり、現在は学問の神様として親しまれる。太宰府天満宮の御墓所の上に本殿が造営されている。
非常に才能、能力のある人をねたみからかオトシイレタ ?
当時劣等感を抱いたであろう人にとっては、いなくなることでラクになった ? 自分のプライドを保つことができるようになった ?
-
この教訓は生かすことはできているだろうか
同じアヤマチは起きているだろうか ?
それとも、防げているだろうか

絵 (ペン画) について。 もう一つの
大きく有名な神社は尊いですが、まず近くのそれなりの神社を。 という思いからも載せております。
(僭越ながら余計なお世話とは承知の上にて。 お寺に親しみがあるお方は、お近くのそれなりのお寺はいかがでしょうか )
Powered by goo blog