見た目は同じ水でもまったく違う水があるということは、飲み比べてみれば誰にでもよくわかります。
塩素の多い都会の水道水はコップ1杯飲むと胃にたまってしまい、それ以上飲みたくなくなります。
一方、おいしい湧き水はいくら飲んでも飲みあきることなく、お腹がガポガポになることもありません。ビールを飲まない人は、ジョッキに何杯もお代わりするビール党を見て「なぜあんなにたくさん飲めるのか」と疑問を抱きます。これはビールの炭酸ガスや香りや味が飽きさせないだけでなく、アルコールが含まれているので吸収が早いという理由があります。
しかし、同じ水なのに、いくらでも飲めるというのはどういうことでしょうか。科学的にはっきりわかっていることではありませんが、1つは水分子の状態が違うのではないかという説があります。
水の最小の状態は、2つの水素と1つの酸素が結合した状態です。空気中では、この分子が浮遊しています。このH2O分子がたくさん集まった状態が水で、空気中では雨となって降り注がれるわけです。ただし、H2O分子が集まるとき、個々の分子はいくつかずつのグループになって固まり、そのグループが集まって水を形成しています。
この水分子のグループのことを「クラスター」と言います。見た目はまったく同じ水でも、分子レベルのスケールで見ると、クラスターの大きさはかなり異なっていることがあります。塩素処理された水道水は一般にクラスターの大きい水で、湧き水などの自然に浄化されたきれいな水は一個一個のクラスターが小さいという特徴があります。水道水を括水器で浄化した水も、必ずといってよいほどクラスターが小さくなっています。つまり現象面だけを見れば、おいしい水というのはいずれもクラスターが小さくなっていて、クラスターの大きい水というのはすぐにお腹がガポガポになっておいしくない、ということになります。それが何故なのかということに関しては、さまざまな推論がありますが、完全には解明されていません。
塩素の多い都会の水道水はコップ1杯飲むと胃にたまってしまい、それ以上飲みたくなくなります。
一方、おいしい湧き水はいくら飲んでも飲みあきることなく、お腹がガポガポになることもありません。ビールを飲まない人は、ジョッキに何杯もお代わりするビール党を見て「なぜあんなにたくさん飲めるのか」と疑問を抱きます。これはビールの炭酸ガスや香りや味が飽きさせないだけでなく、アルコールが含まれているので吸収が早いという理由があります。
しかし、同じ水なのに、いくらでも飲めるというのはどういうことでしょうか。科学的にはっきりわかっていることではありませんが、1つは水分子の状態が違うのではないかという説があります。
水の最小の状態は、2つの水素と1つの酸素が結合した状態です。空気中では、この分子が浮遊しています。このH2O分子がたくさん集まった状態が水で、空気中では雨となって降り注がれるわけです。ただし、H2O分子が集まるとき、個々の分子はいくつかずつのグループになって固まり、そのグループが集まって水を形成しています。
この水分子のグループのことを「クラスター」と言います。見た目はまったく同じ水でも、分子レベルのスケールで見ると、クラスターの大きさはかなり異なっていることがあります。塩素処理された水道水は一般にクラスターの大きい水で、湧き水などの自然に浄化されたきれいな水は一個一個のクラスターが小さいという特徴があります。水道水を括水器で浄化した水も、必ずといってよいほどクラスターが小さくなっています。つまり現象面だけを見れば、おいしい水というのはいずれもクラスターが小さくなっていて、クラスターの大きい水というのはすぐにお腹がガポガポになっておいしくない、ということになります。それが何故なのかということに関しては、さまざまな推論がありますが、完全には解明されていません。












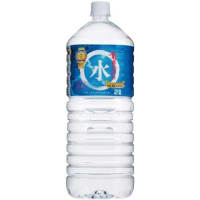







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます