
1995年に発表された論文によると、難しく挑戦的な課題をこなしたときの成績と、失敗を指摘された時の反応は、対象の学習や知識に対する信念が関連しているとのこと。※今回取り上げる成績とは、主に学業成績を指す。
具体的には、「知識は単純かつ不変のものであり、常に相対的な答えが発生するもの」「知識の習得は早ければ早いほどいい」という考えを対象が抱いている場合、その対象は自身の学習能力や学習した内容を過大評価し、また振り返りという行為を省くため成績が下降する傾向にあるという。
上記の2つの考えを持つものは、学習した内容が誤りであったとしても修正せず、誤りへの指摘に嫌悪感を抱く。知識や学習態度の修正を感情的にはねのけるため『学ぶ』という行為が阻害され、結果的に成績低下につながるという。
上記の考えを持つものは、おそらく通信簿に「学ぶ気のない学生」と評価されることだろう。赤点のテストは一瞥するだけで、補習に精を出さず文句をたれ、なのに次のテストでは自信満々で受けて、同じような間違いをする。生徒からも軽んじられるような、そんなイメージだ。
また、上記の考えを持ったことによる成績低下は、以前に学習した知識に影響されないという。過去の成績がいいものであっても、それによる成績低下は免れないということだ。
ちなみに、上記の考えを持った対象は「失敗をより強烈な攻撃であると受け止めている」かもしれないという仮説から、学習への軽視の度合いと学習性無力感(対象自身ではどうしようもできない刺激が継続して与えられると、対象はその刺激からの逃避をあきらめるという現象)との関連性も調べられているが、今のところ有意な関連性は見つかってないようだ。
なお今回の研究では、「知能や学習能力は生まれつきのものである」などの能力に関する偏見は、成績にあまり影響を与えないとしている。
ーーー知識は複雑で流動的だし、学びは時間をかけてもいいものである。
この一文に納得するかしないかで、知識の吸収率はだいぶ変わってくるのだが、
……いまだに、中学校の授業では取り扱われてなさそうだ。
参考文献
Qian, G., & Alvermann, D. (1995). Role of epistemological beliefs and learned helplessness in secondary school students' learning science concepts from text.










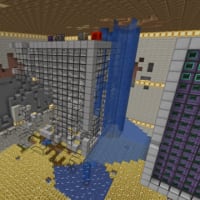
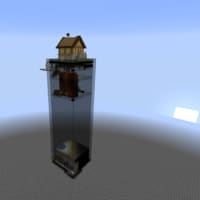



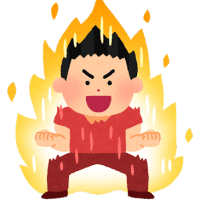



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます