という講習会に行ってきました。
石油危機があって昭和54年から、
省エネ法に基づく規制がはじまり、
平成11年から、次世代省エネルギー基準になりました。
その時以来の改正で、
しかも、今までは「ここはこうした方が良い」という誘導基準だったのですが、
今回の改正では、段階的にではあるものの、
平成32年にはすべての建物で義務化されるということのようです。
住宅の性能を表すものは、Q値(熱損失係数:床面積あたりどのくらい熱が逃げるかというもの)
というものが採用されていましたが、
家の形状や面積によっては不利になることもあるということもあって、
U値(外皮平均熱貫流率:屋根や壁などの外側の部分からどのくらい熱が逃げるかというもの)
+1次消費エネルギーで評価する事に代わります。
車の燃費のように、この家は光熱費や暖冷房費がどのくらいで住めるみたいな基準になると面白いと思います。
ただ、義務化されるということは大歓迎なのですが、
世界的に見て日本は断熱基準が低いということもあったので、
次世代基準から、さらに一歩踏込んだ対策がされるかと思っていました。
しかし、フタをあけてみると、
「次世代基準の義務化」のみになってしまったようです。
また、換気がちゃんとできるかどうかということでも重要なC値
(隙間相当面積:家の中にどのくらい隙間があるか)
に関しては、○○以下という数値目標が出ませんでしたし、
断熱をすればするほど大切な結露対策に関しても、
配慮事項にとどまっています。
単純に断熱材を厚くして、断熱サッシを選べば、
U値はそこそこな数字が出ますから、
弊社のように高気密・高断熱に対して考えている工務店と、
それなりにやっている量産ビルダーとの比較が出来なくなってしまいます。
また、低炭素認定住宅(詳細は後日)についてもそうですが、
断熱気密を充実させなくても、
なぜか太陽光発電等、設備だけ充実すれば、
認定を受けられるという矛盾も感じました。
断熱化の一番のポイントとしては、床の段差を無くすように、
寒い日や暑い日でも家の中の温度差をできるだけ少なくして(空気のバリアフリー)、
「健康に暮らす」ということです。
だからといって、すぐに大切な我が家がダメになっても良いということではありません。
「義務化するとレベルが下がる」という講師の方の言葉が印象的でした。
健康な暮らしとまじめな家づくり
http://www.ujiie.com/
読んでいただきありがとうございます
ランキングに参加しております。クリックして応援お願いします!
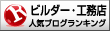

最新の画像もっと見る
最近の「家づくりのこだわり」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2018年
人気記事





