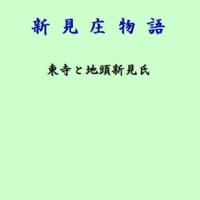上:雄株の雄花 下:参考までにハゼノキ雄花と雌花アップ
下:ヤマウルシの葉

下は参考までにヤマハゼの葉
上1段:ヤマハゼの葉 下:ヤマウルシの果実
上右:刺毛の生えた外果皮があらかた脱落して縞模様が見えている
ヤマウルシの小高木の幹
ヤマウルシ (山漆 ウルシ科 ウルシ属 学名 Toxicodendron trichocarpum syn. Rhus trichocarpa 落葉小高木 雌雄異株 花期5,6月 花期9,10月) 和名は栽培種に対し山に自生する“漆の木”の意。樹皮は灰褐色で、茶褐色の縦長の皮目が目立つ。葉は奇数羽状複葉で互生し枝先に集まってつく。小葉は6,7対、側脈は10対ほど、葉はやや短く幅がある(ヤマハゼはもっと細長く側脈は20対ほどと多い)。葉軸および小葉の葉柄から主脈にかけ毛が密生。雌雄異株で各々単性花をつける。雄株の雄花は黄緑色の花弁5片が反り返り雄蕊5が突出する。雌株の雌花は未観察であるがハゼノキのそれと同様であろう。果実(核果)は球形で房状に生って下垂し、外果皮に刺毛が生える。秋に褐色に熟すと外果皮が割れ落ちて、白い蝋質の中果皮に覆われ縦縞模様の核が現れる。冬芽は裸芽で褐色の短毛が密生、側芽は小さい。葉痕は大きく、楯形~縦長ハート形。当地では山腹の散策路に結構多く見られる。冬芽や果実の観察は手袋さえ着用すれば無難に接写できるが、ウルシオールを盛んに分泌する花期は敬遠したい。まあそれでもいつか近接したい。
属名Toxicodendron ![]() 毒性のある+木 (漆毒=ウルシトキシン/ウルシオールをもつ樹)
毒性のある+木 (漆毒=ウルシトキシン/ウルシオールをもつ樹)
Rhus ウルシ科のある種のギリシャの古名 rhous をラテン語化したもの(一説)とある。
種小名trichocarpum ![]() 有毛果実の、果実に刺毛のある
有毛果実の、果実に刺毛のある
ウルシノキ (漆の木 ウルシ科 ウルシ属 学名Toxicodendron vernicifluum ![]() 仮漆(ワニス 英varnish)を生ずる) ウルシノキとヤマウルシの生物学上の違いは不詳。樹皮を傷つけると滲み出る樹液(生漆)はウルシノキの方が多量採取できるとことから、古くから生漆採取に利用されてきた。「大植物図鑑」には「漆樹に2種あり一を細葉冬肌(そよご肌)、一を梨肌(ナシハダ)と称す。前種は外皮粗剛にして浸液薄く、後者は皮厚く軟滑にして良好なる漆液を出す」との記述が見られる。(この2種がウルシノキとヤマウルシを指すのか分からないが、ヤマウルシの樹皮はどちらかというとソヨゴの樹皮に似る)
仮漆(ワニス 英varnish)を生ずる) ウルシノキとヤマウルシの生物学上の違いは不詳。樹皮を傷つけると滲み出る樹液(生漆)はウルシノキの方が多量採取できるとことから、古くから生漆採取に利用されてきた。「大植物図鑑」には「漆樹に2種あり一を細葉冬肌(そよご肌)、一を梨肌(ナシハダ)と称す。前種は外皮粗剛にして浸液薄く、後者は皮厚く軟滑にして良好なる漆液を出す」との記述が見られる。(この2種がウルシノキとヤマウルシを指すのか分からないが、ヤマウルシの樹皮はどちらかというとソヨゴの樹皮に似る)
ツタウルシ(蔦漆) 紅葉2012-11-22
ハゼノキ(&ヤマハゼ)2012-10-13
ヌルデ 雄花と雌花2012-09-14