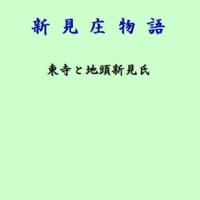花(蕾)の基部に一対の苞葉と幼葉が見える

下:花のつきかた2例 冬芽が綻び対生する葉の腋から花柄が伸びて苞が開き筒状花をつける「
↑上段:葉腋から1本の太い花柄を出しその先に苞が開き2個の花に分かれる(子房2室、双子の果実がなる)
下段:一葉腋から花柄1本、葉は対生するので2本の花柄を伸ばし、各花柄の先に苞を開き1個の花をつける


ウグイスカグラ (鶯神楽 スイカズラ科 スイカズラ属 学名Lonicera gracilipes 落葉低木) 和名はウグイスが神楽を舞う姿に見立てたことに由来する説などがある。花期は3,4月頃~5,6月頃、対生する葉腋から各々伸びた花柄の先に花筒の長い漏斗状花をつけ下垂する。対生する葉腋から太い1本の花柄が出てその先に二つの花をつけているのを観察した。おそらく子房が2室に分かれたもので、双子の果実がなるであろう。花冠は淡紅色で5裂、黄色の葯5、柱頭が突出。
冬芽は混芽で2対の葉と4個の花が同時に展開するのを観察した。
果実は液果で、初夏に透明感のある赤紫色に熟す。摘んで口に入れるとトロンとした食感があり微かに甘い。山道の傍らで散見される他庭木も時々見かける。枝に刀の鍔(鍔)のようなものががついているのを見かけることがある。これは徒長枝に見られ、対生した葉柄の基部が広がり、お互いに枝を抱く形で合着して鍔状になったものである。冬芽は薄い芽麟に包まれるがこれが脱落すると裸芽状になる。
属名Lonicera リンネがAdam Lonitzer(独の数学者・植物学者1528-1586)に因んで命名
ウグスカグラには以下のような種類がある。写真には葉が無毛で艶やかな個体や葉や花筒にうっすらと毛が見られる個体が混在している。ウグイスカグラとヤマウグイスカグラの見分けはできていない。ミヤマウグイスカグラは未見。
ヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. gracilipes 枝、葉柄、花柄に毛が散生。
ウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. glabra 茎から花まで無毛。種小名 gracilipes はgracili-pes 細い脚の意 細長い花筒を表すのであろう。glabraは無毛。
ミヤマウグイスカグラ Lonicera gracilipes var. glandulosa 葉や花冠、子房・果実に繊毛が多い。glandulosus 腺(腺毛)のある。
Adam Lonicer, Adam Lonitzer or Adamus Lonicerus (1528 -1586) was a German botanist. Lonicer was born in Marburg, the son of a theologian and philologist.
アダム・ロニチェルはドイツの植物学者。彼はマルブルグで神学者そして言語学者の息子として生まれた。
He studied at Marburg and the University of Mainz, and obtained his Magister degree at sixteen years of age. He became professor of Mathematics at the University of Marburg in 1553 and Doctor of Medicine in 1554. His true interest though was herbs and the study of botany.(wikipedia)
彼はマルブルグとマインツ大学で学び16才でマジスター(修士号)の学位を取った。25才でマルブルグ大学の数学教授に、翌年には医学博士になった。しかし彼の本当の興味はハーブと植物研究であった。
余談 カグラ・・・備中神楽:備中地方にて古くから行われてた荒神に奉納する荒神神楽(猿田彦の舞=勇壮華麗な剣舞)に演劇性の高い神代神楽(素戔嗚命=須佐之男命の大蛇退治等)などを加えて完成された郷土芸能。国指定重要無形民俗文化財 (「備中神楽」で検索)