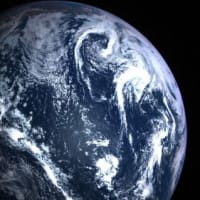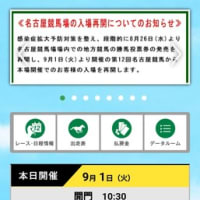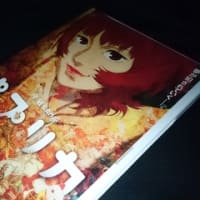遅ればせながら、スカパーで、先日行われた本場アメリカのブリーダーズカップ(BC)を見ました。
メインのクラシックでは、アメリカのスターホース「カーリン」号がまさかの敗北。。。
地元では、現役最強スターホースの敗北に、日本では考えられないほどの衝撃だったことでしょう。
解説の合田直弘氏の見解では、今年の開催地、サンタアニタの全天候馬場(ニューポリトラック)が少なからず影響したとのこと。
ここ数年、アメリカでは、これまで主流を誇っていたダート馬場から、この全天候馬場への移行がどんどん進んでいるとか。
馬の脚元に安心・・・というのは、ここ最近のニュースからも疑問符がつく気もしますが、なにより維持経費が安いというのが主催者にとって魅力なのでしょう。
そういえば、約2年前にもこのブログで同じような話題を取り上げました。
ニューポリトラック馬場に関する記事
→ 「ダート≠砂≠全天候型?」
2年前の記事の中でも述べているように、日本では「中央競馬」と「地方競馬」という、発足の経緯も、歴史も、また現在でもアイデンティティーを二分するような大きな流れができてしまっているというのが現状です。
そして、その二つの流れがいまや経済的規模において非常にアンバランスな状態にある。
そこが難しいところです。
地方競馬でも、もし今年のブリーダーズカップのように、ほとんどのレースで素軽い切れ味勝負の馬ばかりが勝ちまくったら?
地方競馬最大のアイデンティティといえる「ダート」、または「ダート馬」の存在価値はなくなるも同然でしょう。
ダート最強馬の存在価値はいかに?
今のような日本における競馬の主体のアンバランスさの中で、必死にそのアイデンティティーを探っている地方競馬にとって、それは翼をもがれるようなもの。
アメリカのように、”それが時代の流れなら・・・”というわけにはいきません。
また、馬産地の影響も計り知れないでしょう。
あのカーリンがダート2000m戦であっさりと欧州の芝短距離馬の切れ味に屈したように、これからはパワーで押し切ってゆくような馬は生産されることはなくなるかも知れません。
これはまさに血統地図すら塗り替えかねないことです。
環境の変化に適応しより優れたものだけが生き残り、それ以外は淘汰されていく。。。
歴史的に見てそれ自体は悪いことではないのかも知れませんが、日本の馬産地の現状も非常に厳しいものです。
おいそれと生産を百八十度変えることができる牧場も、数少ないことでしょう。
さすれば行く末は・・・?
ますます強者の一極集中、そして全体の活力を失っていき、やがては競馬界全体の衰退も目に見えています。
競馬界全体のことを考えるならば、この全天候馬場、今のままのテクノロジーでは地方競馬主催者も即導入・・・というのは危険な気がします。
ダート競馬なんか、この際止めればいい。。。
確かに、それもひとつの考え方。
アラブ馬が淘汰されてしまったように。
ただ、芝貼って競馬ができるような地方競馬場なんか今やどこにもないでしょうから、さすれば必然的にこのニューポリトラックが救世主ということになる。
でもしかし、それでは地方競馬自体のアイデンティティーが失われて存在価値がなくなってきてしまう。
どちらにしても、イコール=地方競馬の存続はありえない・・・ということになってしまうのでしょうか?
それとも新しいアイデンティティーを生み出していくか?
時代は、素軽い動きを求めている・・・・・。
盛岡オーロパークの行く末も、気になるところです。。。