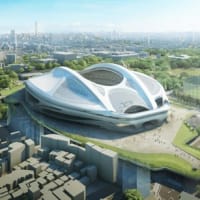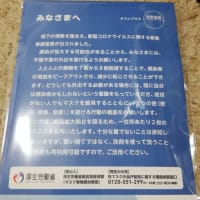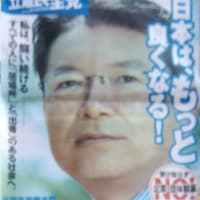『「越中先生」として親しまれ…』
長崎の郷土史家、故・越中 哲也 さん(99) 大正10年、1921年に長崎市の光源寺で生まれた
長崎の歴史や文化の研究や普及に努めてきました。 長崎の食や風俗、キリシタン文化など
幅広い分野の研究に取り組み、「長崎学」を体系的に発展させた。
長崎市立博物館の館長や長崎歴史文化協会の理事長
平和問題にも取り組み、「県九条の会」共同代表も務めた。
1995年に長崎新聞文化章、97年に勲五等瑞宝章、
2001年に龍谷賞を受けた。21年、長崎純心大名誉教授。
NBCテレビで 国宝や国重要文化財、長崎くんち歴史を親しみやすい語り口で解説
越中さんは生前、最も楽しかったことについて
長崎くんちで踊町の桶屋町の一員として関わったことだと話していたそうです。
生前に揮ごうした「くんち」の文字が印刷された手拭いの発売日でもありました。
越中さんのくんちへの思いを受け手ぬぐいを作っていた井村さん。
手ぬぐいは越中先生にも届けられました。
精霊流しの解説では、「先生が『来年は僕が精霊船に乗るけん』と言ったら『いや、先生まだよかって』と
言いながら、先生といつも話をしていました。解説を長年務めた。
長崎弁の語り口や名文句で「越中先生」と呼ばれ親しまれました。
長崎市 田上 市長 「努力をされて学んでこられたことを分かりやすく、
多くの人に伝えていただいた越中先生の話で
長崎の歴史や文化に興味を持った人がたくさんいる。ありがとうございますと伝えたい」
越中 さんの甥 土肥原 弘久 さん 「長崎で生まれ育った本当の長崎人。
長崎人の感覚に加えて歴史の研究者としての顔。両面があって越中哲也が成立していた」
妻の越中 京子 さん 「小屋入りのときには中止だと分かっていながら、
お諏訪さんの周りをうろうろしていた。
もう一回、桶屋町のくんちを楽しませてやりたいと。でも、かなわなかった」
長崎市都市経営研究所 宮川 雅一 所長 「長崎学というおもしろい分野があるということを
教えてもらって、私なりに楽しむというか、人生晩年を楽しく過ごさせていただいた」
丸山町自治会長 山口 広助 さん 「しっかり遺志は引き継いでいると私は自覚しているので、『次の長崎学は任せとかんね』という感じですね」
長崎を愛し、市民からも愛された越中先生。参列者は静かに手を合わせて、
最後の別れをしました。
葬儀は、26日午後1時から長崎市の大橋メモリードホールで執り行われました。
長崎の郷土史家 越中 哲也 さんの通夜に約300人参列
越中さんにヨイや~ヨイや~ヨイや~、くんちの時、叫んだな~「ご苦労様でした。
合掌」