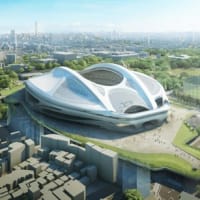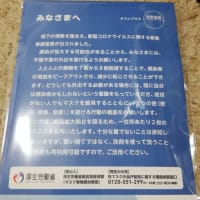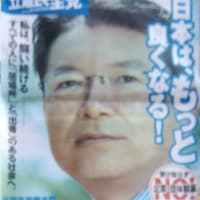『揆はなぜ原古城に籠もったのか?』
石垣が残る原城跡で。
歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」
天草・島原地域でキリシタン一揆が発生したのは、寛永14年(1637)10月のことだった。
キリシタンに対する弾圧ときびしい年貢収奪に耐えかねた両地域の農民が一揆を企てたのである。
近年の研究は、やむにやまれず民衆が暴発したというイメージではなく、
改易されたキリシタン大名小西氏らの旧臣すなわち牢人や庄屋たちが頭目となって、
談合のうえでつまり計画的に決起したことを指摘する。
天草四郎(益田四郎時貞、洗礼名フランシスコ)を大将とした一揆軍は、
肥後本渡城(熊本県天草市)などの天草支配の拠点を攻撃し、岡本大八事件で有馬氏は国替
11月14日に本渡の戦いでは、富岡城代の三宅重利(熊本藩重臣、明智秀満の子息)を討ち取った。
勢いに乗った一揆勢は、唐津藩兵が籠もる肥後富岡城(熊本県苓北町)を攻撃したが、攻めきれなかった。
島原の一揆勢は、松倉氏の島原城(森岳城)を攻撃したが、こちらも善戦するが落城には至らなかった。
城跡を発掘した結果、一体としてまとまった遺骨が見つからず、
惨殺してバラバラに捨てられていたことが判明している。その上に石垣を崩して
埋めたまま3世紀以上の年月が経過したのである。
凄惨と言うほかないが、同じ取材で訪れた陸奥九戸城(岩手県二戸市)における発掘で発見された惨殺遺骨と同様だった。
確か入館してすぐに見ることができたのだが、現在は資料館がリニューアルされて一番奥に陳列され、
遺骨の発掘状況がわかるように三層に分けて丁寧に展示している。
本丸跡にたつ天草四郎像。本施設は、世界遺産登録推進のため平成26年4月にオープンしたそうだ。
石垣が残る原城跡で。
歴史作家・安部龍太郎氏による歴史紀行「半島をゆく」
天草・島原地域でキリシタン一揆が発生したのは、寛永14年(1637)10月のことだった。
キリシタンに対する弾圧ときびしい年貢収奪に耐えかねた両地域の農民が一揆を企てたのである。
近年の研究は、やむにやまれず民衆が暴発したというイメージではなく、
改易されたキリシタン大名小西氏らの旧臣すなわち牢人や庄屋たちが頭目となって、
談合のうえでつまり計画的に決起したことを指摘する。
天草四郎(益田四郎時貞、洗礼名フランシスコ)を大将とした一揆軍は、
肥後本渡城(熊本県天草市)などの天草支配の拠点を攻撃し、岡本大八事件で有馬氏は国替
11月14日に本渡の戦いでは、富岡城代の三宅重利(熊本藩重臣、明智秀満の子息)を討ち取った。
勢いに乗った一揆勢は、唐津藩兵が籠もる肥後富岡城(熊本県苓北町)を攻撃したが、攻めきれなかった。
島原の一揆勢は、松倉氏の島原城(森岳城)を攻撃したが、こちらも善戦するが落城には至らなかった。
城跡を発掘した結果、一体としてまとまった遺骨が見つからず、
惨殺してバラバラに捨てられていたことが判明している。その上に石垣を崩して
埋めたまま3世紀以上の年月が経過したのである。
凄惨と言うほかないが、同じ取材で訪れた陸奥九戸城(岩手県二戸市)における発掘で発見された惨殺遺骨と同様だった。
確か入館してすぐに見ることができたのだが、現在は資料館がリニューアルされて一番奥に陳列され、
遺骨の発掘状況がわかるように三層に分けて丁寧に展示している。
本丸跡にたつ天草四郎像。本施設は、世界遺産登録推進のため平成26年4月にオープンしたそうだ。