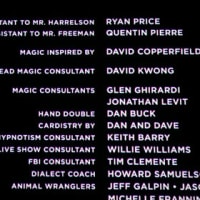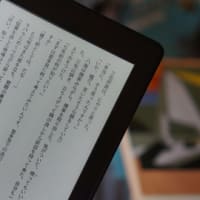マジックの演技の時に手が震えることは多くの人が経験していると思う。
以前、私がマジック教室を持っていたとき、生徒である学校の先生や
仕事で人前で話し慣れている人などにその日にやったマジックを
前で演じてもらっていた。
すると、その人達の手が震えていることがあった。
つまりどんなに人前に出ることに慣れている人であっても
マジックとなると手が震えることがある。
私が最初に手の震えを経験したのは大学のマジックサークルの一年生の時。
その日、その直前までサークルの先輩にマジックを見せていて
その同じマジックを新入生勧誘のために(自分も一年生だったけども)、
キャンパス内を歩く人に見せたときに突然やってきた。
一度こうなると震えを自覚しているのに全く止められない。
そしてこのことは練習不足や演じ慣れていないことが原因で
手の震えを引き起こすのではないことがわかる。
なにしろさっきまで平気でやっていたマジックなのだから。
もちろん、人によって原因は様々だろう。
個人的な考えだが、絶対に手が震えない体質を目指すのは
実はあまり効果的でないと思う。すべての要因を潰したつもりでも
いつまた未知の要因が訪れるかもしれないのだから。
必要なのはむしろ自分がどのような状況の時にそうなるのかを把握し
自分なりの対処法を持つこと。
自分の場合はかつては「自分が試されている」と(自分が思ってしまうような)
環境に弱かった。もう少し詳しく分析すると実際に試されている環境でも
(ネタ見せとかオーディション的な意味合いの場とか)
気持ちをコントロールして自分が見せる側、前にいる人々は自分の演技を
楽しんでくれる人々、観客と、そんな意識を自分の中に作れると
全く問題なく、これに失敗すると手の震えにつながったりした。
これを自覚してからは兆候が訪れても「お、来た、来た」とゆったりと(?)
構えられるし、今では気持ちのコントロール方法も以前より上手くなった。
それと対処法としてはいきなり演技に入るのではなく、
相手と軽く話をして(自分の中で)張り詰めた空気を和ませ、
話を進めながら相手を自分の中で「自分の仲間」、
「マジックを楽しみにしている観客」というグループに入れていく。
また、マジックの演目選びにも自分的にはさらなる保険をかける方法があるのだけど
長くなったのでそれはまた別の機会に。
以前、私がマジック教室を持っていたとき、生徒である学校の先生や
仕事で人前で話し慣れている人などにその日にやったマジックを
前で演じてもらっていた。
すると、その人達の手が震えていることがあった。
つまりどんなに人前に出ることに慣れている人であっても
マジックとなると手が震えることがある。
私が最初に手の震えを経験したのは大学のマジックサークルの一年生の時。
その日、その直前までサークルの先輩にマジックを見せていて
その同じマジックを新入生勧誘のために(自分も一年生だったけども)、
キャンパス内を歩く人に見せたときに突然やってきた。
一度こうなると震えを自覚しているのに全く止められない。
そしてこのことは練習不足や演じ慣れていないことが原因で
手の震えを引き起こすのではないことがわかる。
なにしろさっきまで平気でやっていたマジックなのだから。
もちろん、人によって原因は様々だろう。
個人的な考えだが、絶対に手が震えない体質を目指すのは
実はあまり効果的でないと思う。すべての要因を潰したつもりでも
いつまた未知の要因が訪れるかもしれないのだから。
必要なのはむしろ自分がどのような状況の時にそうなるのかを把握し
自分なりの対処法を持つこと。
自分の場合はかつては「自分が試されている」と(自分が思ってしまうような)
環境に弱かった。もう少し詳しく分析すると実際に試されている環境でも
(ネタ見せとかオーディション的な意味合いの場とか)
気持ちをコントロールして自分が見せる側、前にいる人々は自分の演技を
楽しんでくれる人々、観客と、そんな意識を自分の中に作れると
全く問題なく、これに失敗すると手の震えにつながったりした。
これを自覚してからは兆候が訪れても「お、来た、来た」とゆったりと(?)
構えられるし、今では気持ちのコントロール方法も以前より上手くなった。
それと対処法としてはいきなり演技に入るのではなく、
相手と軽く話をして(自分の中で)張り詰めた空気を和ませ、
話を進めながら相手を自分の中で「自分の仲間」、
「マジックを楽しみにしている観客」というグループに入れていく。
また、マジックの演目選びにも自分的にはさらなる保険をかける方法があるのだけど
長くなったのでそれはまた別の機会に。